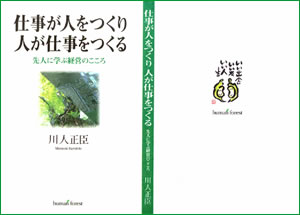幸せな人生を歩むために
2011年09月02日
2011年04月14日
死を迎える時、あなたは…
2011年04月07日
あなたは他力派?自力派?
2011年03月31日
失敗から学ぶ
2010年11月25日
口は禍の門(元)
2010年11月17日
2:6:2の法則
2010年10月20日
百歳/現役
2010年07月05日
コンプレックス
2010年06月28日
頑張れ日本・頑張れ本田圭佑
2010年06月10日
許す心
回答は「言葉にする」は38%で、 前回の調査から12ポイントも減少した
人間関係で、お互いの気持ちを察し合う能力に欠けると、自分勝手に
空気を読む受信能力だけでなく、言葉による、思いの適切な伝達が
2010年04月16日
自ら作ってしまう”限界”
■渡邉美樹「目的のある人生」 夢でなくてもいいのですが、 何か”大いなるもの”、あるいは” 自分の 手が届きそうもないもの” を求めて、一生懸命努力を重ねていくことは、 人間にとってとても大切なことだと思います。
その努力のプロセスのなかで、人間として磨かれ、 成長していくことが できる。 あるいは、沢山の人から「あなたがいてくれてよかった、 あり がとう」 と感謝される…そこに、人間に生まれてきた目的があり、 幸せが あるのではないでしょうか。
夢を持って、懸命に努力してたどり着くゴールを持つことは、 人間として 素晴らしいことです。 努力する人と努力しない人との差は、 夢を持って いるかいないかの違いではないでしょうか。
私は、いつも”夢を二つ”持つようにしています。 一つは、 今自分が向かっている夢です。そして、夢を成し遂げて「ああ、 よくやった」 という達成感をビジュアル化する。もう一つは、 達成した瞬 間に、 次の夢に向かって新たにスタートする自分です。
「理念と経営1月号・巻頭対談」 より
756 【心と体の健康情報】 ~幸せな人生~ 「自ら作ってしまう”限界”」
「あなたの病気には治療法はありません」…そう宣告されたらあなたは何を思い、どうするでしょうか? 東大法学部に入学して一ヶ月。 弁護士になる夢に向かって走り出した、内藤佐和子さん25歳を待っていたのは、” 多発性硬化症”という、1万人に1人の難病でした。 神経を覆う被膜が傷つき、 神経がむき出しになる…身体のどこで、いつ発症するか予測のできない難病に侵されたのです。
”笑点”のメンバーの1人だった、落語家の林家こん平さんが闘っているのもこの病気だ。内藤さんは、 医師から法律家への道を断念するようにと忠告された。 病気を憎んだ時期もあった。 それでも、持ち前の前向きな性格は変わらなかった。
様々な学生団体の活動に参加した。ビジネスプランコンテストに優勝して、100万円の賞金を獲得した。 自らの体験を著して出版…2008年”出版甲子園”に入賞。 昨年十月には 「難病大学生」を著し、出版している。
手足がしびれ、視野が狭くなる症状が何度か起きた。対症療法のステロイド点滴を10回くらい受けた。 朝目覚めると、体が動かないかもしれないという恐怖心がつきまとう。 それでも「難病になる前より充実した人生を送っている…と断言できる」 と自書に書いている。
最近になって、インターネットの検索サービス会社を立ち上げた… 収益の八割を難病の研究に寄付するという。医療技術の進歩を待って病気を治し、「弁護士になりたい」という夢を捨てていない。「限界の壁は、 自らつくってしまうものである」ことを教えられた。 中日新聞『中日春秋」
***************************************
二十代の初め、いつ治るとも知れない病に掛かり、 無期懲役刑の囚人のような闘病生活を体験した。その数年後に、アメリカで新薬が開発された… お陰でみるみる回復…自宅療養の後、 28歳の時社会復帰した。
アメリカで新薬が開発されなかったら…開発が十年遅れていたら、30歳まで生きられたかどうか? 難病を患い、 死と向き合う体験があったからこそ…その後の人生…人の何倍も幸福で、 何事があってもプラス思考で受け止められるようになった… 病のお蔭で真の幸福を知ったのです… 「人間万事塞翁が馬」です。
2010年04月08日
安岡正篤・海老の話
2010年02月25日
天命(天職)を知る(2)
■繁栄する農業 (職場の教養)
農業を営むTさんは、
妻と二人の息子と従業員で、楽しく仕事に取り組んでいる。
周辺の農家の多くは後継者が無く、やむえず廃業に追い込まれる中、
Tさんの農業は元気です…それにはわけがあります。
Tさんは農業が大好き…
23歳で独立した時、「自分の好きな農業で起業し、多くの仲間と共に、生涯農業に関わりたい」と、
大きな希望を抱いて働き始めました。その後、「農業が好き」という妻にも出会いました。
二人の子供は成長し、
地元を離れて東京の大学へ行きました。
卒業後、
「両親と共に農業をやりたい」と、故郷に帰ってきたのです。
Tさんの農業への思いが、
子ども達に伝わったのです。
人は暗い所よりも、明るい所に集まるものです。心を明るくして、 希望を持って、明るく未来に向って働く両親の姿が、輝いて見えたのです。自分の仕事をこよなく愛し、 将来に大きな希望を抱いた時、周りに人が集まってくるのです。
742 【心と体の健康情報】 ~幸せな人生~ 「天命(天職) を知る(2)」
2010年02月18日
吉田松陰の”天命”
2010年02月02日
日本人と西欧人/文化・考え方の違い
~幸せな人生~
「日本人と西欧人/文化・考え方の違い」
2010年01月21日
結婚っていいもんだよ
■熟年離婚
熟年夫婦…妻の多くが本気で離婚を考えているのに対し、夫の大半は
「まさか、うちの家内は…」と、楽観視している場合が多いのです。
「一心同体」「偕老同穴」のように、仲よく連れ添う四文字言葉は、
2009年12月09日
与える幸せ
2009年11月05日
夜回り先生「世界は広い」
ところが、把握しているはずの自分という人間が、往々にして制御不能に陥ってしまうことがあります。
2009年10月26日
人は何で評価するのか?
■心に残ることば「できる」
2009年10月19日
禅の心・眼を閉じ”空”を感じる
2009年10月13日
禅問答…自分は何者か?
2009年09月03日
幸福は、汗みどろに生きる中から掴むもの
2009年08月27日
野村克也の野球人生(4)
2009年08月19日
野村克也の野球人生(3)
2009年08月10日
野村克也の野球人生(2)
2009年08月03日
野村克也の野球人生
2009年07月27日
今日を大切に出来ない者に、未来はない
2009年07月21日
後始末の心得
【心と体の健康情報 - 683】
~幸せな人生を歩むために~
「後始末の心得」
一息入れたり、間をおいてからでは、緊張感が途切れたり、 おっくうになったりして、
結局はやらないようになってしまうのです。
お礼状を送るなど、手抜かりなくやっておくことです。
2009年06月29日
プラス発想の成功哲学
2009年06月09日
やる気が出る秘訣
■中日の守護神"岩瀬"のスイッチオン
プロフェッショナルは、本番前にプレッシャーを跳ね除ける一連の"決まり事"をやって、持てる力を発揮する。 毎回決まった手順を繰り返して、本番に臨むのです。
(メルマガ665号プレッシャー克服方)
5月上旬、史上4人目の通算200セーブを達成した、中日の守護神岩瀬。
岩瀬は通常5回前後になると、ブルペンで肩慣らしの投球を始め、6回から7回と、試合展開をにらみながら、徐々に集中力を高めていく。
8回から、呼ばれたらすぐ登板できるよう更に集中し、仕上げていく。
岩瀬はこれを、「スイッチを入れる」と表現している。
いったんスイッチが入ると、誰も寄せ付けない岩瀬がそこにいる。
中日スポーツ
【心と体の健康情報 - 671】
~幸せな人生を歩むために~
「ヤル気が出る秘訣」
「百年に一度の不景気」「消費低迷で売上が落ちた」…業績が悪化すると"ヤル気"をなくし、売れない理由を、
環境や人のせいにしていないだろうか?
「やりたいことをやらせてもらえない」「職場の雰囲気が悪い」など、ヤル気が出ない原因は様々です。
プロフェッショナルも、いつも順調だったわけではない…逆境にもがきながらも、モチベーションを保ち、這い上がってきた。彼らは、
いったいどうやってヤル気を掻き立ててきたのか?
「ヤル気」とは、目標をなし遂げ、達成感やお金などの報酬を得ようとする欲求から生まれてくる。ヤル気が出ないということは、「目標・
報酬」のどちらかに問題があるということです。
■モチベーションアップ法(1) 「あこがれの人を持つ」
プロフェッショナルの多くが、"良き師匠"との出逢いがあって、それを転機としてきた。
脳動脈瘤の手術でその名を知られる、外科医の"上山博康"上山は若き日、師事する脳神経外科医"伊藤善太郎"から、
ある言葉を伝えられた…「患者は命をかけて、医者を信じる」
伊藤のようになりたいとの思いが、上山をプロ中のプロへと磨き上げていった。
脳の前頭葉には、相手の動作を見た時、あたかも自分も同じ動作をしたかのように、反応する神経細胞があると考えられている。
師匠の良き振る舞いを見ていると、前頭葉が反応し、自分も気づかないうちに、同じ振る舞いをするようになる。
それが能力アップにつながると、考えられているのです。
ゴルフを例に挙げると、プロゴルファーのスイングを、ビデオで繰り返し何度も見て、スイングイメージを頭に描き、練習する…
プロのスイングを真似ようとするのです。
「あこがれの人」がいない場合は、身近な人の"良いところ"に注意を向けます。
例えば、人前で上手に話せるようになりたいなら、スピーチ上手の人をよく観察します。話題の選び方、組み立て方、間合いの取り方、
話す時のしぐさ、目線の配り方など、学ぶところがいっぱいあります。
■モチベーションアップ法(2) 「小さな"成功体験"を大切にする」
脳というのは"成功体験"を通してしか、ヤル気が起きません。
小さな課題でいい…「これがクリアできたらうれしいな」っていう、そういう何かを自分で見つけていく…それが大事なのです。
今年石川県で、昨年に続いて100キロ歩が開催される。
100キロ歩にチャレンジし、完走したいと思うなら、先ず25キロ、そして50キロと、成功体験を積み重ね、
やれば出来るという自信と信念を積重ねていく…。
プロフェッショナル達の中には、高い目標はあるものの、長い間成果が出ず、苦しみぬいた人が少なくない。
世界で初めて、農薬や肥料を使わずにリンゴ栽培に成功した、リンゴ農家の木村秋則さん…木村さんは8年間リンゴの自然農法を続けるが、
実が生るどころか、花さえも咲かなかった。
生活費にさえ事欠く極貧の中で、木村さんを支えたのは、小さな成功体験だった。
「何度もやめようと思った。自然農法の桃とかナシとかブドウはよく実っていた…きっといつかは、リンゴも出来るはずと…」
どんな小さな成功でも成功すれば、脳の中で"ドーパミン"という物質が放出されます。すると、
脳は喜び"快感"という報酬を得ます。
「苦しみを乗り越えると、快感が待っている」…それが脳に刻み込まれたら、自然と勇気が湧いてくるのです。
今は名をなしたプロフェッショナルも、小さな一歩を根気よく積み重ねて、大輪の花を咲かせたのです。
NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から
2009年05月26日
プロのアイデア発想法
■ひらめき
戦後の日本碁院を代表する棋士"呉清源"。若い頃、ときに夢の中で"妙手"を見つけたという。「眼が覚めてから、 その形を覚えていることがある…」と、作家・川端康成が著書「名人」に、本人から伝え聞いて書いている。
ビートルズの名曲「イエスタデイ」は、ポール・マッカートニーが、夢の中に現れたメロディーから生まれたと、言われている。
一芸に抜きんでた人は、夢の中にも、その天才的才能が表れるものらしい…。
人が見たもの、描いたものが、脳信号の動きをもとに、画像に再現する技術…京都の国際電気通信基礎技術研究所が、
開発に成功したという。
「□」や「×」などの図形やアルファベットを、見た人の脳から、情報として読み取り、コンピューターの画面上に映し出すことが出来るのです…
。
近い将来、睡眠中に見た「夢」や、脳裏に描く空想を、コンピューターが再現し、本人が人に伝える意志の有無に関わらず、 知ることが出来るようになるだろう…。
【心と体の健康情報 - 667】
~幸せな人生を歩むために~
「斬新な発想を生み出す、プロのアイディア発想法」
数日前に私が見た夢…先生が"造形モデル"(見たこともない素敵なデザインだった)を示し、このモデルを参考に、
オリジナリティな作品を創るようにと、学生に宿題を出した。
夢の中で…良いアイディアが湧かなくて悩む私…ふと、「サンゴと熱帯魚」を題材にすることを思いつく…
作品のアイディアが次々浮かんでくる…目が覚めた後も、そのアイディア…覚えていました。
「締め切りが直前に迫っていても、アイディアがまとまらない…」「何か良いアイディアがあれば、教えてほしい」…
私たちの切実な願いである。
どのように脳を活性化すれば、アイディアがスッと出てくるようになるのでしょうか。
そこのところを、プロフェッショナルに是非聞いてみたい…真剣な悩みです。
プロフェッショナルと言われる人たちは、どのようにして斬新な発想を生み出しているのでしょうか?
Q.「アイディアがひらめく」とは、どういうことでしょうか?
新しいアイディアは、ゼロから生まれたりしません…今までの経験や知識を組み合わせることで、生み出されます。そうした経験や知識は、
脳の"側頭葉"に蓄えられます。
アイディアが必要になると、側頭葉の上部にある"前頭葉"から、側頭葉に指令が発せられます。すると側頭葉は、蓄えられた記憶の中から、
「これはいい」と思うものを組み合わせて、前頭葉に送ります。幾つか送られてきた中から、前頭葉が採用したもの…それが「ひらめき」
となって、頭に浮かんでくるのです。
■迷ったら寝る…
「"寝る"発想法」
夜中にふと目が覚め、思わぬアイディアが浮かぶ…
そんなことがあって、忘れてしまわないようにと、枕元にペンとメモを置いて寝る…そんな体験、誰でも一度や二度はあると思う…。
眠りが覚める頃に…アッわかった!脳は、人が寝ている間も考えているのです。
「考えなければならないことがあったら、家に帰って寝る…迷ったら寝る」
これが、発想の極意なのです! 翌日の朝「ああ、こういうことか…」と…。
これは、昨年「崖の上のポニョ」で大ヒットを飛ばした、宮崎駿監督の言葉です。
「アイディアに行き詰ったら、15分でもいいから昼寝する…寝ると違いますよ」と、宮崎監督は言う。
松本清張の名作「砂の器」…1人の刑事の執念が、寝覚めた時、ひらめきとなって、迷宮入りを救っている。その第12章・ 混迷の一節…
|
「もう一つ、手紙を出すべき相手があった。それを思いついたのは、今朝…寝床の中である。今西(刑事)
は目のあくのが早い方だった。 |
Q.なぜ、寝るといいんだろう
昨年、新作「崖の上のポニョ」が話題になった宮崎監督。良いアイディアが見つからない時、
1時間ほど昼寝をする…起きがけに、あれだけ行き詰ったかに見えた問題が、解けてしまう…そんなことがよくあるという。
「人間の作業能力は、起きた瞬間が一番高い」
人が起きて何かしている時は、脳は絶え間なく入ってくる情報にさらされ、蓄えてある記憶がバラバラのまま、まとまらない。
眠っている間に、経験や知識が整理されていくのです。それで、寝て起きた時にアイディアが湧いてくるのです。しかし、
寝さえすればアイディアが浮かんでくるかというと、そうはならない…大事な条件が一つある…「とことん考えてから、寝る」
ことです。
考えて、考えて、一日考えていると、さすがに脳は「勘弁してくれ」となり、気絶したみたいに眠りに落ちて…眠りから覚める頃に
「ア~わかった…」
プロフェッショナルの多くが、幾度となくこんな体験をしている。とことん考えたら、脳はよりポジティブに働く…「考えて、考えて、
とことん考えてから寝る」…
これがプロフェッショナルの「寝る発想法」なのです。
NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から
2009年05月19日
プレッシャー克服法(2)
■趣味のゴルフが、プレッシャーに強い体質を養う
一番ホール…さあ本番、初っぱなのドライバーショット…緊張が走る。
今日こそは…とクラブを構えるが、プレッシャーが緊張となり、普段の練習通りの力が出ない。プレッシャーに強くならなければ、
ゴルフは上手くならない…。
プロは本番直前、いつも同じメニューで、集中力を高め、スイッチをONに切り替えていく。(NO600 重圧と戦うイチロー)
いつも同じ動作で…柔軟体操で軽く体をほぐす。手袋をはめ、手を軽く握り締める…その時「ヨシ!」と、スイッチが入る。
一番ホールに立ち、まず素振り…自分の番が来たら、左袖をちょいと引っ張ったり、クラブをチョンと地面を叩いたりする…打席の後ろに立ち、
方向と落とし所を見定める…いつもの決まった歩数で、同じリズムで打席に向かう…クラブを正眼に構え、背筋を立て、構えの姿勢に入る…。
そうしたさりげない動作を繰り返して、集中力を高めていく。本番前に毎回同じ"決まり事"をやって、平常心を保つ。集中力を高める。 そうやって、プレッシャーを跳ね除けていくのです。
【心と体の健康情報 - 665】
~幸せな人生を歩むために~
「プレッシャー克服法(2)」
いざという時…思うように力が発揮出来なくて、思い悩む…
プレッシャーを克服し、普段通りの力を発揮するには、どうしたらいいのでしょうか?誰もが持つ悩みです。
その答えは、
「脳を活性化させて、プレッシャーを解消する」
さあ、これから本番…脳の「スイッチをON」にします。スイッチが入った瞬間、脳が集中的に働き出し、プレッシャーがあっても、
いいパフォーマンスが出来るのです…。
スイッチをONにする時、頭の中でモードの切り替えが行われます。
私たちの脳には、「集中モード」や「リラックスモード」など、様々なモードが眠っています。プロは本番に臨む時、この「集中モード」
を呼び起こして、プレッシャーを乗り越えていくのです。
では、「どうすれば、集中モードを呼び起こすことができるか?」
モードの切り替えは、前頭葉で、無意識の中で行われるため、自分の意志ではコントロールが難しいと考えられています。ところが、
それをコントロールできる、プロフェッショナルがいるのです。
前号では、プレッシャー克服する方法は、「苦しい時にも、あえて笑う」でした。
プロは、どんな苦しい時でも笑顔で、プレッシャーを笑い飛ばす。
否定的な事は一切言わず、考えず、何事にも前向き、肯定的に…今、自分に出来ることは何かを懸命に考え、良いと思ったら、
惑わず実行する。
更にもう一つ、プロがやっているプレッシャー克服法があります。
「本番前の"決まり事"を持つ」
ことです。
大リーガーのイチローは、本番前の"決まり事"を固く守ることで知られている。
球場に入ると、決まったメニューを淡々とこなす。打席では、狙いを定めるように、バットを立てる。一連の動作をキチッとこなしていくと、
本人の意識には関わりなく、スイッチが入るのです。
決まり事の内容は人様々ですが、共通するポイントは、何かしら"体を動かす"ことです。 脳のモードを、自らの意識で変えることは難しいのですが、本番前に、いつも同じパターンで体を動かすと、運動系の神経回路から、 信号が前頭葉に送られ、集中モードへ切り替わっていくのです。
毎回決まった手順を繰り返して本番に臨む。プロは"決まり事"をやって集中モードに切り替え、プレッシャーを跳ね除け、
結果を出すのです。脳がプレッシャーに負けると、本番に集中することが出来ません。
ですから、いざ本番という時、プレッシャーを跳ね除ける一連の"決まり事"をやって行けば、集中モードに切り替わり、
力を発揮出来るのです。
NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から
2009年05月12日
プロのプレッシャー克服法
■「まさか」の坂
昨日11日、メーカーの招待で、春の海外コンベンション・ラスベガスツアーに出発する予定が…中止になった。
メキシコで発生した新型インフルエンザが中止の理由…思いもしなかったことです。心待ちにしていた海外旅行…仕方ないとは言え、残念です。
8年前の2001年の秋も、ニューヨーク・コンベンションが、出発直前になって突然中止になり、悔しい思いをした。
9.11アメリカ同時多発テロが起きたのです。
昨年まで史上最長記録を更新していた好景気が、突然悪化したように、人生にも上り坂や下り坂がある。更に人生には、今回のような「まさか」
という坂があることを知らなければならない。
【心と体の健康情報 - 663】
~幸せな人生を歩むために~
「プロのプレッシャー克服法」
何かにチャレンジする時、準備不足や経験不足がプレッシャーになって、うまくいかなかったらどうしよう…とネガティブになり、
不安でがんじがらめ…普段の力を出せなくなってしまう…。
プレッシャーを抱えながら、いかに自分の力を出していくか…きついノルマや成果主義、熾烈な競争にさらされる現代社会では、
誰もがプレッシャーとの戦いを強いられる。
常に大きな成果を求められるプロフェッショナル…降りかかってくるプレッシャーも大きい。そのプロ達は…
ある同じことを実践しているのです。
プレッシャー克服方(1)
「苦しい時にも、あえて笑う」
どんな苦しい時でも、笑い飛ばす…
笑顔でプレッシャーを跳ね飛ばす。
海外で巨大プラントの建設を率いる"高橋直夫"氏…
「笑って仕事しないとダメだ。考え過ぎると、頭や体の動きが鈍くなる。
苦しくてもあえて笑えば、プレッシャーの中でもいい仕事が出来る」と言い切る。
| 笑いの効用は、科学的にも解明されている。 | |
| ○ | ドイツの研究者が行った「笑いの実験」 |
| Aのグループには、ペンを縦に口にくわえ、笑えないようにした。 もう一方のBのグループには、横にしたペンを歯で噛んで、笑っている顔を作り…そして、漫画を読ませた。 両方に漫画の印象を十段階で評価させたところ、笑いの表情を作ったBグループの方が「面白かった」と評価したのです。 つまり、心の底から笑わなくても、作り笑いをしただけで、脳は影響を受け、 考え方がよりポジティブになることが分かってきたのです。 ポジティブになることで、前頭葉が適切に働き、プレッシャーがかかっていても、的確な判断、 良いアイデアを生み出しやすくなると、考えられている。 |
|
| Q. | 「いざという時に力を発揮できるようにするには、脳をどのように活用すればよいのでしょうか?」 プレッシャーを解消する相談で、最も多かった質問です。 |
| A. | 仕事に入る時、「スイッチをONにする」ある?行動をする。 スイッチが入った瞬間、脳が集中的に働き出し、プレッシャーがあっても、プロは、 いいパフォーマンスができるようになるのです…。 |
いざ本番…スイッチをONにする時、頭の中で、モードの切り替えが行われる。
私たちの脳には、「集中モード」や「リラックスモード」など、様々なモードが眠っています。プロは本番に臨む時、「集中モード」
を呼び起こして、プレッシャーを乗り越えているのです。
問題は「どうやって集中モードを呼び起こすか?」に関心がいく。
モードの切り替えは、前頭葉が無意識のうちに行うことが多いため、自分の意志では、コントロールが難しいと考えられています。
ところが、自分の意志をコントロールすることができる、プロフェッショナルがいるのです。
次号につづく
(NHKプロフェッショナル 仕事の流儀から)
2009年04月14日
仕事が直感(観)力を磨く
■総入れ歯に見た職人魂
意外と知られていないが、祝い事に欠かせない「水引細工」は、
金沢の伝統工芸の一つである。
07年春"北国風雪賞"を受賞した水引職人の匠"津田剛八郎"氏は、
40歳の時まだ若いのに、総入れ歯にした。
水引を歯で引っ張って結ぶ際、歯茎に水引が食い込んで、歯茎を傷める。
そこで、一ヶ月かけて全ての歯を抜いてしまった。
我が身を削ってでも、仕事に打ち込もうとする、職人魂がそこにある。
大正時代からの老舗津田家…家業を守るための心構えを聞くと、
「気を張って積み木をしているようなものだ」と、津田氏は語る。
木を寸分違わず重ね合わせていけば、高く積み上げられる。
しかし、いい加減に積めば、すぐに傾き崩れるだろう…。
「積小偉大」という言葉がある。
毎日コツコツ、小さな仕事でも手を抜かず、仕事に励めば、
しだいにお店に信用が付き、お客様が店を守ってくれるようになる。
【心と体の健康情報 - 656】
~幸せな人生を歩むために~
「仕事が直感(観)力を磨く」
"プロ・匠"と言われる人には、並外れた"チョッカン"力が備わった人が多い。
瞬間的に感じとって判断する「直感力」と、物事の本質を見抜く「直観力」に長けているのです。
コンピュータが得意とするのは「しらみつぶし」。
将棋ソフト「ボナンザ」は手ごわい…6万局の棋譜をベースに作戦を学び、数十万局のデータベースを抱え、百万局面以上を、
わずか1秒間で読み尽くすという、大変な優れものです。
布石や守りを"1万項目"に分けて得点化し、形勢を判断する…現在このソフトと対抗して勝てる棋士は、500人くらいだろう。
しかし、ソフトの完成度をいくら高めても、人間の「直感力」とか「大局観」の領域には、コンピュータは入り込めない。
例えばプロ棋士は、対戦棋士の表情・仕草などから、微妙な心の変化を読み取り、対局を有利に導く術を心得ている。
コンピュータには、そこまで読み取る力はない。棋士の足元まで近づけても、トッププロには勝てないのです。
ところが、コンピュータが完全解読して、プロと対等に戦えるゲームがある。
北米で人気の、はさみ将棋に似た"チェッカー"だ。
数年がかりの計算が出した結論は「引き分け」…それはミスのない時で、ソフト相手に1手でもミスを犯せば、もう勝ち目はない。
"チェッカー"の局面数は、およそ「10の20乗」。
取った相手の駒も使える"将棋"は、「10の71乗」…これは、全宇宙の星の数「10の22乗」をはるかに上回る。
それが"囲碁"になると、局面数は"無限大"に近づいてくる…。
世に一流と言われる人は、「直感(観)力」に長けている。
直観は、漫然と浮かんできた「ひらめき」とは違う。長年の蓄積によって身に付いた"力"だ。カメラのピントを合わせるように、瞬時に、
的確で正確な判断を下す能力を備えている。
TVで…味噌を"量り売り"しているおばさん店員を見て驚いた…
味噌をシャモジにすくって、秤に乗せるとぴったり1キロ…
針はぴったり1キロを指している…何度やっても、ぴったり1キロ…
"匠の技"である。長年の経験が直感力を高め、プロの技になっている。
技能オリンピックで、金メダルが取れる熟練旋盤工のレベルになると、1ミリの千分の一の誤差を識別する。精密機械も、 千分の一の誤差を読み取れるが、長年の経験と勘を駆使する人間の指の感覚には、とても勝ち目はない。
経験を積み重ねることで、「大局観」が養われる。
仕事を一枚の絵のように眺め、羅針盤のように全体の方向性を決め、仕事全体を指し示す能力が備わっていく。
若いころは頭の回転が速く、行動力に長けるが、経験が浅いため、大局的にモノを見ることが出来ない。そのため、一つひとつ、
目の前の仕事をこなしていくしかない。
"直感(観)"には、雑念や余計な思考が入ってこない。純粋な目でパッと見て、仕事の流れを把握する。直感(観)力の70%くらいが、
正しい判断になるのです。
将棋を例に挙げると、プロといえども全部の手は読めない。
何を捨て、何を残すかが重要になり、勝負を分ける。勝ち負けを競う相手がいる以上、自分の思考能力だけでは将棋は打てない。
わからない中を、直感(観)力を頼りに手が進んでいく。
ソフトが進化して、コンピュータが、プロ棋士の力に近づきつつある。
いくら考えても分からない詰めを、将棋ソフトは、1秒もかからずに解いてしまう。
人間は、経験を積み重ねながら、力をつけていくのに対し、ソフトは、序盤はアマチュア級なのに、終盤の詰めになると、
プロ並みの力を発揮するのです。
明らかに人間と違う。人間には共通した思考・センスがある。
生理的に受け入れられない恥ずかしい手もある。ソフトにはそんなものはない…先入観も違和感も判断ミスもない…一手一手、最善・
最短の手で攻めてる。
ソフトの目には"駒"は映らず、数字の世界が広がるだけ。良い手を指せても、その意味はソフトには分からない。人間は、 勝負の過程で"創造性"を発揮し、"直感(観)力"に磨きをかける…そして、自分らしい個性が…微妙な感情の動きが盤面に表れてきて、 勝敗を左右する。
読売新聞「経験で磨く大局観」より
二十代の初め、人生を豊かなものにしたいと、一年近く碁会所に通い、先生直々囲碁の手ほどきを受けた。今思えば、 若い時に囲碁を習得したことが、マネージメントの大局観を養うのに、プラスになったと思う。
2009年04月07日
親孝行
■この不景気…中村天風師なら何と言うか?
天風先生がいま生きておられたら、目をカッと見開いて、こうおっしゃるでしょう…
「売れない…お客が来ない…だからどうだというのか!どうしろというのか!
不景気なときに、不景気だと言ったら、景気はよくなるか!?」
人の世のために役立つ「事業」をするというのなら、まず人の世のために役立つ「自己の確立」が第一である。
人の「幸福」を願うなら、まず自分が幸福でなければならない。
自分が幸福であるかないかは、人生に対する自分の思想が「積極的」か、「消極的」か…人生をどう生き、どう考えるか…でわかる。
清水榮一著「心の力」より
※中村天風(明9~昭43) 華族に生まれながら、軍事探偵として満州へ…。
死の病を治したいと、欧米・インドを放浪。その間、コロンビア大学医学博士、日本人初のヨガ直伝者となる。帰国後、銀行の頭取、
製粉会社重役となるも、大正8年一切を投げ打ち、大道説法者に…。皇族・政財界の重鎮をして"生涯の師"と言わしめ、
天風門人となる者後を絶たず…。
【心と体の健康情報 - 654】
~幸せな人生を歩むために~ 「親孝行」
先月のお彼岸…お墓参りに行き、先祖の墓石をピカピカに磨いてきた。
そして先週末…兄弟集まって、母の17回忌、父の33回忌の法要を行った。
墓参りをして気になるのは、参り手のない放置された墓があること…。
先祖の墓を守り継ぐ者が途絶えたのでしょうか…少子化の影響でしょうか…。
親族が亡くなった後の法要は、初七日に始まり、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌と、近親者を招いて供養する。 一般的に、三十三回忌をもって供養の最終年忌とし、五十回忌の供養は、おめでたい祝い事になる。(浄土真宗)
日本人は、長い歴史「親孝行」を"人の道"と考え、大切に受継いできた。
そして、世界一長寿国と言われる国を作ってきた。江戸時代から明治・大正・昭和と、親孝行の大切さを子ども達に教え、
"孝"が如何に大切かを今に伝えてきたのです。
それが戦後の民主教育の中で、失われてしまった。私たちは、誰からも親孝行の大切さを教わらなかった…当然、子ども達にも、
親孝行の大切さを教えていない。
今は「親孝行をせよ!」という言葉が、どこからも聴かれない社会になったのです。
日本人の平均寿命は80歳を越えています。
猿やライオンなど、動物の世界では、年老いて餌が捕れなくなると、群れから離れ、
死んでいった。ライオンやシマウマの社会に、親孝行はない…走れなくなったライオンは飢えて死に、走れなくなったシマウマは、
他の動物の餌食になった。
ところが人間は、年老いて1人で生きていけなくなっても、20年や30年は生きられる。
それは人間の社会だけが、自然界の生存の法則にはない"孝"という行為をするからです。
1人で食べていけなくなった年寄りを、周りの人たちが助ける…。
"孝"によって、体力・気力の低下した年寄りでも、長く生きることが出来るのです。
この"孝"…「仁」や「義」のように、本能として、生まれながらに備わっているものではない…教育によって育まれるものです。
「論語の友」
ここで問題なのは、今の社会、老いた老人を世話し、支えているのは、家族ではないということです。育ててもらった恩もどこえやら、 実の親を、当たり前のように養護老人ホームに入れ、人任せにしてしまう…。
年寄りを、家庭で介護できる環境にないのが大方の理由だが、厄介払いでもするように、一切を他人まかせにして、 見舞いに行こうともしない…そんな家族がいるのも事実です…介護放棄である。「親孝行」の意識が希薄になっているのでしょう。
私は三男ですが、父親の会社を継いだことから、結婚後両親と同居。
父が…そして母が…老いて病に臥し、旅立っていく時、妻には苦労をかけたが、付きっきりで看病した。
何れは老いて人様のやっかいになり、死んでいく。その時、誰に死に水を取ってもらうつもりか?…我が子の顔が浮かんでくるだろうか?…
「いずれ養護施設にでも入るから、心配しなくていい…」と、当たり前のように子ども達に言うが、本心だろうか?
本当にそれでいいのだろうか? 病院で寝たきりの年寄りが、「孫の顔が見たい…家に帰りたい…家で死にたい」と訴える…。
年寄りが「長生きして良かった」と、本心から思える社会にするには、家族みんなが"考"を考える社会にしていかなければ、老後の幸せは、
おぼつかないでしょう…。
2009年03月24日
将来に備えて
■将来に備えて…
40年後の2050年…あなたは何歳になっているでしょうか?
2050年…日本の総人口を占める65歳以上の割合が42.2%になり、老齢化のピークを迎えるのです。過去、どこの国も経験したことのない、驚異的老齢化社会が、21世紀末まで続くのです。
どんな世の中になっているだろうか?…バスの運転手も、医者も看護婦も、70歳以上の年寄りにも働いてもらわなければ、社会も経済も回っていかないだろう。
今は不況…失業者が出た、モノが売れないと騒いでいるが、これから先、世の中はもっと厳しくなることを覚悟しなければならない。
憲法で国民の権利が守られている。が、国民の4割が65歳以上になって、国は、私たちの生命・財産、最低限の生活を保障できるだろうか?
国が当てにならないとするなら、暮らしや家族は、自分で守らなければならない。
贅沢や無駄を慎み、出来るかぎりの貯蓄をしておかなければならない。
冬の時代が迫りつつある今、いつまでもキリギリスをやっている訳にはいかない。
そんな日本が嫌なら…どこか?暮らしやすい外国へ脱出することです。
【心と体の健康情報 - 650】
~幸せな人生を歩むために~
「将来に備えて…」
今週の倫理591号「日本人の原点に返り 大波を押し返そう」を転載します。
世界銀行は2005年、開発途上国人口の四分の一にあたる14億人が「貧困層」であるとの統計を発表した。
現在、地球上には、約67億4千万人の人口が溢れており、貧困層は総人口の20.7%…日本円に換算して、一日140円未満で生活している人々です。
我が国では、生活に困窮する国民に、様々な生活保護を行なっている。
最低限度の生活の確保を目的とした「生活保護制度」(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助)が充実しており、最低でも月額6万円以上の援助が約束されている。
国によって、物価の違いなどで、一概には言えないが、世界の基準に照らしてみると、我が国には、一人として世界基準に該当する生活困窮者はいないということになる。
さらに、日本人は他国に比べ、非常に恵まれた環境の中で暮らしている。
食糧難で餓死することはないし、四季折々の食料も豊富です。また、治安も安定し、夜間の外出もよほどのことがない限り、事件や犯罪に巻き込まれることはありません。
飲料水は公園や公共施設、至るところにあり、高レベルの教育が受けられます。
医療も充実していて、世界でも冠たる長寿国として有名です。
あるアメリカ人が来日した折に、日本のホームレスが、街角で新聞を読んでいる姿を見て、「彼らは字が読めるのになぜ働かないのか? アメリカでは、読み書きできない者がホームレスになる…日本はどうなっているのだ」と、驚いたという。
幸せや豊かさの基準は、人により様々ですが、世界の生活水準から客観視すると、戦後私たちは、長年にわたって世界で最も安定した生活を保ち続けてきたことになる。
が、そんな幸福とは裏腹に、いつしか拝金主義がはびこり、日本人が大切に守ってきた「謙譲の美徳」や「相互扶助の精神」「心の豊かさ」などは、どこかに置き去れてしまったようです。それが今日の日本の弊害の原因…と、指摘する人がいる。
百年に一度といわれる経済不況の今、私たちは改めて、日本人の原点に立ち返らなければならない。
「感謝は最高の気力」と言われます。何気ない当たり前の暮らしの中に、幸せと豊かさ、喜びを見いだす…「ありがとう」の精神が、すべての感謝につながるのです。
「運命を切り開くは己である。境遇をつくるも亦自分である。己が一切である。
努力がすべてである。やれば出来るのです」
(万人幸福の栞37頁)
2008年12月02日
天から与えられた我が命…何に使うか?
■光市、母子殺害事件
最愛の妻子を殺された"本村洋"23歳。
青年は、こぶしを握り締めて震えながら言った…「僕は…僕は…絶対に犯人を殺します」
妻子を殺された深い悲しみの中、裁判を傍聴し、マスコミや、国民に訴え続ける。
幾度となく、司法の厚い壁に跳ね返される…それでもなお、敢然と挑み続けた。
自殺を考え、遺書も書いた。絶望の淵を彷徨う青年を励まし、支え続ける人たち。
巨大弁護団に1人で闘う青年。亡き妻と娘のためと、愛と信念を貫いた…。
一審の山口地裁、二審の広島高裁とも「無期懲役」…だが、最高裁は差し戻し判決。
9年にわたる辛い闘いの末、ついに「死刑判決」を勝ち取ったのです。
裁判の場では、被害者の無念の思いを汲み揚げる場がない。
被害者は蚊帳の外におかれたままの、日本の司法界。
"本村洋"は「司法の在り様」を大変革させた人物である。
死刑廃止論者も、肯定論者も、今一度見つめ直さなければならない事件です。
講談社「なぜ君は絶望と闘えたのか」
【心と体の健康情報 - 622】
~幸せな人生を歩むために~
「天から与えられた我が命…何に使うか?」
今の時代、大人も子どもも、なにかイライラして「将来に希望が持てない」…
そんな人が多くなってきている。
子どものとき飼っていた犬が、保健所に処分されたからと、その恨みを30年も持ち続け、殺意を募らせ、 関わりのない市民を殺害するに及んだ、犯人の異常性…人の命を虫けらのように軽んじる、恐ろしい世の中になったものです。
「今週の倫理586号」は、「この世に生を享け、与えられた"命"を何に使うのか?」
がテーマ…日頃、"命"について深く考えることがないだけに、この号を読んで、いろいろ感じるものがあります。
以下、今週の倫理586号から…
自身の人生の中で、絶望の淵に追い込まれるような出来事に見舞われながらも、
その後自暴自棄になることなく、いよいよ自分の人生に対して、真正面から真摯に 向かう人が、時としています。
1999年4月、山口県光市で起こった凄惨な母子殺害事件で、大切な家族を喪った
"本村洋"さんも、そうした中の一人ではないで しょうか。
事件後、公判が進む折々での、ご本人の会見や、事件に関するマスコミ報道等でご存知の方も多いでしょうが、 『なぜ君は絶望と闘えたのか本村洋の3300日』(新潮社 門田隆将著)には、氏の事件直後からの心の葛藤や、また本村さんを支え続 けた、周囲のたくさんの方々との、交流が綴られています。
事件で、18歳の少年が逮捕された。が、「少年法」が壁となって、家庭裁判所の判断によっては、 事件の詳細を遺族さえ知ることなく、闇から闇に葬り去られる可能性がありました。
同様の事件が1997年、神戸で起こり、その猟奇的な犯行は、世間を騒がせました。
担当の刑事の配慮により、本村さんはその被害者(当時11歳の少年)の父親と交流を持つことができ、
同じ境遇を体験した者同士ということで、大変勇気づけられたそうです。
担当刑事は、本村さんが、最愛の家族を守ることが出来なかった自分を責めて、自殺を図ることを危惧していたのです。実際、 本村さんは、一審判決の直前、両親と義母に「遺書」を書いています。
また本村さんは、初公判が迫り、心が落ち着かない時期、勤務先へ辞表を出しています。
会社に迷惑がかかる…との思いからでした。しかしこの時、辞表を受け取った上司は…
「この職場で働くのが嫌なのであれば、辞めてもいい。
君は特別な経験をした。社会に対して訴えたいこともあるだろう。
でも君は、社会人として、発言していってほしい。労働も納税もしない人間が、社会に訴えても、
それはただの負け犬の遠吠えにしかならない。君は社会人たれ」と応え、
また、「亡くなった奥様もそれを望んでいるんじゃないか」と、諭したそうです。
これを契機に本村さんは、単に裁判の終結を静観するのではなく、積極的に社会に対し、被害者として発言し、 事件が社会の目に晒されることで、司法制度や、犯罪被害者の置かれる状況・問題点を、見出だしてもらうことに、全力を注ごうと決意しま した。
この背景には、本村さんの幼少期の闘病経験や、妻子の「命」、さらには犯人の「命」 に必然的に向き合わなければならない状況にあったことから、「死生観」というものの存在を、感ぜずにはいられないのです。
「この世に生を享け、与えられた"命"を何に使うのか?」という大命題は、
常に私たちに突き付けられているものですが、意識することはなかなか難しいものです。
多くの人々に支えられ、そして、天国の最愛の妻子に背中を押され、何度となく挫折感を味わった9年間の長い闘いの末、犯人に、 自らの罪と向き合わせた本村さんですが、見舞われた悲劇は察して余りあります。
「絶望」という状況の中でも、投げやりになることなく、「使命感」をもって取り組まれた本村氏の姿勢は、 個々の人生を歩む私たちに、大切なことを教えてくれるのです。
2008年11月25日
私ほど不幸な人間はいない
■子どもの頃、父親から学んだ「質素倹約」の心得
「上見て暮すな、下見て暮せ…」
自分より良い暮らしをしている人を見ると、つい、うらやましく不足の思いに駆られる。
自分より貧しい人が沢山いることを、忘れないことです…。
今日こうやって、家族揃ってご飯が食べられることに、感謝しなければならない。
いつ、いかなる時も、感謝の心を忘れてはならないのです。
「贅沢は敵」
輪島塗の箸を買ってきて御膳に添えたら、お茶碗がみすぼらしく見えた。
そこで、お茶碗を買い替えた。
そうしたら、麦ご飯ではなく、お茶碗にふさわしい、白いご飯が食べたくなった。
ご飯の次は…おかず…と、贅沢をしだしたらキリがない。
贅沢を覚えたら、後戻り出来なくなる…贅沢は敵だ!
【心と体の健康情報 - 620】
~幸せな人生を歩むために~
「私ほど不幸な人間はいない」
■心のあり様で、幸せにもなり、不幸にもなる
私たちの身の回りに生起する苦難…病気、災難、貧苦などの原因は、その人の心のあり様にあるとされています。
どんなに素晴らしい指導を受けても、受け入れる側が、しっかり受け入れる心を持っていないと、心の転換が図れず、問題は解決しません。
心を、コップに例えると、自分の考え・思いがコップいっぱい満たされているときは、周りの忠告を受けいれようとしません。
人の意見を100%受け入れるには、自分の心のコップを空っぽにしておかなければなりません。
倫理研究所 「今週の倫理580号」より
■幸・不幸のモノサシ(1)
三つの洗面器があります。左から順に20度、30度、40度のお湯が入っています。左手を20度のお湯に、
右手を40度のお湯に浸します。それから、左右の手を同時に、真ん中の30度の洗面器に移します。
20度のお湯に浸けていた手は、「暖かい」と感じるでしょう。
40度のお湯に浸けていた手は、「ぬるい」と感じるでしょう。
同じ30度のお湯なのに、左手と右手は違った感覚を持ちます。
■幸・不幸のモノサシ(2)
園で野宿をしている乞食。道に落ちている500円硬貨を見つけて、
「おお~神様、これで今日の飢えをしのぐことができます」と、手を組み、
天に向かって感謝した。
自動車で通りかかった金持ち…道路に光るものがあったので、スピードを緩め、
よく見たら500円硬貨だった。しかし、クルマを止めずにそのまま走り去った。
乞食には、500円硬貨は大金ですが、金持ちには、ほんのはした金。
落ちていたお金…はした金に見えるか、大金に見えるかは、受け取り手しだいなのです。
■お釈迦様の教え
お釈迦様の時代。インドのコーサラ国に、ガウタミーという女性がいました。
彼女には一人の男の子がいました。結婚して、なかなか子どもが授からなかったのですが、ようやくにして生まれた子どもです。
彼女の可愛がりようは、いささか常軌を逸していました。
ところがその男の子、突然死んでしまいました。よちよち歩きを始めたばかりの、かわいい盛りの死です。
ガウタミーは、子どもの死体をかかえて、街中を走り回ります。
「どなたか、この子を生き返えらせてください」
彼女は狂ったように叫んでいます。何日も子どもを抱えて離さなかったため、腐り始めて、臭いがしています。それでも彼女は、
死体を離そうとしません。
『女よ、わたしがその子を生き返らせる薬を作ってあげよう…』
そう声をかけた人がいました。お釈迦さまです。
そしてお釈迦さまは、ガウタミーに、薬の原料となる"カラシ種"を貰ってくるようにと、お命じになりました。
ただし、条件が一つありました。そのカラシ種は、これまで一度も死者を出したことのない家から貰ってきたものでないと、 効き目がない…と。
ガウタミーは、街中の家々を訪ねて回ります。
「お宅では死者を出しましたか…?」
どの家も、どの家も全部、死者を出したことがある家ばかり…ある家では去年、子どもが死んだと聞かされました。夫が死んだと、
涙ながらに語る妻もいました。
ガウタミーの狂気は、少しずつおさまっていきます。
悲しみに打ちひしがれているのは、自分だけではないことがわかってきます。
どの人も、じっと悲しみに耐えているのです。
彼女はお釈迦さまの所に行きます。『女よ、カラシ種を貰ってきたか?』
「いいえ、お釈迦さま、もう薬はいりません。この子をダビに付してやります」
ガウタミーは力強く、そう答えました…。
新潮社 ひろさちやの「般若心経・第8講」
2008年11月18日
一つの煩悩にすべてを懸ける
■仏教は、人間の心を十段階に分けている
・ 地 獄 (幸福を感じることのできない世界)
・ 餓 鬼 (欲望の世界)
・ 畜 生 (倫理感が欠落した世界)
・ 修 羅 (闘争を好む弱肉強食の世界)
・ 人 間 (精神的なものを求めるが、まだ物欲の強い世界)
・ 天 上 (人間以上に精神的なものを求めるが、油断すると地獄に落ちる世界)
・ 声 聞 (しょうもん・いい人の教えを聞いて、近づこうとする世界)
・ 縁 覚 (えんがく・何かの機縁で、自から悟る世界)
・ 菩 薩 (自から悟り、人をよくしていこうとする世界)
・ 仏
この十段階の世界…別々に存在しているのではない。
一人の人間の中にある、心の動きをいいます。
そして、人は、その心の状態に似合う生き方をします。
「地獄を見てきた。お前は餓鬼だ! 畜生にももとるヤツ。修羅場をくぐった」
など、折に触れ、日常会話でお目にかかる。
が、"天上"から上の段階の言葉は、「仏様のような人」と言ったりする以外、
日常会話で使われることがない。
"物欲"から脱することの難しさ、故でしょうか?
【心と体の健康情報 - 618】
~幸せな人生を歩むために~
「一つの煩悩にすべてを懸ける」
禅の教えによると、人間の心には八万四千もの煩悩があるという。
なぜ八万四千かというと、人間の毛穴が八万四千あると信じられているからです。
その一つひとつの毛穴から、人間の体の中にある"煩悩"が、じわじわとにじみ出てくるのです…それほどに、
人間には沢山の煩悩があるのです。
禅の世界では、厳しい修業を積んでいると、いずれ"悟"が開けてくる。
悟りを得ようと思うなら、煩悩を克服しなければなりません。
ところで、煩悩を克服するとは…どういうことでしょうか?
"悟る"とは…どういうことしょうか?
それは、人間の煩悩をすべて無くしてしまうことでしょうか?
そうではありません。
人間の煩悩は、修行を積んだからといって、無くなるものではありません。
ならば、どうするのか…"たった一つの煩悩にすべてを懸ける"のです。
すると、人間は悟りを開くことができるのです。
つまり人間には、八万四千ものいろんな迷いがあり、いろんなことに迷っているから、自分の持てる力を思いっきり生かして、
人生を充実させることができないのです。
それを「たった一つの何か?」に、人生のすべてを懸けて生き抜けば、
初めて、迷いから吹っ切れることができるのです。
例えば、何度試みても納得できる焼き物が焼けなくて、五年、十年、二十年と、失敗を繰り返し、尚、本物を求めて、 一つのことに懸命に努力し続ける焼物師…月日が経ち…いつしか匠の技を身につけ、悟りを開く…そんな職人の姿を想像すればいいのです。
人間は、一つのことに人生の全てを…頭も、心も、体も、すべてを打ち込んで、統合された姿になったとき、最も大きな能力を発揮し、
充実した姿になっていくのです。
「一つのことにどこまで没頭し、
なりきれるか」…ということです。
衆議院議員 小野晋也著「日本人の使命」より
「自分が志し、目指したその道を天職と思い、一生やり続け、生き抜く…」
それが唯一、本物への道であり…何か一つ、一生やり続けるものを見つける…
禅の教えの「たった一つの煩悩に、すべてを懸ける」に、相通じるのです。
2008年11月11日
天職・一生やり続けるものを見つける
■人生が面白い
職業に 上下もなければ 貴賎もない
世のため 人のために役立つことなら 何をしようと自由である
しかし どうせやるなら 覚悟を決めて 十年やる
すると 二十歳からでも 三十までには一仕事できるものである
それから十年本気でやる
すると 四十までには頭を上げるものだが
それでいい気にならずに また十年頑張る
すると 五十までには群を抜く
しかし 五十の声を聞いたとき 大抵の者は息を抜くが それがいけない
これからが仕上げだと 新しい気持ちで また頑張る
すると 六十ともなれば もう相当に実を結ぶだろう
だが 月並みの人間は、この辺で楽隠居がしたくなるが
それから十年頑張る
すると 七十の祝いは盛んにやってもらえるだろう
しかし それからまた十年頑張る
すると この頃が一生で一番面白い
【心と体の健康情報 - 616】
~幸せな人生を歩むために~
「天職・一生やり続けるものを見つける」
■「仕事っていうのは…」
小野二郎さんは鮨を握り続けて57年。この春話題になった「ミシュランガイド東京版」で、世界初の鮨の三ツ星店に選ばれた。
三ツ星の評価を得てからは、3か月先まで予約でいっぱいという。
一日に600個(30人前)は握るが、いくら握っても肩や手首は凝らないし、腰にも来ない。
57年握ってきて、動作が型になり、力むことがない。
三ツ星になったことがすごいこととは思っていない…それが店の評価のすべてじゃない…大事なことは、与えられた仕事を手抜きせず、全うする…これに尽
きると思うんです。
そもそも自分は、鮨職人になりたかったわけではない。料理の才能だって大したことはない。3年前、”現代の名工”に選ばれた時も「どうして自分が?」というのが素直な気持ちでした。
7歳で奉公に出されて、頼る身寄りも帰る家もない。首になれば飢え死にするしかないから、目の前の仕事を必死にやるしかなかった。だから、この仕事は
合わないとか、向いていないとか、そんな若い人を見ていると、一言言いたくなる。
「仕事っていうのは、合う合わないじゃなく、こっちから努力して合わせていくものだ…」
読売新聞「時代の証言者」から抜粋
以下は、”夜回り先生”水谷修先生、「明日を求めて…こどもたちへ」からの抜粋です。
遠藤明さんという…73歳の江戸前寿司職人のお話をします。
江戸・四谷で「まとい寿司」というお店を、もう半世紀近くやっている。
彼の口癖は、「俺たち寿司屋は、ただ魚を切って売る魚屋じゃない。
塩をしたり、酢や昆布で締めたり、一手間かけてお客に魚を出す。これが職人の仕事だよ」
東京湾でタンカーが炎上し、東京湾の魚が捕れなくなったときは、店をしめた。
それほど江戸前にこだわった人でした。
私は、彼と今から30年前の21歳の時に知り合った。
当時も寿司は大変高価で、学生ぶんさいがカウンターに座って、お好みで注文して食べることのでき
るようなものではありませんでした。
それでも、アルバイトでお金を貯めて、有名なお店に半年に一度は通っていました。
4月でした…私は、アルバイトで稼いだ1万円を財布に入れ、当時有名だった”まとい寿司”の暖簾をくぐりました。
カウンターに座り、圧倒されました。周りには、私が見知っている有名な俳優や、政治家たちが座っていました。私は、遠藤さんに言いました。
「私は学生です。今日は1万円しかありません。これで支払えるだけの寿司を食べさせてください…」
それを聞いた遠藤さん。
「学生さん、好きなだけ食べていきな。あんたのその1万円、汗流して苦労して貯めた金なんだろう…あんたの1万円は、この店に来る有名な連中の10万円
以上の価値がある…いいかい、学生さん…客を育てるのも、寿司屋の職人の仕事なんだよ…」
それ以来、私は遠藤さんを父のように慕い、30年間お世話になってきました。
遠藤さんの口癖は、「俺の寿司を食べて、お客さんが幸せな顔をしてくれる。それが、俺の一番の幸せだよ…」
彼の寿司は、客によって…また箸で食べるのか、手で食べるのかによって…シャリやネタの大きさ、形が変わっていました。憎いほどの本物の職人でした。
「本物になる」ということは、実に簡単なことです。
「自分が志し、目指したその道を天職と思い、一生やり続け、生き抜く…」
それが唯一の本物への道です。何か一つ、一生やり続けるものを見つけることですね…。
2008年09月30日
嫌なことを進んで受け入れる
■韓国大河ドラマ「ファン・ジニ」
妓生(キーセン)を描いた、韓国の大河ドラマ「ファン・ジニ」(毎週日曜夜NHK・BS/24回)が終了した。次週が待ち遠しくなる、 見ごたえのあるドラマだった。
妓生の娘に生まれ、芸妓として生きることを運命づけられたファン・ジニ。
芸を身につけるための厳しい師匠との確執。ライバル妓生との競い合い。
ジニに思いを寄せる、宮廷の男たちとの悲恋…。
苦しみの中で、ジニは真の芸道を究めていく…。
身分が低く、差別と偏見の中で生きなければならない妓生。 厳しい修行に耐え、芸妓のトップに上り詰めた一握りのキーセンのみが、認められ、
尊敬される身分になれる。
「チャングムの誓い」は、宮廷料理と、当時の医学を極めるストーリーでした。
「ファン・ジニ」は、妓芸と舞の奥義を追求し、韓国ドラマ史上最も豪華で、
艶やかな"衣装"が、毎週見る者の目を楽しませてくれる…。
この二つのドラマから、中世韓国宮廷文化を垣間見ることが出来た。
※ファン・ジニは、16世紀朝鮮王朝時代に実在しだ妓生。当代きっての詩人であり、芸と音楽をこよなく愛する芸術家として、 後世にその名を残す。
【心と体の健康情報 - 604】
~幸せな人生を歩むために~
「嫌なことを進んで受け入れる」
マザーテレサが偉大なのは、腐臭ただよい、うじ虫が湧いている乞食を、一人ひとり慈しみ、抱きしめる…その、 誰も真似のできない姿にあります。
「乞食の姿をしてはいるが、本当はイエス・キリストなのです」と、マザーテレサは言う。抱きしめているのは、乞食ではなく、
イエス・キリストなのです。
「イエスさまは、私がどこまで信心しているかを試すため、私が一番受け入れにくいものに姿を変えて、私の目の前に現われたのです」と…。
私たちの周りには、顔を合わすのも、口を利くのも嫌な人って、いますよね…。
それは、ご近所の人であったり、勤め先の上司であったり、お姑さんだったりする。
イエス・キリスト、或いは仏さまが、その人に姿を変えて現れてきた…と思うようにすると…どうでしょう。そう思えば、
どんな嫌な人でも受け入れることができるようになるでしょう…。
「自分にとって一番受け入れにくい人が、長いスパンで人生を見れば、自分を一番成長させてくれる人になる」
逆に、付き合って楽しい人は、自分を堕落させてしまう人であることが多い…。
私が社会に出て、最初に勤めた会社…営業で採用された4名の新入社員が、営業部のそれぞれの課に1名ずつ配属された。
私は営業一課、2年先輩のTさんが、私の直属の上司になった。Tさんは、いうところの鬼軍曹。徹底的に、とことんしごかれた。
他の部署の3人はと見れば、しごかれている気配もなく、毎日楽しそうに仕事をしている。
当時、「何で、私だけが…」と恨めしく思い、T先輩の部下になったことを、うとましく思ったものです。T先輩は几帳面で神経質… 箸の上げ下ろしまで口やかましく言う…姑の嫁いびりのように、毎日叱られていました。
2年後、今度は営業二課に配属された…課長は男前の遊び好き。
営業マン必修? 酒・バクチ(花札・マージャン)・女遊びなど、課の先輩たちから教え込まれた。三年目は地獄から天国へ移ったよう…
居心地が良かった。
3年勤めて、更に大きな夢・目標にチャレンジしようと退職…東京の某社へ再就職した。
その後、T先輩も会社を辞められたと…風の便り。今はどこでどうしておられるか…?
お会い出来たら、当時のお礼を言いたいものです。
辛かった入社1~2年目…T先輩の厳しい指導のお陰で、今の私があるのです。
2008年09月16日
ゆで蛙
■私の好きな言葉 ユダヤの格言
人は転ぶと 坂のせいにする
坂がなければ 石のせいにする
石がなければ 靴のせいにする
人はなかなか 自分のせいにはしたがらない
日頃の私達の姿を、痛烈に皮肉った言葉です。
問題を周りのせいにしている間は、正面から問題に取り組もうとせず、
いつまでも問題は解決しないでしょう。
ですから、「会社の業績が悪いのは、世の中が不景気のせい」と言っている間は、
決して業績が良くならないでしょう。
人と交わる時、口にしてはいけないのは、「愚痴る」「言い訳をする」
「人の悪口を言う」の三つ。この三つのどれかを言いそうになったら、
ユダヤのこの格言を思い出すことです。
【心と体の健康情報 - 601】
~幸せな人生を歩むために~ 「ゆで蛙」
[蛙の話ーその1]
水が入った大鍋の中に、捕まえてきた何匹かの蛙を入れた。
水を得た蛙は安心し、のんびり泳いでいる。
「バーン!」、突然机を叩いた。蛙は驚き、慌てて鍋から飛び出していった。
今度は、用意していたお湯を鍋に入れ、ちょうどいい湯加減にして、再び蛙を入れた。
蛙はゆったり手足を伸ばし、いかにも気持ちよさそうに泳いでいる。
鍋を下から温めはじめた。
徐々に水温が上昇し、熱湯になった。すると蛙は茹でられて、死んでしまった。
同じように、机を「バーン!」と叩いていたら、どうだろう。
蛙は状況の変化に気付き、飛び退いただろう。
しかし、ぬくぬくとぬるま湯につかっているうちに、蛙はつい油断をしてしまい、
気付いた時はもう遅過ぎた。飛び上がるエネルギーを失い、死んでいった。
人生も経営も同じだ。ぬるま湯が徐々に熱せられ、水温が上がってきていることに気付いていながら、
昨日まで何事もなく生きてこられたことにかまけて、危機感を失ってしまう。
昨日も今日も変わらない。明日も今日と同じだろうと思っているうちに、命を失う羽目に陥る。皆さんよくご存知の、「ゆで蛙」
のたとえである。
地球温暖化に、何とかせねばと危機意識を持ちながら、昨日と変わらぬ生活をしている私たち…蛙の逸話だと、笑ってはいられらい…。
[蛙の話ーその2]
桶には、おいしいミルクが入っている。その桶を二匹の蛙が覗き込んで、「おいしそうなミルクがある…一緒に飲もう」と、
桶の中に飛び込んだ。
お腹一杯ミルクを飲んで、ご機嫌の蛙たち。そろそろ外に出ようと、桶の縁の方へ泳ぎ出した。ところがどうしたのだろう。
思うように体が前に進まない。体全体にミルクの幕が張ってしまい、身動きが取れない。もがき続けているうちに、体力が消耗しだした。
「諦めたら死んでしまう。もう少し頑張ろう…」と、根性蛙が声をかけた…が、
「僕はもうクタクタだ…手も足も動かなくなった。もうおしまいだ」
もう一匹の根性なし蛙は、泳ぐのを諦めて…溺れ死んだ。
一方の根性蛙、命のある間は…と、必死に手足をバタつかせ、もがきにもがき通した。
すると、いつしかミルクがバターになっていた。
根性蛙、バターの上を歩いて無事桶の縁にたどりつくことが出来た。
坂爪しょう兵「和尚が書いたいい話」より
一所懸命やれば 大抵のことが出来る
一所懸命やれば 誰かが助けてくれる
一所懸命やれば 何事も面白くなる
大坂のN教育研究所の研修を受けた時に、教わった言葉です。
人生を振り返ると、幾度か"ここぞ"という時がある。
そんな時、懸命に努力していると、思わぬ人が手をさしのべてくる…
そのお陰で今がある…その時のご縁が、未来へと導いていく…。
ゆで蛙
■私の好きな言葉 ユダヤの格言
人は転ぶと 坂のせいにする
坂がなければ 石のせいにする
石がなければ 靴のせいにする
人はなかなか 自分のせいにはしたがらない
日頃の私達の姿を、痛烈に皮肉った言葉です。
問題を周りのせいにしている間は、正面から問題に取り組もうとせず、
いつまでも問題は解決しないでしょう。
ですから、「会社の業績が悪いのは、世の中が不景気のせい」と言っている間は、
決して業績が良くならないでしょう。
人と交わる時、口にしてはいけないのは、「愚痴る」「言い訳をする」
「人の悪口を言う」の三つ。この三つのどれかを言いそうになったら、
ユダヤのこの格言を思い出すことです。
【心と体の健康情報 - 601】
~幸せな人生を歩むために~ 「ゆで蛙」
[蛙の話ーその1]
水が入った大鍋の中に、捕まえてきた何匹かの蛙を入れた。
水を得た蛙は安心し、のんびり泳いでいる。
「バーン!」、突然机を叩いた。蛙は驚き、慌てて鍋から飛び出していった。
今度は、用意していたお湯を鍋に入れ、ちょうどいい湯加減にして、再び蛙を入れた。
蛙はゆったり手足を伸ばし、いかにも気持ちよさそうに泳いでいる。
鍋を下から温めはじめた。
徐々に水温が上昇し、熱湯になった。すると蛙は茹でられて、死んでしまった。
同じように、机を「バーン!」と叩いていたら、どうだろう。
蛙は状況の変化に気付き、飛び退いただろう。
しかし、ぬくぬくとぬるま湯につかっているうちに、蛙はつい油断をしてしまい、
気付いた時はもう遅過ぎた。飛び上がるエネルギーを失い、死んでいった。
人生も経営も同じだ。ぬるま湯が徐々に熱せられ、水温が上がってきていることに気付いていながら、
昨日まで何事もなく生きてこられたことにかまけて、危機感を失ってしまう。
昨日も今日も変わらない。明日も今日と同じだろうと思っているうちに、命を失う羽目に陥る。皆さんよくご存知の、「ゆで蛙」
のたとえである。
地球温暖化に、何とかせねばと危機意識を持ちながら、昨日と変わらぬ生活をしている私たち…蛙の逸話だと、笑ってはいられらい…。
[蛙の話ーその2]
桶には、おいしいミルクが入っている。その桶を二匹の蛙が覗き込んで、「おいしそうなミルクがある…一緒に飲もう」と、
桶の中に飛び込んだ。
お腹一杯ミルクを飲んで、ご機嫌の蛙たち。そろそろ外に出ようと、桶の縁の方へ泳ぎ出した。ところがどうしたのだろう。
思うように体が前に進まない。体全体にミルクの幕が張ってしまい、身動きが取れない。もがき続けているうちに、体力が消耗しだした。
「諦めたら死んでしまう。もう少し頑張ろう…」と、根性蛙が声をかけた…が、
「僕はもうクタクタだ…手も足も動かなくなった。もうおしまいだ」
もう一匹の根性なし蛙は、泳ぐのを諦めて…溺れ死んだ。
一方の根性蛙、命のある間は…と、必死に手足をバタつかせ、もがきにもがき通した。
すると、いつしかミルクがバターになっていた。
根性蛙、バターの上を歩いて無事桶の縁にたどりつくことが出来た。
坂爪しょう兵「和尚が書いたいい話」より
一所懸命やれば 大抵のことが出来る
一所懸命やれば 誰かが助けてくれる
一所懸命やれば 何事も面白くなる
大坂のN教育研究所の研修を受けた時に、教わった言葉です。
人生を振り返ると、幾度か"ここぞ"という時がある。
そんな時、懸命に努力していると、思わぬ人が手をさしのべてくる…
そのお陰で今がある…その時のご縁が、未来へと導いていく…。
2008年08月08日
「ありがとう」のことば
■心に残ることば
★NHK土曜ドラマ「マチベン」"安楽死を裁けますか?"から…
「誰かのための人生ではなく、自分のための人生でありたい」
「自分のための人生ではなく、誰かのお役に立つ人生でありたい」
さて、あなたの人生はどっち?
どちらの人生にも、その生き方には、深い意味があると思うのです…。
- 私の母親…16歳で嫁ぎ、角隠しの下から、
初めて夫となる人の顔を見たという。
夫が74歳で亡くなるまで…夫と姑に仕え、6人の子どもを育てあげ、したいことも我慢して、ひたすら家族の為に尽くし抜いた人生でした。 - 広島県呉の、旧海軍仕官学校を訪れ、2700柱の特攻英霊の遺書・遺品を見て…今に生きる私たち… 国のために散っていった若者たちの念いを、無駄にしてはならないと思う。
【心と体の健康情報 - 591】
~幸せな人生を歩むために~「ありがとう」のことば
ありがとうは 人の心を動かす魔法の言葉
ありがとうは 人間の最大の喜びの表現
ありがとうは 慢心しがちな自分を、
謙虚な自分へと導いてくれる
我が社は来年3月、起業30周年を迎える。
共に歩んできた代理店の皆様と、7月から「30周年ありがとう」キャンペーンを実施している。
「ありがとう」…"感謝の心"が湧き出てくるこのことば…日本語で、最も美しいことばと言われている。
ありがとうで心に残るのは、亡き昭和天皇… 左手で帽子をちょこっと持ち上げ、頭を下げて「あ・り・が・と・う」…よく見うけられた光景です。
ありがとうを言う…その奥には、相手に対する感謝の心があります。
感謝の心は、謙虚な気持ちから生まれてきます。ですから「ありがとう」と「感謝」と「謙虚」はひとつにつながっていて、
ありがとうは、言った人の人柄をより高める働きがあります。
修養団の中山靖雄先生は、ありがとうの反対語は、「当たり前」と言っている。
「不満」ではなくて、「当たり前」が反対語になるのです。
豊かで、平和な時代を満喫して暮す私たち。欲しいものは、何でも当たり前に手に入る。
そして、知らず知らずのうちに、「感謝の心」を忘れてしまっている。
近頃の世相を見ると、今まで「当たり前」に思われていたことが、壊れ始めている。
今までのように、欲しいものが当たり前に、手に入らない時代になろうとしている。
そのことを不平に思い、人のせいにし、犯罪に走る者も出てくる。
贅沢な暮らしにどっぷり浸っていながら、尚不足に思う私たち。
これから先の世の中…年を追うごとに暮しにくくなるだろう。
入りに見合う質素な暮らしに、生活のスタンスを切り替えていかなければならないが、容易ではない。
アメリカでは、道を歩いていて肩がちょっと触れただけでも「エクスキューズミー」の声が返ってくる。とっさに応えようとするが…
「ユアー・ウェルカム」が、声にならない。
エレベーターに乗り合わせて、見ず知らずの人に「グッドモーニング」…笑顔の挨拶を交わすアメリカ人。
日本では、同様にエレベーターに乗り合わせても、見ず知らずの人と挨拶を交わすことは無い。エレべーター内の、
あの気まずい沈黙を無くすには、率先して「おはようございます」「こんにちわ」と、笑顔の声掛けをすることでしょう…。
いつも習慣的にありがとうを言っている子どもは、脳のある部分が発達して、
感性豊かな人間に成長するという。
反対に、日頃「死ね!」「きたない!」など、相手を罵倒する言葉を使っているイジメっ子は、脳の感性をつかさどる部分の発達が遅れる…
と、学会で報告されている。
ありがとうと、声をかけた水の結晶が…こんなに美しく、
「ばかやろう」を投げかけた水の結晶が…こんなに乱れ醜いとは。"水の不思議"を知った時の驚きを思い起こす。
人体の70%が"水"。いつもありがとうと、感謝の心で接していると、あなたは…。
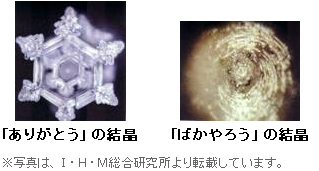
2008年06月13日
話し上手になるには(2)
■「妖怪・さとり」と「千葉周作」
古来から、日本に語り継がれてきた"妖怪"の一つに「さとり」という鳥がいる。
この「さとり」という妖怪、人の心を見透かす力を持っている。
ある時、「さとり」に出会った木こりが、生け捕りにしようとした。
すると「さとり」は、「我を生け捕ろうと思っただろう…」と。
次いで木こりは、斧で打ち殺そうとしたが、やはり見透かされてしまった。
木こりは、これではどうにもならないとあきらめ、再び木を切り始めた。
突然、斧の頭が柄から抜けて、飛んでいった。直撃を受けて「さとり」は死んだ。
<その1>江戸時代の剣客"千葉周作"は、この寓話を引用して言った。
「流石のさとりも、無念の斧には打たれし」
斧には心がなく、流石の妖怪、見透かす術が効かず、打たれてしまった。
続けて千葉周作…
「剣術も、この"無想"の場に到れば、百戦百勝疑ひなし、千辛万苦の労を積み、
"無想"の場に進むべし」と…。
千葉榮一郎扁「千葉周作遺稿」
<その2>米沢興譲教会の田中信生宣教師、「心の力はこう使う」と題した講演で、この寓話を引用。巧みな語り口で、
聴衆を引きつけていく…。
(講演テープご希望の方は、米沢興譲協会へ)
【心と体の健康情報 - 575】
~幸せな人生を歩むために~
「話し上手になるには…(2)」
■話し上手になるためのチェックポイント
- 最初に話す内容を、「一つ何・二つ何」と前置きしてから、話し始めるといい
- 普段のままの話し言葉で話す
- 「例え話」や「実例」を入れて、話しを分りやすくする(状況は詳細に話す)
- 大切なところは「繰り返す」
- 短いセンテンスで話す
- 聴衆のAさんBさんと、話のつど相手を変え、視線を送ります
1対1で会話するように語りかけます - 時々「アイコンタクト」を入れ、聴き手とうなずき合う
- 「大きな声」で語りかけるかと思えば、「声を小さく」したりして、話しに抑揚をつけ、聴衆を引きつける。
- 両手を前に組んで話さない。両手は、大きく小さく動かして、話しを盛り上げる道具に使う(緊張すると、 手が動かせなくなります)
- 「ユーモア」の技術を取り入れる
(言葉遊び・駄じゃれ、面白い話はメモしておいて、笑いを誘う材料にする) - 終始「笑顔」を絶やさず、ありのままの自分を出す
人と話をするとき、話し上手になるより、聞き上手になることの方が大事です。
それが出来なくて、話し手の言葉を取って邪魔をしたり、人の話を自分の方に持っていって、得意になって話す(私のことです)…
まず人の話を聞くのが、思いやりというもの…しゃべり過ぎず、言葉足らずくらいが、丁度いいのです。
以下は、話し上手の事例です。
日頃、人前で話すことを生業とする、米沢興譲教会・田中信生宣教師の講演導入部分です。最初に笑いを誘ってほぐし、
普段と変わらぬ語り口で、センテンスは短く、分りやすい語り口で、聴衆の心を引きつけていきます…。
|
♪北方は美人が多いですね。(会場から拍手) 皆さんね…、今は21世紀に入りましたけれどもォ、 母 「お金のために、そう…一生懸命勉強しろよ~」 お母さんが、息子にこう言ったというんですけどね…。 日本人は、お金を得るために、最大限の努力をする。 |
(以下略)
田中信生先生の講演は、ジョークを織り交ぜ、聴衆を笑いの渦に巻き込んでいく。話が面白いから、もっといろいろ聴きたいと、
録音テープを買っていく…。
「型破り痛快人生」の中村文昭氏の講演もそう…地場産センターの定員300名の会場に、400名も詰めかけ、
入り口のドアの外にまで人が溢れた。
「ツキを呼ぶ魔法の言葉」の五日市剛氏の講演もそう…何度聴いても飽きません。
一方、こうしたタイプとは反対に、静かに淡々と話すのに、聴衆をぐいぐい引き込んでいく…そんなすごい先生がいるのです。
「一隅を照らす人生」の、作家・神渡良平先生や、「歌づくり人生」と題して、自らの生い立ちを語る、作曲家・遠藤実先生などがそうです。
2008年06月06日
話し上手になるには
■エベレスト
15番目の峰とされていた山が、世界最高峰とわかったのは1852年のこと。
101年後に、ヒラリー卿の英国隊が初登頂。そのヒラリー卿の家に飾られていた写真を見て、若きプロスキーヤー三浦雄一郎は、
エベレストに惚れたという。
70年に、8千メートルから滑降した。03年には、当時世界最高齢の70歳で頂上に立った。
異彩を放つエベレスト暦に、先月5月26日、新たなページを書き加えた。75歳7ヶ月で、2度目の登頂を果したのです。
エベレスト頂上へは、15時間かけて登って下りた。
今回に備えて、心臓を手術した。左右に5キロの鉛を入れた靴を履き、重いリュックを背負って街を歩いた。
電車に乗れば、つり皮で懸垂…老いと競い、「75歳の夢」を追った。
「涙が出るほど厳しくて、辛くて、嬉しい」と、頂上から言葉が届いた…。
5/28 朝日新聞「天声人語」
8千メートルの半分にも満たない富士山でも、気力を振り絞って登頂しなければ、頂上には立てない。高山病にも苦しめられるだろう。
私が三浦雄一郎の歳になった時、どんな夢に向かって努力しているだろうか?
患ってベッドに臥せ、生きる希望を無くした老人にはなりたくない。
【心と体の健康情報 - 573】
~幸せな人生を歩むために~
「話し上手になるには…」
「私は話ベタ。だから人前で話すのは大の苦手」という人…本当にそうでしょうか?
話し上手になりたかったら、答えは簡単です…下手でも何でも、あらゆる機会をとらえて、積極的に人前で話すようにします。場数を踏み、
経験を積めば、誰でも上手に話せるようになるのです。
民法TV、ラーメン選手権大会日本一に3度も輝いた、「博多・一風堂」河原成美社長。会社が大きくなって、人前で話す機会が増え、
話ベタを苦にするようになった。
河原氏とは、2年間京都で机を並べ、論語を学んだ。その時河原氏、話ベタを何とか克服しようと「1年間100回講演」を公言した…
「呼んでくれるなら、どこへでも…」
始めた頃は、全身汗びっしょり…しだいに話せるようになり、話し方のコツを掴み、目標の100回に近づく頃には、
聴衆を笑わせるまでに、上達していた。
その間、石川・福井両県の四つの経営者団体にも誘われて、講演している。
20代の頃の私、結婚式のスピーチが苦手で…悩みの種だった。わずか数分間人前で話すだけなのに、
スピーチ事例集を買ってきて原稿をつくり、1週間も前から練習を繰り返したものです。
そんな話ベタ、上がり症を克服しようと、28歳の時店を畳んで、営業では最も厳しい住宅会社に就職…セールスの世界に飛び込んだ。
数年後、大勢の前でリラックスして話せる私に変身していた。
話ベタに悩むあなた…喫茶店などで、親友や恋人と会話を楽しんでいる時は、実に話し上手なのです。 人前で"普段通り"気軽に話すことができるようになれば、あなたは話上手になるのです。
例えば、ゴルフで良いスコアを出した時や、海外旅行での失敗談など、実に生き生き、ジェスチャーたっぷりに、
目を輝かせて話すじゃないですか…。
それが人前に立った時、まったく別人のようになり、話ベタになってしまう…。
何故なんでしょう?
大勢の前で話し始める時、大概「改まった言い方」をします。
普段使わない話し言葉・口調・声・態度で…しかも、上手に話そうとするのです。
結婚式の媒酌人、スピーチの出だし…「本日はお日柄もよろしく、ご多忙にもかかわりませず、ご臨席を賜りまして、
心より厚く御礼申し上げます…」
普段使わない言葉で、改まった口調で話そうとするから、うまく話せないのです。
緊張で声が上ずり、上がってしまう…これではいつまで経っても、苦手意識が抜けません。
私が尊敬する、金沢支店元支店長の女性。会議の席で話す時「おいね、そんながやちゃ~」と、生まれ育った辰口弁丸出しの、
普段のままの口調で、手振り身振り、笑顔満面、身を乗り出すようにして語りかける。
そのスピーチ、実に明るく、親しみがあって、聞いている私たちの心に響くのです。
ですから、結婚式のように、改まったスピーチであっても、友人に語りかけるような話し方をすればいいのす。
「今日は…お忙しい中を…幸せいっぱいの…お二人の門出の席に…お集まりいただき…ありがとうございます」でいいのです。
「本日は…」と、改まった口調で話し始めるから、「…お日柄もよろしく、ご両家におかれましては…誠におめでとうございます」と、
ロレツの回らない、無味乾燥な話し方になってしまうのです。
普段通りに、「今日は…」から話し始めれば、いつもの語り口になるのです。
もう一つ大切なポイントは…会話は、思った以上に「センテンス」が短いのです。
吸って、吐いて…呼吸に合わせた、短いセンテンスで話します。
原稿でまとめた文章は書き言葉…一区切りの文章が長くなりがちです。
センテンスの長い文章を、そのまま話そうとすると、吸って吐いての呼吸バランスが乱れ、平常心が保てなくなります。
ゴルフのスウイングもそう…スウイング・スタートで軽く吸って、ダウンスイング・インパクトで「フゥ~」と吐く…すると、
力みのないナイスショットになる。
"三井住友"で吸って、"ビザカード"で吸った息を吐く…そんな要領です。
2008年05月23日
上がり性克服法(2) 沈黙の恐怖
■今日のことば
~ニューヨーク州立大学病院の壁に書き残された詩~
大きな事をなし遂げるために 力を与えてほしいと神に求めたのに、
謙虚を学ぶようにと 弱さを授かった。
より偉大なことができるようにと、健康を求めたのに、
より良きことができるようにと、病弱が与えられた。
幸せになろうとして、富を求めたのに、
賢明であるようにと、貧困を授かった。
世の人の称賛を得ようとして、成功を求めたのに、
得意にならないようにと、失敗を授かった。
求めた物は一つとして与えられなかったが、
願いはすべて聞き届けられた。
神の意に添わぬ者であるにもかかわらず、
心の中で言い表せないものは、全て叶えられた。
私はあらゆる人の中で、最も豊かに祝福されていたのだ。
神渡良平著「下座に生きる」から
【心と体の健康情報 - 569】
~幸せな人生を歩むために~
「上がり性克服法(2) 沈黙の恐怖」
結婚式に招かれ、来賓スピーチを依頼された日から、憂鬱な日々が始まる。
原稿を作り、何度も練習して暗記して臨んだ当日。披露宴はとどこおりなく進行し、自分の番が近づいてくる…食事は喉を通らず、
胸はドキドキ…。
いよいよ指名されマイクを取り、お祝いのスピーチ…が、途中で真っ白…
気は焦れども次の言葉が出てこない。こんな経験を何度したことか…
スピーチ馴れしていない人…マイクの前に立ったとたん、上ってしまい、頭の中が真っ白。
次に話す言葉が出てこない。
この沈黙の十数秒間が恐怖です。スピーチが上手になりたかったら、カラオケと同じ…場数を踏むことです。場数を踏めば、
誰でも上手になれるのです。
以下、理念と経営6月号「リーダーのための心理学」から…
|
講演の後の懇親会で講師の先生、それまで締めていたネクタイを外して、 人間は、自分のことは気になるけれども、他人のことは、当の本人が気にするほどには、関心がない。ですから、 顔が赤くなると気に病んでも、周りは以外と気にしていない…そういうものなのです。 |
「感性論哲学」 の創始者、芳村思風先生の講義…途中で、突然沈黙してしまうことがある…1分くらいだろうか? 沈黙の間…聴講生は「どうしたんだろう」と、半分居眠りしている人まで目を覚まして、先生の方を見る。
哲学を講義する先生の話は難しい。1時間もすると、まぶたが重くなってくる。
頃合い好しと先生…沈黙の後、突然「なんちゅうか、かんちゅうか、ほんちゅうか…」と、素っ頓狂な声を発する…
会場はド~ッと笑いに包まれる。
先生は、聴講生の眠気をさます手段として、しばし"沈黙"の後、このようなダジャレを言う。何度か受講する中、数えたら、
5つのネタを使い分けていた。
受講中…突然の沈黙…"そら来た!"…会場は大きな笑いに包まれる。
沈黙は決して怖くないということを、私は学んだ。でも、実際の所、30秒間マイクを前に沈黙するのは、度胸のいることです。
私は、次の文句に詰まることがあっても、決して慌てたりせず、"余裕をもって"沈黙…これから話す内容が、
当初話す予定とは違っても慌てず、会場の雰囲気に合わせて、笑顔で話し出すようにしている。
ある時…壇上に上がり、300人ほどの聴衆の前で選手宣誓のように、私がスローガンを一節唱和した後、
続いて会場の皆さんが大きな声で復唱する。
そんな名誉な役を頂いたことがある。
登壇し、マイクの前に立った…スポットライトがまぶしく、私に向けられた瞬間、目の前が真っ白になった! 沈黙…会場も沈黙…
思い出せないまま沈黙…
やおらお尻のポケットから原稿を取り出し、マイクの前に広げ、高らかに唱和した。
そして、無事役目を果した。その沈黙の時間、どれくらいだったのだろうか?
席に戻って、親しい人から「あの沈黙…何か意味があるの?」と言われた。
私が、あがってしまい、頭が真っ白になったことには、気付いていないような振りだった。
2008年05月16日
上がり症克服法
連休明けの8~13日、ロサンゼルス・メキシコ・クルーズの旅を楽しんだ。
写真(1)は、ロサンゼルス/サンベドロ港から、メキシコに向け出航する直前、7万トン豪華客船、モナークオブザシーズ号12階デッキより、港に停泊する5万トン級客船と、
ロサンゼル市街を遠望する…
当日の乗船者は、2700名…乗務員860名を加えての出航。韓国や中国からの観光客もちらほら…私の部屋は3F窓在りのツイン
(窓なしの部屋は安い)…
7階~8階と、上階になるほど客室が豪華で高くなる。
気温は思ったより低く、出発時の金沢と変わらない…半袖では肌寒さを感じた。
毎晩、豪華な晩餐会が催され、シアターでショーを楽しみ、夜更けまでカジノで熱中…タイタニック気分を十二分に満喫できた。
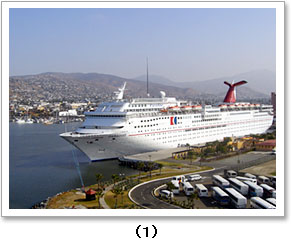

【心と体の健康情報 - 567】
~幸せな人生を歩むために~ 「上がり性克服法」
1ヶ月くらい前に、5歳の頃"目もらい"が出来て、近所の目医者で切り取った話をした。その医者"藪"だったのか、 それ以降瞼が内側にかぶり、"逆マツ毛"に悩まされるようになった。
まつ毛が伸びてくると眼球を傷つけ、結膜炎になる…むじむじ・むずかゆい。
3ヶ月に一度、逆マツ毛を抜きに眼科へ行く。マツ毛を抜こうとすると、痛みを記憶していて、瞼がケイレンする。医者は老眼…
ピンセットの手元が狂って肉をつまんだりするから…尚更です。
60年間逆マツゲを抜き続けた私。敏感症になり、春埃っぽく、紫外線が強くなってくると、目が赤く充血し、涙が出てくる。
20歳前後の思春期の頃はひどかった。女性と向き合うと、緊張で目がむじかゆくなり、顔が耳まで真っ赤になり、
相手を正視できなくなる。学生の頃から人前に立つのが恐怖…会社では、「あ~吉村さんて純情!顔が真っ赤」と、
年下の女子社員にからかわれた。赤面症、対人恐怖症…そんな症状に悩まされたのです。
27歳の時結婚したが、披露宴の席でお礼の挨拶が満足に言えなかった。
これではダメだと一念発起。最も厳しい営業…住宅セールスの世界に飛び込んだ。
営業活動でもまれる中…いつしか症状が消えていった。
以下、理念と経営「リーダーのための心理学」からの抜粋です。
何か心配事があるときに、そこに注意がいく…気にしまい、人に覚られまいと思えば思うほど、よけいに強く反応してしまう。
そんな悪循環に悩まされる。
この症状を、心理学では「とらわれの機制」という。
「私は上がり性、人と接するのが大の苦手…」。若い頃、こんな先入観に悩まされてきた。
なのに、セールスの成績はトップクラス。上がり性で営業が苦手と公言しながら、毎月コンスタントに契約を取ってくる。
お客様には、「この人まじめ、誠実そう…この人に任せれば大丈夫だろう…」と見える。
上がり性が、私の最大の武器になったのです。
ある時気付いた…パーティの司会をした人が、終了後「めっちゃ上った…」と言う。見ている私には、本人が言うほどに、 上っているように見えなかったのです。
大切なのは、上がり症を隠そうとするのではなく、上がり症を"公然"と人前にさらし、上がり症をトレードマークにして生きていく… 不安があっても隠さず、ありのままの自分をさらけ出していく…要は、「こんな私で悪かったね…」と、開き直ってしまえばいいのです。
結婚式のスピーチが大の苦手な人…流ちょうにかっこよくスピーチしようなどと、欲張りなことをと思うから、余計に上ってしまう。 上るのを承知で、ありのままの自分で、"スピーチが下手でごめんなさい"と、肩の力を抜いて臨めば、ビックリするくらい余裕をもって、 上手に話せるものです。
明らかにあがって見えて、声が震えている人…懸命にスピーチしている姿に、聴き手は何故か"感動"するものです。
形式に囚われ、心に響かない、どこかのお偉さんの、形式ばった無味乾燥なスピーチより、ずっといいのです。
親しい友人の前では、何時間でも会話を楽しんでいるのに…「私は話ベタ」と、人前で話をするのを苦手に思っている…。
なら、苦手意識を取るにはどうしたらいいでしょう? それは次号で…
2008年04月11日
仕事が人間をつくる
今年は、オーケストラ・アンサンブル金沢設立20周年。
その目玉、イタリア歌劇・世界三大テノール歌手の1人、ジュゼッペ・サッバティーニ金沢公演に出かけた。
情熱的で繊細、ダイナミックな声質・声量に圧倒される、感動に酔いしれた2時間半でした。
前半は、ヘンデル、モーツアルトの歌劇、そしてロッシーニの歌劇「セリビアの理髪師・序曲」など、オペラ名アリア集…
後半は、「アルルの女」「帰れソレント」「遥かなるサンタルチア」「トスカ」など、おなじみのイタリア歌曲、カンツォーネ…
45名のオーケストラとの共演を堪能した。
演奏終了後も拍手は鳴りやまず、8回もアンコールに応えて曲が演奏され、
最後に「オー・ソレ・ミーオ」を熱唱して、締めくった。
【心と体の健康情報 - 339】
~幸せな人生を歩むために~ 「仕事が人間をつくる」
■『仕事は人生そのもの』 致知出版社・川人正臣/編「仕事と人生・第一章」
仕事をすることによって人間ができてくる
人間ができると、仕事もできる
人間が仕事をつくり、仕事が人間をつくっていくのです
自分の仕事もできない者は、何をやってもできません
仕事をすることによって存在感がでてくる
仕事があるということは、素晴らしいことなんです
生きるということは、仕事をするということです
自分の仕事ができなければ、何をやってもうまくいかない
逃げたら駄目なんだ。徹底的に仕事のことを考えなさい
困難はそのとき辛くても、必ず将来の飛躍になるから
メキシコ人の猟師に、通りかかったアメリカ人の旅人が尋ねた。
「昼日中、のんびりしているようだが、毎日どんな暮らしをしているんだい?」
『日が高くなるまでゆっくり寝て、それから漁に出る。
戻ってきたら子どもと遊んで、昼寝して、夜になったら友達と1杯やって、
ギターを弾いて歌って… これでもう1日終わりだね』
それを聞いたアメリカ人。真面目な顔で、猟師に向かって言った。
「漁を会社組織にすべきだ。まず、大きな漁船を買う。
そして、自前の水産品加工工場を建てるんだ。会社を大きくして、
株を売却すれば、君は億万長者になれる」
『それで?』
「そうしたら人生最高さ! 日が高くなるまでゆっくり寝て、それから釣をして、
戻ってきたら子どもと遊んで、昼寝して、夜になったら友達と1杯やって、
ギターを弾いて歌って…どうだい、素晴らしいだろう」
『 ?… 』
落語にも、似たような噺がある。
大家「八公、真っ昼間からゴロゴロしてねえで、
少しは真面目に働いたらどうなんだい…」
八公『働けって?…働いたらどうなるんだい?』
大家「働いたら…お金が貯まって…遊んで暮せるようになる」
八公『遊んで暮せるようになったら…どうなるんだい』
大家「昼間っから、のんびり寝て暮せるってェことさ!」
八公「ふう~ン、だったらおいら、今その…のんびり昼寝をしている」
日本人は西欧人と異なり、汗して働くことをいとわない。勤労を尊ぶ民族である。
ならば、私たちにとって"働く"ということは、どういうことを意味するのでしょう?
以下、「理念と経営3月号」伊藤忠商事の丹羽宇一郎会長と、作家・江波戸哲夫先生の巻頭対談から…
丹羽会長は4000億の赤字を抱えて、不可能と言われた伊藤忠商事を再建した、名経営者です。
その丹羽会長が、「赤字の仕事に挑めば挑むほど、君は育つ」と述べられました。深い深いお言葉です。
若い時にいつも儲ける事ばかり考えている人は、結果的に「人間力(人間としての深み)」が身につかないでしょう。
田舞通信より
「生き甲斐のある人生を送りたい…」と、願わない者はいない。
一方で、苦労することを避けたがるご時世です。
現実社会を見ると、立派に成功している人は、押しなべて若い頃苦労を体験し、貧乏な暮らしを強いられている。
恵まれた環境では、人は堕落する。豊かで、何不自由ない暮らしの中からは、優秀な人材は生まれてこないのです。
寒風の中で人は育つ。厳しい環境の中で人は磨かれる。
辛い仕事を通して、人の傷みが理解できるようになり、人の苦しみが分かるようになる。
どんなに辛くても、それを乗り越え、成し遂げていく中で人は成長し、育っていくのです。
人は仕事を通して成長する。その"源"は、「評価され、褒められる」ことから始まる。褒められることが喜びになって、更に頑張ろうと…
意欲がかきたてられる。
「お前を頼りにしているぞ!」と、任せられ、認められ、褒められた時、
ヤル気が湧いてくるのです。
伊藤忠商事(株) 取締役会長・丹羽宇一郎
落語の八公のように、何もしなけれは、人として成長することはないのです。
2008年03月14日
フルスイング・高畠導宏先生のことば
■「喜びの涙・感動の涙」
今年の秋、 北陸初の「100キロ歩 (金沢から武生までの距離) 」を実現させようと、 有志が集まり、「歩こう会」を発足させた。
「過去経験したことのない大きな目標に、本気で挑み、懸命に努力し、やり遂げる」
人生のどこかで、このような経験をしておくことは、大変大切なことです。
その時に「本気」を体験した者のみが知る、
「三つの気づき」があります。
一所懸命やれば なにごとも面白くなる
一所懸命やれば 誰かが助けてくれる
一所懸命やれば 大抵のことが出来る
難関をみごとクリヤー…感動で溢れ出る涙…涙…涙
苦難を乗り越え、自らが掴み取った喜びの涙です。
涙には、大きく分けて「喜びで流す涙」と、「悲しみで流す涙」の二つがある。
人生において、 「悲しみの涙」を流さない者はいない。 が、「感動の涙」は、懸命に努力し、目標にチャレンジした、
一握りの者のみが知る"幸福の涙"です。
【心と体の健康情報 - 335】
~幸せな人生を歩むために~
「フルスイング・高畠導宏先生のことば」
反響を呼んだ、NHK土曜ドラマ「フルスイング」。
モデルとなった高畠導宏さんは、プロ野球の打撃コーチ30年のキャリア。
59歳の時一念発起、高校の教師になった。
高畠さんには教師の経験がない。が…臆することなく、30年のコーチ人生で培った
優れた"コーチング力"で、 悩める思春期の子どもたちと、 現場の教師たちを大きく変えていった…。以下、
高畠導宏先生が残した、心に残る言葉です。
人生において最も大切なもの…それは"夢"じゃ。
夢を無くした人生なんて…ペナントレースの消化試合のようなもんじゃ。
夢は自分を強くしてくれます
夢は自分を励ましてくれます
夢は人生に迷った時、
星になって道を照らしてくれます
自分のやりたい事を貫き通す!
とにかく、やり続けるんじゃ…あきらめちゃいかん!
幸せは、苦しみに耐え、我慢強くやり続けているうちに、
真っ暗なトンネルの向こうに開けてくる。
苦しみから逃れようとするな! 逃げたらあかん!
苦しみから逃れようとすると、苦しみは、どこまでも追いかけてくる…。
コーチの仕事は、選手を"おだてる"ことです。
体が覚えてしまっている欠点を、いくら治そうとしても、治りません。
だから長所を伸ばしてやる。長所に目を向けて、そっちを伸ばしてやる。
すると、知らず知らずのうちに、欠点も克服されていくというものです。
欠点を正そうとアドバイスするのは、答えにならない。
自分で答えを見つけるしかない。
立ち止まっていたら、答えは見つからんじゃろう。
立ち止まらせないために"褒める"んじゃ。
野球は、私にいろんなことを教えてくれました。
今度は私が、野球の楽しさを子ども達に教えてやりたい…
それが私の野球への恩返しなんです。
<自信をなくしかけている野球部の生徒に…>
手を見せなさい…よう練習しとる…これなら大丈夫じゃ!
今まで通りでいい!…何も、変えんでいい!…自分を信じなさい
全国制覇…ワシは本気じゃ。
一試合、一試合、誰が負けると思うて戦う…勝つことだけを信じる!
それはつまり、全国制覇を信じるということでしょう…
監督!あんたが信じてやらんで、誰が、あの子らを信じます…
<県大会・準々決勝で負けた後、選手たちに…>
確かに、甲子園へ行けることはすごいことだ…目標は全国制覇じゃから。
しかし、甲子園が君らの人生の終着駅であってはならんのじゃ。
「1つのボール」に、選手、家族、監督やコーチ、観客、いろんな人間の
思いや人生が詰まっている…それを投げて、打って、笑って、泣いて…
<卒業式の日・最後のホームルームで…>
先生が、みんなの門出に送る言葉…それは"気力"じや。
みんなに尋ねる…"気力"とは何じゃ?
生徒 …「頑張ることです」「根性」「生きること」「精神力」
先生が思う"気力"とは、"あきらめない"ことじゃ。
諦めちゃいかん!
9回裏、2アウト、ランナーなしでも、何点離されとっても、
諦めない気持ち…これが"気力"じゃ。
気力は、人を思いやることで…強くなる。
人から思われることで…もっと強くなる。
これからの人生、いろんな困難が待ち受けているじゃろう。
もうアカン、投げ出そう…そう思うことが何度もあるじゃろう。
そんな時に、この言葉を思い出してほしい…気力じゃ、気力!
諦めん気持ち…気力で、乗り越えてほしいんじゃ。
このドラマで「本気」とは何か…「本気」
の大切さを教えてくれる。
どんなに大きな「夢」「志」があっても、本気でなければ、何も叶えられません。
本気で取り組むことが、人生にいかに大切かを教えてくれるのです。
2008年03月07日
一生を貫く天職を持つこと
■木村 基(州宏)さんのご冥福をお祈り申し上げます
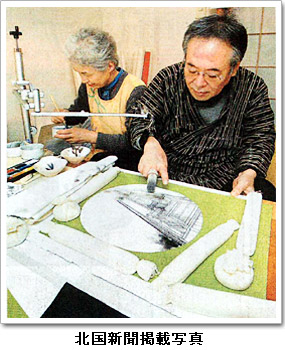
<葬儀の席で、奥様・節子さんのご挨拶>
医者に「万人に一人の難病…余命わずか」と言われ、残された時間はわずか…
夫は、病気になってただの一度も、「何で私がこんな病に掛からなければならないのか…」と、不幸を嘆いたり、
当たり散らしたことはありませんでした。
体が動く限り、創作に意欲を燃やしていました。
徐々に、体が動かなくなり、筆が持てなくなりました。
それでもあきらめず、指先に絵の具を付けて画き続けました。
そして、「この歳まで生かさせて頂き、ありがとうございます…」と、笑顔を絶やすことなく亡くなりました。残された命を全うしたのです。
【心と体の健康情報 - 334】
~幸せな人生を歩むために~
「一生を貫く天職を持つこと…」
★人生には、二つの生き方がある
一つは、定められた「運命」のままに生きていく人…
もう一つは、「運命」に立ち向かい、新境地を切り開いていく人…
20年近いお付き合いのある、友禅作家の"木村州宏"さんが亡くなられた。
不治の難病と戦って1年9ケ月…まだ62歳の、惜しまれるご逝去です。
謹んでご愁傷申し上げます。
亡くなられた翌日のテレビニュースで、木村さんがお元気だった頃のお姿を…
病の後、体がいうことを利かなくなり、指で画いているお姿を…
自らの生き方を語っているところを…映し出していた。
終始笑顔を絶やさぬお姿を見て、目頭が熱くなった。
80年代、バブル景気で売れに売れた高級呉服。
バブル崩壊後は、全く売れなくなった。
呉服屋さんは不況で立ち行かなくなり、問屋団地の親しくしていた呉服問屋も倒産した。
金沢の伝統産業、加賀友禅は壊滅的打撃を受けた。
友禅作家の木村州宏さんも、問屋筋からの注文がぴったり途絶え、お先真っ暗の状態に…。
勉強熱心で、何事にも前向きな木村さん。
「きっと打開する道があるはず…」 と、知恵を絞った… 今まで経験したことのない、営業の世界にも打って出た。
そんな時、お客さまから「キティちゃん」を絵柄にした着物の注文が舞い込んだ。
「これだ!」と、キティちゃんのパテントを所有する東京のサンリオに日参し、OKを取り付けた。
過去誰もやったことのない新しい商品を開発したい、顧客層を開拓したい…と、情熱を燃やしたのです。
次第に忘れ去られる着物文化。箪笥の中に眠っている着物に、日の目を当てようと、着物を着て…歩こう会「着物de探検隊」を、
石川県で最初に立ち上げた。
問屋に依存して手をこまねいていては、仕事が来ない… 作家活動ができないし、食べてはいけない。
直接消費者に接し、需要を掘り起こすしかないと、始めた「歩こう会」
人前で話すことが苦手な、職人気質の木村さん… 着物と友禅を愛する気持ちから、ツテをたどっての懸命な働きかけで、
賛同者が集まってきた。
「この歩こう会。平成13年4月の第1回目から、数えると35回続けたことになります」 と、振り返る奥様の節子さん。
新しい着物の未来を創造したい… 歩こう会を成功させたい…主催者夫婦の姿が、生き生きと輝いて見えた頃です。

平成15年の秋、京都から「南蛮船来航の図」の製作依頼が入った。
南蛮船とその前を行きかう異邦人や武士を、何拾分の一の縮尺で、実物そっくりの船と人形をつくらなければならない。
未経験の人形づくり… 約半年、寝食を忘れ、試行錯誤を繰り返しながら、懸命に作品に打ち込んだ。
翌年の3月、完成間近という知らせを聞いて、作業場を訪れた。
作品は、素晴らしい出来栄えだった。
木村さんは、一つ一ついとおしむように、作品を手に取り、見せてくれた…昨日のことのようです。
その時の心労が、病気を呼び寄せたのでしょうか…仕事中に時折"手がしびれる"ことが…何だろう…2年後の平成18年5月、
金沢医科大学病院で精密検査。
「※体の筋肉を動かす神経系統が退化しつつあり、近い将来、重度の身障者になることは免れません。現在の医学では治療方法がありません…
」と、死刑宣告に等しい通告を受けたのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・
★「人は、"ごめん"と言って死んでいく人と、
"ありがとう"と言って死んでいく人に分かれる。
人に惜しまれて、感謝されて…
ありがとうと言って死んでいける人間になりたい」
※病名…「筋萎縮性側索硬化症」
2008年02月29日
NHK土曜ドラマ「フルスイング」
■「可能性思考研修・基礎コース」再受講
先週、大坂N経営研究所の「可能性思考研修基礎コース」を再受講した。
この研修、12年前に1度修了している。今回は2度目…なのに新鮮だった。
前回気づくことのなかった沢山の気づきを頂いた…素直に受け入れることができた。
感動しっぱなしの3日間だった。
1度しかない人生…
「どうしたら幸せになれるか?」
「どうしたら夢やビジョン、目標が達成できるか?」…
誰もが幸せになりたいと願っている。が、幸せになるための考え方や、方法、
行動が間違っていれば、どんなに努力し、どんなに幸せになりたいと願っても、
幸せにはなれない。
何か新しいことにチャレンジする時、「よし! やるぞ~!」という思いと、
「やめとけ、やめとけ…今更頑張ったところで、しんどいだけや」という思いが、
心の中で綱引きする。
「幸せになりたい…なのに自分の中に、それを妨げようとするものがある」
「心の奥底で、足を引っ張るマイナスの観念とは…何か?」
プラスの観念とマイナスの観念 、 そのどちらが強いかで 、 人生の方向が天と地ほど違ってくる。 3日間の研修から、今まで気づかなかった、新しい自分を発見するのです。
【心と体の健康情報 - 333】
~幸せな人生を歩むために~
NHK土曜ドラマ「フルスイング」
先週まで、6週に渡り放映された、NHK土曜ドラマ「フルスイング」。
見応えのある、心にしみるドラマだった。
ドラマのモデルになった高畠導宏さんは、プロ野球の打撃コーチとして30年間七つの球団を渡り歩き、「教える」
ことに人生の全てを捧げた実在の人物です。
育てたタイトルホルダーは、落合、イチロー、小久保、田口など、延べ30人に及ぶ。
58歳の還暦間近…突然球団から解任された。
その後、セ・リーグの球団から誘いがあったが断って、一念発起、翌年の平成15年、59歳で高校の教師になった。
福岡県の私立進学高校へ…社会科の新米教論として、単身赴任したのです。
教師経験のない高畠さん…
臆することなく、30年のコーチ人生で培った優れた " コーチング力 " で 、
悩める思春期の子どもたちと、現場の教師たちを大きく変えていった…。
ドラマで高畠さんを演じた、俳優"高橋克実"(トリビアの泉の司会で知られる)さんのド迫力演技は、
見ている私をドラマの中に引きずり込んでいく…。
ドラマで、自ら悩み、迷い、葛藤する姿…高みから何かを教えるのではなく、「 生きる力 」 を伝えようとする熱意…「俺だけの先生」 「私だけの先生」と、子ども達に思わせる、 「 好きにならずにはいられない 」教師がそこにいる…。
高畠先生…毎朝、校門の前に立ち、登校してくる生徒一人ひとりに声をかける。
生徒の表情から、心の浮き沈みや、体調の良し悪しを掴み取ろうとする…。
ドラマを見ている私たちの心を捕らえて離さない、高畠先生の人間性、魅力。
挫折だらけの人生だったからこそ、 挫けそうな選手や子ども達を必死に応援し、
支えようとしたのではないでしょうか…。
このドラマで、「本気」とは何かを教えている。
どんなに大きな「夢」「志」があっても、本気でなければ、叶うものも叶えられません。
本気で取り組むことの大切さを…すばらしさを…教えてくれるのです。
テレビの前の私に置き換えたとき、どれたけ本気で物事に当たっているか?…
はなはだ心もとない。
高畠さんは、教師になってわずか1年後に、すい臓ガンで倒れた。
入院3ヶ月、志半ばで永眠。
つむじ風のように吹き抜けていった。先生の" 志 "は、同僚の先生方に受け継がれ、残っていくのです。
「フルスイング・ホームページ」から
2008年02月22日
幸せに生きる秘密(3) 幸せになる方法
どんな時にも、「ありがとう」の気持ちを…
喜ぶ・怒る・哀しむ・楽しむ…人の気持ちは日々に移ろい、変化していく。
モチベーションの高い時もあれば、自分らしさを見失ってしまう時もある。
しかし、どんな時でも、ありがとうの気持ちを持ち続けたいものです。
・喜びに溢れる時は、誰かの援助のお陰と…感謝する
・怒りを抑えられない時は、自分の努力が足りなかったからと…反省する
・哀しい時は、それが自分の人間らしさだと思い直し…頑張る
・楽しい時は、まわりへの感謝を忘れず…大いに楽しもう
「理念と経営・現場力1月号」より
【心と体の健康情報 - 332】
~幸せな人生を歩むために~
「幸せに生きる秘訣(3) 幸せになる方法」
誰もが幸せになりたいと願っている。
ところが、幸せになるための考え方や、方法が間違っていれば、どんなに努力し、どんなに幸せになりたいと願っても、
幸せにはなれないと思うのです。
以下、杉井保之氏「幸せに生きる秘訣」は、そのことを問いかけています。
3回目の今日は、幸せになる方法について考えてみます。
幸せになる方法には、2つのことが考えられます。
1つは「幸せになろうと努力すること」
2つ目は「今の幸せを味わうこと」
1つ目の「幸せになるために、何をどう努力すればいいか?」については、私のブログのカテゴリーから、 「 幸せな人生を歩むために 」 を開いて、 読んでいただければ、 何か掴めるのでは…と思います。
2つ目の「今の幸せを味わうこと」については、「幸せに生きる秘訣」で、以下のように語っています。
|
今の日本の子ども達…1人部屋にこもって、ゲームやパソコンに没頭し、好きな音楽を聞き、 友だちとはメールや携帯で話す…。 何故、1人がいいのだろう? お父さんが汗して働き、 お母さんが毎日食事を作ってくれているから、 今の幸せがあり、
幸せに暮せるのです…そのことに気づいていない。 |
以下、「理念と経営1月号/現場力」から… 経営学者ピーター・ドラッカーは、
「人間は大昔から、仲間をつくるために働いている」と言っている。
人間の最大の欲求は、食べることではなく、「集団の欲求」なのです。
人間は食べ物がなくても、しばらくは生き延びられます。
しかし「集団の欲求」が満たされないと、いろいろな問題や障害を引き起こします。
この「集団欲」を満たしてくれるのがコミュニケーションです。
人間関係、コミュニケーションは…思いやりの気持ちを表す"挨拶"から始まります。
ありがとうは、
人の心を動かす魔法の言葉です。
ありがとうは、
人間の最大の喜びの表現です。
ありがとうを言うことで、
つい慢心しがちな自分を、謙虚な自分へと導いてくれます。
ですから、家族のふれ合いで、事あるごとに"ありがとう"が飛び交う環境を、育んでいきたいものです。
2008年02月15日
幸せに生きる秘密(2)
■島田洋七 「お婆ちゃんの教え」 NHK課外授業から
1980年代、 島田洋七はB&Bという漫才コンビのツッコミみで、 お茶間の人気極まりなく 、
ツービートや紳助・竜助をも凌駕する勢いだった。
その後、漫才ブームが終焉。
後輩の明石家さんまや、島田伸助の人気が高まるのとは対照的に、いつの間にかブラウン管から姿を消していった。
頂点を極めながらもどん底に落ち…自暴自棄になりかかった時、子供の頃のお婆ちゃんの言葉を思い出し…再度、 這い上がることが出来たのです。
「人生には絶頂期がある。
しかし、そこにいつまでも留まろうと思わないことです。
ころ合いを見て、頂上から下りてくる謙虚さがなければなりません。
いつまでも頂上に居たいと思うでしょうが…
頂上は人の住むところではありません。
木も生えていなければ、水もない。嵐が来たら吹き飛ばされるでしょう。
『折角登りつめたのに…』などと思わないことです。
山を下り、沢に下りてくれば、木の実や美味しい水、岩魚など、
本来人が住む、心安らぐ場所が、そこにあるのです…」
【心と体の健康情報 - 331】
~幸せな人生を歩むために~
「幸せに生きる秘訣(2)」
誰もが幸せになりたいと願っている。
ところが、幸せになるための考え方や、方法が間違っていれば、どんなに努力し、どんなに幸せになりたいと願っても、
幸せにはなれないのです。
フイリピンやインドネシアなどを旅して、外国から、改めて日本を見ると、日本は本当に平和で豊かで、安全で、 暮しやすい国だと思う…。
ビックコミック川柳に、「自殺者が いちばん多い 長寿国」というのがあった。
恵まれた、豊かな国に住みながら、何で自殺なんかするんだろう?…
以下、杉井保之氏「幸せに生きる秘訣」は、そのことを問いかけている。
こんなに便利で、豊かな国に暮していて、どうしてこんなに不幸な人が多いのだろう。
1年くらい前に、集団自殺が2度3度と続いたことがあります。
「何故?」って理由を聞くと、『これから生きていて、いいことってあります?
ないのなら、積極的に生きる意味なんてないじゃない…』
あなたなら、その時どう答えるでしょうか?
「そんなことはない…」って、説得するのでしょうね。
私だったら…
『あなたの言うとおりですよ…幸せになんかなれっこないと諦めて、
何もしなければ、いつまでたっても幸せになれないと思うよ…。
誰だって、幸せになりたい、幸せになろうと、努力しているんだから…。
努力していても、なかなか幸せになれないのに、幸せになろうと
努力しなければ、幸せになれるはずなどないじゃないですか…。
でも、「幸せになれないっ」て辛く思うのは、幸せになりたいと
思っている証拠。
ここで考え方を変えて、幸せになれる生き方を、試してみては
どうでしょう…死ぬのは、それからでもいいじゃないですか… 』
ただ生きていても、幸せにはなれません。
幸せになろうと努力しない人が、幸せになれるはずがないのです。
幸せになりたかったら、"幸せの種"を蒔かなければなりません。
"幸福"という植物は、とても育ちにくい植物です。
ちょっと手を抜くと、直ぐ枯れてしまいます。
だからこそ一生懸命育てる…そうしたら芽が出てくる。
一生懸命育てて芽が出てきたら…最高に嬉しい…幸せを感じると思うのです。
いずれ花が咲くことを楽しみにして、丹精込めて育てるのです。
誰が育てても 、 何もしなくても育つような植物だったら 、
花が咲いても感動しないし 、 幸せなど…何も感じないでしょうね。
幸せは、努力した人だけが…努力した人だけに、与えられるものでしょうね。
2008年02月08日
幸せに生きる秘訣
■遠征ゴルフ
昨年からの企画で、 雪の無い関西へ遠征してゴルフを楽しもうと、 3日の日曜、
まだ明けやらぬ朝6時に出発…滋賀県・竜王GCへ。
ところが前夜、大坂から名古屋・東京にかけて、思いもよらぬ雪が降った。
幹事もしやと、車中から問い合わせたら、関西方面はどこもクローズ…うっそ~。
引き返すことになったが、石川県は雪が降らなかったのに、海沿いの片山津も、千里浜も、全て残雪でクローズ…
ようやく能登ゴルフの予約が取れた…安堵…。
11人を乗せたマイクロバス… 丸岡でUターンして、 心ときめかせ能登へ… 車中はお酒が配られ、
ワイワイ遠征気分で…県内を3時間半掛け、目指すゴルフ場へ…お笑いです。
北海道スキーツアーの時もそう…天候不順で、小松から飛行機が飛ばなかった。
が、誰一人帰ろうとしない。早起きして家を出て、今更中止解散はない…。
JRを乗り継いで、 関空から飛んだ。 スキーをかついだ一行が、 大坂に向かう姿…
何とも滑稽…。
今回もそう… 何処もクローズというのに、「ゴルフを中止しよう」と言い出す者は一人もいなかった。
【心と体の健康情報 - 330】
~幸せな人生を歩むために~
「幸せに生きる秘訣」
今年の正月も幸せを願って、 石浦神社、 尾山神社、 白山比咩神社と、
神社詣での梯子をした。
誰もが幸せになりたいと願っている。いくら神様にお願いしても、思っているだけでは幸せにはなれません。幸せになる考え方や、
方法が間違っていれば、どんなに努力し、幸せになりたいと願っても、幸せにはなれないのです。
以下、杉井保之氏の「幸せに生きる秘訣」での問いかけです。
|
これまで、沢山の人に「何のために働くのか?」という問いかけをしてきました。 それでは、いくらまじめに働き、勉強しても、幸せにはなれません。 皆さんにお尋ねしたいのですが、「 幸せ 」とは、人それぞれ全く違うものでしょうか?
人それぞれ形は違っていても、 大きな眼で見ると、 人が求める幸福は、
皆同じだと思うのです…。人に好かれることは嬉しいことです。 |
進学・受験シーズンを迎え、親は、子どもの受験結果に一喜一憂する。
我が子が、クラスの誰よりも成績が良いことが、子どもの幸せになると信じて
疑わない親…。
|
学校へ行く目的は、勉強だけではないと思うのです。 |
どの家庭の母親も、 子どもに「 勉強しなさい!」と、 うるさく言うが、 本音は、
幸せになって欲しいから、「勉強しろ」と言っているのです。
勉強よりも、もっと幸せになる方法があれば、「勉強しろ」とは言わないでしょう。
子どもの頃の学業成績が、大人になって後の幸せを保証する… と断言できるでしょうか?比率はわずかでしょう。
幸せになる条件の中の一つにしか過ぎないのです。
40人のクラスで、成績上位に入れるのは数人…親のDNAを受継いだ我が子…スズメの子はスズメです。勉強が嫌いなら、
その子の何を伸ばしてやれば、将来幸せになれるか?
それを見つけ、伸ばしてやるのが親の役目でしょう。
しゃにむに、大学を目指させることだけが、幸せの道ではないと思うのです。
我が子が、三流高校にしか入れないとしたら、恥ずかしい思いをするのは親。
それが嫌だから、「勉強、勉強」と言っているのではないでしょうか?
私の1つ下の弟は、勉強が出来ませんでした。そこで父は、中学校を卒業して直ぐ、東京のハンドバック製造会社に、
職人として住み込ませました。
弟は30代半ばに独立。今では、業界1.2の優秀な職人として、立派に成功…
取引先から重宝がられているのです。
2008年01月18日
より良い夫婦関係
■結婚四十年、奥様への変わらぬ愛
昨年11月、一緒にハワイ観光した福井市のK社長。
以前、浜名湖へ一泊二日の温泉旅行に出かけた時、宿に着くやK社長、奥様に絵葉書を書いていた。
「明日、ハガキが届く頃には家に帰っている…なのに、何故?」って尋ねたら、特に意味はなく、長年の習慣だという。
結婚四十年…今も変わらぬ奥様への愛… 頭が下がります。
●共働き30年の私たち夫婦。夫婦円満の秘訣を挙げると…
(1)夫婦は、自分に不足するところを補いあう間柄…
"感謝の心"で接すれば、自然と「ありがとう」の言葉が湧いてくる…
(2)心を込めて、「おはよう」「行ってらっしゃい」「お帰り」「お疲れさま」
「おやすみなさい」…労わりの心で挨拶すれば、労わりの心が返ってくる。
(3)食事どき、食後のくつろぎどきの夫婦の会話を大切にする。
大切なのは、「相手の話をよく聴くこと」「会話を楽しむこと」。
分っていても、時には口げんか…つい、耳をかさず、言い分を通そうと、
声を荒げる自分がいる。
(4)食事の後片付け。洗濯する・干す・仕舞う・アイロン掛け。
身の回りの整理整頓…自分のモノは自分で…できることは自分でやる。
【心と体の健康情報 - 327】
~幸せな人生を歩むために~ 「より良い夫婦関係」
共働き・一人っ子家庭の多い今の社会。
家の中は静まり返り、家族揃って会話を交わす機会が、昔に比べ少なくなった。
公園には、子どもたちの遊ぶ姿がない。
一人部屋に閉じこもり、ゲームに興じる日々…そんな家庭環境で大人になっていく。
人は十人十色、考え方が違う。なのに、自分と違った考えを、受け入れることができない。
また、相手に自分の考えや思いを伝えることも下手…努力することもしない。
対人関係に悩み、人間嫌いになっていく…。
良い人間関係を形成するには、"対話"が不可欠。
対話によって、お互いの理解が深まり、信頼関係が培われていく。
信頼は相手を受け入れ、認めるようになる。自己開示して、素直に聴き、素直に話せるようになる。
何でも肯定的に受け入れることが出来るようになる。
「夫婦円満の秘訣」
川柳に、「バスの旅 しゃべらないから夫婦だよ」や、「一生の不作と二人認め合い」というのがあった。
|
「ある生保会社のアンケートによると、一日の夫婦の会話時間が30分以下の夫婦が、4割もいるという。 そう回答した人の三人に一人が、「配偶者に愛情を感じていない」と言う…。 聴き上手になるための研修会で、アドバイザーから… 今度は、語りかけに耳を傾けてもらい、相づちを打ってもらうようにすると、和やかに会話が弾むのです。
夫婦の会話。まずは、相手の話をしっかり聴くことです。 中日新聞「言いたい放談」 |
「ありがとう」「ごめんなさい」…こんな短い会話、「どうも照れくさくて」と、タイミングを逃して言いそびれ、
気まずい思いをしている夫婦や親子…意外と多いものです。
そんなご家庭に、とっておきの手法があります。
便箋に「ありがとう」「ごめんなさい」など、自分の気持ちを書いて、妻や夫、子どもの机の上に置いておけばいい…娘が高校生の頃、
父親の私に反抗…この手を使って謝ってきた。
小さな便箋二枚に、小さな字でびっしり…たったこれだけで、父娘のわだかまりが消え、すべて解決したのです。
私の誕生日に娘から、可愛いハガキが届いたことがある。同居しているので、手渡せば済むこと…それをわざわざポスティング。 郵送されて私の手元に届いた…その演出がたまらなく嬉しい。
真似て、私が60歳の還暦の年、長年連れ添った妻に、感謝の気持ちをしたため、投函。5~6年経った今も、 「宝物のように大切にしまってあるのよ」と、最近になって知った…。
2008年01月11日
幸せの青い鳥
「一人をもって国興り、一人をもって国滅ぶ」
これは、前防衛事務次官守屋氏の"座右の銘"です。
1年前の1月、一人で防衛庁を引っ張って、"省"昇格を実現させ、晴れがましい思いをした直後、相次ぐ不祥事で、
一人で"省"の信用を失墜させた…。
彼が好んだ言葉どおりになったのは、皮肉としか言いようがない。
この事務次官のように、世渡り上手に地位や名誉や財産を手に入れ、成功を手にしても、心が貧しく、倫理や道徳に欠落したものがあれば、
いずれは信を失うことになる。
過去に私は、手相や面相に興味を持ち、趣味にした時期があった。
前防衛事務次官…事件直後、TVに映し出された顔に、どことなく暗い影が見られ、気になっていた。
その後、次々悪事が露見して…やっぱりそうだったか…。
【心と体の健康情報 - 326】
~幸せな人生を歩むために~ 「幸せの青い鳥」
世界中の人々から愛されてきた、ベルギーの劇作家モーリス・メーテルリンクの童話「青い鳥」。
この戯曲が書かれた1908年は、自国の権益を主張して譲らない国々が、やがて雪崩を打って第一次世界大戦に突入していく前夜…
まさに一触即発の不安定な時代でした。
今は21世紀。
望むものは何でも手に入る、平和な世の中にありながら、"青い鳥"を求めてさ迷う人の何と多いことか…。
メーテルリンクが、100年前に鳴らした警鐘が、再び、私たちのすぐ近くで鳴り響いているのです。
クリスマス・イブの夜、木こりの子供チルチルとミチルの兄弟は、"幸せの青い鳥"を探して旅に出ます。
旅先で待ち受ける冒険の数々。二人は時空を超え、不思議な出会いを通して、それまで知らずに見過ごしていた沢山のことを経験します。
しかし、青い鳥はどこにも見つかりませんでした…。
やがて夜が明け、長い旅を終えて自分たちの家に戻った二人は、青い鳥が自分達の直ぐ身近にいることに気付きます。
チルチルとミチルが捜し求めた"青い鳥"とは、いったい何だったのでしょう?
劇団四季「青い鳥」から
中国、宋の時代にも、似たような"詠み人知らず"の詩があります。
『 尽日(じんじつ) 春を尋ねて春を見ず
芒鞋(ぼうあい)踏み 遍(あまね)
く隴頭(ろうとう)の雲
帰来適(きらいたまた)ま 過ぐる梅花の下(もと)
春は枝頭に在りて 己に十分 』
「一日中、春を尋ねてみたが、何処にも春を見出すことができなかった。
向こうの山、こちらの谷、あちらの丘と随分歩いたが、やたらと草鞋(わらじ)をすり減らすばかりだった。
家に帰って、ふと門前を見ると、梅の花が1、2輪、いともふくよかに良い香りを放って咲いている。
なんだ、春はここにあったではないか…」
(春を"道"と言い換えてもいいし、"真理"と置き換えてもいいでしょう)
私たちの周りには、立派な家に住み、高級車を乗り回し、豊かな暮らしをしている人達がいる。そうした人の持ち物と、 自分の持ち物を比較して、つい、幸・不幸を推し測ろうとしがちです。
また、金銭欲の強い人は、その卑しさが…、心の貧しい人は、その貧しさが…、顔に表れてきます。
反対に誠実な人、正直な人は、その誠実さや正直さが、オーラのごとく伝わってくる。
故に、暮らしが貧しいからと、心まで貧しくなってはいけないのですが、これが難しい。どうしてもひがみ根性が出てしまう。
「今年は良い年でありますように…」と初詣に行き、手を合わせてきた。
幸せの"青い鳥"…つい、目を外に向け、幸せを探し求めようとします。
遠くに求めなくても、"青い鳥"は、自分の心の中に潜んでいるのです…。
そのことに気づき、育んでいけば、幸せは向こうからやってくるようになる…。
2007年12月18日
苦悩体験が、人生に成功をもたらす
■成功者になる条件は「貧乏に生まれること」
貧乏が人を鍛え、偉人・英雄を創り上げていく。
キリストは叩き大工の子で、「貧しき者は幸いなり」と説いている。
孔子も生涯、貧乏暮らしで過ごした。
豊臣秀吉は水飲み百姓から、位人臣を極める関白にまで、昇り詰めている。
アメリカの富豪カーネギーは、「腕一本で巨万の富を作る必要な条件は、貧乏に生まれることである」と、自らの体験を語っている。
先週、倫理法人会で、長野県で裸一貫、事業に成功した社長さんの講演があった。
小学生の頃家が貧しく、お昼の弁当を持たせてもらえなかった。
同級生が昼食を終え、グラウンドに飛び出して来るまて、校庭で空腹をこらえていた…。
私の知る限り、幼少の頃、誰よりも貧しい暮らしを強いられたのは、作曲家の"遠藤実"であろう。
戦時中、東京から新潟に疎開。
浜辺の電気もない、ムシロを敷いただけの、すき間だらけの船小屋…真冬の北風が吹きすさぶ中、凍えた母子が寄り添い、屑拾いをして、
乞食同然の暮らしをしていた。
卒業の時母は、小学校で穿いていた半ズボンを二つつなぎ合わせ、息子の門出に穿かせている。その幼い頃の苦渋体験が、 作曲家になって後、心にしみる名曲を次々と生み出す、源になっている。
【心と体の健康情報 - 324】
~幸せな人生を歩むために~
「苦悩体験が、人生に成功をもたらす」
徳川家康。幼名は竹千代。
6歳の時、尾張の織田信秀の元へ送られ、人質として2年間過ごす。
それから人質交換で駿府へ移され、義元の下で少年期を過ごし、元服している。
秀吉が没した後、天下統一を為しえた家康。幼少の頃、人質で過ごしたことが、
よく気の回る、人心掌握に長けた家康を育んだのです。
以下、「白隠禅師・座禅和讃に学ぶ」からの抜粋です。
人は、他人の幸福を見ると、何か喜べない妬みの心が湧き、人の不幸を見ると、ひそかにほくそ笑む…そんなさもしい心が湧いてくる。
他人の悪い所は、口をきわめて非難し、他人の善い所はけなしたくなる… そんな、いやしい心も潜んでいる。
人生の苦しみは、「自己愛」から生まれてくる。自分のことが何よりも可愛い。
そうした狭い考えが、苦しみや悩みを生み出していく。
「生きることの執着」「名誉への執着」「人並みでありたい執着」から、苦悩が生まれてくる。
身の回りに生じる苦悩を、5つつ挙げてみると…
(1)癌の宣告を受けるなど、自分が死の宣告を受けたり、直面した時
(2)自分に最も身近な妻や夫、子どもが死を宣告されたり、直面した時
(3)倒産や風水害、人に騙されるなどして、生活が根底から破綻した時
(4)失恋、離婚に直面した時
(5)いじめに遭うなど、劣悪な人間関係に巻き込まれた時
何れも不眠症に陥り、苦悩は片時も頭から離れず、人生に失望する。
将来に希望が持てなくなり、苦しみから逃れるには死ぬしかないと、思い詰め るようになる…。
こんな時、静かに目を閉じて、自分の心と向き合うようにします。
自己を客観的に見つめることで、本当の自分が見えてくる…どうあるべきかが見えてくる。
禅寺で座禅をして、自己を問い直すのも、一つの解決方法でしょう。
死にたくなるほどの苦悩に遭遇した時こそ、己の本性に出遭える又とない機会になる。
苦悩を体験することなく、人生を終えるに越したことはない。が、己の真の姿を見い出せないまま、一生を終えることになる…。
月刊誌「理念と経営」に毎号連載される、「逆境!その時経営者は」を読んで、 苦悩の極みを経験した者にしか、手にし得ないものがあることを学ぶ…。
12月号は、倒産・一家離散に追い込まれた経営者が、見事再起した話です。
社長と労苦を共にした、専務の規子さんは、私と約1年間机を並べ、経営者のスキルアップ研修を受けた間柄…。
今回の掲載を読むまで、そのようなご苦労があったこと…まったく知りませんでした。
「実るほど、頭を垂れる稲穂かな」の、素敵な奥さんです。
ゲーテの言葉に、「涙とともにパンを食べた者でなければ、人生の味はわからない」というのがある。
"死ぬほどの苦労"を、自ら望んで体験したい…と思う者はいないだろう。
しかし、苦労した人間でなければ、人生の深さや真髄を味わえないだろう…。
苦労らしい苦労も知らず、歳を重ねただけの私には、分りえないことです。
2007年01月23日
好きな自分を生きる/命がけて人生を楽しもう
■心に残ることば
「誰かのための人生ではなく、自分のための人生でありたい」
「人は、"ごめん"と言って死んでいく人と、
"ありがとう"と言って死んでいく人に分かれる。
ありがとうと言って死んでいく人間になりたい」
NHKドラマ「マチベン」"安楽死を裁けますか?"より
【心と体の健康情報 - 277】
~幸せな人生を歩むために~
「好きな自分を生きる/命がけで人生を楽しもう」
「病気の心因は心の不自然さにある。 病気はありがたい自然からの注意…
喜んで受け、生き方を正すとき。そうすれば、おのずと癒えていく 」
ストレスが原因で胃潰瘍になって入院。健康を取り戻して退院しても、日常生活で原因となる「ストレス」を取り去らない限り、
また再発する可能性が大だ。
真の健康を取り戻すには、ストレスが発生しない環境に改善していくことです。
以下、ざ・ぼんぢわーく工房/第31集 下地規子さんの
「自分を好きになりませんか」からの抜粋、その2です。
|
一度ガンを患って再発したK子さんが相談に来た。 「K子さん、あなたは病院に行くか、癌で死ぬかでしょ…。 実は、ご主人もあまり具合が良くなくて、ずっと薬を飲み続けていてね、毎食きちっと食事をとり、薬を飲む。 そのため奥さんに居て欲しいのです。 彼女は毎日、外へ出かけるようになった。ご主人の冷たい視線も気にならなくなった。
奥さんはニコニコ出かけていく。カラオケに行こうと誘われ、行った。これがまた楽しい。
人生には楽しいことがいっぱいある。 親戚がカナダにいるので、「じゃ、行きましょう」と、カナダにも行った。娘たちが、「お母さん、
元気なうちにどっか旅行に行こう」 その間に、病院から"もう亡くなられたか"と思って、電話が入ったそうです。「どうしてますか?」『はい、 元気にしてます』と言ったら、電話を切られたそうです。 彼女は入院する日の、日付メモを持っていたんです。それをずっとポケットにしまい込んでいたと、言っていました。
そして、入院の日付メモから3年目に、市の健康診断を受けに行きました。 人生、ただ長く生きようとするだけでは、意味がありません。 |
病気になると、医者にすべて頼ろうとする。医者は、病気を治してくれる。
しかし、病気を治すために最も大切なことは、自ら、本気で「治りたい」「絶対に治ろう」と思い続け、病気に負けまいとする、
強い意志を持つことです。
人の体には、病気を起こすものに抵抗し、それに対処しようとする能力がある。
人が持つ、「自然治癒力」の力に、もっと目を向けなければならない。
2007年01月16日
好きな自分を生きる
■日本精神
戦前、日本の統治国となり、日本の教育を受けた台湾に、日本人が失ってしまった「日本精神」が、60年を経た今も息づいているという。
ところが、戦後の日本人は、日本人であることの「自信」と「誇り」を失ってしまったと、言われるようになった。
台湾には、日本人が学ぶべき「正しい日本史」が残っていて、日本統治時代を正しく評価する、歴史観教育が行われているという。
台湾人と台湾の中に、日本人の本当の姿を見つけることができるのです。
台湾に巨大ダムを建築し、今も台湾で尊敬と敬愛の念を持たれている、我が故郷金沢出身の"八田與一"土木技師は、「日本精神」
を代表する人物として、台湾の人たちに語り継がれている。その日本精神は、以下の四つの規範で言い表わされる。
(1) 嘘をつかない (2) 不正をしない
(3) 全力をつくす (4) 失敗を人のせいにしない
11/30 北国新聞「時鐘」
【心と体の健康情報 - 276】
~幸せな人生を歩むために~
「好きな自分を生きる」
友人から、ざ・ぼんぢわーく工房/第31集「自分を大好きになりませんか」と題した本をプレゼントされ、読んだ。
第31集を書いた下地規子さんは、沖縄で「ネットワークこころの会」を主宰している。以下、下地規子さんの「自分を好きになりませんか」
からの抜粋です。
|
「自分を大好きになりませんか…」 ところが、無理して嫌いな自分を生きている人がどれほど多いことか。楽しい人生を送るためには、 「どんな自分が好きか?」を考え、好きな自分を生きるようにすればいいんです。簡単なんです。 好きな自分を生きることを選択をすればいいだけです。嫌いな自分が分ったら、「あっ、
こういう生き方をする自分が嫌なんだ…」 ねえ、怒る自分が嫌いだったら、笑う自分になればいいでしょ。 そこで「選択する」ことから始めます。 例えば「ボランティアしましょう」と言われ、「行かないと何か言われる」。あるいは 「行かないと嫌な人だと思われる」そうやって、無理して無理を重ねて、 ストレスが溜まるというような生き方をしている人が多いんですよね…。 「ストレスのない生き方をしましょう」。そして、自分自身の中をホントにクリアーにして、 「自分が何をしたい人間なのかを、見つけていくようにしましょう…」 そのためには「常に行動する」ということを心がける。
|
「やりたくない」と、自分を肯定的に受け止め、そのように行動したら、周りの人たちは「自分勝手で我がままな人」と、
白い目で見るのでは?と思ってしまう。
ならば、「そう思われないよう行動すればいい」となり、やっぱり無理をして、ストレスを溜めてしまうといういうことに、なりはしないか…
?
要は、自分のことばかり考えず、人にどう思われているかなど、気にせず、人の役に立つことをしたり、良いと思ったことを、
素直な気持ちでやればいいのです…。そのうちに、何も考えなくても体が勝手に反応するようになる。
いつしかそれがその人の人格となり、幸せな人生を歩むことが出来るでしょう。
2006年12月21日
若く見える人、見えない人
■老夫婦、食事での会話。
夫 「あっ! ズボンの上にこぼしちゃった…」
妻 「駄目じゃない、ちゃんとハンカチを膝の上に乗せておかなきゃ!」
夫 「このハンカチ、年を取るにつれて上がって、首元に挟むことになるよなぁ~」
妻 「そうよ、最後は顔の上にのせておしまいヨ!…」
夫 「……」
脳梗塞を患うと、ご飯をぼろぼろこぼすようになる。ところが当の本人は、そのことに気づかない。
年をとると、いずれはなんらかの病を患い、床に伏せ、人様の世話になって死んでいかねばならない。 2025年には、3軒に一軒が、
65歳以上の夫婦二人、或いは一人住まいになるという。
まだ先のことと、考えたくはないが…実のところ、誰の世話になって、どのような場所で安心して死んでいけるのか? 妻?息子?娘?、 自宅で?施設で?病院で…?
【心と体の健康情報 - 274】
~幸せな人生を歩むために~
「若く見える人、見えない人」
二ヶ月前、中学卒業後初めて、50年ぶりの同窓会に出席した。初めてということで、幹事から紹介され、一人ひとりお酌して歩いた。
一番端の席に、足が悪いのでしょう、低い椅子に腰掛けて、一段高いところで食事をしている人がいた。
そこで私は大失態をした。年恰好から、"先生"が同席されていると勘違いして、ご挨拶に行ったのです。「吉村と申します。
卒業以来50年ぶり、先ほどから先生を拝顔し、先生のお名前が思い出せません」と言ったら、「バカ、私も同級生だよ…」
二週間後、記念写真が送られてきた。Yさんは若い頃から童顔、50代半ばにしか見えない…10歳は若い。後列のMさんは、
苦労したのでしょう?
70半ばに見える。シワやシミが多く、尋ねたら、病気をしたという…。
50を過ぎると、白髪が目立ち、頭が禿げ上がってくる。若く見える人、老けて見える人、私たちの年齢になると、
前後20歳くらい齢が開いて見えてくる。
まだ若いつもりでも、写真は正直。
写真に写る己の姿は、何ともむさくるしく爺むさい…写真を直視することができない。
若く見える人は、大概仕事を持っている。そして、忙しそうに飛び回っている。
現役バリバリ、心にハリをもって働くことが、若々しさを演出するのでしょう。
私が三十歳の頃、「しいのみ学園」が話題になったことがある。映画にもなった。
遥か昔のことと思っていたら、昨年4月、30数年ぶりに、何と101歳になられた曻地三郎園長が、講演に現れたのです。
まるでタイムスリップ…。100歳を過ぎた今もなお、現役バリバリなのです。
二時間立ったままマイクなしで講演。しかも自らあみ出した"棒体操"を約十分間、私達を立たせての実技指導。101歳なのに、 棒を片足立ちで、組んだ両手の中をくぐらすのです。身体は柔らかく大変お元気。とても101歳の老人には見えません。
ご自身は医学博士ですが、他にもいくつか博士号を取得。語学も堪能で英語やドイツ語が得意。更に、ロシアで論文を発表するため、
ロシア語をマスター。
63歳から韓国語を勉強し、5年で自由に話せるようになり、95歳から中国語を覚え始め、話せるようになったという。
90歳を過ぎて韓国に"しいのみ学園"をつくり、95歳の時、民間の身障者施設が未成熟の中国に渡り、"しいのみ学園"を開園。
今後20箇所は増やしたいという。
講演2ヶ月後、アメリカ、ヨーロッパ、南アジアの大学に招かれて、世界一周講演旅行に旅立たれた。そして、
今年も引き続き講演旅行に出かけていった。
102歳になられた現役園長…曻地氏には、余生というものがないのでしょう…。
一世紀を生き抜いて、なお盛んなのです。
また、京都で論語を教えていただいている"伊與田 覺"先生は、今年91歳。
来年も引き続き教壇に立たれるという。毎回3時間近くの講義。ご高齢の老人には見えない、ハイレベルの格調高い講義をされます。
来年、団塊の世代が60歳の定年を迎え、働き場を失う。長年培った経験や能力、まだまだ生かせるのに、もういらないとお払い箱。 国や社会にとって、大きな損失でしょう…。
■曻地三郎(しょうちさぶろう)氏
小学校、女学校、師範学校の教員を経て、現在、福岡教育大学名誉教授。
S29年我が子が小児麻痺の身障者になったが、障害者を受け入れる学校がなく、独力で「しいのみ学園」を設立、
障害者の教育指導に当たる。
医学・文学・哲学・教育学博士。新万葉歌人。そのほか、韓国大邱大学教授・大学院長。中国長春大学名誉教授。著書130冊。
2006年12月05日
福祉が充実すると社会が乱れる(2)
建設会社を営むM社長、32歳の時に独立。妻に支えられ朝から晩まで一所懸命働いた。もともと腕の良かったM社長、 建てた家は評判となり、独立から七年後には、二十数名を擁する会社の社長になっていた。
M社長が夜遊びを始めたのは、ちょうどこの頃。最初は週に二、三度で、それも少し夜が遅くなるぐらいでした。それが連日、
午前様へと変わっていき、仕事は社員任せ。当然、夫婦喧嘩の毎日で、二人の子どもは怯え、暗い家庭になっていったのです。
このような状態で経営がうまくいくわけがなく、一億五千万円の負債を抱えて倒産。債権者を前にM社長は罵倒されるに任せ、
家に帰っては腑抜けのように布団を被って寝ていた。
ここで「何とかしなければ」と立ち上がったのが妻。ある朝、夫の布団を剥ぎ取って、「こうなったのは、あなたのせいだけではない。
私も悪かった…。二人で債権者を回って、迷惑をかけたことを詫びましょう」と言い出したのです。
妻の気迫に押されたМ社長、一軒一軒土下座をして回った。耳を覆いたくなる罵詈雑言の連続。しかし、最後に回った債権者が、 「経営者にとっては、倒産は宿命みたいなものだ。あんたたち夫婦にやる気を感じた。早く返済してもらいたいので資金を貸そう」と、 言ってくれたのです。
それからというもの、初心に返り、夫婦は朝から晩まで、必死になって働いた。
全債務を返済したのは八年後。「妻がいてくれなかったら、いま自分は生きていたかどうか。本当に感謝しています…」と、
M社長は真剣に過去を振り返った。
今週の倫理446号より

【心と体の健康情報 - 272】
~子育て心理学~
「福祉が充実すると、社会が乱れる?(2)」
国会で、毎年三万人の自殺者を減らそうと審議している。ところが、日本や北欧のように、福祉が充実している先進国で、 生きがいを失い、自殺者が増えているのは何故なのか? 考えなければならない現象です。
社会の弱者を保護することは、先進社会にあっては大切なことです。
弱者に対する税制上の配慮、失業救済、身障者・病弱者・高齢者の保護、その他社会福祉の充実によって、貧しい人、
困った人が救済されます。
しかし、どんなに制度を充実させても、ものには程度があって、バランスを失わないことです。弱者になって、福祉の恩恵を受け、 国の庇護に頼ったほうが得だと悟った時、人は哀れにも、自ら、弱者になり下がろうとする…。
こうして、弱者に手厚い保護を加えれば加えるほど、更に弱者が増える社会になる。弱者天国の行き先は、 個人の堕落と社会システムの崩壊…。これ以上の不幸はない。
企業においても同じことが言える。福利厚生を充実させ、社員の給料や待遇を良することが、経営者の責務と考える。
「福利厚生を整えれば、優秀でよく働く人材が集まり、会社の離職率も下がるだろう…」と、ほとんどの経営者が信じて疑わない。
私は、日立家電(18歳の時)、積水ハウス(28歳の時)、ノエビア(38歳の時)、何れの会社も創業間もない頃、その会社に携わり、
頑張ってきた。
創業間もなく、給料が安く、待遇が今よりずっと悪かった頃、毎晩遅くまで必死に働き頑張った。あの頃の方が、社員に熱気があり、
ヤル気に満ちていた…。
そういった、幾つか大きな会社に勤めた経験から、「給料や待遇は良くすればするほど、人は働かなくなる」
「いくら待遇を良くしても、辞める人は辞めていく」という現実を見てきた。
人が一番働く環境は、福祉が充実した会社でも、週休完全二日制でも、世間より給与の高い会社でもないのです。
前の会社で管理職をしていた頃、下請け業者を引き付けておくには、徳川家康の「農民は太らせず、やせさせず」
の状態にしておくことだと、上司に教えられた。下請け業者、儲かってお金が貯まると、百万円もする掛け軸を買ったり、豪邸を新築したり、
クラウンに乗ったりして、働かなくなる?
「活かさず殺さずが丁度良い」と…。
(今の私は、三方良しの精神で経営しています)
家康が、人心を掴むのが上手いと言われる所以の一つは、この言葉も感じられる。給料や待遇は良すぎず、悪すぎず、
ほどほどのとき"人は最も働く"ということを…。
会社経営も、同じことが言えるのでは? 儲かり過ぎず、悪すぎず、ほどほどの時の社長が、一番生き生きとよく働く…。
中日新聞 漫画家 江川達也「本音のコラム」より
2006年11月21日
川人氏・創立5周年式典に参加して
■吉村作治の「エジプト発掘40年展」
先月、世界で初めてルーブル美術館から日本に持ち出された、ギリシャの神々の遺産、彫刻と宝飾品展を見たばかり。
感動覚めやらぬ先週日曜日、京都「えき」美術館で「エジプト発掘40年展」を見た。
早稲田大学、吉村作治教授の調査隊が、エジプトで40年かけて発掘した、5千年~2千年前のエジプト王朝の遺物200点が展示されている。
(11/26まで)
 |
| <ミイラを覆っていたマスク> |
19世紀初頭からエジプトに入ったイギリスやフランスの調査隊。発掘した品々は自国に持ち帰った。早稲田大学の吉村調査隊は、 発掘品を日本に持ち帰ることをせず、そのすべてをエジプト国内にとどめて、保存・研究を行っている。
博士の最高の偉業は、昨年1月、過去発掘されたミイラでは最も古い時代で、しかも未盗掘の完全な状態のミイラを発見・発掘したこと。
今回40年の間に発掘した品々を、エジプト政府の信頼と、特別の協力で借り受け、日本で始めて公開展示することになった。
右の写真はその傑作、"ミイラマスク"ミイラが収められていた木管の他、首飾り、指輪、彫像、女神の護符、王様の鎮壇具など、 数千年前の歴史の遺産の数々が、所狭しと並べられていた。

【心と体の健康情報 - 270】
「川人正臣氏・創立5周年記念式典に参加して…」
先週の土曜日、大阪のホテルでの、川人正臣氏の株式会社ヒューマンフォレスト、創業5周年記念式典に参列。翌日、宇治平等院と、
紅葉の名所東福寺、そして「エジプト発掘40年展」を鑑賞して帰沢した。
*********************************
~川人氏の新しい著書を50名様にプレゼント~
詳しくは、このメルマガの最後をご覧下さい。
*********************************
~会場いっぱい感動に包まれた、 創立5周年記念式典~
[びっくり…1]
ビジョン発表…「25年後の30周年には、1千億円企業になる」
机一つ、電話一台から会社を興し、創立わずか5年で年商5億円を達成された。
その川人社長から新たに、5年後、10年後の目標・ビジョンが発表された。
更に、25年後の30周年には「1千億円企業」になると、声高らかに宣言。
そして25年後の今日、同じ会場で、今日参加の皆様をご招待したいという。
(25年後の会場予約をホテルに済ませて、式典に臨むという念の入れよう…)
[びっくり…2]
5周年を記念して、25年後2031年の30周年記念の「タイムカプセル」を用意した。当日のお祝いの言葉を、
参加されたお客様全員に書いて頂き、カプセルに入れるという趣向…。
25年後の私、丁度90歳になる。「是非出席させて頂きます」と、川人氏に返事した。
[びっくり…3]
5周年を期して、優績社員・功労社員が表彰された。その選出はすべて社員さんの無記名投票によるもの。
社長からの意見や考えは含まれていない。
[びっくり…4]
経営理念・社旗・社章・社歌が決まり、来賓の前で披露された。
"社歌"は、社員さんが作詞した。社員さん・ご家族全員、子どもさんも壇上に上がり熱唱。繰り返し歌ううち、参加者の気分も高まり、
会場いっぱい大合唱になった…。
[びっくり…5]
物事をやりきる根性、「社風」を構築するため…
2006年 4月 社員とその家族「50キロ歩」 にチャレンジ、全員完走。
8月 〃 「富士山登山」にチャレンジ。
10月 〃 「100キロ歩」 にチャレンジ。
目的は、自分の努力と力で涙を流すほどの感動を体験すること…
あえて、過酷といわれることにチャレンジすることで、自分の可能性を広げたい。
いずれも、経験したことのない人にとっては、かなり過酷なのですが、この程度以下では"感動"できないし、
またこれ以上の過酷なチャレンジは危険を伴う。
こういう機会を通じて、社員や家族との絆を深めていきたいと考えています。
「仕事が人をつくり 人が仕事をつくる」86Pより
[びっくり…6]
川人氏が5周年記念に出版した著書をお土産に頂き、喜んでいたら、ヒューマンフォレスト社の回路設計による"DVDプレーヤー"を、
「170名の本日参加者全員にお持ち帰りいただきます」との、川人社長の言葉…。会場がどよめいた。
|
川人氏の新しい著書「仕事が人を作り、人が仕事を作る」 川人正臣氏の新しい著書を、
このメルマガを読まれた50名の皆様にプレゼントします。 「仕事と人生」を読まれた皆様には、是非この続編を読んで頂きたく、 先着50名様にプレゼントさせて頂きます。 ご希望の方は、折り返しメールにてお申込みください。
|
2006年10月27日
運動会抜くなその子は課長の子
北国新聞「子ども討論会」のテーマ、"かけっこ"についての六年生の意見です。
「ビリの子は傷つくから、なくしてしまったら…」 「順位があるから盛り上がる…」
「競い合った方が自分の力が出せる…」。中には「走るのが遅い子は、前の方
からスタートすれば…」という、面白い意見もあった。
でも…、前の方からスタートする子が勝ったりしたら、いじめに合いそう…。
成長度合いに、大きな開きが出る小学生。運動能力に、どうしても差が出てくる。
勝ち負けにこだわる教育ではなく、強い者が弱いものに手を差しのべる、そんな
教育であってほしい。
ところが、「先生が生徒をいじめていた…」なんて、とんでもないTV報道。
学校現場も、落ちるところまで落ちてしまったようです…。
教える側の先生に、倫理観・道徳・人間性が欠落しているのでしょう…。
当の先生が悪いというより、先生の子どもの頃の家庭や教育環境が悪かった
からでしょう。
安倍内閣のキャッチフレーズは、「美しい国日本。敗者が復活できる国づくり」
美しい日本にするために、教育を含め、何をどう意識改革していくのか?
今一つ見えてこない?

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 147】
~幸せな人生を歩むために~
「運動会抜くなその子は課長の子」
雪印事件から早や七年になる。企業犯罪は性懲りなく繰り返され、収まりそう
にない。なぜこのような事件が繰り返えされるのだろう?
そこには封建時代のなごり?「藩」の主従関係に近い社風が垣間見える…。
私は以前、業種の違う二つの「大藩(会社)」に仕え、禄を食んだ経験がある。
大きな会社は、組織と上下関係がガッチリしていて、歯車の一つとしての責任
は重く、みッちり働かされた。有給休暇を取る余裕もなかった。
会社の都合が全てに優先し、家庭も私生活も犠牲にして、身を粉にして働いた。
企業戦士と言われて頑張ってきた世代なのです。
現在も仕事に追い回され、過労死するといった、労働災害があとを絶たない。
一年前のJR西日本の脱線事故。事故を起こした若い運転手、お客様の安全よ
り、遅れを取り戻すことの方が大事…。懲罰が頭にちらつき、何とか遅れを取り
戻そうと事故を起こし、死んでしまった。
会社から月給という禄を与えられ、会社が世間の常識やモラルに反することを
習慣的にやっていても、「お家(会社)第一」
のじゅばくにかかり、見ざる・言わ
ざる・聞かざるの、家畜ならぬ"社畜"と化している…。
岐阜県庁で裏金が発覚し、処置に困り、500万円を燃やしてしまった職員…
まだ記憶に新しい。三菱自動車のリコール隠しもそう…。月給は口止め料、
もしくはガマン料である…。
大きな会社、個人の力は小さい。一人問題意識を持ったところで、どうなるも
のでもない…と、私は思ってきた。
ところが「内部告発」というやり方で、企業のモラルを正そうとする動き…見逃
せない。企業の良識、まだ失っていないということでしょうか? 会社への忠
誠心が薄れてきたことも、その一因でしょう…。
私が勤めていた頃…実力で所長から部長になり、将来は取締役と言われたA氏。
ところが、五十前の働き盛りに、突然後輩に道を譲るようにと言われ、机が一つ、
部下が一人もいない閉職に追いやられた。日頃、A氏の傲慢な言動を嫌った部
下が、連名で社長に直訴した、というのが表向きの理由…。
閉職になった途端、面倒を見た部下が離れていく…。出世コースから外された
無力さを思い知らされ、居場所を失ったA氏、寂しく退職していった。
講談社の「平成サラリーマン川柳傑作選」には、そうしたサラリーマンの悲哀が
数多く詠い込まれていて、どれも、身につまされる…。
「運動会 抜くなその子は課長の子」
「ああ言えばこう言う奴ほど偉くなり」
「持ち歌を歌ったばかりに 左遷され」
「社宅では 犬も肩書き外せない」
「シッポ振るポチに 自分の姿見る」
「客よりも上司を立てる大会社」
2006年09月19日
自分らしく生きるとは?
「神様からのメッセージ」 大野勝彦(詩絵集/やっぱいっしょがええなあ)
な…体が欠けたんじゃ、それでも生きるんじゃ、それだから生きるんじゃ…
何だ偉そうに、「格好悪い、ああ人生おしまいだ」なんて、一人前の口を叩くな
あのな、お前が手を失って、悲劇の主人公みたいな顔して、ベッドでうなって
いた時な… 家族みんな、誰も一言も声が出なかったんだぞ
ご飯な、食卓に並べるのは並べるけど、
箸をつけるものは、だぁれもいなかったんだぞ
これまで一度も、神様に手なんか合わせたことがない、三人の子どもらナ
毎晩、じいさんと一緒に正座して、神棚に手を合わせたんだぞ…
バカが、そんな気持ちも分らんと、「なんも生きる夢がのうなった」だと…
そんなこと言うとるんだったら、早よ、死ね! こちらがおことわりじゃ
(途中略)
両手を切って、手は宝物だった。持っているうちに気づけばよかった
それに気づかんと、おしいことをした。それが分かったんだったら…
(途中略)
あの三人は、いじらしいじゃないか。病室に入ってくる時、ニコニコしとったろが
お前は、「子達は、俺の痛みも分っとらん」とグチ、こぼしとった…
本当はな、病室の前で、涙拭いて「お父さんの前では、楽しか話ばっかするとよ」
と、確認して、三人で顔でうなずき合ってから、ドアを開けたんだぞ…
(途中略)
歯をくいしばって、度胸を決めて、ぶつかってこんかい!
死んだつもりでやらんかい!
もう一遍言うぞ、"大切な人"の喜ぶことをするのが人生ぞ! 時間がなかぞ…

【心と体の健康情報 - 261】
~幸せな人生を歩むために~
自分らしく生きるとは?」
「仕事と人生」、どっちの方が大きく、大事だろう…?
仕事が人生をつくり、人の一生に大きく関わっていく。が、"人生"という器は
一つだけ! 壊れてしまえばそれまでだ…。仕事という器は、いくらでも代わ
りがある。人生の器の方が、仕事の器より遥かに大きいことに気づく…。
そんなことに気づかず、小さな器の仕事に、大きな器の人生を無理やり押し
込んで、あがいてはいないだろうか…。一度しかない人生…仕事で人生を
犠牲にするようなことがあってはならない…。
二回に渡って、「大学を出ることの意味」を考えてみた。
大学進学は、自らが志す人生目標への、大切なステップ。ところが、なぜか
大学に合格することが目的になり、合格し、夢が叶ったら、気が抜けてしまい、
それから先の人生を深く考えようとしない。
目標がなければ、今に目が向く。我慢し続けた青春を、取り戻そうとするかの
ように、バイトに遊びに夢中になる。人間を磨かなければならない大切な時を、
無為に食いづぶす若者が目立つ…。
そんな若者が多くなったのは、社会人になった後の、幸せの掴み方・考え方に、
拒否反応を示す若者が増えてきたからではないでしょうか…?
幸せとはほど遠い人生を、大人たちが懸命に歩いている姿を見て…、
どうしたら「自分らしい人生」が歩めるか…、見つけられないでいる。
大学を出て、難関を突破して入った大企業。家族に祝福され、その時は未来が
約束されたかのように思う。入社してまず驚くのが、社内に溢れる優秀な人材。
頑張らなければ、取り残されてしまう。
勤めた会社で、人生の成功を掴むには、出世競争に打ち克たなければならない。
業績を上げ、高い評価を得ようと、懸命にならざるを得ないのです…。
ようやく学力競争から抜け出たと思ったら、今度は仕事漬けの人生…どこまで
いっても競争、競争…きりがない。家庭や家族を犠牲にしてまで、追い求める
ことには思えないのです。人生、どう生きればいいのか…、将来が見えてこな
いのです。
経営者を見る目、売上額と従業員の数で、経営者の器の大きさを推し量る。
故に?どの経営者も、会社を大きくしようと懸命になる。
たまたま運に恵まれ、時流に乗って会社を大きくしても、経営環境が変化して、
為すすべも無く会社を潰してしまう。そんな事例を数え切れず見てきた。
拡大路線をひた走り、器以上の会社にしてしまったがゆえに、支えきれなくな
って、仕事だけでなく、家族までも失ってしまう羽目に…。己の器に合った堅
実な経営を心がけていれば、幸せな人生になっただろうに…。
経営に失敗し、自殺まで考える社長さん。今の仕事に人生のすべてが凝縮され、
とても手放せないのは分ります。人生より仕事の方が大事なのでしょうね?
でも、自分と家族の幸せのための仕事でしょう…。突き放して、客観的に見つ
めれば、今の仕事、幸せな人生を手にするための、手段にしか過ぎないのです。
だから、今の仕事で幸せになれないのなら、サッサと諦め、新しい人生を模索
すればいい…。今の仕事にこだわるばっかりに、人生を、未来を、見失なうこ
とになってしまう。
 ある日、突然の事故で両手を失った"大野勝彦"氏。
ある日、突然の事故で両手を失った"大野勝彦"氏。
昨日までの家業で、天職の農業。その農業を諦め、新しい人生を模索しなければならなくなった。
事故がきっかけで、それまで隠れていた才能が開花した。
絵手紙詩画の第一人者として、その名を日本中に知られるようになった。
今までの人生の何十倍も、世界が広がったのです。
(9/14 石川TV・PM8時 アンビリバボーで放映)
これは例外かもしれない。
が…人の一生、
「吉凶禍福はあざなえる縄のごとし、人間万事塞翁が馬」
何が良くて、何が不幸か、 過ぎ去った後になってみなければ分らない…。
2006年08月29日
サラリーマン2:8の法則
来年、300万人の団塊の世代が定年を迎える。支払われる退職金は約60兆円。
その使い道が気になる? 銀行の調査によると、一位は住宅リフォームに使われ、
次いで海外旅行だそうです。人生の節目を記念して夫婦で出かけるのです。
4月上旬、日本一の豪華客船"飛鳥2"が、世界一周の旅へ横浜を出航した。
参加費は一人1,600万円。募集早々満室になった。息子に事業を譲ったとか、
定年退職を節目に、夫婦での申込みが多かったという。
この旅行、夫婦で参加すると、新築マンションが購入できる金額になる。
庶民暮らしの私には、お金が無いこともあるが、"もったいない"が先に立ってし
まう。3千万・4千万出しても、世界一周旅行したいと思う人は、お金持ちです。
退職金60兆円。そこから約8兆円のお金が消費に回るという。株や投資信託な
どの金融商品には手を出さず、残りの約50兆円はしっかり貯蓄。企業のお金が
個人名義に振り替るだけという…。
これから定年になる団塊の世代は、それ以前に定年になった人より、生活を
楽しもうとする意識が強く、5~6年は消費の後押しをしするだろうというのが、
その筋の予測。

【心と体の健康情報 - 258】
幸せな人生を歩むために
「サラリーマン2:8の法則」
「勝ち組」「負け組み」という言葉は、企業間競争の中で使われる言葉です。
終身雇用制が過去のものになろうとする中、サラリーマンの世界にも「2:8の
法則」つまり、二割の社員が"総支給給与"の八割を独占し、八割の社員が
残った二割の給与を分け合う時代、実力がモノを言う時代になろうとしている。
今から30年前、セキスイハウスの中間管理職の頃、年に二回、賞与配分の
幹部会が持たれた。丸一日かけて、遡る6ケ月間の業績から、部署ごとの賞与
配分率が決められていった。業績上位と下位の営業所とでは、受け取る額に
最高30%くらいの格差が生じた。
部署に配分された賞与は、部下の業績・貢献度に照らして振り分けていく。
営業社員や、技術社員は40~60万円、内務の女子社員は20~30万円の
範囲で、査定に従い振り分けていく。当然、業績の良い社員と、そうでない
社員の受取額に格差が生じてくる。
年俸制が当たり前になった今、会社への貢献度で評価。役職・業績・能力に照ら
して、毎年給与額が決められていく。
以下、UFJ総合研究所 主席研究員 森永卓郎「年収300万円で人間らしく
生きるか…」からの抜粋です。
|
年俸制が給与制度の主流になるにつれ、所得層が三つに分類される。 ほとんどのサラリーマンはBクラスに入る。「百倍の法則」
と呼んで |
吉本興業のような実力がモノをいう世界。桂三枝の年収が一億円。
一方、年収百万円にも満たない、食えない社員も沢山いる。プロの世界では、
早くから「百倍の法則」が働いている。松井と二軍選手の所得格差を見れば分かる。
ホリエモンや村上世彰氏のように、百倍どころか、数年で何百億円稼ぎ出し、
世間を騒がせる新人類も現れてくる。
|
人生には、二つの選択が考えられる。頑張って大金持ちになるか、 対して、一般的サラリーマンの生活は、テレビ、冷蔵庫などの耐久 |
周りを見渡すと、我が子の才能を見い出し、幼い頃から鍛えぬき、一流人に育
てるケースが珍しくなくなった。ゴルフの藍ちゃん、卓球の愛ちゃん、イチロー
選手などが良い例。スポーツだけでなく、歌手、俳優、碁士など、実力が問わ
れる世界で、近年目立って増えてきた。
そこまでいかなくても、我が子の才能、優れたところを見い出し、まだ物心つ
かない頃から、スパルタ英才教育を施すお母さん…。ゴルフ練習場で、小さな
子に付っきりで、ゴルフのイロハを教えているお父さんの姿を、よく見かける。
2006年04月25日
本当に反省できたら、顔つきが変わる
 京都駅美術館「えき」で、モネ、セザンヌ、
京都駅美術館「えき」で、モネ、セザンヌ、
ゴーガン、ゴッホなどの「印象派」の名画を
鑑賞した。目玉は、ルノワールの
「レースの帽子の少女」。
モネやルノワールの作品には、「点画」
が多い。自然界のキラキラと輝く色彩を
キャンバス描き出そうと、絵の具を混ぜ
ると、どうしても色がにごってしまう。
光に包まれた自然の色彩を描き出すに
は、絵の具を混ぜずに原色のまま、同
じ大きさの小さな色彩の粒を沢山並べ
て描き出す「点画手法」をあみ出した

【心と体の健康情報 - 241】
~幸せな人生を歩むために~
「本当に反省できたら、人間顔つきが変わる…」
NHKで放映中の韓国ドラマ、「チャングムの誓い」に出てくる悪役女優たち、
悪いことを企んだときの目つき・表情は、まさに悪人そのもの。見ていて腹が
立ってくる。一流俳優の証しであろう…。
私にも相手にも同じことが言えるのだが…、初対面の人の第一印象、わずか
数分で、相手が何ほどの人物なのか分ってしまうから恐ろしい。
苦労した人か、器が大きいか、小さいか、大らかか、細やかな人か、優しいか、
大概察しかつく。相手の表情、目つき、言葉、態度etc、日頃の姿が表情・
態度に表れてくる。お互い、そうやって相手を推し量るのです…。
今人気絶頂の六星占術の細木数子。「来るべき運命のすべてを解き明かす」と、
毎晩どこかのTV番組に登場する。彼女は直感力に長けた話術の天才である。
あのクリクリした大きな目で、「ずばり言うわよ!」と、マジマジ見つめられたら、
ヘビににらまれたカエルのように、細木の術中に引き込まれてしまう…。
何か悪いことをして、ひた隠しにしている人。会社が倒産寸前なのに、平静を
装っている人。私の経験では、そういった人の顔色はどす黒く、陰気で、どこ
か身体の具合でも悪いのでは? そんな表情をしているものです。
以下、コラムニスト・秋庭道博氏の「きょうの言葉」からの抜粋です。
|
「本当に反省できたら、人間顔つきが変わるものだ」
それは、心からわびていないからだ。そもそも「遺憾だ」とか、「あってはならないことだ」 などという言葉は、謝っていることにはならない。 |
国会の答弁、「善処する」なども、自分の責任を棚に上げた、ごう岸そのものの
言葉だろう。エライ人ほと、責任を取ろうとしない…。
だから、「二度とあってはならない」と言いながら、同じことがたびたび起こる。
反省することのない当事者。当然、顔つきも態度も変わらない…。
2006年03月31日
「てんびんの詩」から学ぶ
■ユダヤ商法に学ぶ
ユダヤ人は「倹約するほうが、金儲けより難しい」
と、私たちに教える。
「せっかく稼いでも、倹約して、無駄使いを止めなければ、財産を築き上げる
ことはできない」と…。
・20世紀の初頭、東欧の迫害から逃れるため、着の身着のままアメリカに移住。
必死に働き、お金を蓄えたユダヤの人たち。ただ蓄え・倹約するのではなく、
将来いざという時にそなえ、より重要な目的のために貯金したのです。
・そういった歴史的背景から、ユダヤ人は倹約家。金銭にこだわる。財布の紐を
解く前に、その品物に値する価値と目的が、果たしてあるかどうかを仔細に検
討し、見極める。熟考の末、支払う段になっても、値引きやサービスの余地が
ないか交渉し、少しでも倹約しようと努力する。
・倹約はケチと混同されがち。が、ユダヤ人は一旦事態に直面したら、思い切っ
て惜しげもなく大金を投ずるのです。
「理念と経営2月号」

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 118】
「てんびんの詩から学ぶ」
毎年四月になると、新入社員の「飛び込み研修」を行なう。
研修は2~3ケ月続き、目標に到達した社員から順に修了していく。
最近はこらえ性がなく、折角難関突破して入社した会社を、辞めていく人が多
くなった。苦労の経験がないから、耐えられないのでしょう…。一番の問題は、
行き詰って悩んで親に相談したら、「嫌なら辞めてもいい…」と言う、子どもを
甘やかす親の存在です。
3月、商業界の一泊研修で、久しぶりに近江商人の物語、「てんびんの詩」を
鑑賞した。私の会社も研修で使ったが、鍋ぶたが売れた瞬間は、何度見ても
涙がこみ上げてくる。
この映画は、故"竹本幸之祐"監督(石川県羽咋市出身)が、鍵山秀三郎氏の
資金援助を得て、二十数年前に作られた名作です。
物語の中で、私たちの教訓となり、心にしみることばが随所に出できます。
母「働く人の喜びや、しんどさがわからんようでは、人の上に立てやしまへんえ
…。人に出会うて、ご挨拶も出けんで、商人(あきんど)になれますか!」
「商人は、自分を恥ずかしめるようなことをしてはいけません。 頼みます、
お願いします…て、頭下げて、売れるもんやおまへんえ…」
(飛び込み研修の目的の一つに、きちんと挨拶のできる人間になることがある)
祖母「代々、分をわきまえることを大事にしてきました…。儲けの少ないときは
始末をして、極力、出を抑えることや。ご先祖が、梅干や塩をなめてしのい
できたさかいに、今日があるのです」
「日頃商人(あきんど)は、質素でなければいけません。 しかし、商いのため
やったら、惜しみなくお金を使う。 楽をするためや、贅沢のためにお金を使
こうてはなりませぬ。自分が始末してでも、お客にちょっとでも有利な商いを
する…。そのために、お金を使うことや」
(私の父親の時代の商人の基本的な考え方でした。ユダヤの商法と相通じると
ころがあります)
百姓「百姓はなんぼ頑張って精を出し、きばっても、入ってくるもんには限り
がある。食うだけで苦労して、一生終わるのが百姓や…。
それに引き換え商人はいい。己の才覚と努力で、いくらでも発展するやな
いか…」
祖母「子は今、親離れするための行をしとるとこや…。母親だけが辛いんでは
ない、子の修行は親の修行でもある。大作も、それくらいの苦しさを乗り
越えれんようでは、跡取りにはなれしません。 苦しさを乗り越えんと、
一人前の人間にはようならん…」
母「あせったらあかん!一度決めたら最後までやり通すことや…。
途中で投げたら、後悔することになるえ…」
父「商いは、天秤棒といっしょや…、どっちが重とうてもうまく担がれん…
お客と売り手の心が一つになったとき、初めて商いが成り立つんや…」
母「うまいこと売ろう思うたかて、あきしまへん! 一生懸命生きている姿を
知ってもらうしかあらしまへん…正直な子やな…、優しい子やな…、信頼
できる人間やな…、役に立つ人やな…と思わはるさかい、商いがでけるん
や…」
叔母「親戚に頼ったり、家柄でモノを売ろうとするさかい、売れしまへんのや。
自分の商いをせなあきません。
誰の力も頼らんと、自分の知恵と努力と人柄で商いをすることや…」
「お前は自分のために鍋ぶた売ろうとしとるやろ。自分の都合ばかり考えと
らんと、人のために商いをすることや…」
「商いとは、お客様のお役に立つためにするもんや…。人の役に立ってみな
はれ…、そんな人、誰からでも好かれ、モノが売れるようになるんや…」
「家業を継ぐとは、自分をころして、お客様やお店のみんなのために奉公す
ることや…」
「商人に一番大事なのは、買うてくれるお客様の気持ちになって商いをする
ことや…」
大作「人の道に外れたことをしては、商いはない…」(ふと、鍋ぶたを川に投げ
れば、売れるのではと頭をよぎった時…)
「親戚やからと、甘えとった…。叔母さんは鍋ぶた買うてくれるより、もっと
大事なものをくれはった。商人になるための一番大事なものや…。
それまで私は、ただ鍋ぶたが売れればいい、それだけしか考えなんだ…。
買うてくれる人の気持ちなんぞ、考えもせんかった…」
ようやく売れた。物が売れた喜びと、見ず知らずのお客様が、私を抱きしめて
泣いてくれた感動が一緒になって…、商人ほど素晴らしもんはないと思うた。
「売るもんと、
買うもんの心が通わなんだら、モノが売れんのや」
ということを
…痛いほど身にしみました。
始める時に父親が、「売れたら分かる」と言うた意味…、売れてみて初めて、
「これが言いたかったんや…」と分かりました。
…このように、てんびんの詩は観るたびに、いろんな気づきを与えてくれます。
古き良き時代の商人の物語「てんびんの詩」。そこから、商人の心を学ぶ…。
どんなに時代が変わろうとも、"人と人との心の結びつき"は永遠です。
ところで、「てんびんの詩」の続編を知らない人が多い。
第二巻は、奉公先から中学へ通い、韓国で飛び込み行商を実習する。風俗習慣
の違い、言葉の壁、そういった苦難を乗り越え、「客とは何か」「売るとはどんな
ことか」を学ぶ。第一巻に劣らず、涙なしには見られない、感動の作品です。
三巻は、太平洋戦争という時代の流れに翻ろうされる。大作は召集され戦地へ。
敗戦でイギリス軍の捕虜収容所を経て帰国。戦後の財産税や農地解放で裸同然
に…。度重なる苦難を乗り越え、新たなる希望が…。感動の大作です。
2006年02月10日
企業理念と信用
1月30日、お昼を食べながらTVを見ていたら、欠陥木造住宅に住む夫婦の話
が…。あまりにもひどい施工。問題の箇所が次々と大写しになる…。
以前、住宅会社に勤めていた時に、体験したことです。
屋根も葺き、内部造作も進み、内装工事に入った矢先、施主からクレームが出た。
「即刻、やり直せ!」と言う。現場は「問題にするほど、工事に欠陥がある訳ではな
い」と、甘く見た。
45坪の邸宅。二階までしっかり組み上がっていて、「はいそれでは…」というわけ
にはいかない。現場サイドで事を穏便に治めようとして、こじらせてしまった。
責任者の私の耳に入った時は、大事になっていて、「全部壊して最初から建て直
せ!」と、施主は大の剣幕。どうにもならなくなり、本社の専務に相談した…。
帰ってきた返事は「施主の言う通り全部壊してやり直しなさい。損得より信用だ!」
施工費は値切られ、遅延損害金も払わされた。その一件で、その年の営業所の
利益は飛んでしまった。今も忘れられない、富山での出来事です。

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 111】
~幸せな人生を歩むために~
「企業理念と信用」
1月末、松下電器から葉書が届いた。表に「松下電器より心からのお願いです」
とある。20~14年も前の、不良FF暖房機の回収に懸命になっている。
昨年から、TVコマーシャルやホームページに告知しているが、それだけでは
不十分と、全国すべての所帯に宛て、DMを発送した。
回収に要した費用は、昨年だけで230億円だという。人命を守り、失いかけた
信用を取り戻すためとはいえ、これほど膨大なリスクを決意した、松下電器の
経営姿勢には、頭が下がる。
それと相反することをしたのが、大手ビジネスホテルチェーンの"東横イン"。
私の京都の常宿である。価格が安く、サービスも悪くない。朝食無料が魅力で
、よく利用する。
許せないのは、検査終了後、改装する段取りに、あらかじめなっていたこと…。
計画的に、検査機関の目を"ごまかす"行為が、会社ぐるみで行われていた。
姉歯やヒューザーと同罪じゃないですか!
このニュースは当初、ライブドア事件の陰に隠れて、あまり目立たなかった。
釈明のための社長の記者会見がまずかった。俄然、マスコミが騒ぎだした。
この企業、身障者にはまったく無理解。「お客様のために…」と言いながら、
収益性を最優先する社風。
「使われないスペースは無くせ…」と、社長の指示。経営者の資質・社会的道義
が問われる。モラルの低さにはあきれる。どんな経営理念の会社なんだろう?
この事件が起きる前の東横インのイメージは良かった。支配人など、管理職の
ほとんどは女性。女性を積極登用して、急成長したホテルとして知られている。
女性支配人の募集は経験不問。最初から素人を採用した。
素人には、「ホテルとはこう…」といった固定観念がない。自由な発想が、朝食
無料サービスや、アダルトビデオ放映廃止となって表れた。優しく、人当たりが
よく、きれい好きな女性の特性が生かされ、男性では気付かない細部にも目が
ゆき届く。日本旅館の"女将"が、登用のヒントになっている。
2000年6月、雪印食中毒事件に端を発し、その後何度となく繰り返される
企業モラル喪失事件。消費者の信用を失墜し、会社存亡の危機に陥り、
経営陣が平身低頭するのを、何度見てきたこだろう…。
ところが、自分の会社のこととなると、モノごとの本質が全く見えていない。
私たちの世代は、政冶・経済・教育、全ての分野でリーダー的位置付けを担って
いる。戦後教育を受けた最初の世代です。その世代が日本を動かしているのです。
豊かさを求め、ひたすら会社の為と働いてきた。物欲・金銭欲が強く、利己的
で自分本位。社会性・道徳性に欠け、公徳心が薄い…そんなことが気になる。
問題が自分に及びそうになると、自己保身に走り、責任を取ろうとしない…。
いさぎよさがない…。男の器、総体的に戦前教育を受けた親の世代に比べ、
小さくなったような気がする…。
2006年02月07日
ユーキャンドゥイット/交流分析
昨年暮れ、 娘に薦められて「ハッピーバスデー」を読んだ妻。
感動して、もう一度 読みたいという。 ならばと、私も読んだ…。
児童書として1997年に刊行され、「お母さんも読んで…」と、子ども達が
「ぜひ大人に読んでほしい本」として読み広がり、ベストセラーになった。
内容は、「不登校・差別・イジメ・虐待・命」、そして「生」という、重い題材
がテーマ。
クラス全員で本を読み合っているうち、"いじめ"が自然消滅したという。
また、この本を読んだ大人たち、今まで見えなかったものが見えてきて、
「ハッ」としたという。

【心と体の健康情報 - 231】
~幸せな人生を歩むために~
「ユー キャン ドゥ イット/交流分析」
人間関係には、良い人間関係もあれば、悪い人間関係もある。
良い職場、良い家庭というのは、必ずといっていいほど、良い人間関係に包まれ、
明るくヤル気にあふれ、職場にあっては業績もよく、社員の満足度も高い
といえます。
しかし、そういった中にも、人間関係でしょっちゅうトラブルを起こしたり、
ヤル気を削いで、雰囲気を悪くさせる人がいるものです。
以前勤めていた会社で一年間、管理者養成研修を受けたことがある。
営業部門の中間管理職七人が対象。指導には、東京の人材育成コンサルタント
会社が当たった。
研修の内容は「管理者としての自覚」。自己を鍛えるだけでなく、部下のほめ方・
叱り方、心理学、経営哲学など、幅広い分野に及んだ。
研修でインパクトがあり、興味を引いたのは「交流分析」
。
エリツク・バーン博士の心理学です。
「自分が持っている本来の能力に気づき、その能力の発揮を妨げている
様々な要因を取り除いて、自らが持つ可能性に向けて生きていこう… 」
というもの。
しょっぱなから、その研修は始まった。期待と不安の中、テーブルを挟んで
向い同士座り、そのうちの一人が、皆の前に座らされた。
「はい、皆さん、これから一年間、七人がより親密に、心を開いて、本音で学
び合えるようになるための、最初の研修を行います…。
それでは、皆さんの前に座っているAさんの、優れた所を5つつ、欠点を5つ
つ、模造紙に書いて下さい。その後Aさんから、自分の利点と欠点を発表し
ていただきます。続いてAさんに向かって、一人づつ発表していきます…。
七人全員、交代でやっていきます」
会社では仲のよい同僚…。一方で、互いにライバル意欲を燃やし、業績と出世
を競い合う仲…。普段、仕事上で本人を前にして、誉めたり非難したりするこ
とはない。
誉め言葉5つは直ぐに書けた。しかし、欠点を書き出せと言われて、困ってし
まう。二つくらいならまだいい。しかし5つとなると…こんなこと、書いていい
ものだろうか…、発表できるだろうか…。手が止まる。
発表の時になって、講師は大声で怒鳴った。「何をかばい合っている…。
思っていることは、隠さず本音で語れ!心を開示 しろ!気遣いは無用…」
日頃親しい人から、面と向かって欠点を指摘されたことなど、一度もない。
六人が交代で、私の良いところ、悪いところを指摘した。そのたびに心が動揺
し、顔を赤らめ、うつむいて聞いた。研修とはいえ、人の欠点を捜し出して
(これを"あら捜し"というのだろう…)発表するのは、何とも気まずく、後味の
悪いものだ。
ところで、私たちは自分のことを、どれだけ知っているだろうか?
自らの長所・短所に気づき、自分の持っている「能力と価値」に気付けば、
対人関係は、必ず良くなっていくだろう。
「自分にしかない、素晴らしい能力や価値があるのに、それを発揮出来ないで
いるのは、それを妨げるものがあるからである。その要因に気付いて、取り除
いていこう」というのが、この研修の目的である。
こうして、心の内面を心理学から分析し、学習し、体験することによって、
素直な気持で、外に向かって自己表現出来るようになる。前向き・肯定的に
物事に対処出来るようになっていく…。「ユーキャンドゥイット」の精神が生き
てくるのです。
2006年01月17日
人生誰のため、何のため頑張るのか
■人生、最後が良ければすべて良し…
NHK大河ドラマ「義経」で、あかね役を演じた女優の萬田久子さんが、
自らの人生を振り返って、次のように語っている。
「人生はオセロみたいなもの。
途中、白黒いろんなことがあるけれど、最後に白を取れば全部白になる。
人生を振り返ると、途中何年も辛いことがありました…。
けれども、その時期があったからこそ、今があると思うのです。
人生、最後に白を取れたら、すべて良しなのです…」

【心と体の健康情報 - 228】
~幸せな人生を歩むために~
「人生誰のため、何のために頑張るのか…」
誰もが、いい人生でありたいと願っている。だから、自らの人生のために勉強
するのは、しごく当たり前のことです…。
前号で、「勉強は自分のためではなく、人のためにする」というお話をしました。
「自分のためではなく、人のために学ぶ…」。理屈では分かるのですが、今一つ
説得力に欠ける。そこで、更に突っ込んで「人生誰のために、何のために頑張る
のか…」を、考えてみたいのです。
トリノオリンピックまであと一ヶ月。代表選手が次々と決まっていく。
前々回シドニーの女子マラソンで優勝した高橋尚子。「自分がこんな成績を上げ
られたのは、監督さんのお陰であり、応援してくれた皆さんのお陰です」と、
その時のインタビューで語っている。
あれだけの成績を出せたのは、決して自分一人の力ではなく、両親や監督、
応援して下さった多くの方々のお陰だと、自分の中でしっかり受け止め、
それをエネルギーにして走ったという。
そこで思い出すのが、更に四年前、アトランタオリンピツクの時…。
あの時、三位で表彰されたのが有森裕子さん。高橋さんと同じ小出監督に育て
られた。
二位に入ったのがロシアのエゴロワさん、一位はエチオピアのロバさんでした。
NHKは、この三人にインタビューしている。
まず銅メダルの有森裕子さんに、「あなたは何故そんなに一所懸命走るの?」
と尋ねたところ、「私は自分のために走りました」と答えた。
前回は二位、そして今回は三位に終わった。
しかし彼女は、自分自身のためにベストを尽くして走ったのだから、
三位になっても「自分を誉めてあげたい」と、胸を張って言い切った。
その言葉が国民の共感を呼び、その年の「流行語大賞」になった。
銀メダルのエロゴワさんは、同じ質問に対し「それは、家族や親戚のためです」
と答えている。ソビエト崩壊直後のロシアは生活が大変だった。
「自分が頑張れば、家族や親戚が豊かになる」。そのためには、どうしても勝た
なければならない。アメリカに渡り、特訓に耐え、そして、勝利したのです。
金メダルを取ったロバさんは、「私は祖国の名誉のために走りました」と、
凛として答えた。
「私は、東京オリンピツクで優勝したアベベ選手を尊敬しています。もう一度
祖国エチオピアに栄光をもたらしたい。その思いから頑張りました」と言う。
それまで無名だったロバさん。無名の新人が、自分と家族のためだけではなく、
祖国の栄光のために、金メダルを勝ち取ったのです。
三人三様それぞれ、熱い思いを胸に、自らが目標とする栄光のために走った。
人が人生を歩むとき、「どんな思いを胸に歩むのだろうか?」。
かけがえのない人生、自分のために頑張るのは当然でしょう…。
それは、自分を大切にする思いの中から、沸き出てくるものだからです。
けれど、その自分は誰の世話にもならず、この世にポツンと生まれてきたわけ
ではありません。必ず両親があり、家族があり、地域があり、国家があり、
世界があり、生まれてきた時代が関わってくる。
国家との関わりでは、あの忌まわしい太平洋戦争で散っていった特攻隊員や、
モスクワ大会ボイコットで、機会を逸した柔道選手などのことが思い浮かぶ。
家族や周囲の人々のお陰で、学校や地域の人々に支えられたお陰で、日本
という国に生まれたお陰で、持てる力を存分に発揮することが出来たのです。
そういう思いを持ち続けていれば、自分の人生は、決して自分のためだけに
あるのではなく、地域社会すべての人たちとのつながりの中で、生かされて
いることに気づくのです。
そこから、自分に、そして周りのすべてに感謝できるようになっていく…。
そういう気持が、「人から与えられることに満足するだけではなく、人のため
に何かをしたい…、社会のお役に立つ仕事をしたい…、両親に恩返しをしたい
…」。そんな思いが、歳を重ねるにつれ、湧き上がってくるようになる。
そんな思いを実現するために、更に「勉強しよう!」という気になるのです。
2005年09月20日
心の花を咲かせよう
■詩人・坂村真民の代表作 「二度とない人生」
二度とない人生だから 一輪の花にも 無限の愛を そそいでゆこう
一羽の鳥の声にも 無心の耳を かたむけてゆこう
二度とない人生だから 一匹のこおろぎでも ふみころさないように
こころしてゆこう どんなにか よろこぶことだろう
二度とない人生だから 一ペんでも多く便りをしよう
返事は必ず 書くことにしよう
二度とない人生だから まず一番身近な者たちに できるだけのことをしよう
貧しいけれど こころ豊かに接してゆこう
二度とない人生だから つゆくさのつゆにも めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめて みつめてゆこう
二度とない人生だから のぼる日 しずむ日 まるい月 かけてゆく月
四季それぞれの 星々の光にふれて わが心を あらいきよめてゆこう
二度とない人生だから 戦争のない世の実現に努力し
そういう詩を 一篇でも多く作ってゆこう
わたしが死んだら あとをついでくれる若い人たちのために
この大願を 書きつづけてゆこう
・この詩を口ずさむと、心が清らかになり、人間が本来持っている美しい心や
優しさが、よみがえってくる。

【心と体の健康情報 - 212】
~幸せな人生を歩むために~
「心の花を咲かせよう」
夏休み、夜中の12時過ぎ、片町のネオンに彩られた繁華街に、高校生だろうか、
女の子たちがたむろしているのを見かけた。
どの子どもたちも、これからすくすくと成長していく若木である。どんな若木も、
大人たちがきちんと育てれば、立派な大樹になるだろう。
親や学校の先生が、地域社会の大人、社会が、慈しみ、丁寧に愛情を込めて
育てるならば、どの子もすくすく育ち、必ず美しい花を咲かせるだろう。もしも
枯れたり、素直に育たない子どもがいるとしたら、それは間違いなく大人たち
の責任である。
以下、致知7月号冒頭の言葉、京セラ稲盛和夫「心を整える」からの引用です。
二十世紀初頭にイギリスで活躍した、ジェームズ・アレンという思想家は、人生
を歩むについて、次のように述べている。
人間の心は"庭"のようなものです。それは耕されることもあれば、
放置される
こともあります。何れにしろその庭からは、必ず何かが生えてきます。
「仕方なや 蒔いたタネなら はえるもの」
もしあなたが、自分の庭に美しい草花の種を蒔かなかったら、その庭にはやが
て、雑草のみが生い茂るようになります。
美しい花がいっぱい咲く庭にしたいと思うなら、庭を耕し、雑草を取り除き、
美しい草花の種を蒔き、それを育くんでいかなければなりません。
「悪いタネ 伸びて刈らねば 身の破滅」
素晴らしい人生を生きたいと思うなら、自分の"心の庭"を掘り起こし、そこか
ら不純な誤った思いの雑草を一掃し、そのあとに清らかな正しい思いの草花を
植えつけ、それを育んでいかなければなりません。
素晴らしい人生を送りたいと思うなら、あたかも庭を耕すように、心の中に
もたげる「悪しき思い」という雑草を取り除き、「善き思い」という種を蒔き、
それを大切に育み育てることだと、アレンは述べている。
このようにして、ともすれば心の中に広がろうとする、「欲にまみれた心」
「憎しみにまみれた心」「怒りに満ちた心」などを取り除き、「慈悲の心」
「愛の心」といった、美しい"花"を咲かせるようにするのです。
「慈悲蒔けば 美しき心 花と咲く」
仕事も人生もすべて、その人の心がそのまま表れてくる。ただひたむきに善き
方向に心を向けて、努力を重ねていくならば、必ず素晴らしい未来へと、導か
れていくでしょう。
「心こそ 心迷わす 心なれ 心に心 心ゆるすな」
2005年09月13日
あなたは性善説、それとも性悪説?
選挙結果が出た。小泉さんの功績は、派閥主導の自民党をぶっ潰したこと。
もう一つは、小泉さんと袂を分かち、自民党を離れていった人たちの後がまに、
女性を多数登用したこと。人気取りと非難の声もあったが、能力のある女性に、
国会議員への道を拓いた功績は大きいと思う。
国連が9月7日、女性の社会進出に関する、興味深い数字を発表した。
「ジェンダー・エンパワーメント指数」である。国会議員や企業の管理職などの
女性の割合がどの程度か、男女の所得格差は? 指数として割り出し、世界
ランキングが発表された。
調査対象80ケ国中、日本は43位。42位はタンザニア。もちろん先進国の中
では最下位。お隣の韓国や中国では、日本の倍近くの女性が、国会議員や、
企業の管理職として活躍している。経済大国と言われながら、女性の社会進出
の機会を狭めている日本の社会風土…。21世紀は女性の世紀と言われる。
意識改革をしなければならないのは、男性のようです。

【心と体の健康情報 - 211】
~幸せな人生を歩むために~
「あなたは性善説、それとも性悪説?」
人間の本性、それは「善である」という人と、人が見ていなければ、或いは法律
がなければ、本能のままに行動したら、人間の本性は「悪」であるという人。
さて、山本さんはどちらでしょうか?
■「性善説」
を唱えた孟子
「人の本性は善であり、不善をするのは物欲がなせるわざ」という説です。
数年前、プラットホームから転落した男性を救おうとして線路上に飛び降り、
電車にはねられ死亡した韓国青年のニュースが、ふとよみがえった。
「川で溺れかかっている子どもがいる。目撃した人は、とっさに子どもを助け
ようとするだろう」。性善説を唱えた孟子は、このようなたとえ話を用い、こう
した人の心を「惻隠(そくいん)の情」と呼んで、
道徳心を説く根源とした。
ほめられたいから善いことをするのではなく、他人の不幸を見過ごしには
できない"本性"が、人間には誰にでもあると、孟子は説いているのです。
■一方の
「性悪説」は、中国戦国時代の末期、荀子(じゅんし)が唱えた。
「人の本性は悪で、先天的に利欲の心が強く、善に見えるのは偽りで、
天性に従って行動すれば、争いが絶えない」という説です。
戦争で敵国へ攻め込んだ時、略奪、強姦など、本能の赴くまま…。
倫理・道徳、刑罰などでもって厳しく縛らなければ、人は何をするか分からない。
"子どもの躾"を例に取ると、子供は生まれながらに「よい子」という見方と、
子供はしつけないと「悪いことをする」という見方に分れます。
「よい子」とする親は放任主義となるし、「悪い子」と思う親は、やかましく躾よ
うとする。
「子育て性善説」
は、戦後アメリカから入ってきた。
「子供は沢山の可能性を秘めている。その子の持っている能力を引き出し、
伸ばしてやるのが教育である。だから、あまり手をかけないほうがいい」
この考え方が戦後の日本の教育界を風びしたのです。本来の日本における
教育は、字が示すように、「厳しさが伴う、教え育てる」である。
戦後新しく入ってきた教育の基本は、「自由に伸び伸び個性尊重」。
私たち人間は、善いものを多く持っているが、悪いものも沢山持っている。
伸び伸びと自由に育てるのはいいことですが、放置しておくと悪い芽も伸びて
きて、手がつけられなくなる。教育によって、悪い芽は早めに摘み取ってしま
わなければなりません。
戦後の民主主義、社会が守らなければならないモラルや、しつけを甘くしてし
まい、自由を履き違えた行為が当たり前のように行われ、誰も止めようとしな
い社会になってしまった。見て見ぬ振りをする社会になってしまったのです。
■もう一つ、古代ギリシャの哲学者ソクラテスの説がある。
「子供は生まれながらに善い子でも、悪い子でもなく、善い子になりたい
と願望している」という説です。
「善い子と言われたい」「誉められたい」「何でもできる子になりたい」と、どの子
も強く願望している。親もまた「我が子を善い子に育てたい」という願望を持っ
ている。
その両方の願望が一つになったとき、健全な教育が可能になるのです。
子供たちが持っている「なりたい願望」を、上手に伸ばしてやり、生かしていく
教育が、大事になってくる。さて、皆さんは、どの説が正しいと思いますか?
2005年09月09日
いよいよ人口減少時代へ!
金沢の中心部、ドーナツ化現象で、三つあった小学校が一つに統合された。人口
の減少と歳入の減少に対応して、小・中学校が統廃合され、市町村が合併してい
く。学校が無くなって困るのは子ども達。そんな子供たちより、郵便局が大事?
利用者が減っても、赤字になっても、残していくという。何んで郵便局だけ?
合点がいかない。
少子化の影響で、人口数万人の町から産婦人科や学校が消えていく。隣の町へ
行かなければ産めないし、学べない。公共性では病院も、学校も、郵便局も同じ。
郵便局を守れと、あれだけ論じた国会議員。何で町から消えていく病院や学校に、
目を向けようとしないのだろう?
大規模小売店の規制緩和で、大資本に顧客が奪われ、私たちの町の商店街は寂び
れ、活気が失われていく。その数、郵便局の数百倍。政治から見捨てられ、切り捨て
られ、何の保護も受けられず、廃業に追い込まれていく…。
でも、郵便局は保護される。公共施設だから? なら何で"世相"が認められるの?
「不公平・不平等だ!」。商店街に育った私には納得できない…。

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 93】
~幸せな人生を歩むために~
「いよいよ人口減少時代へ!」
今回の選挙で小泉政権が掲げる郵政民営化。公務員を減らし、「小さな政府」
を目指すという。日本の将来を見据えたとき、今、急がなければならない政策
の一つでしょう。
急速に少子高齢化が進む日本。十日ほど前、予測より2年早く、今年から人口
減少期に入ると報道された。
日本の人口は約1億2千8百万人。今年、出生が死亡を下回りそう。いよいよ
人口減少時代に入る。2050年には1億人を割る見通し。現行制度のままで
は、あらゆる仕組み・制度が立ち行かなくなる。
人口の減少は、生活環境の活力をどんどん奪っていく。
香林坊に約50年住んでいた私。日本の人口の減少と、香林坊の繁栄・衰退が
重なって見える。
私の子どもの頃、香林坊(石浦町)には140世帯の住人がいて、商店街は活気
に溢れ、どの店も繁盛していた。子ども会はにぎやかで、春と秋の太鼓行列、
百万石祭りの提灯行列などに、私もハッピを着て参加したものです。
ところが、商店街の再開発が進み、大資本が参入してきて、住民は住む場所を
失い、郊外に引っ越していった。人の住まない町になっていった。私が入江に引
っ越す1989年には、町内で生活する人は、私の家族を入れて、わずか3世帯
になっていた。
香林坊周辺の住宅地も同様、空き家は取り壊され、月決めの駐車場へ。空地だ
らけの寂しい町になっていった。若い人は郊外へ移住し、残ったのは年寄りば
かり。路地裏で遊ぶ子どもの姿も見られず、活気が失われていった。若い人た
ちが寄り付かない、老人しか住まない町になった。
そんな香林坊に三十年も前から、人口減と老齢化の中で暮らしてきた。日曜と
いうのに、片町商店街はまばら。10館あった映画館も今はない。空洞化した
中心商店街の寂びれようは、目を覆うばかりです。
以下、8/28中日新聞 「時代を読む/人口減少社会の都市対策」から
| 人口増加時代に造成されたニュータウン。人口が減ると、高層アパ ートの半分は、空き家になる。目に入るのは老人だけで、人影もま ばら。社会を維持するのに最小限必要な、治安を守る警察、消防団 員、病院の医師・看護婦などが不足するようになる。 |
全国の有名なお祭りも、今後若い人手が不足して、縮小せざるを得なくなると
いう。人口の減少は目には見えないところで、徐々に真綿で締め付けるように、
私たちの生活を圧迫していく。
2005年09月06日
あなたにとって、生きるとは…
ふと、二年前に聴いた大島修治氏の講演を思い出した。全身に灯油をかぶり、
火だるまになった。死線をさまよったが、九死に一生を得て、新しい人生を手に
したお話し。心に残った言葉は、
「今、自分は生きている。つい今しがた生きていた自分は既に過去のものとなり、
二度とよみがえることはない。そして今、未来に向かって新たな命を刻んでいく」
その大島氏。忌まわしい事故によって、身体が不自由な身になった。その代わり、
「生きるとは何か…」を悟り、素晴らしい「人生観・生きることの幸せ」を手に入れ
たという。大島氏には、毎月一回、京都の勉強会でお目にかかっている。

【心と体の健康情報 - 210】
~幸せな人生を歩むために~
「あなたにとって、生きるとは…」
8月28日、テレビ金沢「24時間テレビ28・愛は地球を救う」で、丸山弁護士
が100キロマラソンに挑戦し、みごと完走した。やれば出来るものですね。
つい感動して、目頭が熱くなった。
来年私も、大阪の千房が主催する"50キロ歩"に、挑戦してみようかな…。
この番組のテーマは「生きる」。稲垣吾朗がダーツの旅で、「あなたにとって
生きるとは…、何ですか?」…。会う人ごとにマイクを向けた。
突然のことで、どう答えていいか戸惑う人が多かった。一番多かった答えは
「生かされている」だった。
人間に生まれてきたことを、当たり前に思っていないだろうか。
苦しい時には、生まれてきたことを恨んだり、後悔したりしていないだろうか。
以下、一万年堂出版 木村耕一著「こころの朝」からの抜粋です。
|
ある時釈迦が、阿難という弟子に、『そなたは人間に生まれたことを、どのように思っているか』
と尋ねた。 果てしなく広がる海の底に"目の見えない亀"がいた。その盲目の亀は、百年に一度、
海面に顔を出すという。 釈迦『阿難よ、百年にたった一度水面に顔を出すこの亀が、浮かび このように釈迦は教えている。「有り難い」とは「有ることが難しい」 |
10億個の精子が我先にと、卵子に向って泳いでいく。一番先に卵子にたどり
着いた精子のみが受精に成功する。そうやって十億倍の競争に打ち克ち、
一人の人間となって、この世に生まれてくるのです。
もっと言えば、人間ではなく、猫やネズミに生まれる場合もある。限りない生
命の中から、人間に生まれてきたことを、何より喜ばなければならない。
そのことを知ったら、もっと命を大切にするだろう。自殺したり、人を傷つけた
りすることもなくなるだろう。
私にとって「生きる」とは…、
「両親から頂いたこの命、次世代へ命を育み、一度しかない人生、人様の
お役に立ち、生かされているこの命をまっとうすることです」
2005年08月09日
大人って何なの?
今週末はお盆。昨年から今年にかけて、私と人生を共に歩み、夢を追い求めて
きた二人が逝った。私より若いのに… 冥福を祈ります。
「散る桜 残る桜も 散る桜」
今年は戦争が終結して60年になる。戦後の復興、そして発展、経済大国へ…。
バブルが崩壊し、世の中が大きく変化していく中を、大きな不幸に遭遇すること
もなく、幸福な人生を歩んでこれた。
良い人たちに出会い、教え・導いていただいたお陰です。感慨もひとしおである。

【心と体の健康情報 - 207】
~幸せな人生を歩むために~
「大人って何なの?」
高校生の子度たちに、「将来何になりたい?」って質問したら、「大人になんか
なりたくない、子どものままがいい…」、そんな答えが返ってくるという。
将来の夢は?って尋ねても、「わかんなァい…」。尊敬する人は? 「さあ~?」。
大人って、ともかく大変みたい。だから、このまま子どもでいたいと思ってい
るのか、将来のことを真剣に考えようとしない。
落語にこんなのがある。
「やい!熊こう。いつもごろごろして、何で働かねェんだ…」
『あァ、八ッつァんか…。そいじゃ聞くが、何のために働くんだよォ!』
「そりゃぁ~おめえ、決まってるじゃねェか、働いて金貯めて、楽するためよ!」
『なァんだ、そんなことか…、だったら俺、今、そのさァ~、毎日のんびり楽して
らァ~』
今の日本の子どもたち、世界一恵まれた環境に育ち、世界一贅沢が許され、
世界一幸せに暮らしている。生まれた時から、贅沢な生活に慣れ親しんできた
せいか、それが当たり前。感謝の気持ちなどあるわけがない。それよりも、将
来の方がいろんな不安が付きまとう。
黒柳徹子だったか、アグネスチャンだったか、アフガニスタンの難民キャンプ
を訪れたとき、栄養失調で、学校へも行けずに、ドブネズミのようになって働
いている子ども達がいた。
「君達偉いわね! 日本の子どもでも、自殺する子が沢山居るというのに…」
『へェ~そうなの、日本って僕達より、ずっと貧しい国なんだよね…』。
それを聞いた彼女、返す言葉がなかったという。
以下、7/9北国新聞「今日の言葉」、秋庭道博氏のコラムより
|
「大人」とは何だろう? 『広辞苑』には「十分に成長した人」「一人前 たしかに、それはその通りだ。しかし、ときとして、自分自身で 中には、「自分の醜さを知っているのが大人」とか、「ありのままの |
大人は、やたらと分別くさく、保守的になるから嫌だ。いつまでも、子どもの
ように素直で純真で、何にでも興味を持ち、明るく振舞える人間でありたい
ものです…。
ところで、家の中で一番分別くさいのは? もしかしたら私?
女房に決まっているじゃない…。
2005年07月19日
私にとって最も大切なものは…
■「不幸になる三定義」というのがある。
一. 決して素直に「ありがとう」と言わない人
二. 「ありかとう」と言うだけで恩返ししない人
三. 「ありがとう」と唱えただけで、恩返しできたと思っている人
この逆のことを心がけ、実行すれば、幸せになれる…

【心と体の健康情報 - 204】
~幸せな人生を歩むために~
「私にとって最も大切なものとは…?」
人生、幸福な時ばかりではない。苦しみや、怒り、ねたみなどにさいなまれる時もある。そんな時、心の中に生ずる”悪しきささやき”に負けてしまいそうに なる。それは、誰にでもあることです。
正しく倫とした
「生き方信条・人生観」を持って生きていけば、そのような誘
惑に惑わされることなく、正しい生き方を貫くことができるでしょう。
コクドの堤会長が失脚したのはつい最近。今度は三井物産。身近では、川
田工業、コマツも起訴された。こういった企業モラルを失墜する事件は、叩け
ば出る埃のように、企業犯罪は後を絶たず、止まるところがない。
昨日まで”山向こうの火事”と眺めていたこういった不祥事。ついに私の足元
にまで及んできた。
過去お付き合いがあり、尊敬する某地元企業が、商品を偽ったと農水省から
公表され、新聞に報じられた。その後、その記事が事実と反することを知った
が、事情を知らない読者は、新聞の記事の方を信じてしまうだろう。
その会社は、信用回復に大きなエネルギーと時間を費やすことになるだろう。
更にショックだったのは、親しく付き合ってきた某社長が、公金を横領した。
出来心での万引きや、たった一度の痴漢行為でも、人の上に立つ者であれば、
社会は許してくれないというのに…。
一人の人間として、社会人として絶対許せない、やってはいけない行為…。
「嘆かわしい」を通り越して、沸き上がってくるこの怒り…、どう収めたらいい
のでしょうか…。
さて、皆さんにお尋ねしましょう。
「この人生、
自分にとって最も大切なものは何か…?」
真宗大谷派潮音寺 小野蓮明住職が、
講演の中で私たちに尋ねたことです。
会社に、経営理念があるように、一人の人間として、「幸せな人生を送るため
に、大切にし、守っていかなけれはならないものは一体何か?」
自問してみてはいかがでしょうか。何がこの問かけで浮かんでくるでしょうか?
まず「この命」「健康」が浮かんでくる。「家族」「子ども達」も大切です。「仕事」
「お金」「志」「友人」「信頼・信用」「正直」「お役立ち」…etc
大切なものが次々浮かんできます。
最初は「なんだ、そんなことなの…」と、簡単に思うかもしれません。
いろいろある中から「最も大切なものを一つ」選ばなければならないのです。
一つだけに絞るとしたら大変です。あなたにとって最も大切なものとは…、
何でしょうか?
この機会に、「最も大切なもの」「絶対これしかない」というものを深く考え、
一つだけ選んでみてください。
「最も大切なもの」を大切に守り、心の支えにし、生き方信条とするならば、
きっと真っ直ぐに、正しく生きることができるでしょう。
自分にとって最も大切なもの、その一つに”自分自身”がある。
一度しかない人生、自分を粗末にし、自分を喜べない人間にしてはならないの
です。どんなに苦しい時でも、リンとした信念を持って、正しく生きる自分で
ありたいものです。
2005年07月05日
人を育てるとは…
中国政府は今、日本で古くから受け継がれてきた「しつけ」に関心を持ち、
日本に見習おうとしている。
身に美しいを並べて「躾」と読む。これは、日本で生まれた”国字”です。
中国の家庭には、この日本風の「しつけ」の習慣がない。だから、「しつけ」に
該当する言葉が見当たらないのです。
今中国では、一人っ子政策の影響から、子供を溺愛し、甘やかす家庭が問題
になっている。我がままな子どもが増えて、困っているのです。
そこで、日本の家庭で古くから受け継がれてきた「しつけ」に着目し、日本から
学ぼうとしているのです。
ところが、お手本となるはずの日本の家庭、「しつけ」の習慣が失われつつある。
ですから、あまり褒められたものではないのです。
6/26 NHKラジオ放送より

【心と体の健康情報 - 201】
~幸せな人生を歩むために~
「人を育てるとは/叱るより誉めろ」
日頃、何気なく、親は我が子に、上司は部下に、「そんなことでは駄目だ、
ここをこうししなさい…」と、成長を願うあまり、何かにつけよく叱る。
人の上に立つと、つい欠点に目がいくようになり、注意しようとする。
それが癖になり、習慣となって、相手の欠点ばかりに目がいき、気になって
しようがない。見えてくる欠点の数だけ、子供や部下の持つ良いところが相殺
され、消えていく。相手の素晴らしいところに気づかない、親や上司になって
しまう。人を「誉める」ということが、出来ない人間になってしまうのです。
幸せに生きようと思ったら、人を叱るより誉める方がいいに決まっている。
「どこをどう注意しようか…」と考えるよりも、「どこをどう誉めようか…」と
考えるようにしたい。
叱ることはた易い。しかし、誉めることは難しい。誉めるタイミングを間違え
ると、「おべんちゃら」や「オベッカ」になり、心にもない「おだて」になり、
「お世辞」に取られてしまう。
昨日まで、人を誉めたことのない人が、たまに誉めようとするから、ギクシャ
クしておかしなことになる。日頃から、相手の良いところを見つめるようにし
たい。そうしなければ、人を誉めることは出来ないだろう。
人は、誉められると成長する。誉められることは、認められること。
「えッ、あの人が同じ人なの」と思うくらい変わっていく。ところが、注意ば
かりされていると、いじけてしまい、いくら叱っても、注意されたことしか
やらない人間になってしまう。
”叱るよりも誉めろ”。
プラスのストロークを与えるようにする。これが人育ての秘訣でしょう。
叱っていじけさせては、人は成長しません。誉めることで人はヤル気になり、
成長する。叱るより誉める方が楽だし、楽しいのす。
思うようにいかないとき、イライラしてつい人を叱ってしまう。が、それで
もの事が良い方向に向かうということはない。
先日習ったばかりの「コーチング」。相手を「分からせようとする」説得型から、
相手の話を「聴く」ことにシフトした、「傾聴型」でなければならない。
話し合ってうまくいかない時は、自分のやり方が間違っていると思うことにした。
2005年06月28日
人を育てるとは…
6月20日東京で、両親が高校一年生の息子に殺されるという、痛ましい事件が起きた。又も起きた痛ましい事件。日本の国は、家庭は、
どうなってしまったんだろう。
子どもに厳しく冷たい家庭だったという。事件の前日父親に「おれより頭が悪い」と言われ、父親がバカにするから殺したという。
おとなしい性格ゆえに、親から押さえつけられた不満のはけ口を見出せないまま逃げ場をなくし、孤独感を深め、
殺意を膨らませていったという。
親が暖かく心を開いて、子どもの悩みを聞いてやっていれば、起きなかった事件だと、専門家は言う。
家族揃っての食事風景や、愛に包まれた食後の団らんなどがない、ひんやりとした家庭が浮かんでくる。

【心と体の健康情報 - 199】
~幸せな人生を歩むために~
「人を育てるとは…?」
先週の土曜日福井市に出かけ、初めて「コーチング」 を学んだ。学習テーマは「マネージメントコーチングによる人材育成法」。 今まであまり耳にしたことのない人材育成法である。
スポーツの世界では、選手の能力を引き出すために、コーチの存在は不可欠で
ある。
企業に於いても、目標達成のために、リーダーは、社員を組織化し、立てた計画を統制し、指揮を取るに必要な技術・
ノウハウが求められる。
そのために、社員一人ひとりが持つ潜在能力を引き出し、高め、発揮させる、
そんな人材育成手法を学ばなければならない。
例えば問題を抱えた社員を導く時、上司は、一方的に自分の価値観で意見を言ったり、考えを押し付けたり、
決め付けたりしてしまいがちです。
そうではなく、「なぜ問題を抱え悩んでいるのか?」を知り、相手の側に立ち、相手を”思いやる心”
でもって、プラスのストロークを投げかけ、元気を出させ、
やる気を喚起していくように、コーチングするのです。
・相手を認める
・相手の持つ能力を引き出す
・相手を援助し、応援する
相手の間違った考え方を正そうとする指導法ではなく、”変わらない相手”
をどう動かすか? そのために”相手を知り、理解する”ことから始める。
コーチングによる指導は、「こうあるべきだ」とか、「こうすべきだ」といった指示・指導めいた言動は極力避ける。
「積極的に傾聴」し、「相手の気持ちになって、相槌を打ったり」「共感したり」「相手が言ったことを繰り返したり」 して、一旦受け入れて理解を示すことが、コーチングを学ぶ上での、大切なポイントになってくる。
二時間の講座で、何がどう理解できたわけではないが、相手を説伏することに自信を持っていた私には、
インパクトのある勉強会でした。
それまでの私の面談のあり方が、改めて間違っていたということを、理解したからです。
「コーチング」を身に付けることができれば、会社だけではなく、家庭に於いても、子どもたちや夫婦の間が、より一層円滑・
円満になり、父親の存在感が高まること、受けあいでしょう。
2005年06月21日
頭で考えているだけでは身につかない
■徳川家康「東照宮遺訓」
一. 人の一生は 重き荷を負うて遠き路を行くが如し 急ぐべからず
一. 不自由を常と思えば不足なし
一. 心に望みおこらば 困窮したる時を思い出すべし
一. 堪忍は無事長久の基
一. 怒りを敵と思え
一. 勝つことばかり知りて負くる事を知らざれば 害その身に至る
一. 己を責めて 人を責むるな
一. 及ばざるは過ぎたるより勝れり
最初の「人の一生は重き荷を負うて…」は、ズシッと心にしみる言葉です…。
この言葉、家康の言葉ではなく、”千利休”が言った言葉というのが、最近の
歴史家の通説。
どの言葉も、素晴らしい人生訓になる。頭では理解していても、実際に行う
となると…?

【心と体の健康情報 - 198】
~幸せな人生を歩むために~
「頭で考えているだけでは身につかない…」
以下、「ひろやかな心」修養団 中山靖雄先生の講演から…。
| 新入社員研修でのこと。 「あなたの人生のモットーは何ですか?」と尋ねた。答えで一番多かったのが、「初心忘るるべからず」でした。 「私のモットーは、初心忘るるべからずです」と答える社員が、あまりに多かったので、「では…、 あなたの初心とは何ですか?」と尋ねたら、帰ってきた答えは、「……、別にありません」。 なにげないことで、深い意味もなく、なんとなく観念的に答えてしまうことがあるものです。 |
火曜夜8時の人気番組「踊る!さんま御殿!」を真似て、「私の心に残る恥ず
かしかったこと」。それは、小学六年の時のこと…。
クラスのホームルーム、当日は父兄参観日。教壇に立ち議長を務めた。
先生から与えられたテーマは、「あなたの人生のモットーは何ですか?」。
右端のクラスメイトから順に聞いていった。思い浮かばず、黙り込む生徒も
いた。「何かあるでしょう…」と、私は懸命に進行役を務めた。
生徒への質問が一巡して、最後に私の番になった。議事進行に夢中で、
自分のことを話す準備をしていなかった。みんな注目する中、何かを話さなけ
ればと焦る。焦れば焦るほど、頭の中は真っ白! 顔は真っ赤。
何も言えず、時が経過していった。恥ずかしかった…。自尊心はズタズタ…。
そのときのことを、50年を経た今も、思い出すと心がうずく。
引き続き中山先生の講演から…
|
学問をするのはいい。しかし、頭の勉強をいくらしても、それ自体意味をなさないし、身につかない。
理屈だけではダメなのです。 そこで私、「受付は会社の顔ですよね、みんなに明るく接してあげて下さいね」「後ろに”
心一つに親切運動”って書いてあるでしょう…」と言ったのです。
|
人ごとではなく、私たちの会社でも案外同じようなことが起こっているかも…。
頭では理解していても、いざとなると、身についていないことは、なかなか
目的に添ったようにはならないものです。
2005年06月10日
「三方よし」
私が生まれ育った金沢の繁華街香林坊。入江に引っ越してくるまで、47年間住んでいた。自宅の左隣が元第一勧業銀行金沢支店、
右隣が石川銀行本店でした。
両行とも今はもう無い。第一勧銀はみずほ銀行に合併後、売却されて大手資本のホテルが建つ。石川銀行は破産して、APAに売却され、
テナントビルが建つ。
子どもの頃140世帯あった町内会。入江に引っ越す時、わずか4世帯になっていた。商店街の発展のため?と、再開発を繰り返すたびに、 東急109、大和デパート、生保ビルなどの大手資本に取って代わられ、人の住まない町になっていった。 いつしか、 山間の過疎地のようになり、小学校も廃校になってしまった。
子どもの頃、あれほどにぎわっていた商店街。10館あった映画館もすべて廃館。
郊外に移り住んだ後、現在も繁盛しているお店がどれだけあるだろうか?
その中で、今も益々繁盛しているお店がある。隣の片町商店街で本店を構えていた、”芝寿し”さんである。

[吉村外喜雄のなんだかんだ 第82号
~幸せな人生を歩むために~
「三方よし」
今から二十年も前の話になる。芝寿しの梶谷忠司会長の機転から生まれた、「三方よし」 の体験話し。この美談、今も時折人に話すことがある。
最終便の飛行機で小松空港に着いた梶谷会長。所用を済ませて外へ出たら、金沢行きのバスは既に出てしまい、
タクシーが一台客待ちしていた。
それに乗ろうとしたら、後ろから、新婚夫婦だろうか、大きなトランクを引きずってタクシー乗り場にやってきた。
周りを見渡したらタクシーはこの一台だけ。とっさに「相乗りしましょう」と声をかけ、運転手にトランクを開けさせ、
荷物を押し込んだ。
新婚夫婦も金沢だという。高速道路中ほど、美川辺りへ来たとき、ふと「料金はどうしようか?」と思案した。
タクシー代は三千円くらいだろう…。
元々、一人で乗るつもりだったから、全部自分が持てばいい。が、それでは、新婚夫婦は承知しないだろう。
客は三人だから、一人千円づつ割り勘という方法もある。それでは、自分が一番得をする。納得できない。
また、二組の客と考えれば、千五百円ずつになるが、年齢・収入ともに自分の方がずっと上。なんとなく言いづらい。
しかも相手は初々しい新婚さんである。
しばらく考えた末、後ろの夫婦に提案した。
「タクシー代は三千円だが、お互い二千円ずつ出しましょう。そうしたら四千円になります。そこからタクシー代三千円払うと、
千円残ります。それを運転手さんにチップとして差し上げたらどうでしょうか」。新婚さんは、二つ返事でOKした。
梶谷さんも新婚さんも、金沢へ帰るためのタクシー代三千円は、払うつもりでいた。相乗りしたお陰で千円得したのです。
その上、運転手さんまで、思わぬチップを頂き、ほくほく顔。
世に知られる大岡裁きで有名な「三方一両の損」のお話し。名お裁きとして世に知られている。
芝寿しの梶谷会長の場合は、更に一歩進めて、三人とも得をする「三方一両の得」。
トンチが利いたお話である。人に話すたびに、ほのぼのとした気持ちになる。
長年、商業界のエルダーとして、商人道を説いてこられた梶谷会長のお人柄を物語る逸話ではないでしょうか。
この美談が世間に広がったのは、タクシーを降りるとき、新婚夫婦がお礼を言った。その時、
「私は芝寿しの梶谷というものです」と、名乗ったことから…。
新婚さんが家に帰った後、新婚旅行の土産話の中で、この体験話しが出た。
そこからこの美談、「三方よし」の逸話として、口伝に広がっていったという。
それが、私の耳にも届いたのです。
次号の”なんだかんだ”では、有名な大岡裁き「三方一両損」のお話しをします。
2005年06月07日
相手の身になってウイ・サーブ
月刊致知」安藤忠雄&牛尾治朗の対談から…。
西欧諸国は、何百年と豊かさに慣れ親しんできた歴史がある。だから豊かになると、寄付行為や奉仕活動などで、
積極的に社会に還元しようとする。
過去、そういうお手本が沢山あって、豊かさの中でなお立派であることに、伝統的に慣れているのです。
ところが日本は、「おしん」や「野口英世」に代表されるように、貧しさの中の哲学、清貧の論理はある。けれども、
豊かさを手にしてまだ歴史が浅いせいか、豊かさの中の哲学と論理が出来上がっていない。日本人は、豊かさにまだ慣れていないのです。
ところが、ここ数十年、初めて豊かさを手にした日本人は、リッチに生きることや、立派であることに戸惑うのです。
戸惑った日本人は、お金がたまると、個人の豊かさのみを追い求め、物質的欲求の満足に酔いしれ、堕落してしまう人が多いのです。
困っている人たちへの寄付行為や、奉仕活動に還元することへの理解が、まだまだ足りないのです。

【心と体の健康情報 - 196】
~幸せな人生を歩むために~
「相手の身になってウイ・サーブ」
以前、私がライオンズクラブに入会していた頃、学んだことです。
誰もが、思いやりと感動に満ちた人生を歩みたいと思っている。そのためには、相手の身になって考え、
行動することが大切です。
”相手の身になる”ことをライオンズクラブでは、「ウイ・サーブ」
と言います。
”サーブ”とはサービス、相手の身になってサービスをすることです。これがなかなか難しい。
ライオンズクラブは、経営者の社会奉仕団体です。
当時、献腎・献眼運動、ガン撲滅基金設立運動などを、懸命にやっていた。
「ウイ・サーブ」の精神に則り、様々な奉仕活動をやっていたが、当時の私は、公園に銅像を寄付したり、
施設に車椅子やテレビを寄贈したり、街を清掃するといったことに参加して、奉仕活動をしている気になっていた。
困った人たちと直接向き合い、お手伝いする奉仕活動ではなく、
モノを寄付することでもって慈善事業とするような活動が多かった。
日頃のお付き合いの中で、相手のことを思いやって、首を突っ込み過ぎれば、それは単なるお節介。 良かれと思ってやって、「デリカシーに欠ける」と非難されたこともある。
ところで、サービスとは何でしょうか? サービスとは「タダ」ということです。
「金銭で数えられないこと」「無駄・おまけ」。”サービスをする”とは、この無駄、おまけを、いっぱいすることです。
戦後教育で、徹底した合理主義が叫ばれたことによって、生活の中での無駄や損を排除しようとする傾向がある。
お金にならないこと、損することはやらない。計算高く生きる…。今の世の中を見ていると、そんな気がするのです。
一方、台風で水害に遭った豊岡や、中越地震の後、若者が沢山被災地に入り、「ウイ・サーブ」の精神で、
ボランティア活動をしている。こうした若者達を見るにつけ、恥ずかしいのは、お金を少し寄付しただけで、
何もしていない私の方でしょう。
「ウイ・サーブ精神」は、3才の頃からの家庭内の”しつけ”の中から養われる。
幼い頃から家事を分担させ、責任を持たせ、家族の一員として、感謝とお役立ちの精神を養っていく。
勉強一辺倒で、家事を手伝ったことのない子どもは、大人になって、”何かを人にして喜んでもらう”
といった行為の素晴らしさに気づかない。
”損得”で考えるなら、ボランティアをしたところで、一銭の得にもならない。
「ウイ・サーブ」の精神で、お世話になっている世の中にお返しをする…。
ほほ笑みでもって人に接すれば、ほほ笑みが帰ってくる。自分がしてもらって嬉しいことを、相手にもしてあげればいいのです。
しかし、相手が喜ぶことをいくらしても、”見返りを期待する心”が少しでもあれば、「ウイ・サーブ」 の真の意味を理解していないことになる…。
損得など考えず、相手の身になって”無心”でサービース出来る人間になる。
それが当たり前のように出来るようになったとき、初めて、思いやりと感動に満ちた、”何か”
を悟ることができるのではないでしょうか…。
ご存知、元NHKのアナウンサー”鈴木健二”氏が、著書の中でこんなことを言っている。
| 日本人で朝起きて「お早う」って家族に挨拶する人は、一割もいない。
ほとんどはヌーと起きてくる。ところが会社に行くと、100%「お早うございます」と挨拶する。 では、何故家では挨拶しないのか? その答えは、家で挨拶しても一銭にもならないし、 気配りしないからといって、損をすることがないからです。 |
2005年05月13日
憎まれ口
福岡の補選の応援演説で、久方ぶりに田中まき子が吠えた。あの父親譲りの
迫力いっぱいの憎まれ口、よくもまあ~次から次と…、聴衆は大喜び拍手喝さい。
あれだけの憎まれ口に対抗できる男性は、島田伸介くらいだろう。
ここで ことば遊び。「おじん駄洒落」を一つ…
■まき子さんのご主人、田中直紀氏は参議院議員。
親しくしている友人が、「直ちゃん、おまえすごいよなァ」 『何で?』
「まき子さんを奥さんにしたんだもんなァ…。そいで、子供を二人も作った。
おまえは男の中の男だよ!」
『いやァ~、皆さんが思っているほど楽じゃないですョ!』
『私は二宮金次郎ってとこかな…』 「 …? 」
『一生”マキ”を背負って歩かなければならないもの…』
■ ついでにもう一つ、我が故郷の元総理大臣”森 善朗”
内閣発足時、「森内閣は長続きするだろうか?」と、自民党の某代議士が
評論家に尋ねた。
評論家それに答えて、『そうねェ、蜃気楼のように短命でしょうかねェ…!』
「なんで?」 『だって、名前が”しん(森)きろう(善朗)”だもの…』

[吉村外喜雄のなんだかんだ 第78号]
~幸せな人生を歩むために~
「憎まれ口」
久しぶりにことば遊び…。今日のテーマは「憎まれ口」。
”憎まれ口”は、私たち夫婦の間では、無意識に、頻繁に交わされている。
遠慮も気兼ねもいらない間柄。しかも相手のいいところ、悪いところすべて知り尽くしているから、お互い、
憎まれ口をゲームのように楽しみ、ジョークとして聞き流す。
私「俺、これでも外では結構若い女性にもてるんだぞ…」
妻『あら、そうなの、いいわね、どうぞ、どうぞ… そんな物好きな女性いるのかしらァ…? 一度会ってみたいものだわァ…』
結婚して40年近く連れ添っている女房に、「どんなに旨いからといって、
40年も同じカレーライス食っていると飽きるよなァ」なんて言おうものなら、すかさず
『私の方こそ、死んだ後も狭いお墓の中で一緒に暮らすのは、どうもねェ…』
女性は力では男性に太刀打ちできない。その代わり”口”を武器に戦ったら、絶対男性には負けない。
会話を交わすとき、男性は理性をつかさどる”左脳”しか働かないが、女性は感性をつかさどる”右脳”が左脳と一緒に働く。
田中まき子ではないが、機関銃のように言葉がほとばしり出てくる。だから男性諸君、女性と”口”で言い争ったら、
絶対勝てっこないことを肝に銘ずるべきです。
以下、朝日新聞のコラム、天野祐吉氏の「CM天気図」から…
憎まれ口をきくのは楽しい。「死んでも君を放さないぞ」なんて、恋人がキザなことを言ったら、「死んだら離してよ、
怖いから…」と、すかさず憎まれ口をきけるような人が好きだ。
それは、たんなる憎まれ口ではない。相手のオーバーな表現への軽い”批評”や”ヒニク”になっている。
そんな批評が含まれているかどうか…。
そこに、憎まれ口をきく人の”センス”がかかっている。そういうセンスのある人は、憎まれ口を通して、
世間のおかしなところを浮き彫りにしてくれる。
で、それを聞いた周りの人たちが「クスクス」と苦笑する、微笑みを生む…。
私(吉村)が親しくしている、おやつカンパニーの松田好旦社長。つい最近も一緒にお酒を飲んだが、
ウイットにとんだ面白い社長である。
松田社長の会社の「ベビスターおとなのラーメン」のテレビCMを、人気お笑いタレント”青木さやか”がやっている。その”
さやか”の憎まれ口が面白い。
■駅の待合室でぼやく二人のサラリーマン。
「俺たち、今の会社で一生終わっちゃうのかなあ…」。
と、不意に前の席から振りむく青木さやか。『会社がそれを許さないかもね』
■もう一つ、二人のOLが嘆くシーン。
「そろそろ幸せになりたいなぁ~」「なりたいねえ…」。
そこへ顔を出す青木、『誰にお願いしているのよ…?』
どっちも、言わずもがなの憎まれ口である。が、何の努力もせずに、自分の運のなさをこぼしている連中を見ると、
彼女は憎まれ口を叩かずにはいられないだろう。
ホリエモン騒動の時、自民党のおえら方が、「すべてを金で動かそうというのは、いかがなものかねェ」 と言っているのを聞いて、『代議士の先生にだけは言われたくないよネェ…』と、憎まれ口を叩きたくなる。
4月下旬のTVニュース。郵政審議委員会、政府は自民党から一任を取り付けることがなかなか出来ず、深夜までもめた。
そこへ、憎まれ口では大先輩の”ハマコー”が委員会室に入っていった。
「お前ら! 総理にたて突くのなら、自民党を出ていけ!」と、大声でわめき散らす声が、ドアーの外にまで漏れてきた。
こんな暴言、他の代議士だったら唯では済まない。つかみ合いの喧嘩になってしまうだろう。
ハマコーだから通用する憎まれ口なのです。
女房ならともかく、人前での憎まれ口、のどまで出かかっても、ツバと一緒にゴクリと飲み込んでしまう。それを、 青木さやかは、なんの遠慮会釈もなく、スパッと言えて、笑いを誘う。視聴者は、そんな憎まれ口を楽しむのです。
今の日本、おかしなことだらけ。憎まれ口を叩くどころか、見て見ぬ振りをする人のほうが多い。 JR西日本の知って知らぬ振りはちょっとひどいが、そういう人たちに向かって、「どこ見てんのよォ!」って、 彼女は叫んでいるのかも…。
2005年05月10日
もったいない
この連休、北と南の生物が混在し、種類の多さではナンバーワンと言われる、
四国西南端のダイビンク゜メッカ”柏島”で、丸四日間ダイビングを楽しんだ。
 ・コブダイ(体長1メートル)
・コブダイ(体長1メートル)
熱帯魚の王様ナポレオンフイッシュに
負けない堂々とした風格
後ろに写っているダイバーで
その大きさがわかります…。
| ・コブダイがこちらに向かってくる |
 |
| ・カメラの前30センチまで近寄ってきて興味深げに私を観察している。 海のドラエモンかな |
 |

【心と体の健康情報 - 192】
~幸せな人生を歩むために~
「国連本部で”もったいない”が唱和される」
私たちの年代は「もったいない世代」 。貧しかった頃の習性が、体中にしみ付いている。
古くなったスーツ、捨てられずに仕舞ってある。お魚は、身一つ残さずきれいに食べるし、お弁当を買って食べるとき、
ふたにくっついた米粒をきれいに掃除してから食べる。連休の間、若い人たちと海に潜ったが、二十代の仲間たち、
ふたに付いたごはん粒には目もくれない。
私は、ごはん粒一粒でも粗末にすると”罰があたる”、と躾けられて育った世代。
一・二日前に賞味期限切れの食品。妻が捨てようとするのを押し止めて、「勿体ない、まだ大丈夫、私が食べる…」。
もう少し言わせてもらうと! 買って数年のまだ十分使えるカラープリンター。
紙が詰まって修理依頼したら、既に廃品、交換する部品が無いという。
「そんな馬鹿な! まだそんなに使っていないのに…」。メーカーに直接文句を言ったら、たまたま残り在庫があって、
交換してくれた。
技術革新の激しい昨今。デジカメなど、1年もしないうちに商品価値がなくなる。「もったいない…」。 ん…、
半値でも何でも、捨てるなら分けてほしい。
ところが部品のストック期限が切れたら修理不能、捨てるしかない。修理できたとしても、部品代に人件費、出張手間etc、
買うほどかかってしまう…。
日本の消費文化、壊れたら捨てる。食い散らかして、余ったら捨てる。
私の気持は複雑。まだ何ほども使っていないのに…。修理すれば十分使えるのに…。まだたっぷり残っているのに…。
「ああ勿体ない」が頭をもたげてくる。
こうした使い捨ての文化、無駄遣い、いずれ許されない時代が来るだろうに…。
三月八日付の北国と中日、両方の新聞に「勿体ない」がニュースになっていた。
2003年の留学生が集う「ジャパンテント」で、能登総持寺祖院の板橋興宗住職が、
世界80ケ国から集まった留学生に、日本語を象徴する言葉の一つ、
「もったいない」を説いた。
このとき住職は、「勿体ない」には経済的観念ばかりでなく、例えば一枚の紙に宿る”命” への思いが込められていることを話した。外国人には理解し難いだろうとの思い込みがあったが、多くの留学生が、 ほぼ正確にその意味を理解していた。
ニューヨーク国連本部でも、各国から集まってくる政府の代表が、声高らかに
「もったいない」を日本語で唱和したという。
音頭をとったのは、昨年アフリカの女性で、始めてノーベル平和賞を受賞した、
ケニアの環境副大臣”ワンガリ・マータイ”さん。
この二月に来日したとき、「勿体ない」に込められた深い意味を知って、感銘を
受けたのだという。
地球環境保護に欠かせない”言葉”。無駄な消費の削減、資源再利用、修理を言い尽くす言葉。
マイターさんは、「MOTTAINAI」のロゴ入りTシャツを作り、キャンペーンの先頭
に立つという…。「もったいない」が国際用語として認知される日も近いようです。
2005年05月06日
ジミー大西の新しい人生
4月23~24日、私たち夫婦は、息子夫婦と1歳と3ケ月の孫の手を引いて、
京都へ家族旅行した。京都駅に着くや、まず駅ビル伊勢丹デパートへ。
お目当ては、七階の子ども服とオモチャ売場。
用のない私?は、その間、同じ階にある伊勢丹美術館へ…。
前々から鑑賞したいと思っていた「ジミー大西作品展」です。 (^-^)/~
まばゆいばかりの作品100点。一点一点に魅了し、じっくり鑑賞した。

[吉村外喜雄のなんだかんだ 第77号]
~幸せな人生を歩むために~
「ジミー大西の新しい人生~キャンバスからはみだせ~」
「人は誰でも、一隅を照らすだけの力量を与えられてこの世に生まれてくる」
これは人間学の師、安岡雅篤のことばです。同じことを森信三先生も語っている。
「誰もが、一通の封筒を持って生まれてくる。その封筒には、その人の人生の使命が書き込まれている。封筒は、
四十の頃までには開くようにしなければならない。ところが封筒を開くことなく、一生を終えてしまう人のいかに多きことか…」
。
ジミー大西といえば、吉本興業のお笑いタレント。仲間の”アホの坂田”などと、
お茶の間に笑いを振りまいていた。最近TVで見かけないと思っていたら、タレントを廃業して、画家になっていた。
そのジミー大西さん、あの天才ピカソと見まがうような、すごい絵を描くのです。
 「母とぞうきん」  「ゴール前」 |
彼のプロフィールを紹介しよう。94年に、ジミーがTV局の企画で描いた絵が入賞した。その天性の作風が注目された。
その後、芸能生活のかたわら個展を開いたり、巨大壁画やポスター、絵本などを制作するようになり、 あの岡本太郎に絶賛された。
自由奔放、まばゆいばかりの色彩。
キャンバスからはみ出んばかりのエネルギッシュで独創的な構図。
遊び心いっぱいの既成概念にとらわれない作風は、見るものを引き付けて放さない。知らず知らず口元がほころび、 童心へと導い込んでいく。
96年芸能界を引退。画家一筋の人生へ…。
あこがれのピカソの故郷、スペインに移住。ジミーを誰一人知らない異国の地で、
胸の内にあった芸術への想いを一気に爆発させ、本格的創作活動に入る。
そして、”大西秀明”のペンネームで、次々と作品を生み出していった。
ピカソは私の好きな画家の一人です。ピカソ展には何度か足を運んだ。
こうした作風の画家は、いずれも既成概念にとらわれず、自由奔放、天才肌。
そのデザインは”ミレーの落穂拾い”のような、キャンバスに細かく描写していく足し算型ではなく、どんどん引き算して、
いかにシンプルに描き、エレガントさを引き出すか…。そんな作風が魅力なのです。
菩薩美人の版画家、宗方志功。切り絵の放浪画家、山下清。何れも色彩鮮やかで、躍動感に溢れ、
シンプルでダイナミック。見る人を引きつけて放さない。
芸能人では、墨彩画の片岡鶴太郎が異彩を放つ。
TVではアホ役をやらされていたジミー大西。あのタレントにこんな素晴らしい才能があるとは…。 人は分からないものです。今まさに天から与えられた使命を開花させようとしている。日本のピカソ、今後の活躍が楽しみです。
「ジミー大西作品展」は5月15日まで、京都伊勢丹美術館で見ることができる。
機会があれば、是非立ち寄ってみてください。
2005年04月22日
遊びがまじめを活性化する
連休はどのように過ごされますか? 私は四国高知でスキューバーダイビング。
私の趣味はその他、ゴルフ、スキー、水泳、旅行、山歩きetc 四季折々、自然
を満喫できるものが大好きである。
”静”の趣味は、囲碁(日曜)、映画・演劇・音楽鑑賞
(土曜)。土曜日NHK総合
韓国ドラマ「オールイン・運命の愛」が逃せない。暇があれば読書。中でも戦国
ものが面白い。教養講座を受けたり、美術館巡りをするのも楽しい。
昨日は京都で論語を学んだ。先月の京都は、高島屋画廊で日本画壇創設の
巨匠、下村観山、横山大観などを鑑賞した。「よくそんな暇があるね」って言わ
れるが、その気になったら、時間って作れるものです…。

[吉村外喜雄のなんだかんだ 第76号]
~幸せな人生を歩むために~
「遊びがまじめを活性化する」
私の趣味に囲碁がある。囲碁は宇宙の世界。思考力を高め、モノ事を大局的に
見る目、先を読む目を養い、変化に即対応する力を養ってくれる。逆境にあって
もあきらめることなく、チャンスがくるのを待つ。
十年くらい前まではマージャンもよくやった。勝負勘を養い、相手の微妙な心の変化が分かってくる。いずれも、
営業力の奥行きを深めてくれる趣味でしょう。
私の好きな棋士”加藤正夫”名誉王座が突然亡くなった。これからの活躍が期待されていただけに、残念に思う。
加藤棋士の全盛期は、昭和50年から65年にかけての頃。
その加藤棋士、何度もタイトルが手に届くところまで行きながら、優勝決定戦で
負けてしまう。七度もいろんなタイトルに挑戦しながら、七度すべて負けてしまい、実力ナンバーワンと言われていながら、
一個のタイトルも取れない時期があった。
悩んだ末、当時三羽がらすの一人で、数々のタイトルを保持していた石田芳夫
九段に、「どうしたら壁を破れるか? どうしたら勝てるようになるか?」と尋ねた。
最大のライバルからの相談に、一瞬戸惑った石田九段、次のように答えたという。
「加藤君は真面目すぎるよ。少しは遊ばないとダメだよ…」。
生真面目で通っていた加藤棋士。その忠告に従い、遊び歩くようになった。
その後、勝負勘が鋭くさえわたり、十四年連続タイトル保持の新記録を打ちたて、全盛期を迎えた。
八起会の野口会長は講演の中で、「私のように飲む・打つ・買うと、遊び呆けて
会社をつぶす社長は、一割くらいのものだろう。 八割強の社長は、超真面目人間。真っ黒になって、働いて、働いて、
そのあげく倒産夜逃げ…。
真面目だけでは、経営者としての”バランス”が悪い。おまけに、ノイローゼ
になったり、自殺するのは、真面目で通っている社長ばかり」と語っている。
毎年何か一つ教養講座に顔を出すのも、私の趣味のうち。昨年から続けている
月に一回の「論語を学ぶ会」で、ユニ・チャームの創業者、高橋慶一朗会長の講演を聴いた。 以下、その講演から…
「遊びは仕事の邪魔になる」といった、仕事と遊びを、対立関係でとらえるのはやめよう。 遊びの活力を仕事にも 生かし、遊びでもするように働くのが理想である。遊びがまじめを活性化してくれる。
人間は、働く動物であると同時に、遊ぶ動物でもある。
遊びを仕事の対極に置く考え方はもう古いと思う。遊びか、仕事か、という選択はしないようにしたい…。
仕事が充実するから遊びの時間が楽しく、遊びの時間が生きているから、仕事が活性化する。この二つは、
対立関係にあるのではなく、補完関係にある。
実際、優れた人は、仕事を遊びみたいに楽しくこなしているものです。
遊び心いっぱいで、楽しみながら仕事をしている。むろん仕事には、苦しいことも沢山あるが、
遊びのときに発揮される活力を、仕事に生かすことはとても大切ですし、
仕事に必要とされる創造性や想像力は、遊びによって大いに養われるものなのです。
ですから私たちは、うんと働き、うんと遊ぶようにしなければいけない。まじめが遊びを生かし、
遊びがまじめを活性化するのです。
「仕事が楽しくてしようがない」という人は、仕事そのものが趣味になっている。
他のどんな楽しいことにも、興味がそそがれることはない。仕事を通して世の中のお役立ちを実感し、
更に懸命に打ち込んでいく。いつしか人の真似のできない”匠”の域に到達する。
だが、人には相性というものがある。いくら頑張って仕事をしても、身が入らず、仕事が好きになれない人もいる。もし、 そうなら、未練など残さず、さっさと転職してしてしまうことです。
2005年04月19日
日本人として知らねばならないこと
ユダヤ人を百五十万人もガス室へ送り込んだナチス・ドイツ。この一月下旬、
ポーランド南部のアウシュビッツ強制収容所解放六十年を記念して、イスラエル
の首相、フランスのシュラク、ロシアのプーチン大統領ら、約四十カ国の首脳と
関係者が集まって、記念式典が行われた。
その数ヶ月前、あの忌まわしい戦争とナチズムの狂気が風化しつつある事件が
起った。英国のヘンリー王子が、ナチスの制服姿で仮装パーティーに出て、問題
になったのです。
つい最近再婚した、父のチャールズ皇太子は怒り心頭。息子にアウシュビッツ
訪問を命じたという。ところが、英国の世論調査では、「アウシュビッツ」を知ら
ないと答えた若者が半数に及ぶという。

【心と体の健康情報 - 190】
~幸せな人生を歩むために~
「日本人として知らねばならないこと」
先週の土曜日、「3KM研修」の二回目があった。
「三歳の頃の思い出を隣同士
で語り合ってください」と、講師の先生…。私の三歳は昭和19年、太平洋戦争
の真っ只中。その頃のことが、走馬灯のようによみがえってくる。
元、松下政経塾副塾長、現「志ネットワーク」の”上甲 晃”氏は、戦前生まれ
の人達に比べ、今に生きる人たちは「三つのことを知らない」と言っている。
第一に
「貧乏を知らない」
私(吉村)は、
戦後の何もかもが貧しかった時代、兄弟、祖母、満州から引き
揚げてきた叔父家族、合わせて13人が一つ屋根の下で生活した。 生活は
貧しく、昭和29年、十三歳の頃まで、朝ご飯は芋がゆ、おやつも芋だった。
兄のお下がりを着て育った私は、モノを捨てることができない。古くなくなった
上下のスーツ、大事にしまってある。お魚などは、身一つ残さずきれいに食べ
る。JRでお弁当を買って食べるとき、端から米粒を一粒ひと粒、きれいに掃除
しながら食べる。貧しかった頃の習慣がしみ付いている。
「勿体ない世代」である。
今に生きる若者たち、貧乏を知らない。生まれながらに豊かで、豊かな暮しが
当たり前。にもかかわらず自殺者が多いのは、何故だろう。
第二に
「戦争を知らない」
私(吉村)は昭和十六年生まれ。
あの戦時中の、映画のシーンなどに出てくる
生活を、詳細に記憶している。
隣の家の軒先には、いつも数人の兵隊さんが村田銃を抱えて座っていた。
ガラス窓は目張りし、茶の間の電灯を風呂敷で覆い、店の中に防空壕を掘っ
たことなど、沢山記憶している。
夜、空襲警報が鳴り、B29が不気味な音を響かせ飛んでいった。疎開先で見
た富山の空襲。焼夷弾が落とされるたびに、医王山の彼方がボコン、ボコンと
真っ赤に燃えた。まだ四歳、打ち上げ花火のようだったことを覚えている。
今に生きる私達は戦争を知らない。日本がアメリカと戦争したことも、長崎に
原爆が落とされたことも知らない。そんな若者が増えてきている。日本の歴史
を振り返って、今ほど豊かで平和な時代はない。なのに、嘆いて暮らしている
人がいるのは何故なんだろう。
第三に
「神仏を知らない」
私(吉村)が子供の頃は、
お年寄りと同居するのが当たり前。仏壇の前で手を
合わせ、お参りする姿を見て育った。
「ご先祖に申し訳がない」「バチが当たる」「閻魔様に舌を抜かれる」など、
知らないうちに、私の心の中で一種の宗教的役割を果たしている。
今の人は神仏に手を合わさない。食事どきにきちんと両手を合わせ、神仏に
感謝してご飯をいただく人は稀である。
進駐軍が推し進めた戦後の教育改革の目的の一つに、日本人から大和魂を
抜き取ることがあったと、京都の研修講師、伊與田先生(安岡正篤の高弟)が
語っていた。
戦後の貧しい暮しの中、両親は子どもにかまっている余裕はなく、学校で倫理・
道徳を教わることはなかった。善悪をしつけられたのは、幼稚園のときだけ…。
そういった戦後世代が今、日本の政治・経済の中核にいる。政治家や、事業
経営者の倫理が問われ、モラルが問われる…、その原因はこんなところに
あるような気がする。
2005年04月12日
日本人として知らなければならないこと
ユダヤ人を百五十万人もガス室へ送り込んだナチス・ドイツ。この一月下旬、
ポーランド南部のアウシュビッツ強制収容所解放六十年を記念して、イスラエル
の首相、フランスのシュラク、ロシアのプーチン大統領ら、約四十カ国の首脳と
関係者が集まって、記念式典が行われた。
その数ヶ月前、あの忌まわしい戦争とナチズムの狂気が風化しつつある事件が
起った。英国のヘンリー王子が、ナチスの制服姿で仮装パーティーに出て、問題
になったのです。
つい最近再婚した、父のチャールズ皇太子は怒り心頭。息子にアウシュビッツ
訪問を命じたという。ところが、英国の世論調査では、「アウシュビッツ」を知ら
ないと答えた若者が半数に及ぶという。

【心と体の健康情報 - 190】
~幸せな人生を歩むために~
「日本人として知らねばならないこと」
先週の土曜日、「3KM研修」の二回目があった。
「三歳の頃の思い出を隣同士
で語り合ってください」と、講師の先生…。私の三歳は昭和19年、太平洋戦争
の真っ只中。その頃のことが、走馬灯のようによみがえってくる。
元、松下政経塾副塾長、現「志ネットワーク」の”上甲 晃”氏は、戦前生まれ
の人達に比べ、今に生きる人たちは「三つのことを知らない」と言っている。
第一に
「貧乏を知らない」
私(吉村)は、
戦後の何もかもが貧しかった時代、兄弟、祖母、満州から引き
揚げてきた叔父家族、合わせて13人が一つ屋根の下で生活した。 生活は
貧しく、昭和29年、十三歳の頃まで、朝ご飯は芋がゆ、おやつも芋だった。
兄のお下がりを着て育った私は、モノを捨てることができない。古くなくなった
上下のスーツ、大事にしまってある。お魚などは、身一つ残さずきれいに食べ
る。JRでお弁当を買って食べるとき、端から米粒を一粒ひと粒、きれいに掃除
しながら食べる。貧しかった頃の習慣がしみ付いている。
「勿体ない世代」である。
今に生きる若者たち、貧乏を知らない。生まれながらに豊かで、豊かな暮しが
当たり前。にもかかわらず自殺者が多いのは、何故だろう。
第二に
「戦争を知らない」
私(吉村)は昭和十六年生まれ。
あの戦時中の、映画のシーンなどに出てくる
生活を、詳細に記憶している。
隣の家の軒先には、いつも数人の兵隊さんが村田銃を抱えて座っていた。
ガラス窓は目張りし、茶の間の電灯を風呂敷で覆い、店の中に防空壕を掘っ
たことなど、沢山記憶している。
夜、空襲警報が鳴り、B29が不気味な音を響かせ飛んでいった。疎開先で見
た富山の空襲。焼夷弾が落とされるたびに、医王山の彼方がボコン、ボコンと
真っ赤に燃えた。まだ四歳、打ち上げ花火のようだったことを覚えている。
今に生きる私達は戦争を知らない。日本がアメリカと戦争したことも、長崎に
原爆が落とされたことも知らない。そんな若者が増えてきている。日本の歴史
を振り返って、今ほど豊かで平和な時代はない。なのに、嘆いて暮らしている
人がいるのは何故なんだろう。
第三に
「神仏を知らない」
私(吉村)が子供の頃は、
お年寄りと同居するのが当たり前。仏壇の前で手を
合わせ、お参りする姿を見て育った。
「ご先祖に申し訳がない」「バチが当たる」「閻魔様に舌を抜かれる」など、
知らないうちに、私の心の中で一種の宗教的役割を果たしている。
今の人は神仏に手を合わさない。食事どきにきちんと両手を合わせ、神仏に
感謝してご飯をいただく人は稀である。
進駐軍が推し進めた戦後の教育改革の目的の一つに、日本人から大和魂を
抜き取ることがあったと、京都の研修講師、伊與田先生(安岡正篤の高弟)が
語っていた。
戦後の貧しい暮しの中、両親は子どもにかまっている余裕はなく、学校で倫理・
道徳を教わることはなかった。善悪をしつけられたのは、幼稚園のときだけ…。
そういった戦後世代が今、日本の政治・経済の中核にいる。政治家や、事業
経営者の倫理が問われ、モラルが問われる…、その原因はこんなところに
あるような気がする。
2005年04月05日
過去は変えられる(4)
幸せな人生は、ひたすら目標を叶えようと努力した人だけに与えられる。
1940年から1980年の40年間に渡って、ハーバード大学において、
1940年当時、同じ生活環境の人達を対象に、その後の人生を追跡した。
40年後の調査では、やっと生活している人が約80%、
普通に生活している人約20%、豊かな人生を送っている人は3%でした。
そして何とその3%の人は、残り97%の人の収入のすべてを合計しても、
更に三倍を上回る収入を得ていたという。
やっと食べている人は、40年間漫然と日々を過ごした。
普通に生活している人は、一応目標はあった。
豊かな生活をしている人は、「目標を見えるところに貼って、やり続けた」
これを学んだのは、私がノエビアを始めた頃。当時、ノエビアの社長が
全国の代理店育成に飛び回っていた。その時の研修から学んだものです。
その後しばらく、自社の研修でも使われていた。

【心と体の健康情報 - 188】
~幸せな人生を歩むために~
「過去は変えられる(4)」
土屋ホームの創業社長であり、土屋経営の土屋公三社長は、自社の社員教育で実践してきた 「3KM」「千分の一の向上運動」を、広く経営する人たちに提唱して、中小企業の育成・指導を行ってきた。
「小さな持続が人生にとっていかに大きな力となり、人生を変えていくか…」。昨日の自分より今日の自分を、 千分の一だけ向上させようという、自己啓発運動です。
「昨日の自分より、千分の一、ほんのちょっとだけつま先を上げて、背伸びする。たったそれだけの努力を毎日続ける。 それを三年、五年と続けたら、びっくりするほど成長しますよ!」と教えられた。それがメルマガを始める動機にもなっている。
■千分の一の向上運動
(1) 昨日の自分より、
今日の自分を千分の一だけ向上させます。
(2) 一年365日のうち、三日坊主で二割のロスを見て、
300日だけ向上したと します。
(3) 一年間で 「千分の一 × 300日」=三割アップ
十年で三割のロスを見ても 10倍
二十年で 100倍
三十年で 1,000倍
四十年で 10,000倍
せっかく目標を立ててやり始めても、三日坊主に終わってしまうという経験は誰にでもあります。
「やっぱり自分には無理だ」とあきらめたりせず、「三日坊主もOK」と、気持ちを楽に持って、また続けるようにします。
そんなことを何度も繰り返して、一年で三割、十年続ければ十倍、二十年で百倍、三十年で三千倍、四十年続けると、
何と一万倍にもなるのです。
以下、小野晋也「日本人の使命」からの抜粋です。
| 一日1%の成長を、もし複利で数学的計算をしたら、1.01の三百六十五乗。
もし、今日が100だとしたら、一年後には、三十七倍の3,700くらいになります。
二年経つと千倍以上になるのです。 これは、1%成長するということが、具体的に何かということではありません。 「人間的に成長する。人格的に成長する」、こういうことは数字で表せるものではありません。 しかし、毎日1%の成長を心掛けていれば、人間というものは、どこまでも大きく成長していくものです。 |
■トイレ掃除三十年の、
イエローハット鍵山秀三郎氏が好んで使う中国の教え。
誰もが、やれば出来る簡単なことであっても、やり続けることによって…
十年 偉大なり
二十年 恐るべし
三十年 歴史になる
五十年 神のごとし
毎日ほんのわずか、千分の一だけ背伸びをする。これは、誰でも簡単に出来ることです。毎日千分の一という、
ほんの少しの自己啓発の継続が、人生を大きく変えていくのです。
■宮本武蔵は剣の修行で…
「千日の訓練を”
鍛”といい、万日の訓練を”練”という」と語っている。
万日とは三十年、生涯修行ということでしょう。このように、絶え間のない持続によって目標が達成されるようになり、
幸せな人生を手にすることができるのです
2005年03月29日
過去は変えられる(3)
三月上旬、プロジェクトX「ツッパリ生徒と泣き虫先生」の再放送を見た。当時京都で最も荒れていた学校。その伏見工ラグビー部を、 高校日本一の名門校にまで育て上げていく、熱血先生のドラマ。
初戦、名門花園高校に”112対0”で負けたときに流した屈辱の涙。その悔しさをバネに猛練習。一年後再度の花園戦。必死に戦い、 終盤同点から奇跡のトライ、雪辱を果たした。その時流した感動の涙は、出場選手一生の宝になった。
それが引き金となって、その後二度の全国制覇をなし遂げ、全国に名が知れるようになった。
ツッパリ生徒に、体当たりでぶつかっていく山口良治先生の魂の声が、見ている私たちの心までゆさぶる。知らず知らず、
感動の涙がこみ上げてくる。

【心と体の健康情報 - 187】
~幸せな人生を歩むために~
「過去は変えられる(3)」
私の会社は、雇用関係で結ばれた社員はわずかしかいない。代理店契約を取り交わし、 フルコミッションで働く人たちで構成されている。そういった人たちを動機づけて成功へと導くのが、 会社のスタッフの仕事です。
動機づけは面談から始まる。将来なりたい姿を明確にさせ、自らその目標にチャレンジし、 成果を手にしたときの姿を想像させる。努力が実って、目標が達成された時、その時湧き出る「喜びの涙」 がいかに素晴らしいかを…。
「悲しみの涙」を経験しないものはない。しかし、「喜びの涙」を人前で流したことのある人は意外と少ない。
いまだかって成し得たことのない目標に必死にチャレンジし、成果を掴み取ったとき、心の底から湧き出る”喜びと感動の涙”。
人生、これほど幸福で素晴らしいものはない。
私が所属する経営者の集まりで、「幸せプランニング3KM」という名の研修が、先月から始まった。
「3K」とは、個人のK、家庭のK、会社のKの三つを総称した言葉です。研修の目的は「個人の成功」「家庭の幸福」
「職場での貢献」、それぞれにスポットを当て、将来自分がなりたい姿・
夢を明確な目標にして、日々その実現に向け最善をつくすという、大変意味のある研修です。
「3KM」を知ったのは、二十年くらい前。土屋ホームの創業社長”土屋公三”氏が、 自社の社員教育で絶大な効果のあった、この人材育成手法を、中小企業の成長発展に寄与すべく、コンサルタント会社を設立。 石川県へ啓蒙講演に来られたのがきっかけです。
まず夢を念い描きます。そして、その夢を実現するための目標を明確にします。
一年後、三年後、十年後、そして晩年までの自らのあるべき姿を書き出し、人生を設計します。「いつまでに、何を、
どうするのか」。そして、その目標を達成するため、きちんと計画を立て、その実現に向け、
日々努力していこうというものです。
以下、日創研SA講師”坂東弘康”氏の講演、「松下幸之助に学ぶ成功への情熱」からの抜粋です。
ある時、松下幸之助は「経営にもいろんな規模があるんや~」と言われた。
私はそれを聞いて、直感的に松下電器のような大企業もあれば、従業員数名の零細企業もある。
そんな企業の大小のことを言うのかな~と思った。
「最小単位の一番小さな経営とは何かいな?」と、松下幸之助は尋ねる。「皆さん何やと思います? これはね、”一個人の、自分の人生の経営” のことなんや…。ところで皆さん、 どないな夢描いてまっか?」
かけがえのない人生、やり直しのきかない人生。この人生、
どんな夢を描いて生きてきただろうか? その夢を実現するため、努力しただろうか?
例えば「三年後の何月何日までに、具体的に何をどうしたいのか?」
きっちり紙に書いて、目標設定して行動しているだろうか? 「……」
そこで、それを明確な目標に書き出して実行する。それが「3KM」なのです。
目標のない人に計画などない。計画がなければ、今日一日無為無策、日々無駄に暮らすことになる…。 目の前の与えられたことを無難にやり過ごすだけの人生になってしまうだろう。果たしてそれで幸せな人生といえるだろうか…。
坂東氏は続けて…
|
経営者の皆さんは、会社を経営することばかり考えているようですが、その前に、
自分の人生の経営を考えなければなりません。自らの生き様が必ず会社経営に影響します。「家族の経営」
も大事です。「子育て経営」もおろそかに出来ません。
おうちの中で、お父さんやお母さんは、子供たちに夢を語って聞かせているでしょうか?
家庭内に問題を抱えていて、会社経営がうまくいくはずがありません。 |
「一個人の経営」も、「子育て経営」も、「会社経営」も、「国家経営」も同じことです。どれが上で、 どれが下というものではなく、みんな大事なのです。
2005年03月22日
困ったことが起きても悩まない
先週の土曜日、妻とオーケストラ・アンサンブル定期公演を鑑賞した。
お目当ては「ブラームスの交響曲第1番」。
ベートーベン以外の曲では、トボルザークの「新世界」と並んで好きな曲だ。
ブラームスがベートーベンの「第9運命」に出会ったのは22歳の時。
この不滅の第九に並び称される作品を作りたいと、それから21年間思索を繰り返し、43歳の時に完成した名曲なのです。
その調性はどことなく「運命」に似て、「タタタ・タン」と、波が寄せては返すような鮮明なリズムが曲の流れをリードする。映画
「オペラ座の怪人」のような重厚な旋律に乗って…。
もう一つのプログラム「ブルッフのブァイオリン協奏曲」は、ニューヨークから来たヴァイオリン奏者、アン・アキコ・
マイヤーズのダイナミックな演奏に魅了。
50人のオーケストラを従え、左指と右手の絃が奏でる旋律は、「すごい!」の一語につきる。すごく見ごたえがあった。
この金沢の地で、世界一流のバイオリン奏者の演奏を堪能できるとは、幸せ…。
鳴り止まぬ拍手。カーテンコールが七度も八度も続く…。感動の二時間だった。

【心と体の健康情報-186】
~幸せな人生を歩むために~
「困ったことが起きても悩まない」
10年連続全国高額納税者に名を連ねている、”斉藤一人”氏の講演から…。何事も、 ものは考えよう…、「なるほど…」と、納得できる考え方です。
日々暮らしていく中で、いろんな悩みを抱え込んでしまう。しかし、私には「困ったことが起きて”
悩む”」ということがない。「困ったことが起こらない」のです。
日々暮らしていれば、様々な問題が生じてくる。目の前に現われる問題は必ず解決できることなのです。
神様は、解決できない問題を出したりはしない。
だから、目の前の問題を一つ解決すると、”一段”階段を登ったことになる。
しばらくすると、また問題が出てくる。それをクリヤーすると、また一段階段を登ったことになる。
そうやって、クリヤーする問題の数だけ、登っていく階段の数だけ、世の中が見えてくるようになる。
それだけ多くの幸せを手にするようになる。
一般に人は、問題を”悩み”として受け止めてしまう。私には、
問題の階段を一歩一歩上がっていくだけのことと思っている。階段があるから、一歩上に上がる。
それを繰り返しているに過ぎないのです。だから「困った」と思うことがないし、
問題が悩みになることもない。
例えば「今月は赤字で、お金がない」。そんな時は、お金を使わないようにすればいい。
あるいは、お金を稼ぐようにすればいい。それで問題は解決する。
思うようにお金が稼げなければ、今までの倍働くのも方法だろう。そうやって行動を起し、目の前の問題を一つ、また一つと、
出来ることからクリヤーしていけば、悩みなど発生しないことになる。
181号「過去は変えられる」で、斉藤一人氏のモノの見方・考え方を紹介しましたが、自分で解決できなければ、
それは悩みになります。
やれば簡単に解決出来ることでも、やる前に「出来ない」と決め付けていないだろうか。決め付けてしまえば、何もしない。
何もしなければ、階段を登ることができない。問題は解決せず、悩みを抱え込んでしまうことになる。
2005年03月15日
才あって徳なき…
トム・クルーズ主演の「ラスト・サムライ」は、日本人の魂「武士道」を追求した映画。
この映画の構想を練ったエドワード・ズウィック監督は、「七人の侍」の影響を受け、新渡戸稲造の「武士道」をすり切れるほど読み、
侍の心を知ったという。
今から百数十年前、日本人の支配階級の象徴である武士。
自らを律し、正義をモットーとし、利欲に走らず、ひとたび約束した以上は、
命懸けで約束を守り、不正や名誉のためには、死(切腹)をもってあがなった。
この本を読んだ西欧人はいずれも、東洋の端にある小さな島国日本に、
これほど厳しく、気高い精神を持った民族が存在しているとは…。
そのことに驚嘆し、尊敬の念を持ったのです。
私たちの先祖が、志も高く、凛として正しく生きてきたことを思うと、今に生きる
私たちの姿はどうでしょうか。利欲を追い求め、不正を恥とも思わず、約束を
平気で破り、事が発覚すれば言い逃れする。同じ日本人に生まれながら、
あまりにも恥ずかしい。

【心と体の健康情報 - 185】
~幸せな人生を歩むために~
「才あって徳なき…」
日本放送の乗っ取り騒動に続いて、西部王国の崩壊がマスコミを騒がせている。
「社員は頭を使わなくていい。黙って指示に従っていればいい…」
堤義明氏のワンマンぶりが浮かび上がってくる。どんなに偉大で、世間的評価の高い人物でも、
弱点や欠点があることを教えている。
私のような下々の凡人も含め、今の50~60代の世代というのは…、中でも政財界のトップにいて、
日本をリードする人たちには「徳」のない人が多いようです。
3/11の朝、突然飛び込んできた国会議員の強制わいせつ事件には驚いた。
更に今朝の新聞。東京MKタクシーの青木社長(41/息子さん?)、酒に酔って駅員を殴り逮捕、会社に辞表提出。
埼玉県警の警部(51)、女性部下のお尻をさわって依願退職。酒の上での失敗を取り上げたニュースが二件も載っていた。
”酒で身を滅ぼす”情けないニュースが立て続け。いずれも、社会的責任のある指導的立場の人たちばかり。40、 50になって、酒の飲み方から教えていかなければならないとは、何ともなさけない。
3/6読売新聞「政思万考・才あって徳なき世界」は、今回のニュースにぴったり。以下、その一部を抜粋しました。
自民党の武部幹事長が駆け出しの頃、先輩議員から「おい武部、政策論議は上下なしだ。
しかし酒席には序列があることを忘れるな!」と教えられたという。
また小泉首相は、
「酒席は人生道場。人間を磨く場所。人は人によって磨かれる。人の話を聞き、酒を飲みながら、話しながら、磨かれる。
この両方が大事だ」と語っている。
直木賞作家の”山口瞳”氏は、1981年1月15日、サントリーが成人を祝って読売新聞に広告を出した中に、 以下の文章を載せている。
「君、人間は少しぐらい”品行”は悪くてもよいが、”品性”はよくなければならないよ」。僕は、
酒を飲むときのエチケットの要諦は、これに尽きると思っている。
酒を飲むのは”修行”であり、酒場は”品性”を向上させるための”道場”であり、”戦場”である。酒では失敗ばかり…、
だから僕は真剣に酒を飲む。
若者諸君! 酒だけを考えてみても、この人生大変なんだ…。
山口瞳氏は、1976年「中央公論」で、逮捕された田中角栄元首相のことを、
「才あって徳なき人物」と論じた。 そして、当時の政財界を風靡して…
「法に触れないかぎりの金儲けは決して悪いことではない。よしんばそれが法に触れるものであっても、 おとがめに遭わなければ悪いことにはならない。さらに、それが法律によって罰せられても、なんら恥ずるところはない。 なぜならば、それは事業を守るためなのだから…。家族を守るためなのだから…」
陽明学の創始者”王陽明”の研究では第一人者の”井上新甫”氏は、
「リーダーは”徳”を身につけよう。”事上磨錬”すなわち、人生いたるところ
修行の場だ」
と説いている。以下、その著書「王陽明と儒教」(致知出版社)の中の文章。
「才」なく「知」なくも、「徳」や「情」があれば、人生間違いはない。
”徳”が根幹、”才”は枝葉である。才より徳のまされるを「君子」といい、
才徳共に兼備していることを「聖人」といい、才徳兼亡を「愚人」という。
「才あって徳なき」人たちが力をもった今の時代。そろそろピリオドを打たなければならない。
政界や経済界を見ていると、有り余る才だけで人生をまっとうするのは難しい。
”才徳兼備の聖人”は望めないにしても、せめて”徳のまされる君子”に一歩でも近づければと思う。
今回のセクハラ事件のように、たった一瞬・一度の間違いで、人生を棒に振ってしまうのは何とも切ない。
このような取り返しのつかない失敗をしないために、「徳」を積んでいかなければならない。
とは言っても、人生「徳」を身につけていくのは易しいことではない。学校教育の場で、倫理・道徳を教えるのも大事でしょう。
しかし、子どものしつけは家庭の中で決まる。まだ物心つかない幼少のころに、やっていいことと、悪いことのケジメを、
しっかり付けさせなければならない。
2005年03月11日
天職にめぐりあう
■趣味の言葉遊び
言葉遊び。今日は酒を飲む席で、日本語の発音に近い韓国語を並べてみます。
”乾杯!”は「こんべ~!」。韓国人は酒豪が多い。韓国の酒場で
「こんべ~!」とグラスを持ちあげたら、イッキ飲みを意味する。
ビールは漢字で”麦酒”と書くが、「めくちゅ」と発音する。
生ビールは、”生麦酒”「せんめくちゅ」と読みます。
ワインは「わいん」、ウイスキーは「うぃすき」、ブランディーは「ぶれんで」、
焼酎は「そじゅ」、水割りは「みじゅわり」で通じます。
日本酒は、”正宗”という漢字を韓国読みにして、「ちょんじょん」と言います。
よく似た言いまわしで、「ちょんちょんに…」と韓国語で言うと、
”ゆっくりやりましょう”の意味になる。”ちょんちょんにやろうよ…”って、
日本語で言っても、何となく通じるじゃない…。
「あんじゅちゅせよ」
”つまみ”は韓国語で
「あんじゅ」と言います。「ちゅせよ」は”ちょうだい”
酒場で「あんじゅちゅせよ」と言えば、何か出てきます。
覚え方は、”あんじゅさん、おつまみちゅせよ(ちょうだい)”

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第70号】
~幸せな人生を歩むために~
「天職にめぐりあう(2)」
(株)芝寿しの梶谷忠司会長。神戸で知る人ぞ知る、(株)甲南チケットの小林宏至社長、 何れも二十数回いろんな職業を体験した後、梶谷会長は四十五歳、小林氏は五十歳になって今の仕事にめぐり合い、 天職を手にした。
今やっている仕事が、たとえ徹夜の連続であってもいっこうに苦にならず、好きな仕事であれば、それは”天職”。
日創研のSA講師 坂東弘康氏は、講演の中で松下幸之助の創業時の逸話を、以下のように語っている。
松下幸之助は”経営の神様”と言われている。その経営の神様も、 創業時に売り出した二股ソケットが売れなくて弱気になり、他の職業に転業しようかと、 思い悩んだときがある。
幸之助は無類の甘党。今の商売をあきらめて、お汁粉屋でもやろうかと、本気で考えたという。
それを聞いた気丈な奥さん、「あんた、なに言うてるの…。そんな弱気でどないするの、しっかりしなさい」
と、思い止まらせたという。
もし、奥さんが「そうね、そうしましょうか…」と言っていたら、
お汁粉甘味のお店で全国展開していたかもしれない。
昨年、京都の研修で、(株)ダン 越智正直社長の成功体験を聴いた。
越智社長は中卒で、丁稚奉公上がりの経営者である。専門店「靴下屋」を全国にFC展開している。
講演の中で印象に残ったのは、
「お前(自分)の心の中の念い、その念が形になったものが”商品となりサービス”となって現れてくるんや。
その程度の念いやから、この程度の商品、この程度のサービスしか出けへんのや!」と、事あるごとに自問したという。
神渡良平著「下座に生きる」の中にも、越智社長のことがくわしく書かれている。
その一部を抜粋して紹介します。
|
「わしは靴下のこと以外は何も知らん!」と、靴下一筋にのめり込んで、 寝ても覚めてもただ一筋に靴下に命を捧げてきた越智社長。靴下のことなら何でも知っている、 靴下馬鹿のような人である。 資本もなければ学歴もない。何もなかったが、ただどこよりも素晴らしい靴下を作りたいという念いが、 今日のダンを作り上げるに至った。そして、他では真似の出来ないものを作っていった。 商売のしがけの頃はないない尽くし。弱気になってあきらめようとする自分を叱ったものだが、 「隣の花は赤そうだ」と迷ったり、「この仕事は本当に自分に向いているのだろうか?」 と腰砕けになることなく、一途にお客様が喜ぶ靴下の改良に賭けてきた。 いつしか正宗の名刀の光を放つ自分になっていた。 人がある職業を選ぶのは、めぐり合わせだ。めぐり合わせには、 天の深い配慮がある。それを拒否することなく、そこで花を咲かせようと頑張るとき、どんな菜切り包丁も、 正宗の名刀に変わっていくのではないだろうか。 |
2005年03月01日
人格を磨け
「こうなったのは、おまえのせいだ!」と相手を指さす。
そのときの手と指のかたちを見るといい。
親指は天を指して運命を呪い、中指と薬指、小指の三本の指は「責任はおまえ自身にある」と、自分の方を指している。
相手を指差しているのは、五本の指のうち、人差し指一本だげである。
物事がうまくいかなくて、人を責めたくなるとき、その責任はおおむね自分にあることが多い。

【心と体の健康情報 - 183】
~幸せな人生を歩むために~
「人格を磨け」
法律のスキ間を突いた、ライブドアの日本放送株取得事件。いくら違法ではないといっても、 時間外取引という闇討ちのような行為で、企業の支配権を奪うほどの大量買い付けは、フェアとはいえない。
一方の日本放送の経営陣。突然降って沸いた会社乗っ取りに、会社と自らの地位を守ろうと、
防衛手段に出るのは当然でしょう。が、株主不在のなりふり構わぬ手法は、非難されても仕方のないところです。
いずれにせよ、主張するところが公明正大、且つ社会的正義の強い方が、株主や大衆を味方に引き付け、
勝利を収めるのではないでしょうか?
以下致知3月号、京セラの稲盛和夫名誉会長「巻頭の言葉」からの抜粋です。
世間には高い能力を備えながら、心が伴わないために、道を誤る人が少なくありません。古来「才子、
才に倒れる」といわれるとおり、才覚にあふれた人は、ついそれを過信して、
あらぬ方向へと進みがちなものです。
そういう人は、たとえその才を活かし、一度は成功しても、才覚だけに頼ることで、
失敗への道を歩むことになる。
正しい方向に導くためには、羅針盤が必要となる。その指針となるものが「理念」 や「思想」 であり、また「哲学」 なのです。その哲学が不足し、人格が未熟であれば、 いくら才に恵まれていても、せっかくの高い能力を正しい方向に活かしていくことができず、 道を誤ることになる。
この「人格」は、 人間が生まれながらに持っている「性格」 と、 人生を歩む過程で身につけていく「哲学」 の両方から成り立っている。つまり、 性格という先天的なものに、哲学という後天的なものをつけ加えていくことによって、私たちの人格は陶冶 (とうや)されていくのです。
では、どのような哲学が必要なのかといえば、それは 「人間として正しいかどうか」ということ。すなわち 「嘘をついてはいけない」「人に迷惑をかけてはいけない」「自分のことばかりを考えてはならない」など、 誰もが子どものころ、親や先生から教わったにもかかわらず、大人になるにつれ、忘れてしまったことです。
誰もが正しいと信じる、親から子へと受け継がれてきた、モラルや道徳がある。
それに反することをして、うまくいくことなど一つもないのです。
今回のライブトアの行為で思い起こされるのが、巨人軍のあの空白の一日。
リーグ規則に払拭しないたった一日の空白。規則の欠点を突いた江川卓獲得事件のことである。やり方がフェアーでなければ、
周りの支持は得られない。支持が得られない行為は、失敗と言わざるを得ない。
外資が今回の事件に注目していて、「日本のライバル企業をつぶす目的で、買収をしかけてくる(2/28読売)」
という。力の強いものが、有無を言わせず力づくで欲しいものを奪い取るといった、狩猟民族アメリカ的手法は、
「みんな仲良く」和を重んじる、農耕民族日本人の肌合いにはなじまない。
一面、堀江社長の行為は、閉塞的だったプロ野球界に新風を吹き込んだように、株主不在の旧態然とした日本式経営に、
大きな風穴を開けることになるかもしれない。
■二宮尊徳翁の言葉
「経済のない道徳は寝言だが、道徳のない経済は犯罪である」
2005年02月22日
過去は変えられる(2)
19~20日の二日間泊り込みで、同友会スキー同好会の皆さんと、上越国際スキー場へ行った。上越を長野方面に曲がらず直進。
関越道の途中にある、金沢から4時間のスキー場です。同じ滑るなら、中越地震の被災地にお金を落とそうと決めた。
高速を走行中、中越地震の影響でしょうか? 路面はアスファルト継ぎはぎ、デコボコのところが何箇所もあった。路肩は3mくらいの雪の壁。
温暖化の影響でしょう。水分をたっぷり含んだ、本来は北陸に降っていた雪です。
ホテル(ホテルグリーンプラザ上越)は東急系列。各室バストイレ付き(700室もある)、ヨーロッパのメルヘンが漂い、 びっくりするくらい豪華。露天風呂付き天然温泉大浴場が何箇所かあって最高。春や秋に、群馬方面に家族ドライブするとき、 お勧めのホテルです。

先週の土・日、上越国際スキー場にて

【心と体の健康情報 - 182】
~幸せな人生を歩むために~
「過去は変えられる」
アメリカの心理学者ウイリアム・ジェームズは、「人間は心構えを変えることによって、
自分の人生を変えることができる…」と言っている。
しかし、ただ単に心構えを変えただけでは、人生が変わったりはしないだろう。
何かをやろうと決めたら、以下の成功サイクルに従って、明確な目標を立て、習慣化するまで、 毎日コツコツとやり続けることです。そうやって、やった事が身に付いたとき、人生が変わっていくのです。
■人生の成功のサイクル
(7)[人生が変わる] → → (1)「ものの見方、考え方を変える]
↑ (更に大きな目標へ) ↓
(6)[運命が変わる] (2)[目標を設定する]
↑ ↓
↑ ↓
(5)[人格が変わる] (3)[行動が変わる]
↑ ↓
← ← (4)[習慣化する] ← ←
高島和雄著「使命感経営」(株)土屋経営より
この人生の成功サイクル。一度決意して目標に向かって漕ぎ出し、サイクルがまわり出すと、止まらない。
もっと旨くなりたい、より難しいことにチャレンジしたいと思うようになるから愉快である。
何か目標にチャレンジして、その努力が実り成果を手にすると、より上のレベルに到達したいと思うようになり、更に大きな夢・
目標に挑戦しようとするエネルギーが沸いてくるのです。
だから人生において、こうしたチャンスにめぐり合ったとき、漫然と見過ごすことなく、
自らの目標として取り込むことが出来れば、「幸福」行きのキップも、同時に手にすることができるのです。
私の周りには、「ノエビアとの出会いのお陰で、私の人生が変わった」という女性や、「日創研の”SA研修”が、
そのスタートだった…」と答える男性が、数多く存在するのです。
私は55歳の時、新潟へ春スキーに行って足を骨折し、アキレス腱断裂の重症を負った。年齢を考えれば、 そこでスキーを止めてしまうところでしょうが、「よし!二度と怪我をしないよう、上手くなってやろう」と、その年の十一月、 スキー同好会に入会。直って間もないのに、翌年の二月、白馬へ連れて行ってもらい、 頂上から皆さんのお尻にくっついて滑った。
それまで、趣味とまではいかなかったスキー。その後毎年、蔵王や志賀高原に出かけて楽しむようになった。そして、
毎冬が待ち遠しくてしようがないという、人生の楽しみを手に入れたのです。
2005年02月15日
過去は変えられる
数日前、久しぶりに神渡良平先生の講演を聴いた。演題は「一粒の麦 丸山俊夫の世界」。
丸山俊夫は、倫理法人会で知られる、倫理研究所の創設者です。
故丸山先生の”幸せになる法則”を語る中で、「苦難は幸福の門である」という一言が心に残った。
淡々とした語り口でしたが、会場はしだいに感動と涙に包まれていった。
神渡先生は、働き盛りの三十八歳の時、突然脳梗塞に襲われた。四日後に意識を取り戻し、右半身麻痺に陥ったが、
懸命のリハビリのお陰でよみがえった。
苦悩の中から「人生一度しかない!」と悟り、作家の道へ。「一隅を照らす」で一躍有名に…
危機を乗り越えてつかんだ人生。「人にはそれぞれなすべき使命がある」という思想で、
人としての生き方を説き、次々と作品を世に送り出していった。
著書には、「安岡正篤」「中村天風」「新渡戸稲造」「森信三」、”言志四録”の「佐藤一斎」など、
人生の師と敬われる人たちを題材にしたものが多い。
中でも、一燈園の三上和志さんと、結核で死の床に伏している少年の話しが載っている「下座に生きる」(月刊「知致」に連載された)
はお薦めです。
”正しい生き方”が求められる今の時代、神渡先生の著書からは、学ばなければならないことが沢山あります。

【心と体の健康情報 - 181】
~幸せな人生を歩むために~
「過去は変えられる」
「過去は変えられるけれど、未来は変えられない」。
こんな常識はずれに思えることをマジに言っている人がいる。10年連続全国高額納税者に名を連ねる”斉藤一人”氏です。
”銀座まるかん”の創業者で、健康食品・化粧品を販売している。「人生が全部うまくいく話」「斉藤一人のツイてる話」など、
16・7冊の著書が今、書店に並んでいる。
普通に考えれば、過ぎ去った過去など、変えられるわけがないと思う。
斉藤氏は「済んでしまった過去は変えられるけれど、これから先の未来は変えられない」
と、逆のことを言う。
「あの時の病気のお陰で、人にやさしくできるようになった」とか、「食うや食わずの貧乏を体験したお陰で、今の幸せがある」
といったことをよく耳にする。
過去のことを「幸せに思う」と思えば、思えるようになる。「昔、あの辛い体験をしたから、今、幸せなのです」と…。 過去にあったことすべてが、今の幸せにつながっていると思えば、これから後の人生、間違いなく幸せになります。
反対に、昨日までズゥ~と不幸だったと思って生きてきた人が、明日から突然幸福になるということはない。
身の回りに起きることすべて、「幸せ」と思えば幸に思えるし、「辛いことばかり」と思えば、
辛いことばかりの人生に思えてくるのです。
昨年9月1日、北京の日本人学校に29人の駆け込みがあった。北朝鮮の人は国を捨てて外国へ逃れようとする。
日本人で、国を捨てて外国へ逃れたいと思う人はいないでしょう。
平和で豊かなな日本に生まれながら、それでも自分は不幸だと思う人は、自分よりももっと不幸な人がいっぱいいることに、
目を向けなければならない。不幸と思うか思わないかは、その人の持つ”幸福の物差し”
の長さで、違ってくるからです。
過去のことはすべて思い出になる。だから、思い方一つで好いようにも、悪いようにも、好きに変えることができるのです。
過去ズゥ~と不幸だったと思っている人は、”不幸癖”がついてしまっている。何でも悪いように考えてしまう。
そんな人のそばにはいない方がいい。その人の隣にいるとくたびれてくる。
不幸癖が伝染してしまう。
自分のことを不幸だと思っている人は、自分より不幸な人を見ようとしない。
何事も、自分よりより幸せな人と比較して嘆いている。そして、自分がいかに不幸かを人に言いたがり、同情を求めようとする。
人は、幸せになるために生まれてきたのです。苦労を背負い込むために生まれてきたのではない。
「苦労は買ってでもせよ!」と言うが、人の苦労話を聞いていると、たいがいは間違った生き方をしているから、
苦労しなければならなくなったケースがほとんど…。
人生うまくいかない時は、「間違った生き方をしている時だ」と思えばいいのです。
神様は苦労させようと、意地悪しているのではない。間違った生き方をしていることを教えようとしているのです。
苦労が続く時は、「どこか、間違ったことをやっているのでは?」と、自らを振り返ってみることです。
しかし、やっていることが正しいと思っている時は、人が見て、どんなに苦労と思っても、当の本人は、
何一つ苦労だとは思っていないのです。
2005年01月11日
人生想い描いたようになる
いつだったか、NHKで見た”人間ドキュメント”を忘れない。
京都で名の知れた西陣織の職人の話です。七十歳のときに、余命残り少ない中、自分の持っている技術を、
世の中のお役に立てないものかと考えた。
ある時、美術館へ行った。そこで見たものは源氏物語絵巻。一千年の歴史で色あせ、虫食いのようになっている。
西陣織でこの絵巻を復元しようと心に決め、作業に取りかかった。あれから三十年。現在百二歳。三十年かけて、大変な思いをして、
全四巻のうち、ようやく三巻まで完成した。
約三百色の縦糸と横糸を駆使して、持てる技術のあらん限りをつくして織り上げた作品。
アナウンサーが尋ねた。「お歳を考えると、完成を急がないといけませんよね」。
老人は答えた。「わしは、未完成のまま死んでもいいと思っている。この模写が、このあと一千年の後に、その値打ちが問われるものにしたい。
だから、いい加減な仕事だけはしたくない」と…。
テレビ画面に映るその姿は、使命感と気迫に満ちて、百二歳とは思えぬ若々しさ。
只々、おそれいって声も出ない。

【心と体の健康情報 - 176】
~幸せな人生を歩むために~
「人生想い描いたようになる」
「天のまさに大任をこの人に降(くだ)さんとするや、
必ずまずその心志を苦しめ、その筋骨を労せしめ、
その体膚(たいふ)を餓えしめ、その身を空乏にし、
行いをそのなすところに払乱(ふつらん)す。
心を動かし、性を忍ばせ、そのあたわざるところを増益せしむるゆえんなり」
これは孟子の言葉です。何か困ったことが起こったときには、「これは、天が自分に大任を降そうとしているのだ」
と思うことです。すると、それが勇気の源となる。
勇気を奮って事に当たれば、困難が一気に解消されて、人生が開けてくるようになる。
新しい年を迎え、神社をお参りしたとき、今年はどんな願かけをしたでしょうか?
人生というものは、自ら想い描いた方向にしか進んでいきません。その一方で、想い描いたようにはなかなかならないのも、
また人生です。
自分がやりたいと思ったことをやり続け、貫き通すならば…。また、人に感謝され、喜ばれることをやっていれば、
愉快で楽しい人生になり、想いが叶うでしょう。
「想わないことは決して目の前に現れることはないし、手にすることはない」
「目の前に現れる問題や障害は、すべて自らが解決できることです」。
このことは、過去何度かお伝えしてきました。
何かをやろうとするとき、自分にとって実現不可能なことは、目の前に浮かんではこないし、想い描くことはありません。
想い描くことは、すべて実現可能なことばかりです。だから本気になって取り組めば、想いが叶うようになるということです。
想い描くとは、「自分にできる」と思ったことです。私達には、
無限の可能性を秘めた能力があります。どんな難しいことでも、同じことを100回続ければ、たいがいのことは、
出きるようになります。100回やって出来なかったら、200回やれば出きるようになるでしょう。
「出きる」と思うから、あきらめずやり続けることができるのです。想いが大きければ、
一生かけなければ出来ないこともあります。小さな想いや目標なら、一ヶ月、半年、
ちょっとその気になれば出きるものもあります。
やってみれば出きることでも、「そんなことは出来ない、出きるはずがない」
「自分には無理だ」と思えば、そう思った瞬間に「夢」がはじけてしまいます。
潜在意識の中にある、自らが持つ無限の可能性を摘み取ってしまうことになる。
運を呼び込むかもしれない折角のチャンスを、自ら放棄してしまうのです。
私は一度も政治家になろうと思ったことはないし、ジェット機のパイロットになろうと思ったこともない。ですから、
そのようなきっかけや、チャンスは一度も訪れてはきませんでした。想い描かないことは、
絶対に目の前に現れることはないのです。
以上、年の始めにあたり、「今年はどんな夢に向かって努力するのか?」と、自らに問いかけているのです。
2004年12月21日
笑いは免疫力を高める
日立の代理店に勤めていた頃の昔話。金沢観光会館でお客様招待バラエティーショーが開かれ、そのお世話役を勤めたことがある。
当時人気絶頂の小林 旭と江利チエミが来るというので、開宴前から長蛇の列。
台本を貰い、リハーサルを見学した。小林やチエミは、台本にない掛け合いジョークの連発で、本番とは一味違った笑いの連続だった。
本番。観客席の中ほどの通路に、江利チエミがしゃがみこむ。その横の席に台本を持った私が座る。 前日飛行機の中で台本を渡されたという江利チエミは、出番が回ってくるまでの間、原稿用紙一枚くらいのせりふを、 ブツブツと繰り返し練習していた。物凄い緊張感が伝わってくる。
いよいよチエミの出番。まばゆいスポットライトがチエミを浮かび上がらせる。
溢れんばかりの笑顔でスクッと立つや、今覚えたばかりのせりふを言う。
五行、六行と私の目が台本を追う。最後の行に近づいたとき、三行ばかりの文章を言い忘れ、飛ばしてしまった。が、そこはプロ。
みごとに演じ終え、舞台に向って客席通路を歩いていった。
あの時伝わってきた緊張感、今もはっきり覚えている。第一線の華やかな芸能人だからこそ、その隠れた苦労は並大抵ではないようです。

【心と体の健康情報 - 175】
~幸せな人生を歩むために~
「笑いは免疫力を高める」
幸せな人生を歩むためには、”くよくよ”せず、何事も”肯定的・プラス思考”で、
毎日を楽しく生きるようにすることです。それが幸せな人生の秘訣になります。
中でも「笑い」
に溢れた生活が幸福を生むのです。
笑いやユーモアは、病気に対する免疫力を高めることが、大学の研究で明らかになつている。「笑い」 の免疫力への影響については、数多くの医学臨床実験が行われ、笑ったり、ポジティブな気持ちになることで、 免疫力が高まることがわかってきている。
笑うことによって脳機能が活性化して”ぼけ防止”になり、関節リウマチの痛みを鎮めたりする。大笑いすると、 腹筋が激しく波打ち、内臓の”ジョギング効果”にもなる。何といっても笑いの一番の効用は、 心身がリラックスすることでしょう。
東京の恒川クリニックの先生が、患者さんを寄席へ連れて行き、漫談や落語などを楽しんでもらい、”免疫力の変化”
を測定する実験を行った。
実験の結果、参加者の73%に、NK細胞の活性化が見られ、数値が上昇した。
中には、数値が32%から58%と倍近くにはね上がった人もいた。
免疫リンパ球「ナチュラル・キラー(NK)細胞」が、
免疫機能を高める働きをするのです。NK細胞は平均して30%~40%持っている人が多く、
ガン細胞の三~四割を殺す力がある。
笑いのある生活は、知らないうちにガンを退治し、体内の活性酸素の発生を抑え、細胞の老化を予防し、
身体を元気にしてくれるのです。
大阪でも、病院を経営する「医誠会」がスポンサーになって、毎月一回「落語寄席」を設け、
健康な地域作りに貢献しようとしている。
「笑う・泣く・
深く眠る」。この三つの行為が病やストレスに打ち勝つ免疫力の源と力説するのは、
日本医大の吉野慎一教授。
リュウマチ患者は、健康な人に比べ、ストレスを受けると症状を悪化させる物質の量が多い。ところが、 落語を聞いて思いきり笑ったり、感動で涙を流したり、手術の全身麻酔で深く眠った後は、 体内のバランスが正常に近づいてくる。
強いストレスで身体のバランスが崩れると、病気になったり、病気が更に悪化したりするのです。日常、 ストレスを避けて通ることはできない。しかし、身体にはそれに打ち勝つ力が備わっていると、吉野教授は言う。
12/19 読売新聞「人の能力どう引き出す」より
私は、気持ちがふさぎがちな時、”綾小路きみまろ”の爆笑スーパーライブ「中高年に愛をこめて」 のカセットテープを聴いたり、お風呂に入った後、好きなビデオを見ながら、焼酎のお湯割りを楽しんだりする。 誰に気兼ねなしに大声で笑ったり、好きなことに熱中することでストレスが発散され、リラックス状態を創り出し、 気分転換してしまうのです
2004年12月14日
自愛の心に欠ける日本人?
街を歩けば、若い人たちは黙々と指を動かし、携帯メールに余念がない。
用があれば、相手がどこに居ようと、呼び出すことができる。好きな時に即刻情報を伝達し合う。
そんな時代だからこそ、デジタルではなく、アナログを象徴する「手紙」や「ハガキ」を大切にしたい。自分の気持ちを相手に伝えるは、
一字一字に心を込め、時には絵手紙にして、受取る相手の喜ぶ顔を想像して投函する。
毎月決まった何人かの人から、季節感たっぷりの絵手紙が届く。貰って嬉しく、印象に残る。差出人の真心が伝わってくる。ならば私もと、 下手な絵手紙の真似事をするようになった。即、相手に意志の伝達ができる便利な時代だからこそ、後々まで手元に残る、 手紙やハガキを大切にしたい。

【心と体の健康情報 - 174】
~幸せな人生を歩むために~
「慈愛の心に欠ける日本人?」
ノエビアで来春、またラスベガスへ行く話しが持ち上がっている。
アメリカへ旅行するのも、もう何回目になるでしょうか? そのたびに気になるのが、
日本と米国の人間関係における習慣や文化の違いです。
米国へ行くたびに、気づくことは、
(1)街を歩く老夫婦、
皆仲良く手をつないで歩いている。
(2)見知らぬ人と顔を合わせたとき、
にっこりと微笑んでくれる。挨拶してくれる。
(3)すれ違いざま、ちょっとふれただけでも、
必ずむこうからエクスキューズ・ミー
が条件反射で返ってくる。
(4)身体障害者には住みやすいよう、
社会が整備され、周りへの接し方が優しい。
今の日本人、見知らず人に対する「慈愛の心」が不足しているのではないでしょうか。
毎朝犬を散歩させていて、時折顔を合わす人に、すれ違いざまに「おはよう」と声をかけると、にっこりと「おはよう…」
と返事が返ってくる。ところが、向こうから声をかけてくることは滅多にない。すれ違うとき、お互いに意識をしているのに、
黙って通り過ぎてしまうことが多い。なんとなくスッキリしない。ちょっと声をかけてあげれば、直ぐに打ち解けて、
返事が返ってくるのに…。
日本では、街角ですれ違ったとき、肩がふれても無言のまま…。悪いと思っても、とっさに声が出ないのです。 逆ににらみ返されることもある。どちらが悪いというのではなくて、条件反射的に 「すみません」の一言が言えないのです。優しさが日本人に不足しているのではなく、 習慣がなくて声が出ないのです。
街で妻と手をつなぐのは「恥ずかしくてかっこ悪い」と思う。文化の違いと言ってしまえば、それまででしょうが、これ、
すれ違いざまに挨拶が交わせないのと同じではないでしょうか。慣れてしまえば何でもないことなのに…。
人の目が気になるのは自分だけ。意識過剰になるのも自分だけ。周りの人は他人のことなど無関心。気にも留めてくれません。
三週間ほど前、又も痛ましい幼児誘拐殺人事件があり、マスコミを騒がせている。
何と、「仕事と人生」の川人さんのご自宅がある町で起こった事件です。川人さん夫妻には二人の愛娘がいる。
内心穏やかざるものがあるでしょう。
お母さんが、我が子に「怖い人がいるから、外で知らない人に声をかけられても、無視して返事しないように」
と言うのが日本。
教会へ親子で出かけて、「知らない人にも、優しくしましょう」と教えられるのが西欧諸国。
日本人は心の優しい民族です。それなのに「慈愛の心」が不足して見えるのは、日常生活に宗教の結びつきが弱いからでしょうか。
米国では、住民の四割が毎週日曜礼拝に出かける。子供の頃からの習慣です。
米国社会では、教会に行かない人は信頼されません。「信心深い正しきアメリカ人」でなければ、
まともな地位につけないのも事実なのです。
余談ですが、大統領選でブッシュ氏が勝利した理由の一つに、信心深いブッシュ氏の姿がある。
これまで底流にあった米国市民のナマの価値観が一気に表出したことが勝因です。
ブッシュ氏は名門の出だが、若い頃酒におぼれたりして、家族の中では問題児だった。その後、宗教に目覚めて立ち直った。
そういった過去が、選挙民の宗教観、正義感をくすぐったのです。
(11/9 京都新聞 京都女子大 柏岡とみひで教授「米大統領選を聞く」 より)
牧師から「汝、隣人を愛せよ…」と言われて育った米国人と、宗教とは無縁の少年期を過ごし、 倫理観が希薄な日本人との違いが、なにげない日常生活の違いに現れてくるのでしょう…。
2004年12月07日
人間万事塞翁が馬
前にも話したが、私は高校二年の時病気になり、大学進学をあきらめた。しかし、大学へ行けなかった分、
それだけ早く実社会で商売のノウハウを身につけることができた。
三年後、将来でっかい商売やってやろうと、東京の会社に転職した。ところが、上京二日前になって病気の再発がわかり入院。
このまま死んでしまうかもしれない…。
いつ治るともしれない長期療養生活へ…。二度も、人生の夢・目標がハジけた。
ところが、長い入院生活のお陰で、古典や哲学書、経営書、囲碁や易学、簿記など、将来に備えた勉強をたっぷりする機会を得た。後に、 そのとき学んだことが生かされた。退院後も療養は続く。ブラブラしていてはダメだと、片町に店を持たせてもらった。そのお陰で、 マネージメントのイロハをじっくり学ぶことができた。
病気のお陰で妻とのご縁を頂き、二人の子供を授かった。その後、再就職した会社で、それまでの経験が買われ?
中間管理職のトップに抜擢された。やること為す事すべて順調。時代の流れが後押ししてくれた。
その後バブルがハジけて多くのものを失ったが、そこから又、新たな幸運を呼び込んだ。「禍福はあざなえる縄のごとし」。
何が幸運で何が不幸か、それは後になってみなければわからない。

【心と体の健康情報 - 173】
~幸せな人生を歩むために~
「人間万事塞翁が馬」
青島幸男が東京都知事のとき、「人間万事塞翁が馬」という中国のことわざが、
広く世間に知られるようになった。
「何が幸運で、何が不幸か、そんなものはわかるものか」という意味である。
昔、塞上の翁のオス馬が逃げてしまつたとき、隣人が「気の毒に! 馬が逃げてしまって…」と言ったところ、
「まあまあ…」とこの老人は悲しまなかった。
数ヶ月後に、この馬がすばらしいメス馬を連れて帰ってきた。今度は隣人が、「いなくなったと思っていた馬が、
いい馬を連れて帰ってきた。まあ、おめでたいことで…」と言うと、老人は少しも嬉しそうな顔をしなかった。
間もなく、子供がこのいい馬に乗って遊んでいたら、落ちて背中を打って、身体が不自由になってしまった。近所の人は 「お気の毒に…」と言ったが、今回も老人は悲しむ様子はなかった。
そうしたら間もなく、隣国との間で戦争が起こって、敵兵が来襲してきた。
国中の若者が徴兵されて防衛に努めたが、戦いが激しく、出兵兵士の十人中九人までが戦死してしまった。
しかし、この老人の子供は身体が不自由だったため徴兵を免れ、父母のもとで幸せに暮らすことができたという。
人の一生というものは、すべてかくの如きものである。「禍福はあざなえる縄のごとし」というように、
幸せと思っていたら不幸になり、不幸と思っていたら幸せつながったりするものである。
人生、良いときも悪い時もある。「逆境」は誰にでも訪れてくる。のがれることはできない。佐藤一斎もまた、言志四録の一つ
「言志晩録」の中でこう言っいる。
「人の一生には、順調の時もあれば、逆境のときもあり、幾度となくやってくるものである。自ら検するに、
順境といい逆境といい、なかなか定め難く、順境だと思えば逆境になり、逆境だと思えば順境になるといった具合である。
だから、順境にあっても怠りの気持ちを起こさずに、ただただ謹んで行動するより仕方がないのである」
今、どんなにどん底の状態で、将来が見えない状態にあっても、希望を失わないようにしていれば、
その内に幸運が訪れてくるようになる。ヤケにならずに、もう少し、もう少しと我慢して、
日々の努力を怠らないようにすることでしょう。
誰しも、ある程度歳を重ねれば、順境も逆境も一つに見て、喜びも憂いとなり、
憂いもいずれは喜びとなることを知るようになる。何ごとも超越して、生かされていることを楽しみ、
今を生きていることを安んじることができるようになるものです。
2004年11月30日
コントロール出来ないことを悩んでも仕方がない
私の言葉遊び、同じ文字を並べた「畳語」。今日は”なぞなぞ”をいくつか紹介します。
江戸川柳に、「同じ字を雨雨雨と雨るなり」
というのがある。
「同じ字をアメサメダレとグレるなり」と読みます。これは誰も答えられない。
雨の「あめ」、春雨の「さめ」、五月雨の「だれ」、時雨の「ぐれ」です。
作者は春、夏、冬の”季語”を順番に並べて、シャレたつもり。
■さてなぞなぞ。次の言葉どう読めばいいのでしょうか?
「私には解けない、無理!」と思ったら、解けるものも解けなくなってしまいますよ。
「すもももももももも ももももも ももももも色 色色色色色色色色色色あり」
「子子の子の子子子 子子の子の子子子」
「平仮名は海海海海海から」

【心と体の健康情報 - 172】
~幸せな人生を歩むために~
「コントロール出来ないことを悩んでも仕方がない?」
以下、(株)オリジンコーポレーション 杉井保之社長の講演からの抜粋です。
自らの感情をコントロールすることは、大変難しいことです。
自分の正しさを基準に物事を見つめ、こだわると、人を非難したり、腹を立てたり、見下したりしてしまいます。
悩み事の大半は、自分ではコントロールできないことをコントロールしようとして悩んでいる。
解決できないことを悩んでいる自分に、気づかなければならない。
その一方で、コントロールすれば、問題が解決するのに、何もしようとしていない自分にも、気づかなければならない。
家庭にあって、奥さんや我が子を、意のままにコントロールしようと思っても、無駄骨に終わるだけです。なのに、
他人の考え方や行動をコントロールしようとする。会社の売上を思い通りにコントロール出来るでしょうか?
それが出来る人がいるとしたら、そこで働く人達を自由にコントロールできる人でしょう。
年齢や時間は、コントロールできない。怒り心頭に達しても、松井選手のように、
自分の感情をコントロールできる人は少ないと思う。
自らコントロールできないことは、受け入れるしかない。ガンを宣告されたら、悩んでいてもどうにもならない。
受け入れるしかないのです。雨が降ったら傘を差すしかない。柔軟に、目の前の状況に合わせて、
最善の方法を選択をしなければならない。
コントロールできることも沢山あります。状況に合わせて、柔軟な姿勢で対応することです。
自分の行動に責任を持つことも大切です。
ところで、自分の性格を変えることができるでしょうか? 性格を変えるなんて不可能と思う人は、
一生性格は変わらないでしょう。変えようと本気で思えば、変わっていくものです。もの事の始めに、
どう思うかで決まってしまうのです。
信念を持ってもの事に当たるのはいい。しかし、信念を持った人をントロールしようとするのは不可能に近い。信念を持つとは、
裏返せば人の言うことを聞かない頑固者になることでもある。そして、その信念が正しければいい。
しかし、間違った信念であれば悲劇になる。オウム真理教が良い例である。
また、幹部社員を前にして、「来年の売上は今年の三倍」と提示したら、誰一人受け入れようとしないだろう。
信念などなくても、自らが持つ常識や経験が邪魔をする。今の時代、5%~10%アップなら常識。それでも大変です。しかし、
こういう常識の中にいる限り、今やっているヤリ方の範ちゅうでしか、もの事を考えようとしないだろう。
従来のヤリ方のまま、 ただ「頑張れ」と言うだけです。
ところで、三倍の売上を目指す以外に選択の道がないとしたら…。
「今までのやり方のままでは駄目だ」となる。根本からヤリ方を変えるしかないだろう。そこで、「やって出来ないことはない」
と思えば、可能性は広がっていく。
しかし、「不可能だ、出来ない」と思えば、それから先、一歩も前に進まないだろう。
■畳語の答え
・「李も桃、桃も桃、桃も百色十色あり」と読みます。
・「猫の子の子猫、獅子の子の子獅子」
・「アイウエオ」
海女の「ア」、海豚の「イ」、海胆(うに)の「ウ」、海老の「エ」、海髪(おごのり)の「オ」
2004年11月19日
おはようの挨拶は先手必勝
■二千円札
新札が発行されて早や一ヶ月。一足先に新札発行された二千円札、今年で四年になるが、相変わらずの不人気。
最近は滅多に見かけることがない。
嫌われる理由は、自販機の対応機が少ないことにあった。今回、新しいお札の発行に伴い、自販機が刷新されている。
二千円札対応機が増えれば、普及に弾みがつくのではないでしょうか。
以外なのは、二千円札の流通枚数。既に五千円札を抜いてしまっているという。
世界各国で最も流通しているのは「2」の単位の紙幣。使い勝手が良いので、今後普及していくでしょう。それと、”五万円札”
があるといいなと思うのは、私だけでしょうか。

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第57号】
~幸せな人生を歩むために~
「おはようの挨拶は先手必勝」
滋賀ダイハツ販売グループのオーナー”後藤昌幸”氏は、破産状態の会社を再建した後、三十年以上の長きに渡って、
滋賀県下販売台数一位の座を維持してきたことで有名です。日本広しといえども、
ダイハツのディーラーがトヨタより販売台数が上回るというのは、他に例をみません。
以下、後藤氏が「仕事のコツ、人生のコツ」と題して語った中からの抜粋です。
|
会社を、同じ理念と思想を持った人間の集団にしていくには、 社長自身がまずしっかりしないといけない。社員は社長の背中を見ている。 だらしない背中を見せていたら、社内にいつの間にかだらしないムードが漂ってしまう。それとは逆に、 上に立つ人に気構えさえあれば、会社は勝手に良くなっていくものです。 私が経営者の皆さんにアドバイスしたいのは、朝、
誰よりも早く出社することです。早く出て、
出社してくる社員さんに「おはよう」と声をかけて、迎え入れる姿勢は、非常に大事だと思うのです。
|
社員さんも同じではないでしょうか。誰よりも早く出社して、後から出社してくる社員さんや、上司に向かって、
元気よく「お早うございます」と声をかければ、良い印象で見られること受け合いです。きっと、
良いポジションの仕事が回ってくるでしょう。
上司で一番よくあるケースは、自分は偉いと思っているわけではないが、朝は一番遅くに出社してデスクに着き、
すれ違う社員さんの「おはようございます」の挨拶を心地よく受ける。また、夕刻社員さんが仕事を終えて退社するとき、
「お先に失礼します」と言ってくれているのに、デスクの資料に目を通したまま、相手も見ずに「お疲れさん」
と言ってしまう。
これでは、本当にお疲れさんという「心」が社員さんに伝わりません。必ず社員さんの方を向いて、
笑顔できちんと目線を合わせ、心から「お疲れさまでした」と言って送り出すことです。
こんなことを書いている私も、まだまだ努力が足らないようです…。
2004年11月16日
ありがとうが言えますか
相手の立場に立って、相手の視点で自分を見つめてみることの大切さを、某医院の先生が語っています。 (倫理研究所”田形健一”氏の講演より)
私は、毎年秋の紅葉時、妻を伴って京都へ一泊旅行をする。日頃の妻のご苦労に感謝するためですが、実は、京都四条の” 日航プリンセス京都ホテル”の会員になると、誕生月の宿泊料金が、年齢分だけ割引(63%引き)になる特典を利用することにある。
今回の目的は、この秋一般特別開帳された、天龍寺の法堂天井に描かれた「雲龍図」を見ること。
法堂の天井中央、直径九mの円相の中に躍動するみごとな龍。驚いたのは、法堂の中、左の端へ行っても、右端から見上げても、
龍がぎょろりとした目でこちらを向き、見下ろしていることです。顔の大きさ・形までが変わって見える。
驚き、感動して、堂内を飽きもせずぐるぐる歩き回って、見上げていました。
右の絵がそうですが、目は兎、鼻はラクダ、角は鹿、手は虎、爪は鷹、鱗は鯉、お腹はハマグリを表している。

【心と体の健康情報 - 171】
~幸せな人生を歩むために~
「ありがとうが言えますか?」
”ありがとう”と”感謝”
の二つを忘れずに、笑顔を絶やさず、思いやりある言動をしていれば、
何事もうまくいくようになります。感謝の心は「ありがとう」
の言葉になって表れてきます。
「ありがとう」、この何でもない一言、いざとなると声になりません。何故か難しいのです。「ハイ!」と言うのと同様、
「恥ずかしい」という思いを取り去らない限り、度胸のいることなのです。
以下、倫理研究所”田形健一”氏の講演の続き。ある社長さんの体験談です。
家庭も会社も今一つうまくいっていない社長さんが、ある研修を受講した。その研修で、結婚してこの方、妻に 「ありがとう」と言ったことがない自分に気づいたのです。妻に小言は言うけれど、「ありがとう」は言ったことがない。
「そんな改まって言わなくても、妻は分かっているから…」と思っていた自分。
いつも夫の健康を気遣い、身の回りの世話をし、祖父母の面倒を見、子供たちのことを、毎日の食事・洗濯…。それを、
当たり前のことのように思い、見過ごしてきた自分。
思っているだけではダメ。勇気を出して「ありがとう」と、妻に言ってあげることです。社長さんは、
今日こそはと意を決して家に帰り、妻を前に座らせた。
「あなた、何なの?」、いぶかしげな妻を前にして、恥ずかしさと緊張のあまり、声が出なかったという。
無言で妻の前に手を付き、頭を下げた。
何故か涙が溢れてきた。察知した妻も、涙ぐんで分かってくれたという。
「ありがとう」が言えるようになると、「お早うございます」も言えるようになる。
今までは、社員さんから「お早うございます」と言われたら、「お早う」と応えるだけだった社長さん。
今は、社長から率先して「お早う」ではなく、「お早うございます」と、社員の方を向いて、大きな声で頭を下げ、
きちんと言えるようになった。
社長の突然の変身に社員は戸惑い、いつまで続くだろうかと、噂したりした。
「自分が変わらなければ、会社は変わらない」。この社長さんの決意が、恥ずかしさを超えた行為となった。これも、
やり始めが大変です。
社長も社員も慣れてくるに従い、ごく自然に、日常事として受け入れるようになった。一年後、たった一つのこの挨拶で、
会社の社風が変わり、業績が良くなっていったという。
どうか世の奥様方、ご主人から「ありがとう」の言葉がなくても、勇気を出して、ご主人より先に「ありがとう」
と言ってあげてください。夫は感動して「私こそ、ありがとう」と、返事が返ってくるでしょう。
家族に「ありがとう」がこだまする。素敵な夫婦、素敵な家族に「ありがとう」。
2004年11月12日
好きなように生きる
福井県の海岸沿いに、巨大越前クラゲが異常発生している。5~6年前から増え始め、 一昨年ごろから漁業に大きく影響するようになったという。
直径1m50cmくらい。重量がお相撲さんほどあって、地引網を引き揚げると、クラゲでいっぱい。漁獲量は減るは、
重すぎて網が破れるは、散々だそうです。
原因はいろいろあるようだが、魚の取り過ぎで、海の生態系のバランスが壊れ、クラゲの餌となるプランクトンが豊富になったことと、
水温の上昇で、繁殖が盛んになったことが挙げられる。
昨年秋、越前でスキューバーダイビングした時、1kほど沖から岸に向かって泳いでいたら、突然巨大クラゲに遭遇して、
心臓が飛び出すほど驚いた。
今年の五月には、太平洋の真ん中のスキューバー・スポット”パラオ”に行ったが、世界一美しいと言われてきた沖縄の珊瑚礁が、
水温の上昇と開発による土砂の流入で、75%が消滅してしまった。熱帯魚も回遊魚もいない海になってしまったのです。
温暖化が、大型台風の異常発生を生んだように、私達の目に見えるところにまで、地球破壊が進んできているのです。

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第55号】
~幸せな人生を歩むために~
「好きなように生きる」
人生、好きなことをして、楽しく暮らしたいものです。
少子高齢化が急速に進む日本。十年後、二十年後の私達の生活環境は、想像を超える厳しいものになりそうです。そこで、
重税、物価高、低福祉と、先行きの
あまり明るくない日本を脱出して、海外で暮らす人が増えてきました。
今日は、ニュージーランドの地で、自らの天職を生かし、楽しく暮らしている、二つの事例を紹介します。
■船越康弘さんの場合
勉強が出来ず、
運動能力もなく、虚弱体質で何の取り得もない平凡な青年(本人の弁)が、二十歳の時に「穀物採食」
を唱える桜川先生と出会い、「玄米食」の素晴らしさを知った。
先生は「食べものが変われば、運命が変わる」と言った。 そして更に、
「人生思った通りになる」「やりたいことがあったら、とことんやり抜くことだ。
堪能するまでやりたいことをやって、自由に愉快に楽しい人生を送り、自分と縁ある人達を喜ばせなさい」
と言った。
桜井先生との出会いが、生きる自信が持てなかった船越康弘さんに、天職をもたらした。その後、
自ら信ずる自然食を広く提供しようと、岡山県で民宿「百姓屋敷わら」を開業した。
15年後更に”食を通して、本当の豊かさと人生を楽しんで生きよう”と、ニュージーランドに新天地を求めて渡り、
永住権を取得した。自然食の普及に、日本とニュージーランドを忙しく行き来しながら、大自然の中で楽しく暮らしている。
「面白がって生きていると、面白がって生きている人が寄ってくる」とは、船越さんの言葉。
■同じく、ニュージンランドで第二の人生を送っている、
久保夫妻の場合
大手コンピューター会社に勤務していた久保さん。
生活のリズム全てが会社中心で、家族と一緒に食事を共にすることが出来ないくらい、仕事に追われた毎日。
たまたま旅行で、ニュージンランドへ出かけたことが、それまでの人生観を変えてしまった。生き方を変え、
家族との係わり方を変えようと決心したのです。
生き方を変えるなら、全てゼロから始めてみたいと考え、オーストラリアのメルボルンに家族で渡航し、
短期の生活体験からスタートしてみた。その短い間、とてもリラツクスすることができ、「ここだ、ここがいい!」
とひらめいたという。
日本に帰国後、早速東京のニュージーランド大使館に永住権の申請をすると、とんとん拍子にことが進み、
わずか二週間で永住権を取得した。
それから12年、幾つかの事業を立ち上げ、事業家として成功した。中でも”ライスボックス”という、
丼ものや寿司などの”ご飯もの”を中心としたファーストフードのお店が、地元に大うけしたのです。
今、久保さんは、7年間手塩にかけたライスボックスと自宅を売り払って、6ヘクタールの土地を購入し、
新たにオーガニック農法(無農薬自然農法)の新事業に取り組み始めた。
外国で暮らすためには、言葉の障害を乗り越えなければならない。誰でも申請すれば永住権が取れるわけではない。
久保氏の場合は、英語が話せたことと、コンピューターの技術が移住地で生かせるため、新天地での生活に問題がない上、
受け入れ国にとっても有用な人材だったことが上げられます。
一方の船越氏は、英語が全く話せない。永住権を取るために、半年近く大使館通いをしなければならなかった。 「自然食」の普及に並々ならぬ情熱を持っていたことが、認められた理由です。
ハワイでも三ヶ月間のプチ体験移住が認められている。現地で実際に生活してみれば、土地・建物の不動産価格、
一ヶ月の生活費や、子供の学費、働き口の有無などが分かります。
滞在三ヶ月間に、英会話教室に入るのもいい。ハワイがいいのは、お米やお魚など、
日本食の食材全てが近くの食品スーパーで手に入ることです。
久保さん夫婦のように、「ここがいい!」と思ったら、それからじっくり計画を進めればいいのです。あなたも、 日本脱出を考えてみませんか? マリンスポーツが年中楽しめるハワイ。条件さえ揃えば、 今すぐにでも移住したいと思っている私です。
2004年11月09日
心の持ちようで幸せになれる
相手の立場に立って、相手の視点で自分を見つめてみることの大切さを、某医院の先生が語っています。 (倫理研究所”田形健一”氏の講演より)
|
私は、真夜中にかかって来る電話に出るときは、自分の声のトーンに事のほか気を使います。掛けてきた相手は、
深夜に私の病院に電話をせざるを得ない、 寝ている私を起すことへの申し訳なさを、おそらく十分に感じながら、それでも思い切ってダイヤルしたのでしょうから、
私は出来るだけさりげなく、そして昼間と変わらぬ明るい声とハリで、「つい先ほどまで、原稿を書いていたところです。
横になったままで話せば、誰でも声がくぐもってしまいますから、電話の相手が気の毒がってしまわないように、
私は起き上がってから、電話を取るようにしています。 |

【心と体の健康情報 - 170】
~幸せな人生を歩むために~
「心の持ちようで幸せになれる」
その時々の世相を反映した、サラリーマン川柳から一句。
「子供ボケもん、俺のけもん、仕事なし、早く帰るも鍵はなし」
「誕生日、急いで帰ればみんな留守」 「父帰る、娘出かける、母寝てる」
以下、倫理研究所”田形健一”氏の講演からの抜粋です。
私達が住む日本、科学文化が発達して、私達の生活は大変便利で豊かになった。
その反面、人と人とのふれ合い、係わり合いは、だんだん希薄になってきている。
家族が一つ屋根の下に住んでいながら、お互いの心が見えない。みんな自分本位
で、バラバラという家庭が増えている。
命を生み、育てる場であるはずの家庭が、ぐらつき、おかしくなってきている。
反対に、虐待、無関心、しつけ放棄の家庭が増えてきている。いまや、家庭が崩壊の危機に直面している。だからこそ、
改めて自らの家庭を見つめ直し、自分自身を見つめ直す必要があるようです。
そのポイントは、まず「自分が変わる」ことでしょう。「人を変えよう、 相手を変えよう」と思っている間は、絶対うまくいきません。自分自身の間違いに気づき、自分を改め、 自分が変わっていったときに、自らの家庭も変わっていくのです。
私(吉村)がそのことに気づいたのは今から十年前。ある研修を三日間受けたことがきっかけです。研修から帰って直ぐ、
妻に「お母さんありがとう」と素直に言えたことが最初でした。その後も折にふれ研修を受け、自分を変えようと努力した。
妻から「あなた、変わったわね…」と言われたのは、四・五年も後のことです。
我が家を見つめてみて、「自分は今何を為すべきか、自分はどうあればいいのか」
と、考えてみることです。夫として、子供たちの父親として、客観的に見つめてみることです。
ところで、子供たちが健やかに育つ家庭とは、どんな家庭でしょうか?
何よりも
「家庭は明るくなければならない」。親子の会話があり、
笑いが飛び交う家庭でありたいものです。幸せな家庭だから朗らかなのではなく、朗らかだから幸福な家庭になるのです。
(前号でもお伝えしました)
明るい家庭を築くための最も有効な方法は、「形から変えていく」ことです。
目に見えない心の状態が、様々な形となつて表れる。言葉遣い、表情、しぐさなどを変えることによって、心が変わっていく。
背筋を伸ばしてにっこり笑う、声を大きくして明るい話題を提供する、上を向く、元気良く歩く、というように形を変えていく。
形を変えると心が変わっていく。
何かあれば笑う、笑いが笑いを誘い、家中明るくなる。笑いは全てを幸せにする。
2004年11月05日
次第に住みにくくなる日本
今回の大地震の震源地長岡で、忘れてならない人物に”小林寅三郎”がいる。
平成十三年五月七日、小泉首相就任所信表明演説で、「米百俵の精神」を引き合いに出した。そして、
長岡藩の逸話が広く国民に知られるようになった。
頃は明治三年、明治維新の際、新政府側につかず、独自の立場を貫いた長岡藩は、戊辰戦争で官軍に町を焼かれ、
石高も七万四千石から、二万四千石に削減され、窮状にあえいだ。それを見かねた支藩の三根山藩が、見舞いとして届けたのが”
米百俵”だった。
長岡藩の大参事(旧家老)の小林寅三郎は、米を藩士に分けず、百俵を元手に学校を作ることを主張した。
窮状にあえぐ藩士らは猛反発し、米を寄こせと詰め寄った。
大激論の末、小林はこう説き伏せた。
「百表の米を分けたところとて、何日ひもじい思いをしのげるだろうか。食べてしまえばそれまでで、
いつまでたっても本当に食えるようにはならない。この米で学校を建て、人材を養成するのが、迂遠だが一番の近道だろう。今、
百俵の米が、その時には千俵にも万俵にもなるだろう」と…。
後の長岡中学で、山元五十六や小野塚喜平次・東大総長らの逸材を多数輩出した。目先の売上に囚われているだけでは、 いつまでたっても会社は変わらないだろう。三年後、五年後のための人材育成が大事なのです。

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第54号】
~幸せな人生を歩むために~
「次第に住みにくくなる日本」
一ケ月ほど前の新聞に、富山県の人口が十年後に百万人を切ると、大きく報道していた。石川県も同様である。
日本の人口は減少していく。政府の予測では、現在一億二千万人余の人口は、毎年0.95%ずつ減少して、
2050年には九千万人に、2100年には現在の半分の六千万人になってしまうという。
人口が減少するのは、子供を生まなくなったからだ。必然的に人口の高齢化が進み、
社会のヒズミとなって重く圧しかかってくる。人口に占める六十五歳以上の比率は、2000年は18%。
国民はそれを重く感じているというのに、2050年には今の二倍の35%にもなる。
人口の減少は、国の経済活力の低下につながり、国の税収入も減少していく。
現在の年金水準を維持しようとしたら、保険料の掛け金を倍にしなければならない。企業も個人も、
このコスト増に耐えられるはずがない。
今でさえ、年金の将来に期待が持てないと、国民の半数近くが保険料を払おうとしないのに…、
どう解決していくのだろうか。
つい先日の新聞でも、消費税を今直ぐ、毎年1%づつ上積みしていって、出来るだけ早く15% にまで持っていかないと、国の財政は持たないと警告している。
しかし、政府が消費税アップを掲げると、国民はそっぽを向いてしまう。だから小泉首相は、
自分の任期中は値上げしないと言っている。小泉さんの後を引き継いだ人が、
最初にやらなければならないことは財政の健全化。消費税の値上
げを断行せざるを得ない。
自民党政権は、国民の首に消費税15%の鈴を付けることが出来るのだろうか。
民主党が政権を取ったら、即実行できるかというと、疑問だろう。
目先の利益と、自己保身に汲々としている国会議員に、百年先の日本を見すえた政治を望むべくもない。
小泉政権は発足当初、国の借金を30兆円以内に抑えると公言していた。それが、
このわずか三年間に160兆円も借金を膨らませてしまった。
最近親しくしている人に、「そろそろ日本脱出する時が来た。生活の基盤をハワイか、
ニュージンランドに移した方がいいかも知れないね…」と、無責任なことを言っている私です。
知り合いの某社長さん。三十年ほど前、北陸の風土に惚れて、工場を東京から石川県に移転し、
家族全員金沢に移り住んだ。そのとき、私の顧客になり、私が図面を引き、お世話をして建てた家に住んでいる。
その社長さん、二十年ほど前、ハワイに住居を構え、会社を息子さんに譲って、生活の拠点をハワイに移してしまった。
今は八十歳近く、老夫婦仲良くハワイで暮らしている。日本が恋しくなると、時々里帰りのように、
息子や娘夫婦がいる金沢に帰って来る。
2004年11月02日
悩み解消法
NHK朝の連続ドラマ”わかば”を見ていて、主人公”わかば”のいつも絶やさぬ笑顔が印象に残る。
男の仕事場、庭師の見習いに入って、怒鳴られる毎日。
どんなに辛い仕事を言いつけられても、叱られている時でも、絶やさぬ笑顔。
同じ見習いの男の子が、「どうしてそんなに笑顔でいられるの?」と、不思議そうに尋ねた。
”わかば”は、「だって、好きでやっている仕事じゃない! どんな時でも笑顔でいたら楽しくなるじゃない…」
昨日、月曜日、ドラマの中で”わかば”が言った台詞です

【心と体の健康情報 - 169】
~幸せな人生を歩むために~
「悩み解消法」
「幸せな人生を歩むにはどうすればいいか?」。特別難しいことを考えなくてもいい。
今までお伝えしてきたように、”ありがとう”と”感謝”の二つを忘れずに、笑顔を絶やさず、
思いやりある言動をしていれば、何事もうまくいくようになる。
後は「ツイてる、ツイてる」と言っていればいいのです。
悩み事なしに生きている人はいないだろう。皆、あれこれいろんな悩みを抱えて暮らしている。
ところで、この文章を読んでいるあなたは、3年前の11月2日にどんな悩みを抱えていたか、覚えているでしょうか?
一年前のことなら覚えているでしょうか? 覚えている人はまずいないと思う。
今悩んでいることも、一年後には忘れてしまっている。「どんな悩みも、時が解決してくれる」
。悩みそのものは解決していないのですが、勝手に消えてしまうのです。
そもそも”悩み”とは、どうにもならないから悩むのです。どうにかなることは、解決してしまっているので、
悩みにはならないのです。
どうにもならなくて悩んでいても、時間が解決してくれます。何事もなかったかのように、忘れさせてくれます。
どんな悩みでも、「私はツイてる」と言って明るく、のん気に構えていれば、一週間経ち、一ヶ月もすれば、
悩みが悩みでなくなってしまうのです。
以下、福井県の(株)ライズ”樋田信雄”社長の講演からの抜粋です。樋田氏は現在、福井県商業界同友会の会長です。 日創研では、MKタクシーなどと共に、ビデオ(DOIT)学習の全国優良モデル企業の一つに取り上げられています。
|
「問題や悩みがあるということは、私に解決する力があるから与えられた」ということです。 「目の前に現われる問題は、自然の法則に沿ってやれば、どんな問題も解決できる」と教わりました。 「私に解決できない問題は、決して私に降りかかったりはしない」と…。 ”自然の法則”とは何かというと、
それは さて、明るくなる言葉の一番は、「はい!」 の一言ではないでしょうか。上に立つ人から率先して 「はい!」と言えば、周りは明るくなります。社長さんが部下から声を掛けられたとき、「はい!」 と元気よく返事ができるでしょうか?社内に「はい!」が行き交うほど、活気が出てきます。 次に明るくなる言葉は、「ありがとうございます」
を言うことです。なにかにつけて、「ハイ!」と
「ありがとうございます」が行き交う職場にすることです。 |
ある組織の例会の場では、名前を呼ばれると「はい」と、元気良く大きな返事ができる。ところが、その私が、そんな慣習のない余所の集まりで、同じように名前を呼ばれると、声が出ない。大きな声で「はい」という、この何でもない行為、いつでもどこでも実行するとなると、何故か難しいのです。
心理学から見ると、集団の中でただ一人、人と違った行為をすることは、「恥ずかしい」という思いを取り去らない限り、度胸のいることなのです。
だから、ふだん挨拶を交わす習慣がない家庭や職場では、基礎から訓練してかからなければ、声が出ないのです。
2004年10月26日
人間幸せになるたちめに生まれてきた
あるベテランの経営コンサルタントの話。
先生はこの十年の間に、約三千組、一万人近い中小企業の経営相談にのってきた。相談者にお会いしているうちに、倒産寸前の経営不振から
「復活できる人」と、「復活できない人」の区別ができるようになったという。
その、気になる復活できる人とは、「性格が明るく、人柄がよく、気配りがきき、周りを明るくし、人を幸せにできる人」
だそうです。つまり、明るい性格が身を助けるのです。
こういった性格の人が、懸命に会社を立て直そうと努力していると、必ず助けてくれる人が現れます。商品を買ってくれたり、
取引先を紹介してくれたり、金銭面以外で支援してくれるのです。
日頃から、巾広い友人を持ち、視野を広め、同業者仲間や取引先、社員さんを大切にすることです。そして、信用と人脈、
技術を蓄積しておくことです。それが、いざという時に役立つのです。
只、過去を振り返ると、”人当たりが良く、人が良い”性格が、倒産の要因と思われるのです。

【心と体の健康情報 - 168】
~幸せな人生を歩むために~
「人間幸せになるために生まれてきた」
以下、妖怪漫画の”水木しげる”氏が、10/5読売新聞連載「時代の証言者」で、 「幸せになるとは?」について語っている。
| 小学校のころ、私は鉄棒が得意だつた。大車輪ができる子供は、 数えるほどしかいなかったから、周りから超人みたいに思われた。おだてられるから、人の何倍も練習する。 好きなことなら相当なことができるわけです。逆に嫌いなことは、怠け者にならんといかん。 人生幸せをつかむためには、1番大切なことなのです。 |
「我が子を少しでも良い大学に入れて、少しでも大きな会社に就職させれば、
幸せな人生が約束される」と、世のお母さん方誰もが信じて疑わない。しかし、現実はどうなんだろう?
私は28歳から38歳までの十年間、サラリーマン生活を送った。勤めた会社は、
住宅建設業界ナンバーワンの一部上場企業の子会社。一流大学を出た優秀な人材で溢れている。
並みの成績では出世競争に勝てない。同僚との競争に打ち克たなければならない。成績が悪ければ、置いていかれる。
管理職の辞令をもらい、チャンスが与えられる。業績を上げ、期待に応えようと頑張り、
仕事漬けの毎日が続く。そうやって役職の椅子を手に入れ、様になっていく。
与えられた職責を果たし、業績が上がれば上がるほど、仕事に追われる毎日。
朝七時に家を出て、帰宅は毎夜十時。十年間、有給休暇を取ることもなく、休日も同僚との付き合いで家にいることはマレ。
家庭を顧みる暇もなく、365日仕事漬けの会社人間の日々だった。
どんなに業績を上げても、翌年はそれを上回る目標数字が待っている。 キリのない仕事漬け人生。そんな人生、何が幸せだろうか?
プロ野球の監督のように、業績が振るわなければ降格され、窓際に追いやられ、出世の道が閉ざされてしまう。
そんな社員を横目に見て、頑張らざるを得ない。
人材豊富な大企業。代わりの人材はいくらでもいる。管理職で居続けるためには、定年まで身を粉にして頑張り抜く覚悟がいる。
「もっと気楽に楽しく、自由きままに生きたい」との思いが強くなり、家族との生活を考えるようになって、
脱サラを決意した。そして妻と二人で化粧品の商売を始めた。
当時は、「ひたすら会社を大きくすることが成功への道」と信じて疑わなかった。
売上額と従業員数で、社会的評価が決まる。事業規模が大きければ立派な経営者。小人数でやっている会社が、
社会から低く見られるのは仕方がない。
右肩上がりの時代。誰もが会社を大きくし、社会的評価を高めようと努力した。
そうすることが、豊かさと幸せにつながり、成功への道と信じて疑わない。
ところが突然のバブル崩壊。バブルの勢いに乗って大きく成長し、社会的評価を手にした企業が、
急激な不況と環境の変化に対応しきれず、バタバタつぶれていった。
夜逃げをした家族もいる。借金の取りたてから逃れるため、離婚した夫婦もいる。
成功を夢見た積極経営のあげくの、あまりにも痛ましく悲惨な姿。友人・知人としてお付き合いしていた人も多く、哀れである。
水木しげる氏の「幸せになるとは?」の続き…
|
サラリーマンも企業経営者も、その大半は幸福になる努力が足りない。まず匂いをかいで、 幸せの方向をちゃんとつかんでから、階段を上がるようにしないといかんです。 幸せにつながらない階段を上がっちゃ駄目ですよ。私達の周りには、 幸福のためには全く役に立たないことをやって、疑問に感じない人が沢山いる。 昔と違って、今が一番幸福になれる時代。「何をつかんで幸せになるか」ということですよ…。 あたふたしているうちに、一生が終わるという感じでしょう。 パプアニューギニア・ラバウルのトライ族なんか、家に包丁が一本あるだけです。 |
幸せになるためにこの世に生まれてきたのだから…、しっかり考えなければならない。
自分にぴったりの幸せの道とは何なのかを、見つけ出さなければならない。
自分にとっての「天職」とは、何なんだろうか?
2004年10月12日
落合監督”オレ流”から学ぶ-2
西部がプレーオフの接戦を制してリーグ優勝した。130試合の長いペナントレースを制したダイエー、
わずか一試合で全てが泡となった。このメジャー方式、イマイチしっくりしない。
ところで、王や落合の練習量の多さは伝説となっている。一郎も例外ではない。
体調管理、道具類のチェック…、人の三倍はコンディションづくりに費やしているという。
一郎は、昨年より一時間も早く球場入り。本拠での試合なら、五時間も前に動き始める。入念なマツサージやストレッチ体操に約一時間。
この積み重ねが、今期大記録達成の大きな要因になっている。
ベーブルース以降ずっと、本塁打の一発の魅力がメジャーの主流であった。
大記録を達成したイチローは、野球の本当の面白さを教えてくれている。

【心と体の健康情報 - 166】
~幸せな人生を歩むために~
「落合監督の”オレ流”から学ぶ(2)」
落合監督は、就任一年目でリーグ優勝した。何が優勝への原動力になったのか。
前号に続いて、マスコミのニュースから、そのヒントを探ってみた。
昨年十月、監督に就任したとき、選手を前にしての言葉。
「私は、三拍子そろった選手を作ろうと思っていません。来春のキャンプ開始までに、皆さん一人ひとりが、
人に負けないものを一つ、目標にしてきてください」
「今レギュラーであっても、ウカウカしていられません。来春のキャンプは厳しい…。皆さんに泣いてもらいます…」
二月、選手一人ひとりの能力を自分の目で確かめるため、キャンプ初日から「紅白戦」をやった。一軍・
二軍の区別をせず、同じスタートラインに立たせ、70人全員一緒になって練習し、競い合わせた。
教えて育てるのではなく、ベテランや急成長している選手の練習を見習わせ、学ばせるようにした。
伸び悩んでいる選手には、何度となく「一芸を磨け」と言って励ました。
監督に自分の力が認められれば、誰でもレギュラーになれる。選手たちの闘争心に火が付いた。 自分のライバルは同じチームの練習仲間。徐々に選手の自主性が引き出され、強い球団になっていった。
【 落合監督が目指すチーム作り、三つの鍵 】
●第一の鍵…目標はっきり
(1)日本一になる
・リーグ優勝ではなく、日本シリーズに勝って日本一になる
(2)選手全員10%のレベルアップ
・「長所進展法」…欠点を直すのではなく、徹底して長所を伸ばしていく。
●第二の鍵…自ら成長せよ
・レベルアップするには、
一人ひとりが、自ら何をしなければならないかを
考える。
今までのように、コーチに言われてやるのではなく、自分で考えよ!
●第三の鍵…コーチも変われ
・コーチは教えることが仕事、
しかし我慢しなさい。選手一人ひとりをしっかり
観察することです。そうすれば、選手が悩んでアドバイスを求めてきた時、
的確な指導ができます。
落合はコーチスタッフに尋ねた。「貴方は、百人の選手を預かったとしたら何人育てられますか?」。十人とか、
三十人とか、答えが帰ってきた。
監督は言った。「百人の中で一人育てることができれば、立派な指導者です」それほど、人にモノを教えることは、
難しいことなのです。
監督も我慢した。五月は主力を怪我で欠いたり、チームの調子が出なかったりして、最下位になった。
そんな時でもじっと我慢して、今一つ力を出せない選手を使い続けた。そして耳元で「お前は絶対変えないぞ」とささやき、
選手を信頼した。
選手たちは、監督の信頼に応えようと毎日頑張った。実戦を重ねるうちに徐々に力がつき、育っていった。いつしか自信となり、
自らの力を信じるチームになっていった。
落合監督には「オレ流」の、自分勝手で我がままなイメージが一人歩きしている。
実際、監督に接してみると、「言葉」の使い方をすごく大事にしていることに気づく。
監督のひと言が、マスコミから歪曲して選手に伝わることが多い。慎重すぎるほど言葉を選ぶ。監督のひと声が、
多くの選手のヤル気を引き出し、エネルギーを与えた。
2004年10月05日
落合監督”オレ流”から学ぶ
イチローが八十年間破られなかった大リーグ記録を更新して、日本もアメリカも大騒ぎ。
松井は本塁打を31本打ち、ヤンキース四番の重責をこなして地区優勝に貢献した。
王や長嶋、松井、イチローが一流と言われる所以は、ここ一番という時に打てる選手だからでしょう。九回二アウト満塁、一打逆転という場面で、
自分とチームのことしか考えていない選手は、何とか打とうと力みが入ってしまう。
長嶋、イチローなどの一流選手は、「スタンドのお客様に喜んでもらおう」との思いで打つから、
力みがない。で、ここ一番という時、期待に応えてくれるのです。
新記録を達成した日のイチローの言葉です。(10/3読売新聞)
「これだけ負けたチームにいながら、こんな素晴らしい環境の中で野球をやれることは、勝つだけが目的の選手だったら、不可能だと思う。
プロとして何を見せなくてはいけないか、何をしたいかということを、忘れてはいけない…」

【心と体の健康情報 - 165】
~幸せな人生を歩むために~
「落合監督の”オレ流”から学ぶ」
私はアンチ巨人の中日ファン。愛知出身のイチロー選手の快挙と合わせて、
この数日は最高にいい気分です。
三冠王を三度達成した大打者落合。”オレ流”の孤高を貫いた現役時代の印象が強すぎて、中日からラブコールがあるまで、
コーチの経験もない。ところが、監督就任一年目でリーグ優勝。みごとなチームに育て上げた。そのリーダーとしての手腕は、
学ぶところがあまりにも多い。
何が優勝への原動力になったのか、新聞に書かれている記事から、垣間見たいと思います。
「過去の監督を手本にしたりせず、独自のものを作りあげていく」。
これは昨年監督就任の時に言い切った言葉。イトーヨーカ堂の鈴木名誉会長の言葉を思い出す。「過去を断て、
常識に囚われるな、今こそ新たなる創業の時、人心をつかみ、経営を革新せよ」。
この言葉のように、これまでの監督とは異なる様々なアイデアにあふれていた。
就任早々、フロントからの選手補強の申し出を断り、現有選手の力で十分優勝可能と言い切った。
まず選手を見る時、先入観を持たないようにした。春季キャンプでは一、二軍の枠を撤廃。全員一つになって練習。「一、
二軍の振り分けは前任者が引いたもの。自分で見なきゃどういう選手かわからない」。
70人の支配下選手のうち、実に56人を一軍で起用し、戦力にしている。
落合監督が掲げたのは「一点を奪い、投手を中心に、その一点を守り切る野球」。
今期中日が放ったホームラン数は、巨人の半分にも満たない。限られたチャンスを生かし、全員で守り勝つ野球に徹した。
優勝決定時の監督胴上げには、一・二軍の選手70人全員が参加して喜びを分かち合ったのが、それを象徴している。
球界の常識を覆す選手起用も特徴の一つだ。4月20日の阪神戦では、右打者のアリアスに対して、左投手の久本を送り、
「左打者に左投手とかいう時代は終わった」と断言。
選手の相性などのデーター、当日の調子など、様々な要素も加味するが、それが「相手を考えさせ、惑わせる。
それだけで勝ちなんだ」と…。
星野監督とはまったく正反対で、決して感情的にならない。その姿は、「失敗してベンチに帰る時のことを考えずに、 プレーに集中できる」と、選手から歓迎された。
敗れた試合の後のインタビューでは、敗因となった選手を責めずに、自ら責任を背負い込む。勝った試合後の会見では、
「選手のお陰、こっちは何もしていない」。
選手を交代させる時は、必ず監督自身がマウンドに向かい、ねぎらう。
考え方の基本は「選手第一主義」。起用した以上、選手を信じ、 力を最大限に出させる。「監督は自分たちのことを守ってくれる」と、監督の気配りが選手たちの心をつかみ、 求心力を高めていった。
今までマイナス査定の対象とされた、併殺打や盗塁の失敗は、チームの意図した結果であれば、 その積極性を評価してもらえる。中日の各打者は、併殺打を怖がらず、思い切り良くバットを振るようになった。
2004年09月28日
長所進展法
魁皇が優勝して秋場所が終わった。我が郷土の栃洋、出島の活躍も素晴らしかった。
ところで相撲の歴史については、意外と知ら ないことが多い。
土俵の中で相撲を取るようになったのは、江戸時代の後半になってから。初期の土俵には、四角のものもあったというから驚きです。
明治になって円形が主流となった。
土俵が出来る以前は、モンゴル相撲のように、グルグル回って取り組んでいたという。土俵が登場して、相撲の技が多彩になった。投げ、
ひねりなどの倒す技よりも、押しや寄りといった、土俵の外へ出す技が主流となった。
押し相撲はスタートダッシュで決まる。そこで、次第に手を下ろすようになり、現在の取り口になった。
昭和三年、ラジオ放送が始まると、放送時間内に取り組みを終わらさなければならない。
それまで無制限だった仕切り時間が、制限されるようになった。
更に、仕切り間隔が70センチになったのは、昭和45年夏場所からというから、意外と新しい。
伝統に固執せず、相撲に次々と新しい様式を取り入れ、良いところを伸ばすようにしてきたたことが、勝負のスピードアップにつながり、
国民的人気スポーツになったのです。
9/9読売新聞から

【心と体の健康情報 - 164】
~幸せな人生を歩むために~
「長所進展法」
船井総研の経営指導手法に、皆さんもご存知の「長所進展法」
というのがある。
以下、船井幸雄会長が語る、長所進展法のさわりを紹介します。
|
私が招かれてお店に行くと、あくる日から売上が30%くらい上がります。 次に「何が一番効率がいいんですか?」と、
坪当たりの売上の一番いい商品を聞き、その商品はあと5%くらい売り場面積を広げ、
商品の店頭在庫を一割ほど広げたらどうかと、お薦めします。 欠点を正す「短所是正法」はやらないようにしています。
その会社、あるいは社員さんの長所を伸ばすことを第一に、指導しています。 ■ツキを呼び込み、幸せな人生にするために、 やらなければならないこと (1)得意なこと、好きなこと、
やりたいことをやる (2)ツキを呼び込むことを考えるようにし、
ツキを落とすことをやらないようにする (3)すべてのことに感謝し、喜びで接し、明るくふるまい、
笑いを絶やさない |
私の会社では、来店される代理店所長に、挨拶と同時に、何か一つほめるようにしている。「今日のお肌きれいですね」
「素敵なお洋服ですね」。ほめればほめるほど、女性は美しくなります。女性の「顔」「髪」「洋服・装身具」
の何れかを褒めるようにします。
夫婦同伴パーティーで奥さんを連れて出ない人がいる。「人前に出すのはどうも… 不細工だから」などと言う男性の家庭では、
お互いほめ合うことがないのでしょう。
中年以降の男性には、奥さんに面と向かって「きれいだね」と言うのが苦手で、ほめることが下手な人が多い。
ところが、そういった男性に限って、奥さんに小言をよく言う。
欠点ばかりを指摘して、「欠点を正せ」と言っても、老化を推し進めるアドレナリンの分泌が盛んになるだけです。
奥さんの欠点ばかり指摘する「短所是正方」では、綺麗になりませんよね。
長所進展法は、経営のみならず、夫婦関係、子育てに於いても、有効な手法と言えます。
2004年09月21日
天職にめぐり合う
アテネオリンピックのおかげで、カラーテレビがよく売れたという。
ところで、去年から今年にかけて、カラーテレビを買った人の八割近くが、
4年後の北京大会までしか見ることが出来ない機種を買わされていることを、承知しているのだろうか?
8年後のオリンピックでは写らないということを…
現在受信しているテレビは、すべてアナログ放送。今年の春から東京、大阪、名古屋の三地区で始まった地上デジタル放送は、 2年後には全国で受信できるようになる。そしてアナログ放送は、7年後の2011年7月には終了する。
その時になったら、何万円か出してアダプターを取り付けれはいいと思っているかもしれない。が、デジタルテレビの売り物である
「高画質」や、「双方向サービス」を楽しめない機種がほとんど。
十年以上は持つと思うから、たいまいのお金をはたいて買っていく。しかし、電波を受信できなくなればただの箱。どのメーカーも、
そのことを販売時に十分説明していないという。
8/29読売新聞「一筆経上」より

【心と体の健康情報 - 163】
~幸せな人生を歩むために~
「天職にめぐり合うこと」
(株)芝寿しの梶谷忠司会長。神戸で知る人ぞ知る、(株)甲南チケットの小林宏至社長。
何れも二十数回いろんな職業を体験した後、梶谷会長は四十五歳、小林氏は五十歳になって、今の仕事にめぐり合い、
天職となった。
将来の職業が定められて生まれてくる人は稀である。”てんびんの詩”のように、何代も続く老舗に長男が生まれると、
其の時から将来が、人生が決まってしまう。
しかし同じ商家でも、私のように三男坊に生まれると、親は外へ出て一人前になってほしいと、”外喜雄”と名付けた。
もの心つく頃になると、将来何になろうかと、あれこれ考えるようになる。今の若者たちに、 「お父さんのような仕事をしたいと思うか?」と尋ねると、「嫌だ」と答える若者が七割近くいる。 お父さんが会社でどんな仕事をしているのか知らないということもあって、 何が自分に向いているのか分からない若者が多いという。
前号まで、「人生できるだけ早い時期に”天職”を見つけること、それが幸福につながる」と書いてきました。 9月12日の中日新聞に、「一隅を照らす」と題して、50代になって天職を見つけた人の話が載っていた。
某社の営業部長をしていたAさん、定年を間近にして、子会社に天下りするのが通例なのに、 何故か経験もノウハウもない、しかも高度な技能を要する、美容師の道を志したのです。
昼、営業部長としての激務をこなしたあと、夜間の美容専門学校に通い出した。
座講の方はともかく、技能実習のハードルは高かった。若いもののように手先が思うように動かず、挫折寸前まで行った。
横浜の郊外にある小さな美容院での修行が始まる。一人前の美容師になるための修行は並みでなく、
不屈の努力と精神力を要した。三度目の挑戦で実技試験を突破したときには、涙か止まらなかったという。
彼が第二の人生に美容師の道を選んだきっかけは、ある老人施設で、九十二歳の寝たきりのお婆さんが、
美容師さんに髪をカットしてもらっているのを見た時です。
生き返ったように、顔面いっぱいに喜びを表したのを見たとき、何ともいえない感動が走り、「私のやりたかったことはこれだ!
人に喜んでもらう私にふさわしい仕事はこれだ!」と、即座に決心したという。
彼の美容院は、福祉美容を目指している。足が不自由になったお客様の送迎、施設や寝たきり老人の家への出張美容。 現在二店舗持ち、三店目の準備に入っているという。営業部長だった時の経験が、新しい経営に生かされているのです。
2004年09月14日
前向きに生きるか? 後ろ向きに生きるか?
先週の金曜日健康診断に行った。二年前、二度骨髄移植のドナーになったことで、 年に一度の健康診断が義務付けられた。
人間の体内には五千ミリリットルの血液がある。それを右腕の血管から取り出して、遠心分離機にかけて左腕に戻す。 二日間かけて二万五千ミリリットル、つまり体内のすべての血液を、繰り返し五回も体外にポンプで吸い出し、骨髄を採取するのです。 従来とは違う、新しい骨髄採取方法を選択したため、その後五年間、骨髄提供者の健康状態を追跡検査する必要があるのです。
この検査と併せて、胃と腸の両方、カメラを飲んで検査をしてもらっている。
今回の胃カメラは新しいやり方だった。点滴を受け、全身麻酔でしょうか?
大きな注射液が点滴の管を通して血管に挿入された。
口に麻酔液を含み、咽を部分麻酔するといった、従来の方法ではなかった。
肛門からカメラを入れて、ブラウン管に写し出されるのを見ていたのは覚えている。が、その後胃カメラを口から挿入した記憶がない。 気がついたらすべて終了していた。カメラを飲む時のあの苦しさを、まったく体感せずに済んだのです??

【心と体の健康情報 - 162】
~幸せな人生を歩むために~
「人生、前向きに生きるか? 後ろ向きに生きるか?」
「運」について、連載してきましたが、
様々な先生の諸説を総括すると以下のようになります。
自分の人生を振り返えるとき、「うまくいっている」と実感する人と、「うまくいっていない」と思っている人の、
二つのタイプに分けられるでしょう。
「人生うまくいっている人」は、”十の内七つ”うまくいかなくても、それを良いように考えます。
うまくいかないことをバネにして、一つでも二つでもうまくいくようにと、努力して生きていこうとします。
「人生うまくいかない」と思っている人は、”十の内二つ”はうまくいっていると思っている。しかし、残る”八つ”
がうまくいかないと歎いているのです。
そして「何で自分だけ、こんな苦しい生き方をしなければならないのか…」と、考えてしまうのです。
人生肯定的に前向きに生きるか、否定的に後ろ向きに生きるかは、ちょっとした受け止め方の違い…なのです。 そのちょっとした受け止め方の違いが、人生を感謝に生きる人と、歎き悲しんで生きる人に分かれるのです。
「心の使い方」一つで、モノ事に対する見方・考え方が変わるということです。
「心の使い方」とは、「どういう考え方で生きるか?」ということです。
万事もの事を見るとき、否定的・後ろ向きに見てしまうと、山ほど無尽蔵に否定的に見えてくるものがあります。
同じものを見ていても、肯定的・前向きに見れば、これも又、無尽蔵に肯定的に見えてきます。
コップに入っている水の量を見て、「半分しかない」と見る人もいれば、「半分もある」と思う人もいる。 もの事を前向き・肯定的に見ることの出来る人は、お金やモノがあろうが無かろうが、それを補って余りある、 幸福な生き方が出来るのです。
ある大学教授が高齢者千人に、元気で長生きする秘訣を調査した。食事、運動、塩分、睡眠みんなまちまちで、 タバコを吸っている人もいれば、一頃人気者だった金さん・銀さんのように、マグロのトロといった脂身の好きな年寄りもいた。 みんなまちまちで、共通した長生きの秘訣が見当たらなかったという。
ただ一つ、全員に共通していたのは、「人生を肯定的・前向きに生きている」ということです。その証拠は、
長生きしている高齢者に「歳」を聞くことです。
「婆ちゃん歳いくつ?」『まだ八十』。「爺ちゃん歳いくつ?」『まぁ~だ九十』。
『まだ、まだ』と答えるそうです。一方、否定的・後ろ向きに生きている人は、『もう!四十八』と答える…。
私達が幸せに生きようとするとき、仏法に言う「身の回りに起きること、全てを生かす」
という考え方が、大変重要になってきます。
松下幸之助の教えに、「この世に無駄なものは一つもない。この世に無駄な人は誰もいない。自分の人生、
無駄な経験など一つもない」というのがあります。
人生思うようにはならない。横道へそれたり、無駄足を踏んだりすることは誰にでもあることです。そのたびに挫折し、
落ち込んでいたのでは、それこそ人生を無駄にしてしまいます。
若いときに挫折を経験したことが、その後の人生に様々な形で生かされていく。
世の中に不要なことは一つもないし、不要な人間など、一人もいないのです。
結論は
「身の回りで起きることは、良いことも悪いこともすべて、必然・必用なことである」
というふうに考えることです。
「起きたことをすべて、自分にとってベストなことだ」と肯定でき、
感謝できるようになったら、運が良くなり、運がよみがえるのです。
運をよみがえらせるのに大切な事がもう一つあります。
それは「人生、
好きなことをして、楽しんで生きる」ことです。
仕事でいえばできるだけ早く「天職」に出合うことでしょう。好きな仕事なら、
たとえ徹夜の連続でも苦になりません。
好きなことをして、楽しい人生を送るには、六つの尊守事項があることは、184号の「運のいい人、悪い人」
でお伝えしています。
田舞徳太郎氏、中山靖雄氏、船井幸雄氏、松下幸之助氏、田中信生氏より抜粋
2004年09月07日
天命の自覚(3)
アテネのオリンピック、日本勢の活躍は素晴らしかった。体操とマラソンは夜中に起きて、 手に汗して見入った。朝のニュースで結果を知ってから見ても、感動はない。毎日がワクワク、ハラハラ、こんな素晴らしいオリンピックは、 東京大会以来だ。四年後は中国で開催される。
その中国は今、経済発展が急速に進む中、沢山の外来新語を生み出している。
パソコンは「電脳」。日本でもよく知られている。ノートブック型は「筆記本」、Eメールは「電子郵件」。
漢字は、紀元前十六世紀の殷の時代に既に使用されていた。中華圏に広がったが、中国に隣接するベトナムと韓国・北朝鮮は、
何故か漢字を国語としなくなった。
漢字文化が継承されている中国、香港や台湾、日本など、地域によって字体が異なる。 本家中国でも1956年以降、字体の簡略化に取り組み、略字化は2238字にもなる。

【心と体の健康情報 - 161】
~幸せな人生を歩むために~
「天命の自覚」
「天命を果たす」とは何でしょうか。それは、人それぞれに備わっている 「長所・強み・個性」を、世のため、人のため活かすことでしょう。
この世に生まれてくるとき、「誰もが役割を持って生まれてくる。今世のテーマ(主題)
を決めて生まれてくる。そして、その課せられた主題を、人へのお役立ちでもって果たしていく」。
このように考えたら、自分にはどんな天命・使命があるんだろうか? と、考え込んでしまう。
人の二倍も三倍も懸命に働けば、それだけ短い時間で、自らの役割、
即ち天命を知ることができるという。人よりも早く天命を知れば、それだけ早く人生の幸福を手にすることができる。
だから一生懸命働くことは、大変意味のあることなのです。
人は歳を重ねるにつれ、人生のテーマも変化していく。十年を一つの単位として、
人生の主題が変わっていくことに気づくのです。
人生に成功する人は、人生の主題を決めている。明確な生き方・人生観を持って生きているのです。
人生、良いときも悪いときもある。明確な生き方や人生観を持っている人は、
人生下り坂になろうとしたとき、踏み止まることができるのです。
|
[目の前に現われる困難で、
越えられない困難はない] もう一つの理由は、自分の目の前に現われる困難や障害は、すべて自分で解 決できることだからです。
私に解決不可能な困難や障害は、目の前に現われたりはしません。
私に誰もオリンピックの選手になれと言うものはいないし、なろう とも思わない。だから、
そのことに悩むことは一切ないのです。 与えられた役割を果たす過程で生まれてくる困難や壁は、すべて「必然・必要」 なことであることも、忘れてはならない。目の前の困難や壁を乗り越えていくこと も、 今世に生まれてきた、自らに課せられた役割だからです。 困難にぶつかり、困難を乗り越えようと努力する中で、自分が果たすべき役割が 見えてくるようになる。この役割を果たすために使われる、自分に与えられた武器が「長所」 である。だから、自分の長所を伸ばそうと日々努力すれば、自分の 役割がわかってくるようになる。 一方、自分の「欠点」、苦手とするところは、今世の役割を果たすために、 「お前には必用がない」と、神様が武器として認めてくれなかったものと、思えばよい のです。 佐藤芳直 「船井幸雄の教え」より抜粋 |
今から23年前、私と一緒にノエビアを始めて、販社に昇格したNさん。
事業にすべての情熱を注ぐタイプには見えず、販社の組織はそれほど大きくはならず、目立たなかった。
8年ほど前、同じ販社を経営しているOさんの勧めでゴルフを始めた。それが性に合ったようで、みるみる腕を上げ、
4年ほどしてシングルになった。
今は、自らの長所(天性)を見出したことで、以前にも増して性格が明るくなり、
生き生きと、何事にもリーダーシップを取る、存在感のある人間になった。
当然、販社の業績も上向きになってくる。
今は、彼からゴルフを取り上げたら何も残らないだろう。ゴルフ漬けの人生を日々楽しんでいるOさん。
ゴルフとの出会いが、自らの天性に目覚め、「天命」を知ることとなり、幸福な人生を手にすることが出来た、
身近な事例といえよう。
2004年09月03日
日本は貧しい国?
オリンピックのおかげで、今売れに売れている薄型テレビ。
「液晶」と「プラズマ」の二つの方式があることは、皆さんご存知です。
しかし、どこがどう違うのでしょうか?
「液晶」は四角い小さな枡の集まりで出来ている。この枡は普段は透明。
背後から光が当てられていて、枡に電気を通すと、光を通す枡と、光を通さない枡が明暗の模様になり、映像になる。
ところで「プラズマ」って何? 拡大して見ると巾0.1ミリの長方形の枡が連なっている。この小さな枡一つひとつが、
蛍光灯と同じ原理で、自らが光を放って明暗を作り、それが100万個も集まって、一台のテレビ映像になる。
どちらも画像性能は似たり寄ったり。「液晶」は30インチ前後を得意とし、消費電力はプラズマの3分の2。「プラズマ」
は63インチなど、大型画面を得意とし、スポーツなどの早い動きに強い。

【吉村外喜雄のなんだかんだ 】
~幸せな人生を歩むために~
「日本は貧しい国?」
(株)アシストの代表取締役のビル・トッテンは米国人です。米国人の目で見た日本。メルマガ166号
「日本人が日本人でなくなった」の続きです。
なるほどと納得できる切り口で、私達日本人を分析しています。
|
今、世の中は不景気だとみんな思っている。生活が苦しいか?そんなことはない。
みなそこそこの生活をしている。確かに、高度成長期に比べれば、モノは売れないし、収入も横ばいだ。
日本人国民一人当たりの平均日給は、12,210円で、 地球上の98%の人より高い。私達の収入が、 地球に住む98%の人より高いのです。そんな民族が、不景気だ、生活が厳しいと騒いでいる。 地球上の87%の人が、日本人の収入の半分以下。77% の人が十分の一以下なのです。更に、三人に二人、69%の人は、 日本人の二十分の以下の収入で生活しているのです。 この現実をほとんどの日本人は知らない。 |
中国の中でも経済成長いちじるしい上海ですら、日本の一日の日給分が一ヶ月の平均給与なのです。 人口15億の巨大な中国、内陸部からいくらでも低賃金の労働力の補給が効くため、この先十年くらいは、 給与水準が上がったりしないというのです。
|
ならば、日本よりも日給の高い国はあるのでしょうか?日本より日給の高い国が三ヶ国あった。
合わせた人口はわずか1200万人。その三ヶ国とは、スイス、ノルウェー、
ルクセンブルクです。この三ヶ国が、
世界で最も成功している国なのです。 |
ところで、今の時代の日本人、”おごれる平家”のように思えてならない。贅沢な暮らしに慣れ親しみ、
平和ボケしてしまっている? 貧しく勤勉な先人たちの汗と苦労のお陰で、現在の豊かな暮らしができるようになったことを、
忘れてしまっている。
今こそ私達は、豊かさを追求し、増やし続けてきた国の借金(国民一人当たり550万円)を減らすことに、
真剣に取り組まなければならない。将来の子供たちへの付け回しを、少しでも減らすことが、
課せられた義務ではないでしょうか。
借金を減らすためには、昔の日本人が皆そうであったように、よく働き、質素倹約に努めなければならない…。 そんなことを言っても、今さら誰も耳を貸そうとしないでしょう…。
2004年08月31日
天命の自覚(2)
一週間後に湯涌温泉で、高校2年のクラス同窓会があり、幹事を務める。
クラスメートの三人に一人は、東京・大阪など県外に住む。
高校2年は、修学旅行や学園祭、部活など、青春の思い出が詰まっている。
86歳になられた先生もお元気で、参加者は19名、皆都合のつく限り集まってくる。上場企業で辣腕をふるった人や、
大学教授になった人もいる。ラーメン屋さんもいる。ほとんどの人が、就職した会社で人生を勤め上げている。
そんなクラスメートも、ぼちぼち第一線から退こうとしている。既に家でブラブラしている人もいる。
欠席の通知をいただいた方それぞれ、一筆添えてあった。
H君、「いつもご連絡ありがとうございます。心や体は元気ですが、お金の貧乏からなかなか脱却できないでいます。一生懸命”今一番”
と頑張っています。皆様によろしく」。Cさん、「環境と福祉の方面で、社会貢献させていただき、元気で頑張っています。孫も5人、
おばあちゃん業大忙しです。とても幸せに暮らしております」。
クラスには、S君とMさんの熱心なお世話役がいる。二人のお陰で、春と夏の2回、三十年近く、 毎年欠かさず続けて来られた。たかが同窓会、されど同窓会。長く続けてきたことが重みとなり、人生を彩っていく。

【心と体の健康情報 - 160】
~幸せな人生を歩むために~
「天命の自覚(2)」
「天から与えられた使命とは何かを自覚し、積極的に生きることが、わが生の目的である」 これは、日本の教育の師”森信三”先生の教えです。
「自分に課せられた天命とは何か? 」と問われて、
私はそれに即答できない。
まず何事も心の中で形づくられる。心の中で形づくられたものが、後から見える形となって現れてくる。
「自分に課せられた天命とは何だろう?」と、自分の心に問いかけてみる。
「お前は何を天職とするのか?」「何が欲しいのか?」「金が欲しいのか?」
「名誉か?」「出世したいのか?」「一体何が欲しくて頑張っているのか?」
「自分が本当に求める道は何なんだろう?」「どうしたら、沢山の人に影響を与えることができる人間になれるだろうか?」
道が定まらないまま、人生を無為に過ごしたのでは、後から後悔することになる。
孟子の言葉に、「朝(あした)に道を開かば、夕べに死すとも可なり」
というのがある。今日、自分の本当の生きる道が見つかったら、明日死んでもいいという。
命と引き換えにしてもいいくらい、価値のあることなのです。
「天命」とは何かというと、それは「その人が持つ長所・強み・個性を、
世のため人のため活かすこと」でしょう。
相撲取りはマラソンランナーにはなれない。マラソンランナーは相撲取りになれません。
子育てにおける親の役割は、子供の持つ才能をいち早く見い出し、伸ばしてやることでしょう。
2~3才の頃に現われてくる個性を見逃さないことです。
お歌が好きな子、お絵かきが好きな子、敏しょうな子、積み木遊びが大好きな子、いろいろです。
今年も200本安打を達成したイチロー選手も、福原愛ちゃんも、親が才能を引き出してくれたお陰で、
自らが持つ天性を開花させることが出来たのです。
私の人生観の一つに、「人生、好きなことをして、楽しんで生きる」
がある。
人生好きなことをして歩もうと思ったら、できるだけ早く「天職」に出合うことでしょう。
好きな仕事なら、たとえ徹夜の連続でも苦にはなりません。
しかし、仕事・仕事と、仕事に追われ、 仕事の中に人生を押し込めてしまってはいないだろうか? 私の周りには、365日仕事一途、単身赴任、 家庭を犠牲にして働いたあげく、体を壊して人生を棒に振ってしまった人がいる。職業病に悩んでいる人もいる。 忙しさのあまり定期健診を怠って、手遅れで亡くなった人もいます。
仕事と人生、どちらが大きいかと問われれば、誰もが人生の方が大きいと答えるでしょう。
仕事の方が人生より小さいのに、大きな器の人生を、小さな器の仕事の中に押し込もうとして、自らの人生を、夫婦の幸せを、
家庭を、健康を、犠牲にしていないだろうか。
幸せな人生を送るための仕事であるはずが、いつしか、仕事のために家庭や、自己を犠牲にして、
不幸を呼び込んでしまっている。
仕事は生きがいを生み、人生を左右する。しかし、仕事で人生や家庭や、健康を犠牲にしてはならないのです。
仕事に失敗して自殺してしまうのは、仕事に人生が奪われてしまった、典型的なケースでしょう。
2004年08月27日
アジアの貧困に学べ
25~26日の2日間、和倉温泉加賀屋あえの風で、商業界北陸ゼミが開催された。
700名近く参加をいただいた中、二人に一人は県外からの参加者。遠く沖縄や北海道、東北、九州など、
全国各地からお越しいただいた。
この催し事を企画運営したのは、わずか60名の小さな組織。半年間、
中心になって準備をしてきた役員の皆さんのエネルギーの高さには、頭が下ります。
大きな全国組織を持った団体が、全国大会を地方で開催することはよくある。
しかし、組織外の一般参加者が70%以上という、こんなとてつもない大きな事業を、三年に一度、
当たり前のように繰り返し開催している組織は、他に例を見ない。
先輩同友から受け継がれてきた、伝統の為せる業なのでしょうか…。
新潟から社員さん14名を引き連れてこられたKさん、奈良から4名で参加いただいたMさん、その他、
私の呼びかけに応じて参加いただいた友人のみなさん、
ありがとうございました

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第44号】
~幸せな人生を歩むために~
「アジアの貧困に学べ」
先々週土曜日の民放、夜九時から放映された「世界が100人の村ならば」で、ロシアのマンホール・ チルドレンを追跡するドキュメンタリーがあった。
モンゴル、カンボジア、ミヤンマーなどのアジアの国々にも、
極限の貧困ゆえに親に捨てられたホームレスの子供たちが大勢いる。モンゴールの冬は、マイナス三十度。街の地下には、
温水菅が通るマンホールがある。捨てられた子供たちがその中に住んで、何とか寒さをしのいでいる。
マンホールチルドレンと呼ばれ、二千名はいるという。
カンボジアの首都には、四万人くらい住むスラム街がある。そこの子供たちは生きるために煙の充満するゴミ捨て場で、
一日中ビンや缶を拾い集めている。
貧くつ街に住む人達には、水を買う金がなく、川の水を飲んでいる。そのため、赤ちゃんがバタバタ死んでいくという。
池間哲郎「アジアのこどもたちに学べ」より抜粋
毎年沢山の日本人が、韓国や中国、ベトナム、タイなどアジア諸国へ観光する。
上海は、中国の中では生活水準が高い方です。それでも、私が見学した工場の女工さんの一ヶ月の平均賃金は、
日本円で七千円くらい。日本の観光客が上海の豪華レストランで支払う夕食代が七千円くらい。
現地の人が一ヶ月近く汗して働き、手にする金額を、一回の飲み食いで使ってしまうのです。
インドのお坊さんが、日本からはるばる観光に訪れたおばさん達に尋ねました。
「遠い日本から、はるばる私の国へ何を求めに来られたのかな?」
おばさん達は、目を輝かせて言いました。「私達はインドの素晴らしい遺跡や仏像を見るためにやってきました。
そして感動しました」
それを聞いたお坊さんは言いました。「どうして日本の人は、そんなに感動を求めてあちこち歩き回るのですか? そのために使うお金を、貧しい人達に施せば、もっと素晴らしい感動を手にすることができるでしょうに…。 感動を求めるのではなく、感動を与える人になってほしい」と…。
今の時代の日本人、あれが足りない、これが欲しいと、求めることばかりで、与えることを知らない。日本人は、 あまりにも豊かで恵まれ過ぎていて、人間として一番大切なものを忘れてしまったようです。恵まれ過ぎていて、 世界の中で最も贅沢で豊かな暮らしをしていることに、気づいていない人が多い。
だからでしょうか? 大人も子供も、ちょっと辛いことがあると、生きる力を失ってしまう。つい十日ほど前の朝、 いつも犬の散歩をしている公園で、首吊り自殺があった。つなぎの作業服を着た四十代の男性でした。
子供や成人の人口比自殺者が、諸外国から見て極端に高いことからして、生きる力が、
世界一弱い民族ではないかと思うのです。
世界の75%の人たちが、日本より貧しく厳しい生活環境の中で暮らしている。
生きるために必死に頑張っている。
日本人の多くは、貧しい国の人から見たら、王様のような暮らしをしている。
そんな幸せな星の下に生まれながら、今の暮らしに感謝するでなく、「まだ、まだ」と、不足を言っているのです。
2004年08月24日
天命の自覚
お盆に、実家へ帰るなど、旅行された方も多いことでしょう。
ところで外国に行くと、言葉が通じなくて困ることが多い。帰ってきた時、次に海外に行く時までに英会話を勉強しておこう…と、いつも思う。
半年ほど前に、民法テレビで画期的な翻訳器が紹介された。私が待ち望んでいたものが実用化されたのです。
翻訳器のマイクに向かって日本語で話すと、話した言葉が英語に変換されて、画面に表示される。しかもそれを英語で喋ってくれるのです。
ロサンゼルスで、通りかかりの人に道を日本語で尋ねたら、変換され、翻訳器が英語で喋る。
それを聞いたアメリカ人が、英語でマイクに向かって道を教えると、即座に日本語に翻訳され、画面に表示される。と同時に、
日本語で翻訳器がしゃべり、道を教えてくれるのです。
今年の秋、十万円くらいで市販されるという。「欲しい~! でも、高い…」

【心と体の健康情報 - 159】
~幸せな人生を歩むために~
「天命の自覚」
致知八月号、特集「何のために生きるのか」で、日本の教育の師”森信三” 先生の教えを今に伝える”寺田一清”氏の文章がある。その中から一部抜粋して紹介します。
| 1998年に、日本、韓国、中国の高校生二千人を対象に、
アンケート調査が行われた。「あなたはお父さん、お母さんを尊敬していますか?」
との問いに、中国は80%が尊敬していると答えている。韓国は52%でした。
日本はわずか10%
。日本の子供は、
十人に一人しか両親を尊敬していないのです。 同じく中学三年生を対象に、「学校の先生を尊敬しているか?」の問いには、 韓国85.4%の子供が尊敬している。ヨーロッパ12ケ国の平均は83.7%。 アメリカ82%。中国80.7%と続く。 ところが、日本の中学生で先生を尊敬する生徒は、 たった21%。5人に1人です。 50% なければ教育現場は成り立たないと言われている中、まことに憂うべき危機的状況にあります。 |
今ほど、日本の教育の在り方が問われるときはない。何故こうなったのか?
戦後教育を受け育った、私達の子育てに大きな問題があったようです。
父兄は学校教育に問題があると言い、先生は、家庭の躾け方が悪いからだと言う。
責任のなすり合いをしていても、問題は解決しないでしょう。
|
自由・人権・個性をはき違えた戦後教育の欠陥が、日本民族をかくも落ちぶれさ せてしまったのです。 国家意識の喪失、親や上長を敬う心の喪失、モノを大切にしないなど、 「モノ豊かにして心貧しき社会」になり下がってしまったのです。 この身があるのは、親があり家があるからである。親があり家があるのは、国があるからであり、
国があるのは、何千年の国の歴史と、国を支えた先人たちの労苦があるからです。 |
以前、「もしも世界が100人の村ならば」が、
メールで送られてきたことがある。
その中の一節。
「…6人が世界の富の59%を所有し、その6人ともがアメリカ国籍。80人は標準以下の居住環境に住み、
70人は文字が読めません。50人は栄養失調で苦しみ、1人が瀕死の状態にあり、1人が今生まれようとしています。
1人、そう!たった1人が大学の教育を受け、そして、1人だけがパソコンを所有しています。もし、冷蔵庫に食糧があり、
着るものがあり、頭の上には屋根があり、寝る場所があるならば… あなたは、この世界の75%の人々より裕福です…」
今の時代に生を受けたことは、何と幸福なことだろう。この日本に生まれたことは、 幸運としか言いようがない。もし私が、タイムスリップして、もう20年早くこの日本に生まれていたら、 赤紙が来て戦地へ行っただろう。又、同じ今の世代に生まれても、アフガンやイラクに生まれていたら、戦いに巻き込まれ、 辛い生活を強いられただろう。
| 両親から今この時代、この日本に生を授かったのは、「天から授かった命」
であり、宇宙の意志によってこの世に送りだされたものであると思わざるを得ない。 それゆえに、「自分に課せられた天命とは何か? 」 天から与えられた使命とは何かを自覚し、積極的に生きることが、わが生の目的である。 |
今こそ、自らに与えられた運命に目覚め、天命を自覚し、自分を生んでくれた父母に感謝し、 先人を敬い、上長に敬意を払わなければならない。そして、自らが存在する国家を大切に守り、育て、 後世に生まれてくる者たちに、先人から受け継いだ日本人の心を、遺産を、文化を、引き継いでいかなければならない。
2004年08月20日
運が良くなる方法/感謝の心
言葉遊びの「畳語」、まだまだネタが尽きません。
「竹屋の竹薮に竹立てかけたのは 竹立てかけたかったから
竹立てかけた」
は、早口言葉としても知られています。
「豚が豚をぶったら ぶたれた豚がぶった豚をぶったので ぶった豚とぶたれた 豚が ブウブウと ぶっ倒れた」
も面白い。
「こ向かいの 小山の小寺の小僧が 小棚の小味噌をこなめて 和尚にこ頭 こずかれた」
・私の作品です。お茶の種類を並べてみました。
「お茶を飲むなら日本茶やむ茶 製茶したもの葉茶棒茶
抹茶ほうじ茶げんまい茶 芽茶粉茶にウーロン茶 白茶青茶、 黄茶に黒茶
みんな知ったる緑茶に紅茶 めでためでたの桜茶、こぶ茶
ぜんぶ飲めとは そりゃむちゃくちゃや やくちゃもない(金沢の方言)」

【心と体の健康情報 - 158】
~幸せな人生を歩むために~
「運勢が良くなる方法(4)感謝の心」
「ありがとう」を言い、「感謝の気持ち」
を持ち続けると、愛が深まっていく。
心がきれいになっていく。このすごい魔法の力を持った二つの言葉、子育てには絶対欠かせないものです。
子供の頃、ご飯をこぼしたりすると「罰が当たる」と叱られた。私達が口にする食べものは、
植物や動物など自然界で育まれた命。それを頂いているのです。
毎日何気なく食べているご飯、そのお米は、お百姓さんの労苦のお陰で口に入ることも忘れてはならない。食事を頂くとき、
お米やお百姓さんに感謝をする心があれば、「いただきます」と自然と手が合わさる。
以下、致知八月号「ありがとうおじさん」からの抜粋です。
| ご飯を例に挙げても、米一粒一粒に命が宿っている。米は、
自分の命を捧げて「私を食べてください」と言っている。 「感謝の心」は、「天からの恵みで生かされている」、 そんな思いから生まれてくる。 「感謝の心」の正反対は「欲に囚われた心」になる。感謝のない状態が 「欲の心」なのです。欲の心は、あれが無い、これが不足と、心が満ち足りない状態から生まれてくる。 その満ち足りない心を補おうとして、「欲の心や、求める心」が生まれてくるのです。 |
子供の成長過程で、「ありがとう」と「感謝」、この二つを繰り返し教え、 躾けなければならない。これは大変大切なことで、親の務めでもあります。
私が幼少の頃通っていた幼稚園は、 武家屋敷の並びにある聖霊病院に付属したカトリック系の幼稚園でした。そこに”ライザ”というドイツ人の美しい先生がいた。 先生は、ドイツ流の家庭の躾け方で、私たち園児を躾けた。
食事の前に繰り返されたお祈りは、今も私の潜在意識の奥深くに眠っている。
食事の前には、必ず「お米に感謝し、天の恵みに感謝し、お百姓さんに感謝しましょう」といった短いお説教があって、
そのあと両手を組んで目をつむり、「天にまします我らが父よ、今日も一日神のお恵みで、食事が出来ることを感謝します。
アーメン」とお祈りしたあと、箸を取った。
食事中に、ご飯を床にこぼしたことがある。「これ、あなたがこぼしたんでしょう?」。
叱られるのが怖かった私は、「自分ではない」と言い張った。暗い物置の中に入れられた。頑固に謝らなかった私に、
「お父さんにきつく叱ってもらいましょう…」。
父親は厳格で怖かった。家に帰って、いつ叱られるかと縮こまっていたことを、今も忘れない。そうやって、食べものに感謝し、
モノを粗末にしないしつけが身についていった。
しかしその後、小・中・高を通して「感謝の心」について教えられたり、学ぶことはなかった。
2004年08月17日
不運は幸運の始まり
■「つきを呼ぶ魔法の言葉」
182号配信のメルマガ、「足るを知る(2)」でご紹介した「つきを呼ぶ魔法の言葉」、 まだ読んでいないようでしたら、文中のファイルをダウンロードして、是非読んでみて下さい。 驚きと感動の世界に引き込まれるでしょう。
著者であり体験者である”五日市 剛”氏が、私の友人、木下孝治氏のお世話で、 金沢で講演することになりました。本人の口から直接お話を聴いてみたいと思いませんか?
会 場 :石川県立音楽堂(全日空ホテル隣)
演 題 :「運命を変える奇跡のコトバ」
(イスラエルでの体験談と、読まれた人にお伝えしていない、その後に起きた、更なる奇跡のお話にご期待ください)
参 加 費 : 大人1500円 中高生1000円
チケットのお申込みは、076-291-1100へ

【吉村外喜雄のなんだかんだ 】
~幸せな人生を歩むために~
「不運は幸運の始まり」
私の人生を振り返ると、新しい未来に一歩踏みだそうとする時、
何故かその方向へ歩み出そうとするのを阻止するかのように、突然病魔に襲われた。
そんなことを二度も繰り返した。そのたびに、自分の思いとは違った人生を歩まざるを得なかった。しかし、
それを不幸に思ったり、不運と嘆くことはなかった。
自分が志した人生とは違っていても、そこに身を置くうちに新しい世界が開かれ、生きがいが生まれる。 違った形で幸運に恵まれ、不思議な出会いや、ご縁をいたくことができた。「運」や「ツキ」にも次々と恵まれた。
人から見れば不幸に見えることでも、「それもまた人生」「起きることすべて必然」と、肯定的に受け止めてしまえば、
不思議なことに、その後、それに倍する幸運にめぐり合えるのです。
五日市さんの不思議な体験は、そのことを如実に物語っている。私も、そこまで劇的ではないにしても、何度となく、
奇跡のような不思議なめぐり合わせや、出会いを体験している。
どんな境遇に置かれても、運やツキは等しく訪れてくると思う。その時の苦しみや悲しみが大きければ大きいだけ、その後、
それに見合うに余る幸運がやってくる。但し、それなりの努力をしていないと、折角の幸運も掴めないでしょうが…。
3月5日のメルマガ157号で、農作業中機械に両腕をもぎ取られた”大野勝彦”氏を紹介しましたが、 ご記憶にあるでしょうか。致知九月号にも、10ページにわたり特集しています。
機械に両腕が引き込まれていく。このままでは死ぬ!と、必死で引きちぎった。その瞬間、「やった! 助かった! 死なずに済んだ! 良かった」と思ったという。両腕を失ったときから、ご飯を食べるのも、オシッコをするのも、 お尻を拭くのも、人の手を借りなければ何も出来ない。なんとも情けない、上半身生きだるまになってしまったのです。
 両手を失って初めて「手は宝物」に気づいた。家業であり、
天職であった農業を諦めざるをえなくなった。代わりに、”湧き出る生”への念いを詩に託し、”生きる喜び”
を水墨画に、義手をつけて表現する、もの書きの人生が始まった。
両手を失って初めて「手は宝物」に気づいた。家業であり、
天職であった農業を諦めざるをえなくなった。代わりに、”湧き出る生”への念いを詩に託し、”生きる喜び”
を水墨画に、義手をつけて表現する、もの書きの人生が始まった。
隠れていた才能が、図らずも開花したのです。
数年後には、農業をやっていた頃の何十倍もの世界が広がり、新たな幸福を手にし、生きがいと、
世の中へのお役立ちが実感できるようになった。
「災い転じて福となす」とはこのことでしょうか。
失ったものは大きかった。代わりに「人への優しさ」「思いやり」「人生とは…」「生きるとは…」、
それまで見えなかったものが見えるようになった。
今まで気づかなかったことを学ばせてもらったという。
「もっと早くこっちの世界に来たかった」と言わしめるくらい、不自由になってから後、手にしたものは大きかったのです。
2004年08月10日
「ありがとう」を言い続ける
【心と体の健康情報 - 157】
~幸せな人生を歩むために~
「運が良くなる方法/ありがとうを言い続ける」
■ご飯をビンに詰め、三つ並べた。
- 一つには、毎日「ありがとう」と言い続けた
- 一つには、毎日「バカやろう」と言い続けた
- 一つは、 全く無視した。
- 一ヶ月後に、毎日「ありがとう」と言い続けたビンのふたを開けたら、 ふくよかな香りがした。
- 毎日「バカやろう」と言い続けたビンのふたを開けたら、ムッとする匂いがした。
- 無視したビンのご飯は腐っていた。
(社会や家族から、その存在を無視されたときほど、辛く悲しいことはない)
毎日毎日「ありがとう」の言葉を投げかけられた水の結晶は、雪の結晶のように美しく整った形をしているという。
人の身体は60~70%が水分で出来ている。いつも「ありがとう」を言っている人、いつも「ありがとう」
の言葉を投げかけられている人の体内にある水の結晶は、美しい雪の結晶のような形をしているのかもしれません。
「ありがとう」の言葉を言い、「感謝の気持ち」
を繰り返すたびに、その人の身体細胞が健康になり、愛が深まっていく。
心がきれいになっていく。
このすごい魔法の力を持った二つの言葉、いつでも、どこでも、誰にでも、その気になれば、今直ぐ実践できるし、自分のものにできる。
ところが、現実なかなか行動が伴わない。簡単そうだが、難しいことなのです。
これを実践して有名になったのが、”ありがとうおじさん”です。
滋賀県の山奥に住み、名前も顔も見せず、「ありがとうございます」の感謝行を、五十余年にわたり続けているという。
「ありがとう」を五万四千回言い続けたら、ガンが治ったという事実を語っている。
「ありがとう」という言葉は、難が有ると書いて「有難う」と言う。そのことは、前号で話しましたが、”あ”
は「天」、”り”は「理」、”が”は「我」、”とう”は「十分」、「天の意志が我に十分に栄(は)
える」という”ことだま”を表しているのです。
特別意味を込めなくても、何事にも「ありがとう」と感謝し続ければ、人間の遺伝子に働きかけ、細胞が元気になり、心がきれいになるのです。
文中に、修養団 中山靖雄「広やかな心」からの引用があります
日々清廉潔白、無欲の暮らしをしている永平寺のお坊さん。ストレス社会の中で暮らしている私達より、 遥かに長命で健康なのは、恐らく、体内の水の結晶が美しいからなのでしょう?
2004年08月03日
運勢が良くなる方法/感謝
「人間には運勢がある。だけど、
絶えず努力していないと運はつかめない」
これは”後藤田正晴”
氏の言葉です。
後藤田氏は、1945年(S20年)台湾から東京へ飛行機で上京することになった。
当初、那覇経由の飛行機に乗ることになっていた。日頃から情報を収集していた後藤田氏は、沖縄は米軍機の戦闘領域に入っていて危険だと、
乗る便を中国大陸沿いを飛ぶ便に変えた。
中国軍には気の利いた戦闘機がなかったからである。最初に乗る予定だった飛行機は、那覇上空で撃墜された。もし乗っていたら、
そこまでの人生運だっただろう。
様々な情報を持っていることが、運を呼び込む要因になります。

【心と体の健康情報 - 156】
~幸せな人生を歩むために~
「運勢が良くなる方法/感謝します」
6月8日にお届けしたメルマガ「足るを知る(2)」の中で、「つきを呼ぶ魔法の言葉」
と題した、世にも不思議な運命を体験した人のお話を添付しましたが、お読みになられた方もあるかと思います。
その中に「運を呼び込む方法」について語っているところがあるので、その箇所を抜き出して紹介します。
人にはツイているとか、ツイていないとか、”ツキ”というものがある。そのツキというものはね、
簡単に手に入るものなのよ。いろんな人がよく使う言葉なんだけど、その言葉を使うと、ツキが回ってくるようになるの。
二つあってね、
一つは”ありがとう”、もうひとつは”
感謝します”…。 ねっ、簡単でしょ。
どんな時にでも自由に使っていい言葉なんだけど、そうねぇ…
ある状況の時にこれらの言葉を使い分けたら効果的かもね。”ありがとう”という言葉は…そうね、
何か嫌なことがあった時に使ったらどうかな。
例えば、朝寝坊しちゃって「わあ~学校に遅刻する!」とか、「会社に遅れる!」なんて時、イライラするでしょ。
そんな時「イライラさせて頂き、ありがとう」と言うの…。車を運転中、事故っちゃって、
そんな時も歯を食いしばって”ありがとう”と言うのよ。どうしてかというとね、
イヤな事が起こるとイヤな事を考えるでしょう。そうするとね、またイヤな事が起こるの。
不幸は重なるというけれど、それは、間違いなくこの世の法則なのよ。だけど、そこで”ありがとう”と言うとね、
その不幸の鎖が断ち切れちゃうのよ。
それだけでなく、逆に良い事が起っちゃうのよ。
”災い転じて福となす”という言葉があるでしょう。どんな不幸と思われる現象も、
幸せと感じる状況に変えてくれるのよ。絶対にね。だから”ありがとう”という言葉はね、魔法の言葉なのよ。
有難う…、「ああ、そうか。難が有るときに”有難う”か!」
それからもう一つ”感謝します”という言葉については、何か良い事があったら”感謝します”
と言うようにします。
例えば、明日待ちに待ったハイキング。晴れてほしいなぁ~と思っていて、良い天気に恵まれたら「感謝します」。
そうそう、この言葉はとっても便利でね、 たとえまだ起こっていないことで一週間も先のことでも、「○月○日晴れました。晴れさせて頂き感謝します」とか、 「○○大学に合格させて頂き感謝します」とイメージしながら言い切っちゃうと、本当にそうなるのよ!! 何の疑いもなくそう思い込めればね!
その気になればだれもが実行できることです。つまり「言葉遣いに気をつけよう」
ということなんです。自分の口から発する言葉が、自分の人生に影響するんです。
何かあれば”ありかとう”と言っている自分。そしてすべてに感謝している自分。「ありがとう」が、
普段何気なく自然に口に出るようになれば、ツキが回ってくるようになりますよ。
2004年07月27日
運勢が良くなる方法
【心と体の健康情報 - 155】
~幸せな人生を歩むために~
「運勢が良くなる方法」
一ヶ月前、京都の研修で「まずい!もう一杯」で有名な、キューサイの社長 ”長谷川常雄” 氏の講演を聴いた。
長谷川社長が胃を病んだとき、野菜ジュースで健康を取り戻した。これはいいと、商品化することになった。 ところが知名度のない健康ジュース。なかなか売れない。しかも不味い。何とか軌道に乗せようと、TVコマーシャルを出すことにした。
社長が発案した「まず~い!もう一杯」は、社内では反対の声ばかり…。
「そんなコマーシャルを出したら、今まで売れていたものも売れなくなる」
長谷川社長はプラス思考の持ち主。結果は、超人気コマーシャルになり、年間50億円を売り上げる主力商品になった。
講演の中で、”運の呼び寄せ方”について色々語っているので、紹介します。
|
人は皆、心の中に大きな袋を持っている。私達が思ったり、言ったりしたことが、 この袋の中に入ってくる。
袋に入ってくる思いは、二種類ある。ピンク色したプラスの思いと、グレー色したマイナスの思いです。 さて、皆さんの心の袋に沢山入っているのは、ピンク色が多いでしょうか? それとも、グレーの色が多いでしょうか? ピンクのプラスのストロークが沢山詰まっていれば、現状に満足し、明るく生き生き肯定的です。 グレーのマイナスが多ければ、自信をなくし、無気力で、何事にも否定的です。 ■ プラス思考を促す言葉 それと
「仕方ないなぁ~」と、起きてしまったことをくよくよしないことです。
何が起きても
「この程度で終わってよかった」「たいしたことない…」と思うことです。
何かあったとき、自己罪悪感にさいなまれて、自分を「駄目な人間」と、落ち込ませないことです。何があっても、 三日もしたら忘れてしまうことです。同じ生きるなら、ノー天気に明るく、楽しく生きていくようにすると、運が開けてきます。 次に大事なことは、何かをヤルとき「成功」 をイメージします。「失敗」 をイメージ すると、何故かそのイメージ通りに失敗してしまいます。 |
私(吉村)がゴルフで何度となく経験していることです。理想的なスゥイングと、飛行コースをイメージして、
無心でクラブを振れば、ナイスショットの確立が高くなり、ツキまで呼び込んでくれます。
又、ミスショットをして最悪のホールになっても、次のホールまで引きずらないことです。悪いことはいち早く忘れ、
プラスのイメージに切り替え、新たな気持ちでプレーするようにします。
プラスのストロークを多くしようとして、マイナスの要因となる自分の欠点や、 苦手なことを改めようとするよりも、自分の得意なこと、好きなことを、更に伸ばしていくようにします。自信が付き、 より前向きに積極的になり、プラスのストロークがいっぱい出るようになります。
結論として、「逃げる」「忘れる」「諦める」などは、あくまでもプラス思考に持って行く手段です。
同じことをマイナスに思考したら、グレーになってしまいます。何事もすべて取りようによって、プラスにもマイナスにもなるということです。
2004年07月23日
自らの努力で運をつかむ
■過去に経験したことのない大きな目標に挑み、その目標を達成 したときに
同時に経験するのが、以下の三つです。
1.
一生懸命やれば 大抵のことが出来る
一生懸命やっていると、
やった分だけ積み上げられていく。
未知の世界がどんどん拓かれていく。
2.
一生懸命やれば 何事も面白くなる
一生懸命やっていると、
山に登るがごとく、登る苦しさよりも、
もう少し、もう少しと、頂上を目指している自分が楽しくなる。
3.
一生懸命やれば 誰かが助けてくれる
一生懸命チャレンジしていると、人の心を動かします。
援助しようとする人たちが周りに集まってきます。
目指す山が高ければ高いほど、その途中の山道が険しければ険しいほど、頂上に上り詰めたときの喜びと感動は大きなものがあります。

【吉村外喜雄のなんだかんだ】
~幸せな人生を歩むために~
「自らの努力で運をつかむ」
以下、倫理法人会「今週の倫理324号」からの抜粋です。
|
アメリカの哲学・心理学者のジェームズ・ランゲは、
「人間は悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいのである。
恐ろしいから逃げるのではなく、逃げるから恐ろしくなるのである」
という説を述べている。
|
目の前に大きな壁が立ちふさがった時、乗り越えられないと思うから、出来ることも出来なくなってしまうのでしょう。
|
同じように、強運に恵まれたから幸せになるのではなく、いつも口癖のように、 将来の夢や目標を語っていると、強運を呼び込み、幸せになれるのです。 生理的に見ると、いつも肯定的な言葉を意識的に選択し、積極的に使っていくことで、 自律神経によい刺激を与え、積極的思考回路を喚起するのです。一人、胸の内でいくら強く思っていても、 自律神経を刺激することができません。人前で繰り返す、前向き・肯定的な言葉や行動によって、 自らの自律神経が刺激され、精神が高揚し、積極的に行動するようになるのです。 高い目標にチャレンジしようとすると、ストレスを感じてしまう。適度なストレスは、 むしろ心に張りを与え、潜在能力を開花させてくれます。普段の行動の中で、ストレスに負けない気力や、 精神力を養うようにしていけば、成功への道が拓けてくるのです。 |
ノエビアには、二次代理店(小売)から、一次代理店(卸売)に昇格する制度がある。一定期間に目標売上を達成すると、
傘下に代理店を持ち、代理店に商品を卸し、代理店所長を育成し、指導することが出来るようになります。
昇格した一次代理店には、更に販社に昇格する道も拓かれています。
このようにしてサクセス階段を上り詰め、販社にまで昇格し、前髪をつかんだ女性が、全国に溢れるほどいるのです。
自らの力で”人生の運”をつかみ取った人たちです。
昇格を目指す第一歩は、動機づけの面談から始めます。まず将来のなりたい姿を具体的にビジアル化していきます。そして、
将来それらを手にした自分を想像させ、目標にチャレンジする決意をさせます。自らの意思で「やってみたい!」
と決意することから始まるのです。
次に、チャレンジする目標と期間を明確にします。チャレンジ期間は六ヶ月間。売上目標を設定し、
その目標を達成することのみに、日常活動のすべてを集中します。
人生の分かれ目は、これから挑戦するとてつもない高いハードルを、プラス思考で見るか、
マイナス思考で見るかで決まってしまいます。
積極的思考回路を喚起する方向に向かえば、「頑張ろう」と意欲が湧いてきます。ところが、日頃何かあるごとに顔を出す、
否定的回路が働くと「私には無理、出来ない」と、ヤル気がなえてしまうのです。
ヤルと決めたときから、自らの運命を変える試みがスタートする。この関門を、自らの努力で突破することが出来たら、
それが自信となり、更なる高い目標に挑戦するエネルギーが湧いてきます。
地道な努力と、やり続ける強い意思があれば、誰でも人生の夢を引き寄せることが出来ます。そして、一回りも二回りも、
大く育っていく自分に気づくのです。”仕事が人間をつくり、人間が仕事をつくる”
のです。
自らの努力で成功を手にした代理店所長は、ノエビアとの出会い・ご縁に感謝する。何より大きなプレゼントは、 人生の幸福を自らの努力で掴み取ったことで、ヤレば出来るという自信を手にしたことです。
2004年07月20日
運命は変えられる?
言葉遊び、「畳語」がふんだん出てくるのが落語の「りん廻し」。
ガラにもなく風流の道を志したハチ公に、横丁のご隠居があれこれコーチする。
「山王の 桜に猿が三下り 合の手と手と 手手と手と手」
「りんりんと りんと振りたる小なぎなた 一と振り振れば 敵はちりりん」
「りんりんと りんと咲いたる山桜 嵐が吹けば 花がちりりん」
「りんりんと 綸子(りんす)や繻子(しゅす)の振り袖を 娘に着せて
ピラリシャラリン」
と、手当たりしだいに披露するご隠居をさえぎって、ハチ公も一句…
「りんりんと 淋病やみは痛かろう 小便するたび チョピリチョピリン」
・私(吉村)も負けじと一句
「ちりりんと 振れども振れども チョピリチョピリン」
(^-^;

【心と体の健康情報 - 154】
~幸せな人生を歩むために~
「運命は変えられるか?」
「人生とは何だろう」。人の一生には運・不運が付きまとう。思わぬ運・
不運に人生がほんろうされる。それと並行して、人生ドラマを構成するもう一つの大きな 要因に
「因果の法則(原因があるから結果がある)」
があります。
日々何かを思い描き行動すれば、必ず「業(この世で為す善悪の行い)
」
が生まれます。その「業」によって生ずる様々な現象・結果が、
運命とからみ合い、人生をおりなすのです。
ここで疑問に思うことは、「運命は変えられるか?」ということです。未来が予測出来ない以上、結果からしか判断できません。
東洋哲学・人間学の”安岡正篤”師は、「運命は善き想い、
善き行いによって変えることができる」と、「立命の学」の中で、
中国の明の時代の遠了凡(えんりょうぼん)の物語を取り上げて説明しています。
| 遠了凡の父が亡くなり、母は息子に、
父の跡を継いで医者になってもらいたいと思っていた。そんなときに、老人が町にやってきた。 老人は、息子をしげしげと見て、「この子は医者にはなりません。科挙(かきょ)の試験に合格して、 偉い役人になる。」と言い、「来年には村の試験に、何人中何番で合格し、再来年には、こういう試験に受かり、 そして科挙の試験には…」と、これからの人生を事細かに占う。 「将来は地方の町の長官になり、結婚はするが、子宝にま恵まれません。そして、 53歳に往生するという運命です」 遠了凡はその通りの人生を歩き、地方の長官に任じられた。そして、人間進むも退くも、出世の遅い早いも、 運命で定められていることだ。いくらやきもきしても、なるようにしかならぬと、固く信ずるようになった。 ある時、高名なお寺を訪ね、参拝して三昼夜坐禅を組んだ。すると、お寺の老師が舌をまいて、 「若いのに素晴らしい。これほど一点の妄想もなく澄み切り、悟りを開いた人には会ったことがない」と言った。 遠了凡は、「何も修行などしておりません。運命が決まっている以上、高望みも悲しむこともしません。 ですから私には、邪念も曇りもないんです」と言った。 老師は驚いて、「心に曇りがないのは、人生をあきらめただけで、 人生を極めて心を美しくしたのではなかったのか…。それでは余りにも哀れだ」と言った。 老師は続けて言った。「運命というものは、決して定まったものではない。天命は自分から作り、 福は自分から求めて手にするものだ。しかるにあなたは、二十年この方、他人から占定されて、 自らの努力で変化しようとしなかった」 「だが、案ずることはない。徳を積めば、有名にも、お金持ちにもなれる。 今から人のために善いことを実行しなさい。あなたの運命は変わる」と説いた。 つまり、自分から自発的に立命をもって修行すれば、運命が変わると説いたのです。 それからの遠了凡は、毎日欠かさず善いことを念い、実行した。そうしたら、 生まれないと言われていた子供を授かり、53歳で死ぬはずが、70余歳まで生きた |
安岡正篤師は、この話を通して「善きことを重ねると、因果の法則が働き、
運命は変えられる」と説いているのです。
2004年07月16日
”お陰様”の言葉に込められる感謝の心
【吉村外喜雄のなんだかんだ 第39号】
~幸せな人生を歩むために~
「”お陰さま”の言葉に込められる感謝の心」
それが「ヘェ~」となり、意外と面白い。
今日は、私たちが普段よく使う言葉、「お陰さまで…」の語源を探ってみます。
私の父は香林坊に店を構えていた。町内の商店主がふらりと店に入ってきて、
「最近暇やねェ~。商いのほうはどうやいね?」と尋ねられる。
普通は『まぁ、ボチボチやわ』と、謙遜して言うところを、『お陰さまで…
』と言う。
父に「何故いつも、お陰さまで…、としか言わないのか?」と訪ねたら、『同じ商
いをしとるもんに、”お客が来んで暇や”と言っても仕方がない。いくら嘆いても、
誰も助けてくれんわいね。だから”お陰さまで…”としか言わんことにしとる…』
「お陰さまで…」の由来については、致知8月号の五木寛之氏と稲盛和夫氏の
対談で、二人が語っている。
| 五木 | 『大阪の人は、「儲かりまっか」と聞かれたら、「お蔭さんで、まあぼちぼちでんな」
と答える。「お陰さまで」の「お陰」は、「御蔭参(おかげまいり)の「お陰」です。 御蔭参りは、伊勢神宮へ参ることです。ですから、「お陰さんで」ということは、「天地神仏のお陰、 世間様のお陰で商売はなんとか儲かっております」という大阪の礼儀を表している言葉なのです』 |
| 稲盛 | 『確かに「お蔭さんで」という感謝の気持ちは、優れた経営者は必ず持っていますね。 俺の才覚で成功したなどとは誰も言いません。「私は運が良かった」と謙虚に語る。つまり神様であるとか、 何かそういう大きな力の支援で成功できたのだと、自分のビジネスの成功をとらえておられる』 |
念のために広辞林を繰ってみたら、「おかげ参り」は、『江戸時代、父兄や主人の許しを得ず、旅費も持たずに家をぬけ出し、 沿道の人々から施しをもらいながら、伊勢神宮参拝したこと。「抜け参り」ともいう』とあった。
北陸ゼミは定員650名。七月中には申込者のめどが立つよう、皆様に参加のお願いををさせて頂いております。
沢山の方にご参加頂き、「お陰さまで!」と、早く言えるようになりたいものです。
そして、受講された皆様からも、「お陰さまで…よかった!」の嬉しい声が聞けるよう、準備をさせていただいているところです
2004年07月13日
あるがままに受け入れる

【心と体の健康情報 - 153】
~幸せな人生を歩むために~
「可能性思考能力/あるがままに受け入れる」
先日の”坂東弘康”氏の講演の続きです。
あの偉大な”松下幸之助”は、”可能性思考能力”が誰よりも高かったという。
”可能性思考能力”とは、「現実をあるがままに受け入れること。その上で、
何事にもプラスの発想で受け止めることができる能力」のことをいいます。
ある時、塾生が松下幸之助に質問した。「戦国の逸話て”ホトトギス”がよく知られています。三人の武将の内、
どの武将の考え方に賛同されるでしょうか?」
信長は「鳴かぬなら、殺してしまえホトトギス」。秀吉は「鳴かぬなら、泣かせてみせようホトトギス」。家康は「鳴かぬなら、
泣くまで待とうホトトギス」。
ご存知、三人の個性をみごとに表現した逸話です。
鳴かないホトトギスは、もしかしたら”障害を抱えている”のかもしれません?
そのホトトギスに、信長は「殺してしまえ」と言う。それは惨いことです。
秀吉は「鳴かせてみせよう」と言う。「褒美をやるから、鳴け!、秀吉のたっての願いじゃ、鳴け!、何で鳴かぬのじゃ、鳴け!
」。これではイジメです…
家康は「鳴くまで待とう」と、ユウチョなことを言う。これでは、一生が終わってしまいます。為るものも為りません。
幸之助はそれ対して、「わしは、三人のどれでもないなぁ~」と言う。
しいて言えば、「鳴かぬなら、それもまた好しホトトギスやなぁ~」と…
人にはそれぞれ、得手・不得手があります。勉強ができなくても、手先の器用な子もいます。今の学校教育は、
勉強ができない子はダメな子として、スパッと切り捨ててしまう。どんな子にも、その子にしかない持ち味、
キャラクターがあります。
まず、「在るがままに受け入れる」。「それもまた好し」と受け入れた上で、
「その子が持つ素晴らしい持ち味は何なのか? それを見つけ出して、育てていく。それが教育であり、人材育成ではないか。
それが親や、幹部の仕事やろぅ」と、幸之助は言うのです。
可能性思考の前提条件は、「現実をひとまず、在るがままに受け入れる」ことなのです。売上が低迷し、赤字体質の企業。
その現実をまず受け入れ。何故そうなのかを見極めた上で、プラスの発想に導いていく。経営者・
経営幹部の可能性思考能力が問われるのです。
マイナス思考をプラスに転換するキーワードは、「それもまた好しホトトギス」なのです。
その上で松下幸之助は、事実を在るがままに受け入れるには、「素直な心」
が大切だと言っている。「素直」というと、
一見弱々しいイメージがあるが、 この場合の「素直」には、極めて積極的・
前向きな意味合いが含まれているのです。
幸之助が会議の席で、「素直に」と発言したときは、「前例や周りの意向に捕らわれるな!」と言っているのです。
「数年前に失敗した事例があります。だからダメだと思います」と発言した社員に、「君、素直でないなぁ…。
前回ダメだったのなら、その原因を追究して、どうやったら旨くいくかのアイデアを出すのが、今日の会議ではないのか?」
と幸之助は言う。
極めて積極的にアクティブなイメージで、「素直」を幸之助は使うのです。
「自分の失敗体験や、自信のなさからくる捕らわれの心」、「素直でない」原因はここにあるのです。
2004年07月09日
イチロー選手の夢
【吉村外喜雄のなんだかんだ 第38号】
~幸せな人生を歩むために~
「イチロー選手の夢」
成功するには、成功するまで続けることだ
辛抱して根気よく努力を続けていくうちに
周囲の状況が変わって 成功への道が拓けて来る
大リーガーで活躍しているイチロー選手が、小学校六年のとき書いた作文を紹介します。
|
僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。そのためには、中学、
高校と全国大会に出て活躍しなければなりません。活躍できるようになるためには、練習が必要です。 そんなに練習をやっているのだから、必ずプロ野球選手になれると思います。 僕が自信のあるのが、投手か打撃です。去年の夏、僕たちは全国大会に行きました。そして、 ほとんどの投手を見てきましたが、自分が大会ナンバーワン選手と確信でき、打撃では、 県大会四試合のうちホームランを三本打ちました。そして、全体を通した打率は5割8分3厘でした。 このように、自分でも納得のいく成績でした。そして僕たちは、一年間負け知らずで野球ができました。だから、
この調子でこれからも頑張ります。そして、僕が一流選手になって、試合に出られるようになったら、
お世話になった人に招待状を配って、応援してもらうのも夢の一つです。 |
アテネオリンピックが目前に迫ってきました。オリンピック選手は何れも天才なのでしょうか? 小さいときから才能があり、 その才能が開花して、やがてオリンピックのメダリストになった人もいるでしょう。
しかし多くの場合は、「小さいとき体が弱く、それを克服しようとしてスポーツを始めた」といったような動機で、 その後の努力が実り、オリンピックの選手になった人の方が多いのです。
すべてが満たされている人は、その恵まれた環境を生かそうとしません。むしろ、持たざるものの方が、
それを手にしようと努力に努力を重ねて、成果を二倍にも三倍にもしていくのです。何も持っていないからこそ、
すべて満たされている人には無い、大切な宝物を手に入れるのです。
2004年07月06日
ものごとをプラスにとらまえる
[人生、どちらを選択して歩んで生きるか?]
■成果を求める人生
成果を得る人は、いい訳をしません。
習慣的に成果に挑戦し、やりつづけます。
苦労することをいといません。
その結果、素晴らしい成果を得て 幸せな人生を送ります。
■いい訳の人生
いい訳をする人は、何かあるごとにいい訳をし、
いい訳の連続で人生を送ります。
苦労を避けて通ろうとします。
その結果 満足すべき成果を手にすることなく、
自ら、不幸な道へと歩んでいきます。

【心と体の健康情報 - 152】
~幸せな人生を歩むために~
「可能性思考/ものごとをプラスにとらまえる」
先日の”坂東弘康”氏の講演からの抜粋です。
あの偉大な”松下幸之助”は、”可能性思考能力”が誰よりも高かったという。
”可能性思考能力”とは、「現実をあるがままに受け入れること。その上で、
何事にもプラスの発想で受け止めることができる能力」のことをいいます。
可能性思考の高い人は、人生こよなく幸せに暮らしていけるのです。そこで、この可能性思考の能力を、
教育訓練によってより高めようというのです。
アメリカの宇宙基地ナサに、とてつもないサバイバル訓練があります。身体能力、I
Q共に高い人達が宇宙飛行士に選ばれている。そういった人達を対象に行われる実験・訓練です。
「戦闘機が、極暑の砂漠に不時着した。そこから、どういう人間が生き残るか」というサバイバル訓練です。
厳しい訓練も後すところ三日というところまできて、隊員には、半分しか水が入っていないコップが渡されます。
わずかコップ半分の水。これ以降の補給は一切ない。これが現実です。
「この現実をどう受け止め、どう解釈するかで、一人の人間の生死が決まる」これが、この訓練の目的です。
この後三日間、ドロップアウトする隊員と、最後まで耐えぬく隊員に分かれます。
ドロップアウトした隊員は、水を渡された瞬間「これで三日間どうやって生き延びろというのか、 絶対無理!」と思った。
クリアーした隊員は、水が半分しかないことを現実として受け止め、この命の水を糧に「ヨシ! 絶対生き抜いてみせるぞ!」
と腹をくくった。
ガラスの容器に入っている液体を見て、「半分も入っている」と見るか、
「半分しか入っていない」と見るかの違いなのです。受け止め方は人によって違います。
可能性思考の能力の差が、苦しい時に出てきます。それが、その人の運命を左右し、人生を左右するのです。
2004年07月02日
元気な時に死を考える
■私の言葉遊び。同じ文句を並べた「畳語」の続きです。
・喜び上手な人のところに、喜びごとが集まってくることを詠った
「喜べば 喜びごとが喜んで 喜び集めて喜びにくる」
・”冬のソナタ”の心境でしょうか…
「心ぞと 心にしれど 心より 心まどわす 心なにせん」
・次の二つはおまけ…
「京の三十三間堂の仏の数は、三万三千三百三十三体あるという」
「狂言師が京から今日来て 今日狂言して 故郷の京都に 今日帰る」
・私の作。 同意語を組み合わせると、以外と簡単に作れます。
『仙人が優れた仙人を 千人の仙人の中から一人の仙人を
選任しようとしたが 仙人が千人の仙人の中から 仙人を一人
選任することは 千に一つもむずかしい』

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第37号】
~幸せな人生を歩むために~
「可能性思考/元気な時に死を考える」
人は誰しも「死」を恐れる。だから誰も、死について真正面から考えようとしない。
何れ必ず死ぬときがくることへの恐れからか、そのことに触れまいとする。
何れ我が身に降りかかってくることだろうが、今は話すことも、考えることも忌まわしい。そうやって、
大切なことを先送りしてしまう。
だから、突然その時がやってきたとき、心の備えが出来ていないから、うろたえ、嘆き、恐れることになる。
壬生の義士のように、武士たるもの日頃から、いざというときの切腹の覚悟ができている。太平洋戦争、
ゼロ戦で散っていった若者も、覚悟ができていたから、みんな笑顔で飛び立つことができたのでしょう。
一般に「死」は忌まわしいもの、暗いものとして遠ざけてしまいがちです。この世に生を受けた以上、もっと自然に、
そして真剣に「死」というものに向き合う必要があるようです。
そもそも人は「他人の死」を悲しみこそすれ、それが原因で恐怖心に襲われることはない。しかし、自分の死を目前にすると、
恐れおののくことになる。
死を恐れるから生命は、その細胞の一つひとつが、全力で生きようとするのです。
「死」は決して怖いものではない。怖いと思う原因の一つに、死んだら何もかも消えてなくなる。灰になってしまう。
無になってしまうとの思いがあるからでしょう。
だから、怖いのです。
浄土宗では、死んだ後に極楽浄土へ行くことができ、禅宗では、来世もう一度この世に生まれ変わることができる。
母親の胎内から生まれてきたのだから、またその故郷に帰るのだと考えれば、死ぬことが怖くなくなるかもしれない。
「死ぬ間際ではなく、いま元気なときに、死のことをどのように受けとめるか?」
考えておくことです。自分を納得させるものを持っておくことが大事でしょう。
死んだら何もかもそれでおしまいと思うのか? 死は永遠の別れと思えば、怖いものになる。死後も魂は生き続けると思えば、
心の拠りどころになるだろう?
死後の世界を信じるか…? 信じなくても、この世に何かを残し、人生の使命を果たした満足感で死んでいくか…。
心の拠りどころ如何で、死というものへの心構えが、天と地ほど違ってくる。
死についても、プラス思考で考えるようにしたい。可能性思考を高めていきたい。年をとるにつれ信心深くなるのも、
そういった想いの現れでしょう…。
文中、五木寛之の「元気に生きる知恵」から、一部抜粋があります
2004年06月29日
苦労は買ってでもせよ!
■孟子の言葉
天が重大な任務をある人に与えようとするとき
必ず まずその人の精神を苦しめ
その筋骨を疲れさせ
その肉体を餓え 苦しませ
その行動を失敗ばかりさせて
そのしようとする意図と食い違うようにさせるものだ
これは 天がその人の心を発慎させ
性格を辛抱強くさせ
こうして 今までにできなかったことも
できるようにするための 貴い試練である

【心と体の健康情報 - 151】
~幸せな人生を歩むために~
「苦労は買ってでもせよ!」
|
|
私にとって、死ぬことよりも怖いのは、病気が再発して、またも3年・5年と、治る見込みもなく、 病院のベット臥せてしまうことです。人生がメチャメチャになってしまう。こんな辛いことはない。
死の間際の苦しみは、せいぜい十日くらいだろう。しかし、治る見込みのない寝たきりの人生は、生き地獄である。 看病する家族の苦しみも含めて、思い出したくもない。それこそ、死んだ方がましというものです。
人は皆、いつかは等しく死を迎える。葬儀に参列したとき、命に限りがあることを感じ、かけがえのないこの命、 「大切にしなければ」と思う。
限りある命だからこそ、「死」に直面したとき、 生きようとする命の本能が働く。
真っ暗闇の怖さを知って初めて、太陽のまばゆさに感動するように…。
人生において、「嘆き悲しむこと」「絶望すること」「先が見えず途方にくれること」、いろんな”苦しみ・悲しみ・怒り” に遭遇する。
こういったことは、人間生きていくうえで、すごく大切な命の働きだと思う。
私達はこういったことを、マイナスのイメージにとらまえ、敬遠しがちです。
しかし、そういった影の部分を体験して初めて、 今まで見えなかった光の部分が見えてくることを、知らなければならない。
その影の部分が深ければ深いほど、大きければ大きいほど、その後に見えてくる光の部分の輝きも、大きいものになってくる。
「若い頃に、苦労は買ってでもせよ!」という。辛いこと、我慢しなければならないこと、自分を厳しく律すること、 こういったことは、誰もが嫌がり、避けて通ろうとします。
竹は、節があってこその竹である。節があるから強い風にもしなり、耐える。
いくらスクスクと成長しても、厳しさを体験しないまま、節のないまま、大きく成長したのでは、嵐がきたとき、 ひとたまりもなく倒れてしまうだろう。
2004年06月25日
幸運と感謝に生きる
禅宗の教えに、病を得たらいずれ”死ねば治る”というのがある。どんな辛く苦しい病でも、
「死ねば治る」のである。しばしの我慢でよいのだからと、病に伴う死への恐怖などはない。自然体に身を任せているからには、
死ぬときがきたら死ねばいい。病の苦痛に勝る難行苦行を積んできた禅僧にとって、病などなにほどのこともないのである。
しかし、我々凡人には、人生、何が苦であるといって、「病」に勝る苦痛はない。
人の世に「病」というものがなければ、どれほど人は幸福であろうかと思う。
「人生とは何だろう」。人の一生には運・不運が付きまとう。思わぬ運・不運に人生がほんろうされる。私は、
数えればきりがないほどの運に恵まれ、今を生かされている。
今日のお話は私事ですので、お読みになりたい方だけ、どうぞお読みください。

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第36号】
~幸せな人生を歩むために~
「幸運と感謝に生きる」
三八豪雪の年の春、雪下ろしで真っ黒に日焼けした私。健康そのものでした。
念願の東京に就職が決まり、旅立つ二日前の三月三十日、フッと、健康診断を受けるなら今と、病院へ検診に出かけた。
検診の後、先生が言った。
「ベッドを空けておくから、午後から入院の手続きをするように」。 『……』
4年前に発病して大学進学をあきらめている。その後、薬を飲み続けて治ったと思っていたら、気づかないうちに病気が再発し、
進行していた。
その日から、隔離病棟のベッドに横たわる毎日になった。
それから七年、病魔との闘いの日々。同世代が、青春を謳歌し、職場で、仕事で人生の土台づくりに励んでいる大切な時期、
私はベッドにひたすらじっと横たわる毎日が続いた。
毎日、お尻に打つ注射が、筋肉の硬直で刺さらなくなり、経験の浅い看護婦の手をわずらわせた。辛い日々だつた。
病棟で共に暮らす患者。3年・5年は当たり前、死んでいく人もいる。亡くなると、看護婦が部屋に入ってきて、
何事も無かったように、その空きベッドのシーツを取替え、きれいにする。数日後、新入りの患者さんが入ってきて、
そのベッドの住人になる。
刑務所の囚人の方がまだましだろう。
あと何年何ヶ月何日で、娑婆に出られる…
と、わかっている。私たち患者は、誰一人、いつ退院できるか、わかるものはいない。「このまま一生、
病院暮らしになるかもしれない…」。そんな不安がよぎる。
ベッドで何もせず寝ているだけの毎日。半年、一年と経つうちに、こんな生活に耐えられなくなってくる。
刑務所なら、毎日運動の時間があるだろう。作業時間もある。たまに運動会や演芸会もあるだろう。しかし、
私達は365日何もなく、何もせず寝ているだけ。
隔離病棟だから、見舞いに来る人もいない。退屈で単調で、拷問のような毎日。
何よりも辛かったのは、朝・昼・晩の病院食。冬、丼の底に水が溜まり、冷たく団子になったご飯、シジミの味噌汁、
がんもどき。毎日同じようなメニューで、味なくまずい食事だった。そのせいか、今でも和食が好きではない。
当時の病棟・病室には、テレビは一台もなかった。一家にようやく一台の時代です。NHKの大河ドラマ「花の生涯」が、
ちまたで大変な人気だった。
外見は健康そのもの。食欲は旺盛。それでいて、じっとして寝ていなければ治らない。有り余るエネルギーのはけ口がない。
じっとしているのが、耐えられない。
「病気から逃れたい」「早く退院したい」と、体が訴え、もがく。辛くて、辛くて、布団の中で、やり場のない自分に、
涙がこぼれ出た。
いつ治るとも知れない中、病棟の患者さんが入れ替わる。亡くなる人、病気が治り、長い闘病生活にさよならをする人。
嬉しそうに各病室を周り、お別れの挨拶をして退院していく。自分はいつになったら退院できるのだろうか?
「何のために、この世に生まれてきたのだろうか?
生きるとは何なんだろうか?」
そんなことを考えるようになった。
そして、哲学書や宗教書を読んだ。そこから、私なりの人生観が生まれてきた。
「過去は振り返るまい。将来をあれこれ思い悩んでも仕方がない」。
「生かされている今に感謝し、今を楽しく、今日を最高に生きよう」と…。
この考え方が、その後の私の生き方を支配した。そして、幸運をもたらした。
入院後しばらくして、アメリカで新しく開発された新薬が試されることになった。
「ストレプトマイシン」「カナマイシン」「トリコマイシン」。次々と試される薬のお陰で、徐々に回復していった。
薬害で難聴になった。
精神的我慢の限界を迎えたころ、ようやく退院することができた。
もしも、最初に病気が見つかったとき、発見が遅れていたら…。
その時気づかなければ、おそらく大学受験で、夜遅くまで勉強していただろう。
四年後に再発したとき、そのことに気づかずに東京に出ていたら…、おそらく、がむしゃらに働いていたことだろう…。人生、
運・不運は紙一重。
何れも、もっと病魔が進行して、苦しむことになっただろう。もっと長い闘病生活を余儀なくされたことだろう。 そうしたら、
今のような幸せな人生を手にすることはなかっただろう。妻とも出合わなかったし、
息子や娘と過ごす幸せな人生もなかっただろう。 もしかしたら、手遅れで死んでいたかもしれない。
たまたま、日本に入ってきた新薬のお陰で命拾いした。早く健康を取り戻すことができた。運がいい、ついている。
よろずの神に感謝した!ありがとう!
想像すると、今でも胸が締め付けられる。あの頃を思い出すと、身震いがする。
しかし、それ以上に、いく重もの幸運に恵まれたことに、なによりも感謝しなければならない。
一度死を覚悟したお陰で、その後の人生はすべて”おまけ”。
毎日やることが楽しくてしようがない。退院後再出発した人生は、信じられないくらい次々と幸運に恵まれた。
やりたいことすべてがうまくいった。日一日に感謝し、好きなことを好きなだけやり、生きたいように生きてきた。
今日一日を最高になるよう生きてきた。仕事でも、遊びでも、何でも一所懸命、全力を出し切るようにしてきた。
一度は死んだ身。だから「今日一日を生き切る」。明日もそうしようと思う。
死はちっとも怖くはない。40年も余分に生きられたことが、何よりも嬉しい。
人生の終りには、「充実した生涯であった」と言い切ることができれば、それでいい。
2004年06月22日
運のいい人・悪い人(2)
■ 人生とは…
人生、良いときも悪い時もある。「逆境」は誰にでも訪れる。のがれることはできない。
このことを江戸時代の学者”佐藤一斎”が、言志四録の一つ「言志晩録」の中で語っている。
「人の一生には、順調の時もあれば、逆境のときもあり、
幾度となくやってくるものである。自ら検するに、順境といい逆境といい、なかなか定め難く、順境だと思えば逆境になり、
逆境だと思えば順境になるといった具合である。
だから、順境にあっても怠りの気持ちを起こさずに、ただただ謹んで行動するより仕方がないのである」
※言志四録
学問・思想・人生観など、修養処世の心得が1133条にわたって書かれた随想録

【心と体の健康情報 - 150】
~幸せな人生を歩むために~
「運のいい人・悪い人(2)」
6月19日福井で、日創研のSA講師でおなじみの、”坂東弘康”氏の講演を聴
く機会を得た。以下、二時間の講演の中からの抜粋です。
|
何事にもプラス思考で考える、「可能性思考能力」
を高めることが大切です。 |
20日、日曜日のTV番組「波乱万丈」のお客様は愛川欽也。番組の中で
「どんなつまらない仕事でも、楽しく仕事をしてきた」と懐古している。モノ事をどのように見つめるかによって、
人との接し方、仕事の仕方が変わってくるのです。
又、こんな時、皆さんはどのように反応するでしょうか?
交差点で側面衝突事故を起した。その瞬間「怪我もなく、この程度の事故で済んで助かった」と思うか、
「ああ~ついていないよ、やってられない」と嘆くのか…。どちらでしょうか?
潜在意識の中の
「運」に関わる思考が、ブラスなのかマイナスなのかによって、
モノ事に対するとらまえ方が全く違ってくるのです。
いくら知識・技術・テクニックを身につけていても、意識の根っこにある考え方、
価値観が否定的であれば、折角身につけたものも、使えなくなってしまう。
[松下幸之助の人を見る目]
松下政経塾が塾生を採用するときの、入塾試験での話。 「松下さんは何を基準にして、人を選んでいるのですか?」
と尋ねたら、「それは、二つある」という。
その一つは
「運の強そうな人」であり、もう一つは「愛きょうのある人」
だと言う。松下政経塾は、運と愛きょうで塾生を選んでいることになる?
どちらも、偏差値のように、点数では表せないものです。運も愛きょうも、極めてあいまいなものです。
そういったあいまいさを基準にして、人を選ぼうとするところに、偉大な松下幸之助の人となりを見ることができるのです。
後日、この話を聞いた塾生が、松下幸之助に尋ねた。「私には運が備わっているでしょうか?」。幸之助曰く「君、
入塾できたことが運の強さだよ!」
選考基準の一つ、「愛きょうのある人」というのは理解できる。人に好かれるし、将来成功する確率が高いでしょう。しかし、
「運の強い人」というのはどうやって見分けるのだろうか?
|
過去の人生を振り返ってみれば、悲しかったこと、苦しかったこと、辛かったこと、
いや~なことがいっぱいある。そういった過去を全部ひっくるめて、運がいい人生だと思う人は、「運が強い」
人なのです。ですから、面接のとき、運が強いのか悪いのか、本人に直接聞いてみればわかることなのです。
|
2004年06月18日
人生チャンスは三度訪れる
■「柳生家の家訓」
出会いや縁を大切にすると、人生が開けてきます。新しいチャンスが芽生えてきます。以下は「柳生家の家訓」です。
「小才は 縁に気づかず」
時代が変わろうと、環境が変わろうと、
いっこうにその変化に気づかない人
「中才は 縁を活かさず」
変化に気づいているのに、何もしようとしない人
「大才は 袖すりあう縁までを活かす」
大きな才能のある人は、わずかの縁にも機敏行動し、
マイナス要因まで
チャンスに変えてしまう

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第35号】
~幸せな人生を歩むために~
「人生チャンスは三度訪れる」
私の好きな言葉に、米国の実業家 アントリュー・カーネギーの言葉がある。
「チャンスに出会わない人間は一人もいない、
それをチャンスにできなかっただけだ!」
人生三度のチャンスが巡って来るという。チャンスの女神には前髪はあるが、後ろ髪がない。(私には後ろ髪があるが、
前髪がない…ちょっと不真面目)
チャンスがくることが事前にわかっていればいいが、通り過ぎてからでないとわからないから、どうしようもない。
■チャンスを、逃さないようにするために、私が心がけて来たことは、
(1)目標のある生き方をすること
(2)多方面に幅広くブレ-ン(友人・知人)
を持つこと
(3)情報を積極的に収集し、
世の中の動きや変化に絶えず目をこらすこと
(4)積極的に行動すること
(じっとしていても運にはめぐり合えない)
人の一生に大きな影響を与えるものに「運」があります。ある日突然目の前に現れる運が「幸運」であったり、「不運」
であったりします。
高校卒業のとき病気で、学校推薦が受けられなかった。そこで一箇所だけ自薦で、日立の代理店の就職試験を受けた。当時、
私が最も苦手としたのが”作文”。そこで、事前に模範的作文を一つ作って、試験に臨んだ。
私が一つ選んだ題目は「実社会に出るにあたって」。試験当日の倍率は七倍。
筆記試験の後、試験官がやおら黒板に「実社会に出るにあたって」と書いた。
ラッキー…。楽勝でした。
ただ、この時運に頼っていたわけではなく、運を呼び込む、いろんな事前準備をして臨んでいる。
学校に内緒で受けたため、「駄目なら次」というわけにはいかなかったのです。
一次面接の後、一週間して二次面接、そして最終面接で採用が決まった。
又ある時、同僚四人で山陰ドライブを楽しんでいたら、一日に二度もスピード違反で捕まった。
「運」は「運ぶ」という言葉であるように、人の出会いが良い運も、悪い運も運んできます。良い運を沢山求めるのであれば、
毎日、東奔西走、善い運を持った人に沢山出会うことでしょう。
ところで、幸運な人に会っていれば「良い運」に恵まれるかというと、そうはならない。目的を明確にして、
その目的達成のために汗をかきかき、人に遭うのでなければ、出合った人から良い運をいただくことはできません。
ノエビアでは毎年春になると、新入社員の飛び込み研修を約4カ月間実施します。
研究所や総務に配属される女性であっても、配属先に関係なく、全員に課せられる研修です。
全く知らない土地で飛び込み営業が始まる。最初一週間は先輩が同行し、飛び込み営業の手ほどきを受ける。
それから後は一人で、自分で考えて毎日飛び込みをしなければならない。
辛く過酷な研修です。毎日、売上と廻った軒数を報告します。売上全国ランキングも公表されます。
最初の意気込みはどこえやら、一週間二週間と、回れども、回れども、誰も話を聞いてくれません。ほとんどは玄関払いです。
成果を持って帰りたいと焦っている間は、何故か、良い運にめぐり合うことはない。一ヶ月、足を棒にしたころ、
心に変化が現われてくる。
昨日まで早く成果を出そう、会社に認めてもらおう、早く楽になりたい、と思ってやっていたが、
「もうそんな売上を追うことは止そう…。お客様に喜んでもらえるような訪問の仕方をしよう。どうせやるなら楽しくやろう…」
と…。
その心の変化が、しばらくして、素晴らしいお客様との出会いを呼び込む。
そこからは幸運の連続。あんなに悩んでいたことが嘘のよう。やること為すことすべて旨くいくようになる。大体そうなる。
ところで、誰もが皆そうなるのかというと、そうはなりません。二ヶ月経っても三ヶ月たってもいっこうに結果が見えず、
悩みぬいた末、折角難関を突破して就職した会社を、辞めていく新入社員が出てくる。
社会に出たとたんに運に見放される人もいるのです。
チャンスは、目標・目的を持って汗を流し、毎日努力の積み重ねをしているからといって、訪れて来るとは限らない。いや、
そうではなくて、チャンスが目の前まで来ているのに気づかず、つかみ方がわからず、通り過ぎていってしまうのです。
2004年06月15日
運のいい人、悪い人
■ことば遊び「畳語」
同じ文句を並べた
「畳語」。今日は三回目です。
春は、『桜咲く 桜の山の桜花 咲く桜あり 散る桜あり』
夏は、
『瓜売が 瓜売にきて売残し 売売帰る 瓜売の声』
秋は、『月月に 月見る月は多けれど 月見る月は この月の月』
・これが江戸川柳では、
『月月に 月見る月は 下女安堵』となる。
この月の月は、お月さまのことではありません。
わからない人のためにもう一句、『豆に花咲いて小豆の飯をたく』
■畳語に冬の句が見当たらないので、一句作ってみました。
『雪が降る 粉雪吹雪 しまり雪 雪降る山に 雪はしんしん』

【心と体の健康情報 - 149】
~幸せな人生を歩むために~
「運のいい人、悪い人」
私の人生、運七割で生きてきたと思っている。
私が尊敬する成功者は、おしなべて「運を呼び込む力が強い」とも、思い込んできた。
ところが、それとは正反対の人生を送ってきて、年商三千億円の大企業にまで育てた社長さんがいる。前号でも紹介した、
100円ショップ・ダイソーの矢野博丈氏である。以下矢野社長の言葉です。
|
私はご覧の通りのごく普通の平凡な男で、頭が悪くて勉強嫌い。能力に欠けている。そして、 運と能力に見放された人生を送ってきた。しかし、「能力がない」「運が悪い」という人生のお陰で、 現在の成功を手にすることができました。 |
倒産夜逃げ、火災、社員の離反と、人生何度となく訪れる「不運」。しかし、その体験を生かし、同じ「不運」
を寄せつけず、最初の不運をバネにして、謙虚に物事に接してきたことが、逆に「強運」を呼び込むことになったのでしょう。
世の中には運のいい人がいれば、運に見放されたと思っている人もいます。
何がそうさせるのか、人生紙一重の差といっていいでしょう。
「自分の身に起こることは、すべて偶然ではなくて、起きることすべてに意味がある」「自分の人生で起きることは、
すべて必然・必要なこと」という考え方がある。
運を呼び込むことができる人間になろうと思ったら、自分にとって不幸なことでも、すべてベストだと、
肯定的に受け入れることだそうです。起きたことすべてに、何か意味があるのです。意味があって起きたのであれば、
起きたことを過不足に思うことはないのです。自分の身の周りに起きたことすべてベストと考える。
このように口で言ってしまえば簡単なことですが、こればっかりは、本人の性格にもよるし、あるいは苦労を重ね、
人生に達観した人でないと、そういう域には達しないだろうと思う。
ところで、「運に恵まれて、好きなことをして人生を楽しもうと思ったら、以下の条件を満たさなければならない」と、
船井総研の船井幸雄会長が”運は必ず甦る”と題する講演の中で語っている。
1. 他人に迷惑をかけない。
2. 良心に反することをしない。
3. 誠の心でもって、すべてに対応する。
(NHK新撰組、近藤塾長が浮かんでくる)
4. 慈愛の心で人に接する。
5. 自分の身の丈に合った暮らし方をする。
6. 運のいい人(ついている人)と付き合う。
(善い友を持ち、悪い友と付き合わない)
日頃、こういった条件に反することをやっていれば、運に見放され、苦労から逃れることはできない。
2004年06月11日
足るを知る-3
【人生に達観した人】
人生に降りかかってくる災難。「それが人生だ」と達観して、何があっても今が最高!今日が最高なんだと、今この瞬間を喜び、
こうして生かされてある命のありがたさを実感できる。そして、すべてに感謝することができ、何があっても素直に受け入れることができる。
そんな人生に達観した人とは…。
一.三途の川を渡りかけて、引き返してきた人。
病気や事故、戦争などで、死の一歩手前を体験し、悟りを得た人。
二.幼い頃に貧乏のどん底を体験したり、倒産・死別など、何度も繰り返す苦難
を乗り越え、人生の機微に触れた人。
三.体力・知力の限界に挑む、荒行・苦行の末、自らの悟りを開いた人。
百円ショップのダイソー、矢野博丈社長の人生は、夜逃げに始まり、度重なる苦難の連続。そういった体験が、
人生の危機を乗り越える直観力を磨き、年商三千億円の巨大企業にまで育て上た。
両親を知らず、兄弟親戚一切なしの天蓋孤児で、孤児院から人生が始まった、カレーチェーン1番屋の宗次元社長。お二人は二番の人生です。

吉村外喜雄のなんだかんだ 第34号
~幸せな人生を歩むために~
「足るを知る-3」
前号に続き、(株)新経営サービース「バイマンスリーワーズ」からの転載です。
| 自然界は、生きとし生きるものすべてが共に生きることで、
バランスを保ってきた。ところがこの60年の間に急速に科学技術が進歩し、人間の幸せを追求する余り、
地球の生命バランスを崩してしまった。 自由主義経済の中で、生死を賭けた企業間競争、拝金思想が、地球を蝕んでいった。二十一世紀の人類にとって、 「勝つか負けるか」の闘争論理ではなく、「いかに大自然と共存共栄するか」という考え方の方に、 少しづつ舵の切り替えをしていく必要があるようです |
市場には競争原理が必用です。競争の中で企業が鍛えられ、共に体質が強化されていきます。
今、企業間のデジカメ戦争はすさまじいものがあります。商品寿命はわずか三ヶ月だという。
次々と新しい商品を市場に送り出し、生き残りのための戦いは熾烈を極める。
販売量で上位を占めた企業(キャノンやソニー)が、更に低価格の商品を市場に投入し、ライバル企業を蹴落としていく。
今後急速に勝敗が決して、二極分化されていくという。
| 競争相手を倒して、獲物のすべてを奪う「闘争」は、
いずれ己を滅ぼすことになる。 「競争」はどちらもレベルが上がるが、「闘争」は、相手が倒れるまで戦う消耗戦になってしまう。 肉食動物が草食動物を、草食動物が植物を、欲望の赴くまま食い尽くしてしまうと、 いわゆる食物連鎖は途切れてしまう。満腹のライオンは、鹿を目の前にしても見向きもしません。 自然に生きる動物たちは、そのことを本能的に知っているのです。ところが、 足るを知らない人間がその自然の摂理に背いているのです。 |
月曜夜八時のNHK番組「地球・ふしぎ大自然」で、蟻食いが、アリ塚に穴を開けて蟻を食べるシーンがあったが、
一つのアリ塚で食べる量は150匹くらいにしかすぎない。決して蟻塚を突き崩したりしない。
蟻たちに与えるダメージが少ないことが、蟻食い自らの生命を守ることになるのです。そのことを蟻食いは知っているのです。
禅修行の中に「生飯(さば)」という食事作法があります。ご飯は全部食べずに、
3~7粒くらいの飯粒を残すのです。これを池の鯉や小鳥など、他の生命にも分け与えるのです。
農村に行くと「のこし柿」という風習がある。実った柿をすべて採り尽くさず、
冬を迎える動物や鳥たちのために残しておく。昔は皆貧乏でした。食べものを残すような粗末なことは、誰一人しませんでした。
そんな時代の中での風習なのです。
必用な分を必用なだけ手元に残し、残りは人に差し上げ施す。謙虚で思いやりのある
「自利利他」の精神を、身につけていかなければならないと思う。しかし、
煩悩の世界に生きている自分には、とても難しいことです。
「足るを知る」の精神は、古来より日本人が持ち続けてきた、”みんな仲良く”
の精本人の心の奥底にあるアイデンティティなのです。
2004年06月08日
足るを知る-2
■「なにかあるのが世の中よ!」
二十日ほど前の177号で、女人禁制の話をしましたが、つい先日、京都で地下鉄に乗ったとき、うっかり男子禁制、
女性専用車両に乗ってしまった。
まさか、京都にも女性専用車両があるとは…! シマッタ!! 私以外はすべて女性。全く気づきませんでした。周りの女性も知らぬふり。
次の駅に着くまで、私も知らぬふりをして乗っているしかなく、デパートの女性下着売り場に間違えてまぎれ込んだような…、
内心恥ずかしさでいっぱいでした。
中村天風師の言葉に、「なにかあるのが世の中よ!」
がある。
本当に何が起きるかわからない…。 生きている以上、いろんなことが起きる。
起きて当たり前。何もなかったら生きている意味がない。いろんな出来事に出会ったら、もう一歩踏み込んで、「では、
どうしたら良い方に展開できるか」と、常にプラスの方向に頭を働かせていくことだと教えている。

【心と体の健康情報 - 148】
~幸せな人生を歩むために~
「足るを知る(2)」
人生、善いこともあれば、悪いこともあります。私は思わぬ不幸に遭遇したとき、「この程度で済んで良かった」と思うのです。
起きてしまったことを、歎いても仕方がないし、そのことのために、失うものがあっても、悔やんだり、
くよくよしたりしない性格のようです。
以下、「致知1月号」で、平成十三年に芥川賞を受賞した禅僧”玄侑宗久”氏と、聖心女子大学教授”鈴木秀子”
氏の対談の中からの抜粋です。
| 禅の世界にも「知足」
(足るを知る)という言葉がある。
「自分の身に起こることは、すべて偶然ではなくて、
起きることすべてに意味がある」と考えます。 私が日本人に生まれたのも、男子に生まれたのも、突然病気になったりするのも、 全部何か意味があることなのです。意味があって起きたのであれば、起きたことに過不足を思うこともないのです。 「生まれたときはみな裸、死ぬ時も又裸。何一つ持ってあの世には行けない。何を不足に思うことがあろうか」と… 』 |
”偶然は必然”、友人の新田哲夫氏から、「つきを呼ぶ魔法の言葉」という、
世にも不思議な運命を体験した人のメールをいただきました。感動と驚きの物語です。50ペ-ジの長文ですので、
時間に余裕があるときに、ゆっくり開いて読んでください。 >>ファイルをダウンロードして読む
| 禅の世界では、例えば何かの角に頭をぶつけたとすると、「痛い!
」と言わずに、「風流だね」って言う。痛いからって、
自分に腹を立てたり、 人に文句を言ってもしょうがないし、逆に人から「ボヤッとしているからだ」
なんて言われると、余計に腹が立ち、 痛みが増します。 ぶつかってしまった以上は、痛みがなるべく速やかになくなる言葉を吐くようにする。それが「風流だね」 なのです。 人生で起こるいろんなこと、バカバカしいこと、楽しいこと、悲しいこと、「それが人生だ」と達観して、 「何があっても今が最高!」と思うことだそうです。 今日は今日でしかない。「今ここに」なのです。 今日が最高なんだと、今この瞬間を喜び、こうして生かされてある命のありがたさを実感できれば、 すべてに感謝することができるようになり、何があっても素直に受け入れることができるようになるのです。 だから、「人生にピークがあって、年とともに衰えていく」という考え方をしない。 今日を最高に生きていけば、明日はもっと最高になる。「人間というのは、生きている限り高まり続けていく」 という考え方です』 |
例えば、私は今六十二歳です。「六十二年間待ちに待った最高のときが、今やって来た」
と考えるのです。
癌の病を克服した人が、「ガンは自分にとって素晴らしい贈り物だった」と言う。
ガンになったお陰で、「生きる喜びを知り、家族のあり難さを知り、身体について実に多くのことを学んだ。
食生活も改善することが出来た。すべてに感謝して生きるようになった」と…。
「すべて、良いことも悪いことも、自分にとって必用なことであり、人生を豊かに生きるために起こること…」と考えれば、
悩んだり悔やんだりすることにも意味があることになる。
常にどう変わるかわからない今を、尊く生きる人生でありたいものです。
2004年06月04日
足るを知る
【足るを知る】
老子三十三章に「知足」がある。
『人を知るものは智 自らを知るものは明なり
人に勝つものは力あり 自らに勝つものは強し
足るを知るものは富み 強めて行うものは志あり』
仏教思想では、
『裸で生まれてきたのだから裸で帰る。人間寝るところ一畳あれば足りる。
人間を入れる棺桶は巾二尺、長さ六尺もあれば足りる』
聖書五章十五節には、
『人は母の胎より出で来たりし如く また裸体にて帰り行くべし。
その労苦によりて得たる物を 一つも手にとりて携え行くことを得ざるなり』

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第33号】
~幸せな人生を歩むために~
「足るを知る」
稲盛和夫氏や、政治評論家細川隆一郎氏などの有識者は、今の日本を根本から立て直すには、”足るを知る”
という精神を学ばなければならないと言っている。
先々週お話を聴いたばかりの、100円ショップ・ダイソーの矢野社長も同じことを言っておられた。
「足るを知る」は、仏教の教え「吾唯知足(われただ、ちそく)」のことである。
昨年京都へ紅葉を見に行ったとき、竜安寺の伝道掲示板に、
『貧乏とは 何も持っていない人のことではなく 多くを持ちながら
まだまだ欲しい欲しいと 満足できない人のことである』
という意味の言葉が掲げられていたのを、記憶している。
禅修行の目的の一つ、”足るを知る”人間になるには、欲望が抑制され、煩悩妄想による迷いもおのずと消え、
いついかなる時も、心清き状態にいられるようになることだという。
今の時代の日本は「物で栄えて心で滅ぶ」と言われているように、私達の生活は買うものがないくらい、
物質的には十分潤っている。ブランド志向のより高価なものを身につけ、より美味いものを食べ歩き、使い捨て、
食べ残しが当たり前となり、「もったいない」という言葉が死語になっている。
以下、(株)新経営サービース「バイマンスリーワーズ」からの転載です。
| バブル崩壊後、アメリカの勝つか負けるかの企業戦略論が、
日本経済社会を覆っている。戦略的には大切でしょうが、相手を倒すことを狙った戦略は、
いずれ己を滅ぼすことになります。 もともと狩猟民族であるアメリカの戦略論に、農耕民族の日本の経営者が、 感化洗脳されていることに問題があると思うのです。 アメリカを代表する企業日本マクドナルド。一昨年の平日半額セールは大ヒットした。 ITを駆使して世界中から最安値の食材を仕入れて、コストダウンを行った成果です。しかしその後、 急速に業績を落としたのは何故か? 平日半額セールは一見、うまくいったようですが、その実「自分さえよければ」という発想から脱していません。 マクドナルドの低価格戦略は、牛丼、弁当、ラーメンなど他の外食産業にも浸透し、デフレを加速させました。 無理な低価格政策は、同業者間の熾烈な競争を生み、取引先から反発を買い、 不信感に陥った消費者も少なくないのです。 |
稲盛和夫氏も言っている。
| 我々はいつまでも豊かさを追い続けることはできない。 永久に経済的な成長を続けることは、地球の破滅につながるだけである。豊かさを手に入れた今こそ「足るを知り」 、現在の豊かさに感謝し、これ以上の物質的繁栄を追い求めることは、もうやめるべきではないか… |
と…。そんな時期に来ていると思う。
2004年05月25日
21世紀、どう生きる
先週の金曜日、広島市の沖合いにある、江田島旧海軍兵学校(現在の江田島術科学校)
を見学してきた。
【心と体の健康情報 - 146】
船が桟橋に着き、大地に足を踏み下ろしたとたん、眼の中に飛び込んでくる校舎。
長い歴史の重みが伝わってくる。
お目当ては、屋外に展示してある回天特攻隊の人間魚雷と、歴史資料館。人間魚雷は、想像していたよりも大きく、しかも精巧で、
船内にはびっしり機関や配管が張り巡らされていた。
次に見学した「教育参考館」には、東郷平八郎や山本五十六元帥の遺品の他、日清・日露・
大東亜戦争時の海軍関係者の書や遺品が展示されていた。
中でも、自らを犠牲にして国のために散っていった、若き特攻隊員の展示室に入るや、その遺書を読み、血に染まった遺品を見つめているうちに、
熱いものがこみ上げてくるのを押さえきれず、深い感銘を受けた。
国を守ろうと、散っていった二千三百柱の特攻隊員の名前が壁一面に刻まれた前では、頭を垂れ、冥福を祈った。

~幸せな人生を歩むために~
「二十一世紀、どう生きる」
先週広島へ行った。広島といえば皆さんもよくご存知の100円ショップ ダイソーの発祥地。
矢野博丈社長の創業時の苦労話を聴く機会を得た。
(株)大創産業は現在年商三千億円、国内に2400店舗、海外に250店舗も展開している大企業です。
約二時間の講演の中で、「今春の入社式で新入社員に伝えた三つの要点」をお話されました。矢野社長の”生き方理念”
が伝わってきます。
これからの時代は、今まで生きてきた二十世紀のようにはならない。
厳しい世の中になることを知っておいてほしい。
私も、社会に出るとき、学生時代の経験から、将来出世するんだ、ひとかどの人間になれると思っていたものです。
それがたった二年半で、女房子供を連れて夜逃げという、どん底を味わうことになったのです。
そして、その半年後には、更に厳しい現実の壁にぶつかることになった。その時私は、運には見放されたが、
能力はあると思っていた。
ところが、セールスの能力がゼロに近い自分がいた。人に物を売ることが出来ないのです。
社会に出てたった三年で、「運」も「能力」もない自分に思い知らされたのです。
それは、もう過去のものなのです。
二十一世紀は 「苦しさを乗り越えていく中に、楽しさがある」
そんな時代になります。
致知出版社の二十五周年記念で、五木浩之先生が講演されました。
その中の言葉です。
「苦しさと楽しさは一対である」「悲しさと幸せも一対である」
二十世紀の日本人は、「楽しさ」と「幸せ」
ばかりを訴求して、人間が枯れてしまった。涙を流さなくなった。
良い日本人というものが無くなってしまった。
ところで、人生で最も美しいものは「一条の光」である。
真っ暗闇の中に射し込む一条の光、こんな美しいものはない。
「今の時代、この一条の光を見ることのできる人は少なくなった」
五木浩之氏が、戦地から引き揚げてくるときの苦難・苦痛・厳しさ・悲しさ・辛さの中から味わった一条の光…。
私たちは、五百条・千条の光を、当たり前のように受けて育ってきた。
二十世紀はそうだったかもしれない。けれども二十一世紀はそうではない。
二十一世紀という世紀は厳しい世紀である。
苦しさの中を乗り越えてこそ、楽しさを見つけることができる世紀なのです。
江戸時代の農家。もし二人以上の子供が生まれたら、食べさせることが出来ない。厳しい生活環境の中、
子沢山では一家が飢え死にしてしまう。
授かった子供を幸せに育てる自信がない。そこで間引く、殺す。
その子にとって生きていることよりも、死んだ方が幸せと思うから、殺すのです。
私の母は、上海から引き上げてくるとき、冬の上海の浜辺に腰まで浸かって、当事お腹の中にいた私を流産して、
砂浜に埋めようとした。
しかし、幸いにも、流すことがでず、私はこの世に生まれてきた。
こんな世の中に生まれてくるのはかわいそうだ、生まれてきても、幸せの薄い子になると思った。当時の状況から見て、
お腹の子が生まれてくるのが幸せか、死ぬことが幸せかを考えたとき、死なせてやることの方が、
この子にとって幸せと思ったという。
「スタートが大切なのではなくて、成し遂げていく、努力し続けるところに価値観がある」
この世に生を受けたスタートの日、
誕生の日を喜び祝うのもいい。しかし、生を受けた後、努力して、人生の幸せを手にした時にこそ、
喜び祝うべきではないでしょうか。
「生きる」とは、そんなに簡単なことではありません。二十世紀、大多数の日本人は幸せを手にすることができた。
それはたまたま、そんな良い時代にめぐり合わせただけなのです。
今までの皆さんは、それほど努力しなくても、幸せでいられた。その錯覚に気づかなければならない。これから、
二十一世紀を生きていく皆さんは、一生懸命働いて、苦労して、自らの手で幸せをつかんでいく。努力をしなければ、
幸せを手にすることが出来ない時代になるのです。
2004年03月09日
な~んか…おかしい
【心と体の健康情報 - 136】
~幸せな人生を歩むために~
「な~んか…おかしい」
以下の文章は、致知1月号「三農七陶」(北川八郎・陶芸家)から抜粋したものです。
世の中な~んかおかしい、何もかもがおかしい。人も天候も社会も政治も、みんな、何かおかしい。
いつまでも企業のトップが頭を下げ、政界も私利私欲の毒まんじゅう。だから、誰にも投票したくない。教育界も混乱し、
学校の先生も自信を失っている。
子供達も学校に行く意味を見失って、登校しない子が増えている。その上、心を病んでいる中高校生のなんと多いことか。そして今年も又、
成人式が大荒れと
なった。
病院も医者も失敗を恐れ、恐れるあまり、また失敗を招いている。こんなに文明が発達しても病人は増え、子供を生もうとせず、
日本中が相互不信に陥っている。
こんなに豊かな日本なのに、すべてが、な~んかおかしい。
世界もおかしくなってきている。悪を退治しようと始めた戦争が、以前にも増して憎しみを生み出し、殺りくの応酬。
何故みんな仲良く共存できないのだろうか?
世の中すべて、な~んかおかしい。
バス停で女子高生が化粧している。交差点信号脇の植え込みは空き缶だらけ。
公の場でのマナーがなっていない。
「子供たちも母親たちも喋らなくなった」と、知り合いの自転車屋さんは言う。
黙って自転車を持ってきて、「パンク」の一言だけ。郵便局の窓口で、無言でお金を引き出し、にこりともせずに去つていく。
街で二人の高校生とすれ違った。仲良く歩いていると思いきや、携帯でそれぞれ別の人と話している。いや、話しているのではなく、
黙々とメールを送っている。
人は、一つ便利なものを手にすると、今まで持っていた大切な能力が失われていく。そのことに誰も気づかない。
車に乗れば足が弱くなる。柔らかい食品を食べていると、アゴが後退する。
空調の効いた部屋にいると、汗をかく能力が衰え、自律神経失調症が増える。
除菌にこだわって、すぐお腹をこわすようになる。
社会も天候も、山も川も、そして人間も正常なコントロールを失いつつある。
日本だけでなく、アメリカもイスラエルもイラクもみんなおかしい。世の中がこんなに豊かになったのに、人々はイラつき、人を信じられず、
利を求め、保身に走り、自分一人の幸せしか考えようとしない。
人はみんな幸せになりたいと思っている。だけど、な~んか…おかしい。
あれがない、これが不足と、求めることばかりで、人に与えることの喜びを知らない。
2004年03月02日
可能性思考能力/あるがままに受け入れる
【心と体の健康情報 - 153】
~幸せな人生を歩むために~
「可能性思考能力/あるがまま受け入れる」
先日の”坂東弘康”氏の講演の続きです。
あの偉大な”松下幸之助”は、”可能性思考能力”が誰よりも高かったという。
”可能性思考能力”とは、「現実をあるがままに受け入れること。その上で、
何事にもプラスの発想で受け止めることができる能力」のことをいいます。
ある時、塾生が松下幸之助に質問した。「戦国の逸話て”ホトトギス”がよく知られています。三人の武将の内、
どの武将の考え方に賛同されるでしょうか?」
信長は「鳴かぬなら、殺してしまえホトトギス」。秀吉は「鳴かぬなら、泣かせてみせようホトトギス」。家康は「鳴かぬなら、
泣くまで待とうホトトギス」。
ご存知、三人の個性をみごとに表現した逸話です。
鳴かないホトトギスは、もしかしたら”障害を抱えている”のかもしれません?
そのホトトギスに、信長は「殺してしまえ」と言う。それは惨いことです。
秀吉は「鳴かせてみせよう」と言う。「褒美をやるから、鳴け!、秀吉のたっての願いじゃ、鳴け!、何で鳴かぬのじゃ、鳴け!
」。これではイジメです…
家康は「鳴くまで待とう」と、ユウチョなことを言う。これでは、一生が終わってしまいます。為るものも為りません。
幸之助はそれ対して、「わしは、三人のどれでもないなぁ~」と言う。
しいて言えば、「鳴かぬなら、それもまた好しホトトギスやなぁ~」と…
人にはそれぞれ、得手・不得手があります。勉強ができなくても、手先の器用な子もいます。今の学校教育は、
勉強ができない子はダメな子として、スパッと切り捨ててしまう。どんな子にも、その子にしかない持ち味、
キャラクターがあります。
まず、「在るがままに受け入れる」。「それもまた好し」と受け入れた上で、
「その子が持つ素晴らしい持ち味は何なのか? それを見つけ出して、育てていく。それが教育であり、人材育成ではないか。
それが親や、幹部の仕事やろぅ」と、幸之助は言うのです。
可能性思考の前提条件は、「現実をひとまず、在るがままに受け入れる」ことなのです。売上が低迷し、赤字体質の企業。
その現実をまず受け入れ。何故そうなのかを見極めた上で、プラスの発想に導いていく。経営者・
経営幹部の可能性思考能力が問われるのです。
マイナス思考をプラスに転換するキーワードは、「それもまた好しホトトギス」なのです。
その上で松下幸之助は、事実を在るがままに受け入れるには、「素直な心」
が大切だと言っている。「素直」というと、
一見弱々しいイメージがあるが、 この場合の「素直」には、極めて積極的・
前向きな意味合いが含まれているのです。
幸之助が会議の席で、「素直に」と発言したときは、「前例や周りの意向に捕らわれるな!」と言っているのです。
「数年前に失敗した事例があります。だからダメだと思います」と発言した社員に、「君、素直でないなぁ…。
前回ダメだったのなら、その原因を追究して、どうやったら旨くいくかのアイデアを出すのが、今日の会議ではないのか?」
と幸之助は言う。
極めて積極的にアクティブなイメージで、「素直」を幸之助は使うのです。
「自分の失敗体験や、自信のなさからくる捕らわれの心」、「素直でない」原因はここにあるのです。
2003年12月12日
哲人・中村天風
■中村天風師について
天風先生がいま生きておられたら、
目をカッと開いてこうおっしゃるでしょう。
|
売れない、お客が来ない。だからどうだというのか! どうしろというのか! 天風会元専務理事 清水榮一著「心の力」より |

【吉村外喜雄のなんだかんだ 第10号】
~幸せな人生を歩むために~
「哲人・中村天風」
一昨日の十日、大島修治氏の壮絶な生への体験談を聞きました。 大島氏の不思議な能力については、
前号お話しましたが、偉大な哲人”中村天風”師の場合は更にすごい。
中村天風師は、明治9年東京生まれ。日清・日露戦争で軍事探偵として活躍。
三十歳のとき肺結核になり、死を目前にし、絶望的な日々の中、心の救いを求めて三十三才で渡米。世界を回り、
著名な哲学者に出会うも成果なく、死を覚悟して帰国の途中、インドの地で”カリアッパ”師と出会った。
ここからよみがえるのです。
ヨーガの聖地ゴーク村で修行することニ年。悟入転生、悟りを得、新しい生命力を手にして、
三十七歳のとき日本に戻ってきます。この時期に天風独自の自己強化哲学が開眼するのです。
帰国後数年で、銀行の他いくつかの会社を経営し、実業界でご活躍されます。
四十三才のとき、突然すべての地位、財産を放棄。単身「統一協会」を創設し、上野公園で辻説法を始めました。
八十六歳のとき、財団法人「天風会」創設。
1968年、九十二歳で没す。
天風師の教えは「積極一貫」。「いかなる状況であろうと、喜びと感謝で迎えなさい。そうすれば、幸福に活きることができる」
と説いています。
天風師は信じられないことをやって見せたそうです。目の前にいる適当な人を手招きして、その腕に五寸釘をブスリと刺す。
刺された人は、さぞや驚いたことと思いますが、何故か痛くないだけでなく、一滴の血も出なかったといいます。釘を抜くと、
何の痕跡も痛みも残らなかったそうです。
人間が持つ潜在的可能性は限りなく奥が深い。私達の常識では推し量れない不思議が、いろいろあるものです。
2003年11月28日
成功する人は地味で謙虚
■森信三 「修身教授録」から
人間学で独自の哲学を確立した”森 信三”先生の「修身教授録」 の中の 第三
十講「謙そんと卑屈」、第三十一講
「目下の人に対する心得」からの抜粋です。
|
「謙そん」とは、一人の人間としての自覚から生まれる「徳」である。
相手に対する自分の分際をわきまえて我が身を省み、差し出たるところがないようにと、我が身を処することをいう。
目上の人に「卑屈」な人ほど、目下には「傲慢」である。 「傲慢」はお目出たさの表れ、「卑屈」はずるさの表れ。己が、すなわち人間が出来ていない証拠である。 目下の人に対する思いやりは、目上の人に仕えた経験と苦労がないと生まれてこない。目上の人の人柄は、目下の人に対する態度と、 言葉遣いによってわかるものだ。 |
ちょっと成功を手にすると、人の言うことに耳を貸さなかったり、人を見下したりして、傲慢な態度を取りがちです。
目上の人に仕えた経験が浅く、苦労らしい苦労を経験したことがない私(吉村)には、耳の痛い言葉です。

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 第8号】
~幸せな人生を歩むために~
「成功する人は地味で謙虚」
先週は倒産する条件を並べてみましたが、今週は成功する条件です。
滋賀ダイハツ販売のオーナー後藤昌幸氏は、破産状態の会社を再建し、三十
年以上毎年トヨタを抜いて、県下一の売上を更新してきたことで有名です。致知
11月号に「仕事のコツ、人生ノコツ」として対談しているので紹介します。
| 成功する経営者と、失敗する経営者の差は、
どこにあるとお考えでしょうか? 長い間いろいろな経営者を見てきたが、結論から言うと、派手な経営者が失敗し、 地味な経営者が成功するということです。 バブルの時に、土地や株に手を出した人は、皆失敗しましたからね。「調子のいい時にうぬぼれず、 調子の悪い時にへこたれない」。これは、経営者の鉄則でしょう。成功している経営者というのは、 皆さん謙虚です。 商売は日々の積み重ね。余計な経費を使わず、どこまでも地味にやっていく。 経営とは、詰まるところ、稼いだ金と経費のバランスなのです。そのために大切にしていることは、 「たとえ一ヶ月であっても、絶対赤字を出さない」という信念を貫くことです。それを社内に浸透し、 社風にしてしまうことです。 |
京セラの稲盛さんの経営も、人一倍堅実なことで知られています。会社がまだ
一千億程度の頃の会社の方針です。
- 忙しいときに忙しいからと、人を増やすと、暇な時に人が余る。人が多い分、楽な仕事の仕方を身につけてしまう。
だから、一年で一番暇な時に丁度よい人員の配置しか認めない。
- 売上のない月は、消耗品以外は、どんなに必用であっても、金額の張る什器備品などの購入は認めない。
昔の商人が守ってきた商いの鉄則は「入りに見合う出」。損益分岐点を重視し、利益が出ないときは、すべてに堪忍・
倹約して出を抑える。モノを粗末にしない。
「入りに見合う出」の精神を守っていけば、商いが危機に陥ることもない。
私の父の時代、当時の商人の堪忍・倹約に対する心構えと徹底ぶりは、今の私にはとても真似られません。
2003年11月07日
ヤマト運輸の奇跡-5
衆議院議員を選ぶ選挙が二日後に迫ってきました。当選しなければただの人。
地元に利益を誘導するタイプの政治家に票が集まる傾向が強いため、国家百年を憂え、政治生命をかける政治家が出てこないように思います。
北国新聞が、地元の立候補者に「尊敬する政治家は?」と尋ねたら、”松村謙三”を挙げた候補者が二人いました。
富山県福光町出身の政治家です。もう一人忘れてはならないのが、我が石川県の”辻 正信”。ベトナムに単身潜入して、行方不明になったまま…
。昔は立派な政治家が多かったですね。
松下幸之助氏は八十五歳のときに、四十億円の私財を投じて「松下政経塾」を創設しました。私がその歳であれば、もう何年も生きられないから、
死んだ後のことなど、気にもかけないでしょうね。明日死ぬとわかっていても、リンゴの苗木を植える松下幸之助は、やっぱり偉い人です。
現在政経塾OBの国会議員は二十名。今回卒業生から四十名立候補している。私の見るところ、国家百年の想いが、
他の立候補者より強いように見受けられます。何名当選するでしょうか?

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 第5号】
~幸せな人生を歩むために~
「ヤマト運輸の奇跡(5)」
元ヤマト運輸、都築社長の講演最終回です。
| 他社との競争に勝ち抜くためには、ヨソにはない強みがなければならない。 クロネコヤマトの「クール宅急便」 。お客様に喜んでもらおうと、やって見たのはいいが、 これは大変なことでした。 第一の問題は、個数が少なく、採算ベースに乗りそうもないこと。 第二に、設備投資にお金がかかること。集荷する小型車に冷蔵庫を積み、 夜中に走る大型車にも冷蔵庫を積み、朝届いた荷物を、溶けないうちにと届けたら留守…。 営業所にも保管用の冷蔵庫がいる。これを全国のお客様に届けようというのですから大変です。 利益優先の経営方針なら、やらなかっただろう。「やってやれないことはない!」 この社風が成功へと導いた。他社との差別化のため、お客様に喜んでもらおうと始めたところ、毎年120% の急成長。 個人向けに始めたつもりが、今では特産品や海産物などを商う、地方の業者さんが利用するようになった。 法人比率が65%。新しい市場が開拓されたのです。 利益を先に考えたり、リスクを恐れていては、新しいことにチャレンジできないのです。 |
どんな素晴らしい学びをしても、一月もすると、学んだことを忘れていくし、学びを生かそうとする意識も遠のいていきます。
頭の中には、何万、何十万個と、記憶したことをしまっておく引き出しがある。きちんと整理しておかないと、
どこにしまったのか、イザという時に取り出せず、役に立ちません。
そこで、「講演や、学習した内容を、いつでも人に話せるように書き記し、要点をまとめておく」。これが私流の記憶方法です。
忘れないうちに、要点を文章にまとめ、整理してから、記憶の引き出しに仕舞っておく。そして、必用な時、
いつでも取り出せるようにしておくのです。
こうしておくと、何年たっても、昨日のことのように、学んだことがよみがえってきます。
2003年10月31日
ヤマト運輸の奇跡-4
■お徳なはなし
旅をより楽しく満足なものにするには、(1)豪華でサービスの良いホテル (2)食事が美味しい。
この二つのうち一つが満たされないと、旅そのものの満足度が低下します。
私達夫婦が京都で宿泊したホテルは、ホテルプリンセス京都。京セラが経営する高級ホテルです。場所も烏丸四条と五条の間にあって大変便利。
このホテルに決めた理由は、誕生月に宿泊すると、年齢分だけ割引してもらえるからです。私は62%引き。折角だからと、
16階の特別室(一泊3万円)をお願いした。この階はセキュリティーされていて、一般のお客様のエレベーターは止まりません。
すごくリッチな気分で宿泊することができました。
その他、結婚月に宿泊する場合にも、特典があるようです。

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 第4号】
~幸せな人生を歩むために~
「ヤマト運輸の奇跡(4)」
元ヤマト運輸社長、都築氏の講演からお伝えしています。
当時、ヤマト運輸が三流に落ちたのは、三つの理由があったと都築氏は言います。
その一つは「惰性の経営」
でした。挑戦しない会社になっていました。そして、
発想の転換ができなくなっていました。 この責任は経営者にあるでしょう。経営者が汗をかかず、楽な方を選択し、
挑戦しなくなったら、 会社は駄目になってしまうからです。
二つ目は「利益第一の経営」
にありました。顧客第一ではなく、自分の会社の利益追求を第一としていました。そして、
顧客の信頼を失っていったのです。雪印や東京電力など、みなそうでしょう。
三つ目は「第一線の運転手の質の低下」
。顧客と直接接する社員さんの質の低下が、客離れを引き起こしました。
そのことに経営者が気づいていなかったのです。
現在のヤマト運輸の第一線の社員の質は、以前に比べ高くなったと思います。
将棋を打つとき、一番活躍するのは、「飛車と角」です。会社では専務や常務に当たります。逆に一番役に立たないのが「歩」
です。歩は最前列に並んでいて、九枚あります。前に一歩進むことしか能がない駒です。昨日入ってきた運転手は「歩」です。
戦力にはなりません。第一線に立ち、お客様と接する機会の多いのも「歩」です。
ところで、将棋の強い人は「歩」の使い方がうまいですよね。相手陣地へ進めていって、「成り金」にしたり、
ここぞという攻めや守りのときに、大切な仕事をさせます。
つまり、歩を金に育てたり、適材適所に駒を動かすことがうまいのです。
2003年10月24日
ヤマト運輸の奇跡-3
| ■私の好きな言葉■ 詩人 坂村真民 だまされて善くなり 悪くなってしまっては駄目 いじめられて強くなり いじけてしまっては駄目 踏まれて立ち上がり 倒れてしまつては駄目 いつも心は燃えていよう 消えてしまっては駄目 いつも瞳は澄んでいよう にごってしまつては駄目 |
「人は困難に出会って初めて人間的真価が問われる」
この言葉は、日創研"田舞徳太郎"代表からいただいたFAXに書かれていた言葉
です。その言葉を坂村真民がみごとに表現しているのです。
さらに続けて、「うまくいっている時、すなわち順風満帆の時には、その人の本当の
姿は現れてこない。人間の価値は、困難に出会った時初めて試される」と書かれて
いた。
坂村氏のプロフィール等はこちらのサイトで紹介されています。
◆坂村真民の世界

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 第3号】
~幸せな人生を歩むために~
「ヤマト運輸の奇跡(3)」
元ヤマト運輸社長都築氏の講演からお伝えしています。
役員会も労働組合もすべて反対する中、当時の社長が絶対「ヤル」と決意したその根拠は何だったんでしょうか?
都築氏の講演を聴くのは今回で三回目です。今回の講演でもそのことに対して、お話はありませんでした。
当時米国の運送業界では、従来の業界常識をくつがえし、「配達日特定」を唄った宅配事業が生まれ、急成長していたのです。
広大な国土の米国。それまでは、いつ相手方に荷物が着くかわからない時代でした。
南部アメリカの国道沿いに点在しているモータープールに、小荷物の取り扱いを依頼し、宅配事業を成功させた人がいました。
勢いに乗って、貨物航空会社を買収し、全国の小荷物を一箇所に集め、翌日全国に配達するシステムを確立したのです。
当時の日本の企業は、米国を視察して、その先進性を取り込むことを常としていた。技術・流通・商業すべての分野で、
米国を模範としていたのです。
又、国内に目を向けると、郵便局という強大な全国宅配ネットが立ちふさがり、宅配事業を新たにやろうという企業はなかった。
そこで、ヤマト運輸は「これしか再生の道はない」と決断したのではないでしょうか。
| ヤマト運輸の前に立ちはだかる最も困難な壁は、運輸省の「規制」
の壁です。社内を説き伏せ、「会社の考え方・体質」を変えるのは、まだ何とかなる。 ところが、運輸省相手となると、押しても引いてもどうにもならない。ヤマト運輸が宅配をやろうとすると、 「規制」の壁が立ちはだかり、ニッチもサッチもいかない。 運輸省が認可した路線でしか運送業務が認められないのです。運輸省に足げく通って規制緩和を訴えたが、 聞き入れてもらえない。当時の橋本運輸大臣を告訴したりもした。 役人との根比べ。関東から順にテリトリー認可の申請を出し続け、全国すべての認可を取るのに十年もかかった。 |
2003年10月17日
ヤマト運輸の奇跡-2

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 第2号】
~幸せな人生を歩むために~
「ヤマト運輸の奇跡(2)」
前回に続いて、元ヤマト運輸社長の講演の続きです。
| ヤマト運輸は、従業員二千名の大きな会社。今までお世話に
なった法人のお得意様すべてを切り捨て、客単価の極端に低い、不安定な個人客に社運を賭けた。
新分野へ挑戦しても成功する確率は低い。失敗は許されない。役員の大多数は、「従来の仕事を継続しながら、 新分野へ徐々に進出する方が安全」と考えた。 もし、当時の社長がその考えを受け入れ、徐々に移行していく安全策で臨んでいたら、 現在のヤマト運輸はなかったでしょう。 宅配業務をやるのは現場の運転手さん。従来の路線の仕事に慣れ親しんできた運転手さんは、 一コ一コ集配する面倒な仕事を並行してやれと言われたら、敬遠することは明らかです。現場の管理職も、 宅配事業がうまくいかなければ、従来の路線に戻ればいいと考えてしまう。 |
全社「背水の陣」で臨んだ。宅配以外に生き残る道がないという危機感が、成功への要因となったのです。
2003年10月10日
ヤマト運輸の奇跡

【吉村外喜雄のなんだかんだ - 第1号】
~幸せな人生を歩むために~
「ヤマト運輸の奇跡」
元ヤマト運輸の社長”都築幹彦”氏の講演を聴く機会を得た。その講演から、今、私達が学ばなければならないことが、
数多くあることに気がつきました。そのポイントを今回から五回に分けてお伝えします。
| 老舗のヤマト運輸は、いつしか三流運送会社になっていた。再起を図るには、 従来のやり方でいくら経営努力しても、ライバル企業も同じように努力していて、見通しが立たない。 そこでヤマト運輸の社長は、国内の運送会社がまだ誰も手がけていない「宅配事業」へ軸足を移すことに、 社運を賭けることにした。 |
企業は「利益を出さなければならない」「顧客の信頼を得なければならない」。両方いずれも大事ですが、
利益を得ることより、お客様から信頼を得ることの方が更に大事です。
頭ではわかっている。しかし「儲かるか儲からないか…」、つい損得を先に考えてしまうのです。
| ヤマト運輸は明治時代からの老舗。今までは、
松下電機の冷蔵庫などを運送していれば良かった。それを全部やめて、
田舎のお袋が都会の息子に送る小荷物だけを扱おうというのです。 業界での成功事例はない。誰ひとり成功しないと思っているから、役員会は反対。 二千名の労働組合も反対。しかし、「今のままでは、会社の将来はない…」 |
と説得を続けたのが、当時の”都築常務”なのです。
もし、会社が目先の「利益」に囚われていたら、現在のクロネコヤマトが存在しなかったでしょう…。
累積赤字で苦しみ、約千名をリストラして、喉から手がでるほど利益が欲しい…、そんな会社のお話です。
2003年08月05日
女性の容姿-2
■登山から人生を学ぶ…
登山は人生そのもののような気がします。途中で苦しくなって、何度も引き返そう、ここで止めようと思います。途中で引き返した人は、以後、
山登りを苦手とするでしょう。でも「ここまで頑張ったのだから」と、又、気力を奮い立たせて一歩一歩自分に挑戦する人もいます。
人生は「やるかやらないか」の選択です。険しい山並みを見て、自分には無理とあきらめるのも一つの選択です。その時の選択が、
その後の人生を方向づけるのです。
普段から足腰を鍛えておかないと、高い山には登れません。人生もそうで、普段から勉学に励み、目標を持ち、コツコツ努力していなければ、
大きなことはできません。
いまだ経験したことのない目標に挑み、達成したことが大きな自信になる。
ほんの少し前に、「いやだ、止めよう」と思っていたことなどどこへやら、更に高い目標、高い山にチャレンジしたいと思うのです。
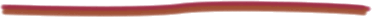
【心と体の健康情報-101】
~幸せな人生を歩むために~
「女性の容姿 2」
女性は、外見がいいと「性格もよく、人間的に優れている」と錯覚します。男性の場合も、背が高くスラッとしている方が有利に働きます。
過去百年間のアメリカの大統領選挙では、二人の候補者で背の高いほうが、圧倒的高い当選率となって現れています。又、
ある米国の大学で、卒業生の就職状況を追跡したところ、「身長が平均より高い卒業生の方が初任給が高い」
という調査結果が出ました。
米国の心理学者ウオルスターは、大学生を対象に「コンピューターによって相手を決めるデートパーティ」を開いた。
学生たちには、あらかじめ性格検査や態度についての調査を受けてもらったが、そのデータは脇に置いておいて、
ランダムにカップルを組んだ。
パーティが終わったあと、同じパートナーと再度デートしたいかどうかを、学生たちに尋ねた。
次回も同じ相手を選んだ人は、どんな性格なのかを調べるのが実験の目的でした。しかし、決め手になったのは、
相手の性格や態度、相性ではなくて、容姿、背丈などの身体的魅力であることがわかった。
男女が出会い、今後も引き続きつき合いたいと思った理由は、外見の美しさやカッコ良さだったのです。
結婚相手を選ぶとき、男性のほとんどは美しい人、つまり
「容姿」が選択の基準になるようです。 女性は、「男は美貌よりも中身」と言いながら、
この二つが密接に係わっていることが、心理学では解明されているのです。実際は、男性以上に外見上での判断と、
男としての値打ちを秤にかけて選んでいるのです。
渋谷昌三「よくわかる心理学」西東社より
2003年08月01日
女性の容姿
【心と体の健康情報-100】
~幸せな人生を歩むために~
「女性の容姿」
美人に生まれたら「人生の幸福の半分を手にして生まれてきたようなもの」と言われます。
何かにつけて美人に生まれると得なようです。
外見がいいと、「性格もよく、人間的にも優れている」
と周りが錯覚します。
小さいころから周りの大人に可愛がられ、大人になってからも、就職や結婚などで、何かにつけ有利に働きます。
だから、どの女性も、自分の容姿に関して、周りから見た客観的評価に比べて、甘めの評価をしたがるのも、
憎めない女心といえます。
そこで女性は、より魅力的に、より美しく見せようと、化粧に余念がないのです。
美しさを強調することで、自らの意識も高まり、まわりの評価も高くなるようです。
ある大学で、女性が魅力的なメイクをしたときと、メイクをしなかったときとでは、
男子学生に与える影響がどのくらい違ってくるかを実験した。
その結果、同じ問題を投げかけたにもかかわらず、魅力的メイクをしていたときの方が、
多くの男子学生の賛同を得ることができた。
魅力的なメイクをしているときの方が、好感をもって受けとめられ、発言に対する評価も高くなったのです。
ただ、見逃していけないのは、魅力的なメイクをした女性本人が、何となく自信に満ちた態度をとり、
言葉や動作に説得力が強まった可能性が高いということです。
更に、自分でメイクをしたときよりも、一流のアーチストにメイクをしてもらったときの方が、
より積極的で明るく振舞うようになり、性格まで一変してしまうのです。
化粧することで心理面に及ぼす効果が大きいのです。
少年院にいる非行少女の顔写真を見せて、大学生に評価を求めたところ、可愛い顔をした少女の方は、
「やむを得ない事情で非行に走ったのだろう」という好的評価をした人が多かった。それに対して、個性的な顔立ちの少女は、
「性格が悪く、犯罪を犯すタイプ」と、否定的な評価をされた。
顔と性格とは何の関連性もないはずなのに、そう感じてしまう人が多いのが現実なのです。
ある女性週刊誌によると、女性が一緒に腕を組んで歩きたくない男性のワースト3は、一位不潔、
二位ハゲ、
三位デブだそうです。
私はハゲのデブですから、女性に好まれるタイプではなさそうです。
2003年07月25日
第一印象
【心と体の健康情報-98】
~幸せな人生を歩むために~
「第一印象」
一目ぼれの経験は? あるとしたら、どんな記憶が残っているでしとょうか?
「一目ぼれ」は、初めて会ったとき「ハッ!」として、「この人だ!」と直感。その後、その相手に視線がクギづけになり、
無関心ではいられなくなった状態を言います。
初対面の相手から受ける感じが第一印象です。会った瞬間、相手の容姿や体形、服装、話し方、態度などからイメージして、
全体的特長を読み取り、相手の印象をつかみとるのです。
第一印象がその後の人間関係を左右します。最初に「信頼できる人だ」という印象を与えれば、
そのイメージがあとあとまで残り、親密性が増します。
逆に、「ルーズで信用できない」というような印象を与えてしまうと、人と同じことをしていても、信頼してもらえません。
待ち合わせの時間に遅れてきたとき、前者は大目に見てもらえる。が、後者は「失礼な人」と、
否定的な印象で受け止められてしまうのです。
初対面のわずか30秒が勝負なのです。好印象を与えるには、外見だけでなく、
内面からかもし出す知性や、人間的魅力も高めていかなければなりません。
しかし、一年や二年で身につくものでもなさそうです。せめて、普段から清潔な身だしなみを心がけ、
笑顔を絶やさないことではないでしょうか。
私は、初対面で「怖い人」という、あまり有難くないイメージを与えているようです。
その後何度か付き合っているうちに、「親しみやすい人」になっていくようです。
初対面のとき緊張して、気難しい顔になってしまうのも、原因の一つでしょう。
自然に顔の筋肉がゆるみ、
笑い顔で接するようになるまでには、時間がかかるのです。私のようなタイプを、「人見知りする人」と言うのでしょうか…?
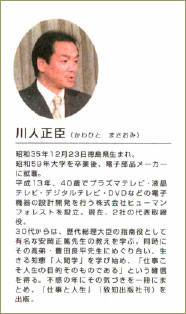 創業5周年を記念して、川人正臣氏は、4年前に出版した「仕事と人生
(致知出版)」 の続編、「仕事が人を作り、人が仕事をつくる」
と名づけた著書を、 (非売品)出版。記念品として参加された皆さんに配布されました。
創業5周年を記念して、川人正臣氏は、4年前に出版した「仕事と人生
(致知出版)」 の続編、「仕事が人を作り、人が仕事をつくる」
と名づけた著書を、 (非売品)出版。記念品として参加された皆さんに配布されました。