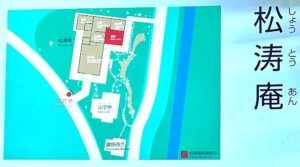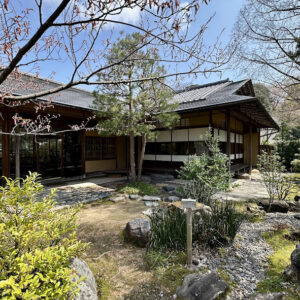2316 「吉村外喜雄のなんだかんだ」
「少年期、人生のどん底を味わった習近平」
習近平、1953年(S28)北京に生まれる。
習主席の父親”習仲勲”(しゅう・ちゅうくん)
は、21歳の時毛沢東共産党政府軍に参加し
、命がけで毛沢東を守った。
その後中国共産党で副首相にまで出世した。
ところが1978年いわれのない嫌疑をかけ
られ、16年間投獄生活。息子の習近平は
恵まれた幼少期を過ごしていたが、父親の
政治抗争で失脚。
15歳の時、地方の貧しい農村に送られる
「下放」を経験した。山肌に掘った横穴住居
で、野犬のような極貧の暮らしが6年間続い
た。
この間に姉は餓死、母親は投獄された。
更に1966~76年まで続いた文化大革命
で、反動分子の子として、習近平は4回も
投獄された。
食べていくためにレンガを焼いて売り歩き、
生き伸びた。
そうした浮き沈みの中で「将来偉くなって
中国を変えてやろう」と志を持つようになっ
た。22歳の時名門清華大学に入学。
卒業後、父親と親しかった国防相の秘書に
なり、軍隊に入隊。
ほどなく共産党員になり、志を実現する
第一歩、河北省の村長になった。
以後20年、地方政治でキャリアを積んだ。
胡錦濤が国家主席だった2007年、次の
指導者として有力視されていた、上海市の
トップが汚職で失脚した。
その後任に、当時隣の浙江省のトップにいた
習近平氏が、横滑りで市長に抜擢された。
以後、出世街道を駆け上がっていく・・
志の道が開けたのです。